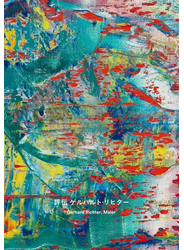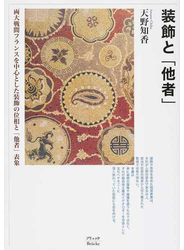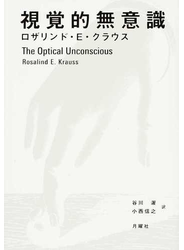ブックキュレーター哲学読書室
ブックキュレーター哲学読書室
抽象絵画を理解するためにうってつけの5冊
一般に難しいと言われる抽象絵画。かつてポロックが「音楽を楽しむように抽象絵画を楽しむべき」と語ったように、作品を感覚的に楽しむのも良いでしょう。ですが、なぜ人間は抽象表現をするのか、様々に考察するのも楽しいものです。抽象絵画を理解するためにうってつけの5冊を紹介します。【選者:筧菜奈子(かけい・ななこ:1986-:美術史研究)】
- 140
- お気に入り
- 12392
- 閲覧数
-
写真の登場以降、揺らぎ続ける絵画の意義を、具象と抽象を問わず様々な角度から問い続けるリヒター。具象から出発して抽象へと至り、その両方の表現を駆使して彼が描き続けているものは、現実の不可解さである。東ドイツのドレスデンという政治的に複雑な出自を持つこの作家の信念と半生が、作品の遍歴とともに細かに語られる。
-

抽象の力 近代芸術の解析
岡崎 乾二郎(著)
作家として、これまで様々な抽象表現を試みてきた岡崎乾二郎が、抽象絵画に対する言説を根本から見直し、覆し、全く新しい角度からその魅力に切り込んでいく。この取り組みによって、これまで西洋の後追いに過ぎないと見なされてきた日本の抽象表現の、その真の意義があぶり出されていく。
-

装飾と「他者」 両大戦間フランスを中心とした装飾の位相と「他者」表象
天野 知香(著)
抽象と装飾とは、一体何が異なるのだろうか。20世紀において、抽象は芸術としての高度な質を持つもの、装飾は単なる視覚的造形として区別されてきた。本書はそうした抽象と装飾の関係性を19世紀末から辿り直すと同時に、そこに西欧における「他者」としての植民地や女性の問題を見出していく。
-

視覚的無意識
ロザリンド・E.クラウス(著) , 谷川 渥(訳) , 小西 信之(訳)
批評家・美術史家として20世紀アメリカの美術を作り上げたクラウス。本書では無意識を軸にシュルレアリスム、ダリ、ピカソなど様々な作品を論じていく。中でも、ポロック、ステラ、トゥオンブリらの抽象絵画をフロイト、ラカン、デリダらの言説と引き合わせることによって、両者をさらに豊饒なものとする第6章は必読。
-

ジャクソン・ポロック研究 その作品における形象と装飾性
筧 菜奈子(著)
「無意識から描くならば形象は必ずあらわれてくる」。このポロックの発言を手掛かりに、初期から晩年の作品に一貫して描かれる形象を探っていく。その過程で浮かび上がってくる文字や記号といった形象は、彼の作品に何をもたらしたのか。具象性と装飾性という、これまで忌避されてきた観点からポロックの絵画の再解釈を試みる。
![]()
ブックキュレーター
哲学読書室知の更新へと向かう終わりなき対話のための、人文書編集者と若手研究者の連携による開放アカウント。コーディネーターは小林浩(月曜社取締役)が務めます。アイコンはエティエンヌ・ルイ・ブレ(1728-1799)による有名な「ニュートン記念堂」より。
ブックツリーとは?
ブックツリーは、本に精通したブックキュレーターが独自のテーマで集めた数千の本を、あなたの"関心・興味"や"気分"に沿って紹介するサービスです。
会員登録を行い、丸善・ジュンク堂・文教堂を含む提携書店やhontoでの購入、ほしい本・Myブックツリーに追加等を行うことで、思いがけない本が次々と提案されます。
Facebook、Twitterから人気・話題のブックツリーをチェックしませんか?
テーマ募集中!
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを募集中です。あなたのリクエスト通りのブックツリーが現れるかも?
テーマ応募フォーム
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを入力してください。
ご応募ありがとうございました。
このテーマにおける、あなたの”6冊目の本”は?
※投稿された内容は、このページの「みんなのコメント」に掲載されます。
コメントを入力するにはログインが必要です