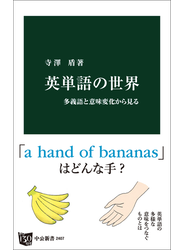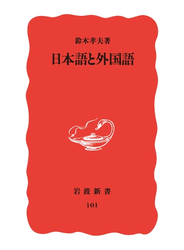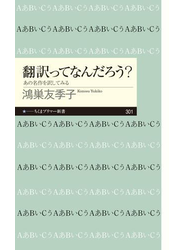ブックキュレーター杏林大学外国語学部准教授 倉林秀男
ブックキュレーター杏林大学外国語学部准教授 倉林秀男
深遠なる「ことば」の世界を冒険するための「地図」となる書籍
英語史・語源、外国語と日本語の比較、翻訳などに関するこれらの書籍には、思わず「なるほど!」とひざを打ちたくなるようなことが、たくさん書かれています。単語の意味を覚えたり、英文を読み込んだりする「英語学習」も大切ですが、「ことば」自体への興味を持ち、視野を広げることも同じくらい大切なことだと思います。
- 149
- お気に入り
- 7387
- 閲覧数
-

英語の歴史から考える英文法の「なぜ」 1
朝尾幸次郎(著)
「3単現にsをつけるのはなぜ?」「なぜmustには過去形がないのか」などといった、英文法に関してよくある疑問を、歴史的な観点から解き明かしてくれます。特に不定詞や冠詞などは、歴史的知識があると格段に理解が深まります。
-
「バナナと手の関係」など、身近な英単語を歴史的に見ると数多くの発見があります。本書で実践されているように、歴史的変化に基づいて、多義語と意味の変化に注目しながら知識を整理していくことで、効果的に語い力をつけることができるでしょう。
-
古池や蛙飛び込む水の音。この時の蛙はa frogそれともfrogs? 「ウチとソト」というシンプルな論理をベースに、英語と日本語の違いを詳らかにし、日本語の特徴を明らかにしています。また、「翻訳」という行為の奥深さを垣間見ることもできる好著です。
-
『赤毛のアン』『不思議の国のアリス』『嵐が丘』『ライ麦畑でつかまえて』などの有名な文学作品を題材にし、平易な言葉で「翻訳家が英文を徹底的に精読すると、どんなことがわかるのか」を私たちに伝えてくれます。本書を読めば、本当の精読とは何かがわかります。
![]()
ブックキュレーター
杏林大学外国語学部准教授 倉林秀男杏林大学外国語学部准教授。博士(英語学(獨協大学))。専門は英語学、文体論。<ことば>にかかわること全般を対象に研究を行っている。日本文体論学会代表理事(2018年~)、日本ヘミングウェイ協会運営委員。著書に『ヘミングウェイで学ぶ英文法』『ヘミングウェイで学ぶ英文法2』(共著、アスク出版)、『ヘミングウェイ大事典』(編集・項目執筆、勉誠出版)、『街の公共サインを点検する』(共著、大修館書店)、『言語学から文学作品を見る―ヘミングウェイの文体に迫る』(開拓社)などがある。
ブックツリーとは?
ブックツリーは、本に精通したブックキュレーターが独自のテーマで集めた数千の本を、あなたの"関心・興味"や"気分"に沿って紹介するサービスです。
会員登録を行い、丸善・ジュンク堂・文教堂を含む提携書店やhontoでの購入、ほしい本・Myブックツリーに追加等を行うことで、思いがけない本が次々と提案されます。
Facebook、Twitterから人気・話題のブックツリーをチェックしませんか?
テーマ募集中!
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを募集中です。あなたのリクエスト通りのブックツリーが現れるかも?
テーマ応募フォーム
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを入力してください。
ご応募ありがとうございました。
このテーマにおける、あなたの”6冊目の本”は?
※投稿された内容は、このページの「みんなのコメント」に掲載されます。
コメントを入力するにはログインが必要です