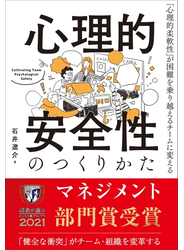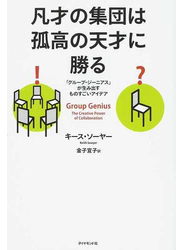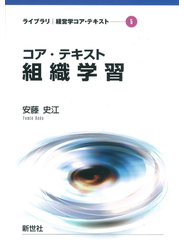人と組織の「創造性」を高める実践知
AIの発達、リモートワークの普及によって、いま私たちの「生産性」が大きく問い直されています。社会のイノベーションを支えるのは、まぎれもなく人間の「創造性(creativity)」です。創造性は、限られた天才に占有されたものではありません。理論と実践知を駆使することで、高めることができるのです。
- 85
- お気に入り
- 5649
- 閲覧数
-

問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション
安斎勇樹(著) , 塩瀬隆之(著)
良いアイデアが生まれないとき。会議が盛り上がらないとき。多くの場合、チームが向き合っている「問い」がデザインされていないことが大半です。問題の本質を見抜き、本当に解決すべき問いをいかに設定するか。課題設定の技法から、チームの対話を活性化する問いかけの手法まで、実践知を体系的に解説した一冊です。
-
人間の「創造性」を阻害する要因を突き詰めると、人が暗黙のうちに形成する固定観念(バイアス)の問題にぶちあたります。本書は現場に蔓延する「厳しい新人研修は有効だ」「競争環境は努力を促す」といったバイアスを、最新の研究知見を紹介しながら次々に揺さぶりをかけてくれます。
-
マネジメント論において注目される、心理的安全性。チームの心理的安全性を高めることは、単に「居心地が良い職場」を作ることではありません。お互いが健全に衝突しあって、創造性を発揮できるチームを作るための、リーダーのヒントが理論的かつ実践的に解説されています。
-

凡才の集団は孤高の天才に勝る 「グループ・ジーニアス」が生み出すものすごいアイデア
キース・ソーヤー(著) , 金子 宣子(訳)
革新的なアイデアは、一人の天才からではなく、グループのコラボレーションから生まれることが、様々な研究結果から明らかになっています。「一人でやったほうが、早いし楽だ」、そう結論づける前に、手に取っておきたい一冊です。
-

コア・テキスト組織学習
安藤 史江(著)
組織が創造的であるためには、組織が変化し続けること、つまり「学び続けること」が必要です。本書は、組織の変化のメカニズムに迫る「組織学習(organizational learning)」の最新の研究知見について解説しています。教科書として持っておきたい一冊です。
株式会社MIMIGURI代表取締役Co-CEO / 東京大学大学院 情報学環 特任助教 東京大学工学部卒業、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。研究と実践を架橋させながら、人と組織の創造性を高めるファシリテーションの方法論について研究している。組織イノベーションの知を耕すウェブメディア「CULTIBASE」編集長を務める。主な著書に『問いのデザイン-創造的対話のファシリテーション』(共著・学芸出版社)『リサーチ・ドリブン・イノベーション-「問い」を起点にアイデアを探究する』(共著・翔泳社)『ワークショップデザイン論-創ることで学ぶ』(共著・慶応義塾大学出版会)がある。
ブックツリーとは?
ブックツリーは、本に精通したブックキュレーターが独自のテーマで集めた数千の本を、あなたの"関心・興味"や"気分"に沿って紹介するサービスです。
会員登録を行い、丸善・ジュンク堂・文教堂を含む提携書店やhontoでの購入、ほしい本・Myブックツリーに追加等を行うことで、思いがけない本が次々と提案されます。
Facebook、Twitterから人気・話題のブックツリーをチェックしませんか?
テーマ募集中!
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを募集中です。あなたのリクエスト通りのブックツリーが現れるかも?
テーマ応募フォーム
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを入力してください。
ご応募ありがとうございました。
このテーマにおける、あなたの”6冊目の本”は?
※投稿された内容は、このページの「みんなのコメント」に掲載されます。
コメントを入力するにはログインが必要です