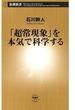1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Tucker - この投稿者のレビュー一覧を見る
「超常現象」をこれまでの科学では説明のつかない未知の現象、という意味で使えば、科学者が毎日研究している対象そのもの、になる。
ただ、一般的には「幽霊」「超能力」などといったオカルトものと、同一視されるので、「超常現象」と聞いた時の反応は人それぞれでバラバラ。
自分は(一般的な意味での)「超常現象」に対しては、「ちゃんと調べれば、面白い事が分かるのでは?」という気持ちと、オカルト肯定派を茶化したいので否定したい、という気持ちが混ざっている。
著者は「似非科学」に対しては、厳しく撲滅を目指しているが、「超常現象」に関しては、ある/ない、という観点ではなく、人間にとって役に立つかどうか、という観点で見ていった方がいいのでは?と主張している。
そして、その「ある/ない」に関しても、3つの段階に分けて考えている。
「存在」にも段階があるので、分けて考えたほうがいい、というのだ。
それは
「心理的存在」
「社会的存在」
「物理的存在」
の3つ。
「心理的存在」は個人の希望や信念など、個人にとって有効であるもの。
対して、「社会的存在」は文化、制度、法律など、ある集団内が共有しているもの。
そして「物理的存在」は物体、物理法則など、人類に普遍的な存在。
「超常現象」も「社会的存在」になるものであれば、"存在する"とみなしていいのではないか、というのが著者の主張。
超常現象を肯定する本、否定する本は本屋に溢れている。
また、テレビでオカルト肯定派と否定派の人を揃えて、言い争いをさせる、という番組はたまにある。
ただ、どちらの主張も相手に伝わっていない。
テレビ番組に至っては、カブトムシとクワガタにケンカをさせて、周囲で野次馬が囃し立てているのと同じレベルのものを繰り返しているだけ。
そういう中、著者のこの観点は新鮮な感じを受けた。
序章で語っているが、著者は、このようなスタンスを「はん幽霊論」と呼んでいる。
「はん」がひらがなになっているのは、「反・半・汎」の3つの意味があるからだそうだ。
本書の構成もこの3つに別れている。
「反」:非科学的主張には反論する。
「半」:半信半疑で検証する。
「汎」:科学と超常現象の折り合える点を探す。
頑なにオカルトを肯定もしていないし、否定もしていない。
が、自分の主観ではあるが、やや肯定側に傾いている感じも受ける。
まあ、この辺りは微妙なので、読む人によって、感じ方は違うだろう。
個人的には、オカルト肯定派を茶化すネタが増える方向に行って欲しいが・・・。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:キック - この投稿者のレビュー一覧を見る
何故か、超常現象には惹かれます。確かに荒唐無稽な現象が圧倒的に多いと思いますが、そうとも言い切れない不思議な話もあるものです。本書は、こうした超常現象について、科学的(超心理学的)な説明を試みたという本です。
大きく3部で構成されています。第1部(第1章~第3章)は「反」の部とし、幽霊体験や目撃報告に対して、科学的成果にもとづく反論を加えていきます。ややくどくて退屈な内容でした。第2部(第4章~第6章)は「半」の部とし、超能力に着目し、「半信半疑」のスタンスを取り、幽霊体験の中に科学を発展させる萌芽を探求していきます。第3部(第7章~終章)は「汎」の部とし、社会に役立つ超常現象もあるという視点で、「無意識」の機能や役割を炙り出しています。
「無意識」の世界に、「不可思議」な現象を解く鍵があるという本書の結論は、ユングの受け売りではありますが、興味深いものがあります。特にシンクロニシティ(偶然の一致)は、日常些細な出来事の中で、誰しも経験していると思います。無意識の科学について、今後の研究成果に期待します。
第1部を「2」、第2部を「3」、第3部を「4」、全体で「3」評価としました。
ところで、私自身は幽霊は見たことがありませんが、幽霊話は大好きです。一方、「正夢」は何度か見たことがありますし、「偶然の一致」は良くあります(正確には若い頃良くありました)。したがって、「無意識」の世界には以前から関心がありましたが、本書を読んで、ますます関心度が増したところです。
題名そのものの内容
2018/05/09 22:06
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:たあまる - この投稿者のレビュー一覧を見る
『「超常現象」を本気で科学する』新潮新書 を読みました。
題名そのものの内容ですが、幽霊や超能力を、ウソかホントかと科学的に判定するのではなく、そういう現象が役に立つか立たないかで考える、という姿勢はとても面白かったです。
血液型で性格を云々するのはとんでもないことですが、お守りや占いなどもそれにとらわれたり依存したりしないで、自分の安心感やモチベーションに生かせればいいんですね。
投稿元:
レビューを見る
≪目次≫
序章 なぜ超常現象を科学するのか
「反」の部ー幽霊をめぐる非科学的主張に反論する
第1章 幽霊が見えた?
第2章 迷信とお守りの誤解と詐術
第3章 夢と幽体離脱
「半」の部ー超能力現象を半信半疑で検証する
第4章 超能力と夢の中の世界
第5章 それは誰のしわざか
第6章 未来がわかるとはどういうことか
「汎」の部ー超常と日常を合わせて広汎に考える
第7章 「無意識」の大きな可能性
第8章 幽霊体験の社会化
第9章 解体される超常現象
≪内容≫
超能力やオカルトを罵倒する本かと思いきや、超常現象の可能性を述べている本。と言っても、眉唾なものははじめから一刀両断だが、ESPカード実験はわずかながら透視能力や予知を見出し、幽体離脱にも科学的な判断を下している。そして、幽霊の目撃や金縛りを含めて、
「無意識」という概念で説明できないか、その可能性を述べている。科学と言うか「心理学」がここまで研究しているのかという驚きで本を閉じた。
投稿元:
レビューを見る
5/28~5/30再読
NHKスペシャルのように超常現象を科学的に解明する本かと思って読んだのだが、科学的に解明した結果(科学として役に立つものとして考えると)創造力に活かすくらいしか役に立たないらしい。とほほ。読んでいて途中からうまく言い負かされている(論旨がすりかえられている)ような気がして、興味を失ってしまった。
投稿元:
レビューを見る
2014.06読了。
何か話のタネになりそうなので読み始めてみた。この本は、「世の中にはびこる超常現象は実はこんな科学のトリックなんだよ!ざまぁ!」という本ではなく、超常現象が本当にあるかどうか分からないけど、この説明のつかない力は現代社会で生かしていけるのかを考える本である。若干タイトルでの期待と異なることがあるので注意(笑)
ただ、内容自体はなかなか面白く、あるのかないのかだけでなく、現代社会に役に立っているのかという新しい視点を垣間見ることができた。不思議なことが起こった時、現実かどうかだけでなく、もしかすると深層心理が引き起こしたことかもしれない、じゃあどう役立てていこうという考えが大事だと分かった。何なのかは分からないけど、生かすことができれば、その人にとって存在していると言っていいんじゃないのかなと超常現象に少し寛大になれた気がする。
投稿元:
レビューを見る
超心理学 顔の認識 リチャードワイズマン幽霊否定派 ジェシーべリング、プリンセスアリス実験 回帰効果の誤認サプリメントとの関係 確証バイアス 認知的不協和の解消 レオンフェスティンガーの実験 エマヌエルスウェーデンボルグ ジョゼフバンクスライン ガンツフェルト実験チャールズホノートン ウィリアムロール、ボルダーガイスト シンクロニシティ、ユング 無意識、続ける事
投稿元:
レビューを見る
期待してたほど面白くなかったなぁ。
実際はまだまだ科学解析がなされていないためか歯痒い感じ、まぁ学者としての良心から来る謙虚さだとは思いますが。
ところで、超常現象については正直何とも思っていない当方ですが、金銭が絶えず見え隠れするところに世でいかがわしいと認識される事実の根があると思うのですが是如何。
投稿元:
レビューを見る
科学の視点から、心霊現象や超能力を理解する本。
心霊現象や超能力を全否定するのではなく「役に立つか立たないか」という視点で解説しているのが面白い。
宇宙人誘拐=金縛り、には驚いたけれど、読むと腑に落ちる。
学生の頃、石川先生の講義が毎週楽しみだったのを思い出した。
投稿元:
レビューを見る
幽霊や超能力などの現象を科学の観点から解説した本。こう書くと普通の超常現象否定本みたいだけど、ただ単に否定するのではなく「そう錯覚してしまうのは何故か?」を分かりやすく解説してくれている。社会にとって役に立つ・立たないという視点から超常現象を論じているのも新鮮だった。
投稿元:
レビューを見る
20141223読了。
超常現象を「反」と「半」と「汎」の視点で見ている。
超常現象が社会的に役に立つかどうか、という点から見ようっていうのはなかなかおもしろい。単に超常現象が存在するか否か、ではないところが面白かった。んなアホな、というところもあるが。
「反」:幽霊や迷信について、科学的に反論。「怖い幽霊」を「明るい幽霊」にし、恐怖心を利用する悪徳商法を客観的に見られるようにする。
「半」:超常現象について「半信半疑」のスタンスで検討。科学を発展させられる部分はないだろうか、という立場で論じる。
「汎」:超常現象とは創造性の延長線上にあるもの。たとえば幽霊を見たことがある人は想像力が豊かであるためアイディアを生み出す力もあるだろう、それを社会に役立てよう、という視点に立ったもの。
投稿元:
レビューを見る
一般向けに簡単に書かれている。ESPとシンクロニシティの関係、無意識と意識が同時に高まった意識状態(第四の意識状態)がESPや神秘体験に関わること、こういった意識が創造性に役立つこと、などが書かれている。科学的で中立であることを考慮しているのが読み取れた。なぜシンクロニシティやESPが起こるのかという原理については謎のまま。これは今後の課題ということか。
投稿元:
レビューを見る
たとえば幽霊について「存在するか否か」で考えるのではなく、「幽霊(という現象や概念)は役に立つかどうか」で考えるのは、非常に有益な視点だと思います。
また、存在についても、「心理的存在(個人的存在)」「社会的存在」「物理的存在」の段階を追っている点も、有益な視点だと思います。
若干、超常現象に肩入れしている印象はありますが、そのバイアスを排除して読むことができれば、示唆に富んだ本だと思います。
科学にとって「疑う」ことは非常に大切な姿勢ですが、「疑う」ことと「否定する」ことは違います。
そういった、科学の基本的な姿勢を確認できる、という意味でも、よい本だと思います。
投稿元:
レビューを見る
幽霊はいるかいないか、ではなく、役に立つかどうかという視点が有効。どのような力で動いたかより、何を訴えかけているのか。無意識が科学されると非常に役立つ。
科学は置いておいて、役立てようと。それはそうかも。
投稿元:
レビューを見る
幽霊や超能力といった類をあるかなしかではなく、実用的な角度で実際にそれが社会や生活に役立つのかを考えるというのは新しい考え方になった。現実と同時に未だ何かとスピリチュアルなことも望まれる現代、個人の認識や科学的にも必要なものの見方だと思う。