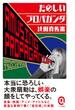プロパガンダという戦争
2016/01/12 08:25
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:人麻呂 - この投稿者のレビュー一覧を見る
第二次世界大戦にいたる過程での、ドイツ、イギリス、アメリカのプロパガンダ合戦の具体例が丁寧に引かれていて、とにかく面白い。プロパガンダというのは、それを見聞きする相手に対して影響を与えるための戦略なのだから、楽しく面白くなければならないという真理を、改めて教えられた。北朝鮮のコワモテの女性アナウンサーのような権威的な喋り方は本当はダメなわけだ。
たのしいプロパガンダ
2021/04/13 10:19
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:雄ヤギ - この投稿者のレビュー一覧を見る
日本でプロパガンダというと本書にも記述があるように、北朝鮮のものが想起され、どうしても主張が強すぎてダサいもの、自分たちはこれではだまされない、という考えになってしまう。しかし本書ではプロパガンダは主張の伝達だけでなく、楽しさを重んじるものだと指摘しており、様々な実例が示されている。
楽しい物は疑え?
2015/11/11 22:33
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:猫目太郎 - この投稿者のレビュー一覧を見る
現在も、知らないうちに行われている(と思われる)プロパガンダ。楽しい、面白い物に紛れている。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:カツ丼 - この投稿者のレビュー一覧を見る
タイトルからして毒舌。後世からみれば「狂ってやがるぜ」といった感じの行為に人を持って行くプロパガンダの「楽しさ」を指摘。
プロパガンダの力
2016/08/23 23:06
6人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オタク。 - この投稿者のレビュー一覧を見る
この本で白けたのは著者が北朝鮮に訪問して、見事に北朝鮮のプロパガンダに引っかかった事だ。ソ連仕込みの手馴れたプロパガンダを韓国人や外国人に見せる北朝鮮のそれは、どこかの誰かみたいに「何でも見てやろう!」と思ったとしても、「朝鮮語が出来る自分が実際に見聞きしたから間違いない!」となってしまうようだ。これでは他のプロパガンダをいくら批判しても意味がない。おかげで、この著者には興味がなくなった。
投稿元:
レビューを見る
<目次>
はじめに
第1章 大日本帝国の「思想戦」
第2章 欧米のプロパガンダ百年戦争
第3章 戦場化する東アジア
第4章 宗教組織のハイテク・プロパガンダ
第5章 日本国の「政策芸術」
<内容>
タイトルは「楽しい」だが、内容は非常に「怖い」。日々何事もないように見ている本、雑誌、テレビアニメ、映画…その中に政府や宗教団体の「プロパガンダ」(宣伝戦)が隠されている。著者は、戦前からの歴史を紐解きながら、具体的な例を次々と提示する。知っていることもあるが、「そうだったのか」も続く。また現代においても、”オウム真理教”や”イスラム国”も例に上がり、最後に安倍政権周りの自民党議員の「政策芸術」の話にまで及ぶ。著者は「まだ稚拙な内容だが、今後はわからない」との分析をしている。百田尚樹はともかく(でも一般の人にはそうは見えないだろうな…)「艦これ」などはいつの間にかいろいろなことが刷り込まれている可能性がある。読み終わって「ぞっ」とした。
投稿元:
レビューを見る
第一章、第二章では大日本帝国のプロパガンダ戦略やソ連やナチスのそれについて書かれていましたが内容的にはやや退屈でした。例えばナチスのゲッペルスなど当時から国民を扇動するためにはエンターテイメント性が必要だと考えていた人たちがいたのは分かったけれど、実例を読んでもあまりたのしさが伝わってきませんでした。歴史的な認識の違いですかね。日本なんかは気質としてみんなもやってるんだから自分も犠牲を払うといった集団意識こそが戦時下の忍従につながっていたのだと思うし、政府のプロパガンダも一億総玉砕なんつって国民を扇動していた部分が一番大きいのではないかと僕は考えていて、「たのしいプロパガンダ」がそんなに当時の日本で機能していたのかどうかは疑問が残るところです。まあ、大日本帝国について扱った第一章の結びでは著者自身も戦前の日本にはプロパガンダに通じた当事者が少なく本書の例に上がっている人たちもプロパガンダを統括する立場にはいなかったから結果的に説教的で退屈だったことには言及しておりますが、彼らが実権を握っていたとしても何も変わらなかったというか、むしろ「たのしくないプロパガンダ」であるにもかかわらず戦前の軍のプロパガンダって大成功していたんじゃないかと思うのです。
第三章の東アジア、四章の宗教(主にオウムとイスラム国)、五章の現代日本におけるプロパガンダについては北朝鮮の国営アイドルグループ「モランポン楽団」や中国の人民解放軍がリリースした「抗日ゲーム」など挙げられている実例がなかなか興味深く面白く読みました。「萌えミリ」やイスラム国の動画配信などは自分も思うところがあったので、挙げられていて良かったです。
気になった点は『右傾エンタメ』について書かれているところで『永遠の0』や『紺碧の艦隊』が例に出ていましたが、それに対して宮崎アニメの『風立ちぬ』は『永遠のゼロ』と同年公開だったのにも関わらず『右傾エンタメ』と批判されることは少ないと作者は書いていて、理由として監督がリベラルだからとか作品論的にどうとか述べているが、いやいや作品の本質はともかくとして韓国あたりで右翼映画として扱われて公開中止までなってましたやん。そのことに触れないで「本書の目的は宮崎論ではないため、ここでは風立ちぬが右傾アニメではないと確認するだけで十分」とか言われても不十分と言わざるを得ないです。それでは自分の論理にそぐわない情報は遮断して都合のいいように操ろうとする著者がまさに気をつけろと言っているプロパガンダと本質が一緒になってしまうのでは。
他にも詰めが甘いなと思う部分は散見されてオウムの勧誘のために制作されたアニメについて書かれている箇所では「オウムでは、出家信者にその技能を活かす役割を与えたともいうから、アニメに関わった経験を持つ者たちが制作したのではないかと思われる」という個所があるけれどこれはまさにその通りであることが村上春樹の『アンダーグラウンド』で該当する信者の口から語られており、そのぐらいの裏を取ってから出版しても良いのではと思ったり、そもそもオウムのアニメのクオリティー云々を書きながら幸福の科学についていっさい触れていないのも���自然で、新宗教のアニメ作品について書くならあっちのが断然すごいのだからそこには触れるべきだったのではないかと思いました。
投稿元:
レビューを見る
四章までは面白かったが、五章は著者の思想が香る『たのしいプロパガンダ実践編』といった印象だった。「ここまで来ると生臭さは拭えない。」
投稿元:
レビューを見る
過去から現代に至るまでのプロパガンダについて、本作では主にエンターテイメント性の高い「楽しいプロパガンダ」を紹介している、ちなみに本作でのプロパガンダの定義は以下のとおり。
”政治的な意図に基づき、相手の思考や行動に(しばしば相手の意思を尊重せずして)影響を与えようとする組織的な宣伝活動”
戦前の日本軍やナチスドイツ、そして現代でも北朝鮮やイスラム国が、娯楽と絡めたプロパガンダを行っている。中でも印象的だったのは、ナチスが1936年のベルリンオリンピックを、国威発揚のために上手く利用した事だ。もし日本も1940年の東京オリンピックを返上していなければ、その後の戦況は違っていたのかも知れない。
今思えば過去のプロパガンダなんて少し滑稽に見えるが、現代の我が国においても、『永遠の0』『艦これ』『ガルパン』などなど、知らず知らずうちに右傾化に誘導されているのかも。
投稿元:
レビューを見る
「ー」
思ったほど面白くない。
右傾エンタメという言葉は便利。
そもそも政治的意図が存在しない行動や言動が世の中に存在するのか疑問。すべてにはなんらかの政治的意図があるのではないか。ピカソのゲルニカは左傾エンタメと著者は言うのだろうか。
投稿元:
レビューを見る
いかに国民の精神を鼓舞するプロパガンダが大切だからといって、上から押し付けていたのではいけない。むしろ、国民が自発的に協力したくなるように仕向けなければならない。そのためには娯楽の活用こそ必要だ。これが清水盛明(陸軍新聞班)の考えであり、また陸軍の総力戦研究の到達点でもあった。(p.18)
考えようによっては、辺境の孤島などどうでもいいともいえる。厖大な国防費をかけてまで、維持・管理する意味があるのかという批判も生じるかもしれない。ただ、国民の間に「独島はわが領土である」という意識を強く浸透させておけば、このような批判を未然に防ぐことができる。ひいては、韓国政府の政策を円滑に進める一助ともなるわけだ。
北朝鮮に比べ、韓国のプロパガンダはあまり目立たない。ただ、目立たないことは存在しないことを意味しない。むしろ、より巧みに自然に浸透させているともいえる。長きにわたって北朝鮮と対立してきた韓国である。同国のプロパガンダの蓄えも、決して侮ってはならないだろう。(pp.118-9)
本書では防衛省・自衛隊の例ばかりをとりあげたが、クールジャパンのコンテンツは「ゆるキャラ」などの形であらゆる官公庁で用いられている。こうしたものが「製作芸術」の名のもとに統合され、政府のプロパガンダに利用されてしまう可能性はゼロではない。(中略)プロパガンダという「毒ガス」は一度発生するとたいへん厄介である。今我々の目の前にないからといって、これに警戒しないでいいという道理はない。(p.210)
投稿元:
レビューを見る
"ここ数年で生まれた「右傾エンタメ」や「萌えミリ」や「政策芸術」などの言葉は、新たなる「楽しいプロパガンダ」の予兆ではないのだろうか"p.4
という問題提起に始まって,ナチスや共産主義,軍国日本のプロパガンダの歴史をたどり,知らず知らずのうちに軍事や戦争に抵抗がなくなっていく国民の意識に目を向ける。戦後の日本に関しては,昔から子供たち戦記ものに熱中してたりしたわけで,筆者が言うように近年特にってわけでもないような気も。
「萌えミリ」の例として,『ガルパン』を大きめに扱って「楽しいプロパガンダ」への警鐘を鳴らしている。
作品自体はともかく自衛隊とコラボした数々のイベントに警戒を向けている。北海道での声優たちとの90式体験乗車,聖地大洗での10式展示などのイベントを挙げて,"やはり現実と虚構の混同が見られることがわかる。…作中の戦車は「スポーツの道具」であって、現実の兵器である戦車とは形状こそ似ていても直接的な関係はない。…にもかかわらず、作中のために現実の兵器にほかならない自衛隊の戦車を活用し、自衛隊の広報にも協力している"(p.199)と憂慮。
投稿元:
レビューを見る
読んでて楽しいです。タイトルの通り。大衆扇動について考えさせられる。民主主義の根本を揺らがせている。
投稿元:
レビューを見る
戦前の日本、欧米、東アジア、宗教組織のプロパガンダが具体例を豊富に挙げて紹介されてある。
それらは自分には関係ないと思うことも可能だろう。
しかし、自民党若手国会議員たちの勉強会「文化芸術懇話会」で立案された「政策芸術」には危険な匂いがプンプンする。
未来の「楽しいプロパガンダ」を防ぐために、過去の「楽しいプロパガンダ」を学び、その構造を熟知しなければならない。
いかに民衆は扇動され、また扇動したのか。現代の社会に当てはめなければならない。
さらっと読めたが、この視点を持つことは非常に大切だと思った。
投稿元:
レビューを見る
古今東西様々なプロパガンダが紹介されており、事例を読むだけでも楽しい。
楽しみつつも、強制的で退屈なプロパガンダは恐れる必要はないが、『楽しい』プロパガンダ−アイドルやアニメ、ゲームなどの娯楽にこそ–に注意を払う必要がある。萌えミリなどはその典型例だし、本の中にもある、自民党若手国会議員の勉強会で議論されているらしい『政策芸術』とやらも悪用されないよう注意しなければならないのだけれど、本当に上手な人が娯楽に思想を忍ばせた時に自分は気付けるか自信がないのも事実。
歴史を参照し、思考実験をすること。警戒心を持ちつつも極端になり過ぎないこと。筆者がプロパガンダを客観的に記載しているように、俯瞰の意識を持ちつつもこれからも政治や文化、芸術、娯楽に積極的に付き合っていきたい。