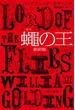1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:飛行白秋男 - この投稿者のレビュー一覧を見る
人生というか、人間の本質というか、きれいごとではないギリギリの状況でどう生きるか。
大人はいない、経験の浅い少年たちはどうふるまうのか。
こういう書物のことを名作、名著というのですねえ。
読まないともったいないです。損ですよ。1100円です。
小さなころに読んだ「十五少年漂流記」に出てくる少年たちはみんな良い子だった気がする
2019/02/07 22:35
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
小さなころに読んだ「十五少年漂流記」に出てくる少年たちはみんな良い子だった気がする。同じようなシチュエーションに置かれたこの少年たちの行動はダークだ。でも、あの立場に置かれたらと仮定するとこの小説に出てくる少年たちの行動の方に真実味を感じる
その後が気になるから★4
2023/08/16 00:22
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:恵恵恵 - この投稿者のレビュー一覧を見る
あざの子の行方とジャックとかは最後残ったのか気になる
ピギーかわいそう
眼鏡民ひとりて
双子かわいそう
ラルフはちょっと大人だけどこだわりすぎでもあった。まあ言いたいことはわかるって感じ。分かってもらえないから執拗にこだわっちゃった感じ。
アニメ化してほしい。
岩城とかちょっと想像できなかった。
島ってそんな大きいの?無人島て豚とか生息できるの?って感じ。
読みやすい、わかりやすい
2018/05/31 23:45
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:wanko - この投稿者のレビュー一覧を見る
英語の本を購入して挑戦してみましたが、難しかったので、日本語のこちらの本を購入しました。読みやすく、わかりやすいです。本を読むのがあまり得意ではないですが、こちらは読みやすいです。どきどきしながら日々読んでいます。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ゲイリーゲイリー - この投稿者のレビュー一覧を見る
少年たちの内なる残虐性、狂気というものが徐々に発露していく描写がおぞましかった。
本作の主人公ラルフをはじめとする何人かの少年たちは、それに抵抗し理性を保とうとするものの、
狂気や暴力の前では理性など無力だと思い知られる。
本作は寓話性や抽象的な要素が多く含まれており、それ故に我々の世界で起こるあらゆることのメタファーとしても読み取れる。
集団として標的を見つけることで、異様な興奮状態に陥り嬉々として攻撃する描写などは、現代のいじめそのもの。
ジャックがラルフに恨みを持つことで、分断に拍車がかかっていく過程は人種問題やヘイトクライムを想起せずにいられない。
本作の舞台となる無人島は社会の縮図としてもとらえることが可能であろう。
いつの時代も我々に必要なのは、槍による武装ではなく、
ほら貝と眼鏡を用いた理性的な対話と団結なのだと再認識させられた。
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ミチ - この投稿者のレビュー一覧を見る
こどもだけが無人島生活をする小説です。ファンタジー小説が好きな方むけです。丁寧な翻訳でわかりやすく読めます。
投稿元:
レビューを見る
恐ろしい小説である。ただ、ほんとうに恐ろしいのは、この作品をたんなる小説として切り捨てることができないからであろう。物語の舞台は無人島で、ある日飛行機事故により少年たちが漂着し共同生活が始まる。ルールなどを定めてはじめのうちはうまくやってゆくが、次第に派閥が生まれ諍いが生じついには殺戮まで起こってしまう。しかし、コレがフィクションであると誰が言い切れるであろうか。人間の本質は、やはり「野蛮人」の側にあるのではないか。スペインの古代遺跡からは、人類最古の殺人の痕とみられる化石が見つかっているという。文明化するよりもはるかに先に、人類は殺人の快楽を手に入れたのである。理性的なピギーやラルフが攻撃される姿は見るに堪えないが、考えてみれば現代社会だっておなじで、道理よりも伝統とか雰囲気とかを重んじる光景はまま見られる。恐ろしいことに、時の総理大臣だって国会で平然とウソをつき、公文書は改竄され、この国の民主主義は危機的な状況にあるというのに、いまだに熱烈に支持し続ける人々が大勢いる。ピギーではなく、みんなジャックのように生きたいのである。難しいことは考えず、とにかく自分たちが良ければそれで満足してしまう。つまり、恐ろしいのは人間そのものなのだ。そういう本質を的確に描き出した作品として、この先も永遠に読み継がれることを願いたい。
投稿元:
レビューを見る
ウィリアム・ゴールディングの代表作が新訳で登場。
まだ若い頃に新潮文庫だったかで1度読んだことがあるので、かなり経ってから再読したことになる。
『果たして子供とはそんなに純粋無垢なものか?』というのは、自分の子供時代をよ〜く思い出してみれば結論が出ることかと思うが、閉鎖空間に閉じ込められた子供たちが狂気に駆られて行く様はけっこうなホラー。そういえば最初に読んだ時も、寓話というよりホラーとして読んでいたなぁ……というところまで思い出した。
投稿元:
レビューを見る
性悪説をこれでもかと描写した作品。無人島で誰の助けも期待できない環境で、少年たちが狂気に飲み込まれていく。
登場人物が酸いも甘いも噛み分けた大人ではなく、まだまだ知識も経験も足りない純粋な子供だということに人間の本質が表れているような気がして、より話の展開が生々しく感じられた。
訳者あとがきを読むことで深く物語を楽しめたが、それを読む前から、最後の将校の「イギリスの子供なら」というセリフに作者の皮肉が強く込められていることが伝わった。
あとがきにも書いている通り、様々な捉え方のできる読み応えのある作品なので、また読み直したい。
投稿元:
レビューを見る
蠅の王
ディストピア小説が好きなので読んでみた。ぶっちゃけ言ってもう少し悲惨で血なまぐさいラストを期待していたので少し残念。解説には、ホロコーストを目の当たりにした筆者が人間の根底にある野蛮さを無人島×子供という環境であぶりだしたかったと書いてあったが、その目的自体は達成しているものの、なんだかほかの同様の作品とあまり変わらず、独自性が感じられなかった。
投稿元:
レビューを見る
ただの子供向けの冒険サバイバル物語と思ってはいけません。
文明社会で育った人間達の、内面に潜む<獣>を著した、非常に示唆に富んだ一冊です。
無人島に取り残された少年たちが、ルールを作って集団でサバイバルをしようとしたのに、予想通り対立していくお話。ノーベル文学賞作家ゴールディングの長編小説デビュー作。
疎開先に向かう飛行機が墜落、少年たちは無人島にたどり着いた。年長のラルフは、聖歌隊を率いるジャックらとともに、サバイバルを試みる。誇りある英国人としてルールを作り集団生活を試みるラルフ。しかし、焚き火の管理や狩りのやり方について、次第に衝突していく。さらに、島に潜む<獣>の存在に、彼らの生活は破綻していく。
ストーリーのポイントは、登場人物が子供だけ、ということだ。
大人がいないということは、体力や知識のみならず、分別のある者もいないということだ。
基本的に両家の出身の彼らは(イギリスの伝統に則り)少年といえども規律を重んじる文明人としての自覚を持っている。
しかし、大人=ルールのいない中で、彼ら自身は自らを律していかなくてはいけない。
さらに鍵となるのは無人島に潜む<獣>だ。
当初、<獣>は少年たちに(直接的に)襲いかかる危険として描かれる。
しかし、物語が進むにつれ、<獣>はより象徴的なものであることに気がつかされる。
分別のない少年集団の中で、唯一、その正体に気がつくのがサイモンだ。
ラルフ(文明人代表)とジャック(野蛮人代表)が権力争いを始める中、サイモンは皆が恐れているものの正体を見抜く。
「おまえは知っていたんだな。わたしがおまえたちの一部であることを。ごく、ごく、親密な関係にあることを!何もかもうまくいかない理由であることを。ものごとがこうでしかない理由であることを」
(p252)
サイモンは<獣>の正体が、自分たち人間の内面であることに気がついている。恐怖、混乱、焦燥、絶望の全てが、自分や仲間が他人に向けている感情であることを知っている。理性ある人(英国人)であるはずの自分が、内側に獣が潜んでいることが、最大の恐怖だ。
だが、そのサイモンの行く末が決したと同時に、少年集団の運命も大きく転換する。
自らを突き動かしているものの正体に気がつかない者は、どうなってしまうのか。
結果的に、物語は理性、というか、文明人の一人勝ちで終わる。
特に、ラストシーンは、登場人物が皆子供であることに二重の寓意をもたせている。
自らだろうと、社会だろうと、結局は内面の<獣>を方法を維持したものが、生き残ることができる、ということだ。
逆にいえば、大人ですらそれを維持できなくなったとき、具体的にいえば戦時下で、人は生きていけるのだろうか、という疑問を投げかけていると言える。
映画「美女と野獣」(Beauty and Beast)を見ながらエマ・ワトソンに見惚れるのもいいけど、骨太の「少年と獣」(Boys and Beast)なストーリーに浸るのも悪くないはず。
文明社会でサバイバルする大人にこそ、ぜひ読んでほしい一冊。
投稿元:
レビューを見る
子供は純真無垢だなんて、そんなことはない。結構残酷で考え無し。いい本だ。
まず、誰も何人いるかを気にしない。年上の子供はおチビちゃんたちの面倒を見ない。
多分、劣悪な環境下で亡くなっていく子もいるはずなんだけど、最後のラルフの発言で、殺されたのが2人、と言うところでも分かるように、ほぼ、自分のことしか考えられなくなり、狂気に近くなってる。
あげく、ボディペインティングやら獣に対する貢物やらをし始める。理性のある子供から殺されていく。
救助がきた瞬間、ピタリとその狂気が削げ落ちる瞬間の描写もよかった。
投稿元:
レビューを見る
まだ半分程度しか読んでないけど、不穏な空気が漂っていて、陳腐な表現だが、【ページをめくる手が止まらない】ってやつなのよ。
投稿元:
レビューを見る
戦争により何らかのトラブルに巻き込まれて、海の孤島にたどり着いた少年たち。
初めはリーダー格の少年ラルフを中心に、ジャック、ピギー、サイモンなど数名が協力して救出を待つかに思えたが、ラルフとジャックの対立が起きて、少年たちの輪は一気に乱れ始める…十五少年漂流記のダークサイドと呼べばいいのかもしれないが、それ以上の深みがこの作品にはある。
おそらく少年同士の対立とそれに同調する取り巻きのエスカレートする行動や、真っ当な意見を言う者もいるが、無力であるが故に無視されてしまうというは第二次大戦の国同士の対立や、ホロコーストを避けられなかった政治家の行動を彷彿とさせる。
それ以上に、エスカレートして暴力に頼り始めると登場人物は名前を失い「野蛮人」とだけ呼ばれる作者の表現手法も、自分の味方には気を使っても、対立する者は「敵」としか捉えない人間の姿を現しているように思える。
そしてなによりも「蝿の王」というタイトル。
何故「蝿の王」なのか?蝿の王が「ベルゼブブ」という悪魔の名前で、「蝿の王様」という意味である事は調べたから知っている。でも、何故この物語のタイトルが「蝿の王」なのか?
物語の中に登場する屠殺された豚の頭蓋骨が自分が蝿の王だと名乗るシーンがあるが、それは何の象徴なのか?
考えさせる謎の多い、それ故に行く通りもの読み取り方ができると思われる作品。
因みに、気づいた人も多いと思いますが眼鏡のレンズで火を起こせるとしたら、それは凸レンズのはずで、ピギーは近視ではなく、遠視ということになる。でも、ピギーは眼鏡がないと何も見えない、近視であるかのように振舞っている。ひょっとするとピギーの眼鏡は単なる虫眼鏡で、ピギーはそれがないと見えないという近視のふりをして、労働をサボっていただけかもしれません。
投稿元:
レビューを見る
海に囲まれた孤島を覆う密林で、闇の深さに怯えながら
花や果実の匂いに身じろぎする少年たち。
彼らは教師も舎監もいない寄宿舎に放り込まれた生徒であり、
または、まるで母の胎内から新しく――かなり暴力的に――
生まれ出ようともがく新生児のようにも映る、が……。
昔、ハリー・フック監督による映画を観て、
嫌な話だなぁ……(笑)と思っていた。
その後、夫の実家の書棚からサルベージした新潮文庫版を
積ん読状態にしたまま、
去年、この新訳が出ていたと知って購入、読了。
飛行機が無人島に不時着し、
少年たちだけで救助を待ちながら暮らすことになり、
島の近くを通る船に気づいてもらうために
焚き火で煙を上げるのだが、
その件だけからでも様々な悶着が引き起こされる。
文明の利器である「火」をコントロール出来るのが
一人前の人間で、
出来なければ獣と同じである……
リーダーのラルフはそんな風に考えるけれども、
事は思い通りに運ばない。
物事を見たまま噛み砕いて理解するピギーと
鋭い直感の持ち主であるサイモンは、
賢さ故に蝿の王ベルゼブブの生贄にされたかのようで、
憐れ。
少年たちにこびり付いた垢や汚れは洗えば落ちるし、
切り傷はいつか塞がるだろう、けれども、
文明社会に復帰したところで、
彼らは楽園のような地獄の記憶を拭えず、
生涯苦しみ続けるに違いない。
嫌な話だ(しかし、面白い)。