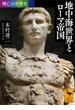古代ローマにおける多彩な人々とそのドラマを生き生きと描いた歴史物語です!
2020/03/02 11:04
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、古代のローマの歴史についてその詳細を余すところなく解説した画期的な歴史書です。多くの歴史学者は、古代ローマ史は、人類のあらゆる経験と知見が詰まっていると表現しています。古代ローマはそれだけ多彩な人々とそのドラマに詰まった歴史をもっていたのでしょう。同書では、「第1章 前146年の地中海世界」、「第2章 世界帝国の原像を求めて」、「第3章 イタリアの覇者ローマ S・P・Q・R」、「第4章 ハンニバルに鍛えられた人々」、「第5章 地中海の覇者」、「第6章 帝政ローマの平和」、「第7章 多神教世界帝国の出現」、「第8章 混迷と不安の世紀」、「第9章 一神教世界への大転換」、「第10章 文明の変貌と帝国の終焉」という構成で、古代ローマの長きにわたる歴史を追っていきます!
ローマ帝国の通史
2020/07/27 06:45
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:福原京だるま - この投稿者のレビュー一覧を見る
ローマ帝国の建国から滅亡(西ローマの方)までの通史がわかりやすくまとめられている。紙幅の問題で記述が薄い部分もあるがとても長い時代を扱っているので仕方がない
はじめてローマ史を学ぶ人に最適
2020/06/12 19:16
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ワッフル - この投稿者のレビュー一覧を見る
古代オリエントのアッシリア、アケメネス、アレクサンドロスなどの巨大帝国から始まり、古代ローマに入る。特にカミッルスなどにも頁が裂かれなかなか興味深かった。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:y - この投稿者のレビュー一覧を見る
ローマ史の要約でしかなく、ローマと地中海世界との関わり、という視点は殆ど感じられなかった。ローマ人の宗教観から、「ローマ精神、ローマ人気質」のようなものがもっと描けるのではないか。
語の選択、使い方にも疑問が多い。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぽぽ - この投稿者のレビュー一覧を見る
ローマ帝国時代の話を聞くと、こんな昔なのにもかかわらず、こんなにも発展して政治的にも成熟していたのかと驚きます。
投稿元:
レビューを見る
塩野七生のローマ人の物語はリアルタイムで読んだので、ずいぶん経ってからのローマ史復習だったが五賢帝の後〜ローマ滅亡までがわかりやすく面白かった。コンパクトでわかりやすく、登場人物も理解できた。
ローマ人の物語は全巻通じて面白いけど五賢帝までが特に面白かった記憶がある。
投稿元:
レビューを見る
古代ローマの成立から周辺国家、強国カルタゴ等を征服し地中海を中心としたヨーロッパの大国となる歴史が、英雄たちを中心に面白く書いてある。ローマ2000年を支えたものが何であったかをひとことで言うのは難しいし、読んでも分からなかった。▼カエサルなど多くの素晴らしい人物も生み出した。王政、共和制、帝政、など国は形を変えて生きながらえる。しかし元老院制や帝政の一時期を除いて周辺国とは戦争が絶えず、国内において特に帝政時は皇帝の暗殺が頻繁に行われる不安定な世であることも知った。日本の江戸時代の平和とは遠い世界であることも痛感した。それでもローマが長く生き残ったのはなぜか、という疑問がやはり残る……。
投稿元:
レビューを見る
ローマ帝国史をコンパクトにまとめた一冊。
単行本の時に読んだが、文庫化したのを機に再読。やはり非常に面白い。
たぶん、単行本時代に本書を読んだのが一番最初のローマ帝国本だと思うのだが、それから何冊か類書を読んだためか、初読時よりさらに面白く読めた。
そのうち再々読する予定。
投稿元:
レビューを見る
わかっていたことだけど、『ローマ帝国』について一冊で何かを述べることが出来る訳無いのは仕方ないよね。
それでも、通史でもやはり面白さは伝わるし、新たな発見もある。
三頭政治のクラッスス、お前どっから出てきたんや?つうか誰や?って疑問について、一部なりとも回答が得られた感あり。
そして、どうしてもローマ帝国の終焉として受けとってしまう時期についても、地方には豊かな部分もあり、新しい時代の序章でもある。そこら辺は気をつけたいなと。
投稿元:
レビューを見る
人類の経験のすべてが詰まっていると言われる古代ローマ史について。
以下、本書より。
【ローマ人の特異性】
なぜローマ人だけがあの巨大な帝国を築く事ができたのだろうか。
異邦人であるポリュビオスだけではなく、古代でも現代でも誰もが興味をそそられる問題である。
ローマ人とはどういう人々であるのか、という問いかけは避けようもない。
住民の数ではヒスパニア人より少なく、活力ならばガリア人より弱く、多才さではカルタゴ人に譲り、学芸ではギリシャ人に及ばない。
そう指摘したのはキケロ。
しかし、神々への敬虔さと慎みではいかなる人々にも引けを取らない、と述べたのもキケロ。
万物は神々の力によって支配されている。
それはどうしようもない宿命としてローマ人の意識の底に潜んでいた。
それら神々の怒りに触れない為には、ひたすら祭儀を怠らない事である。
この事はギリシャ人ポリュビオスの目にも異様に映っていたらしい。
この歴史家はこう語っている。
思えば、ローマは宗教によって他の国々に勝るのではないだろうか。
他国でなら迷信とされる事でも、ローマでは国家統合の要をなすものである。
いずれの宗教行事も壮麗に執り行われ、公人としても私人としても市民の生活をはっきりと規制している。
こうした役割において宗教を凌ぐものはない。
投稿元:
レビューを見る
ローマ帝国史について、一冊で振り返るには最適の書。塩野七生さんのローマのシリーズにて、細かく読み進めていたが、久しぶりにこの一冊で振り返ることが出来た。
地中海史は、奥が深い
投稿元:
レビューを見る
塩野七生氏の「ローマ人の物語」で、ローマ史に詳しく触れた。
本書でその復習になる。
膨大な時間と領域をコンパクトにまとめてあるが、
一冊では少し物足りない感じ。
ただし、要所はしっかりとおさえてある。
投稿元:
レビューを見る
本書はローマ帝国史の概説本だが、定石通りの建国神話からではなく、なぜかいきなりローマ軍総督小スキピオによるカルタゴ制圧の場面で始まる。これは著者の問題意識の視座を如実に反映したものだ。カルタゴやギリシャのコリント崩壊など、ローマがかくも徹底的に敵国を破壊しなければならなかった理由は何か?ともすればローマという国家の体質のうちにあるなにものかが否応なくそうさせるのではないだろうか?これが本書を貫く著者の問題提起である。
その遠因としてまず著者が挙げるのが、元老院という初期ローマを特徴付ける政治体制だ。共和政を構成する元老たちが、父祖の物語を題材に民衆を扇動して戦闘へと焚き付けるファシズムの温床であったとする逆説だ。先行するアッシリア、ペルシャ、マケドニアの諸帝国では単一であった王者がここローマでは複数おり、寡頭政治の中核を成しつつそれぞれが王者としての威厳を備え愛国精神を鼓舞する。その根底で作用したのが、ローマ人に受け継がれる「父祖の遺風」、即ちハンニバルのような敵将といえど優秀な者を称揚し、失敗に寛容だが裏切りや臆病者を強く非難する伝統的精神だという。
だとするなら、真っ先にその精神を体現したのがユリウス=カエサルだということになるのだろう。異民族ガリア人らに対する強圧さと、同胞ローマ人に対する寛容さを併せ持ち、地中海・小アジア世界の征服に果断に突き進んだカエサルこそ、「父祖の遺風」の鋳型としてローマ世界の人々の意識に最初に刻みつけられた存在だった。しかしその一方で独裁者との糾弾を受け暗殺の憂き目にあうのだが、この轍を踏むまいと元老たちとの調和の上に統治を行なった初代皇帝アウグストゥスは「権力なき権威」のロールモデルとして、その後のローマ統治のあり方を規定していくことになる。ここで重要なのは、「権威」の基底においてローマ伝統の神々に対する「敬虔」な態度が要求されたことだと著者はいう。多種多様な民族を統治する帝国の為政者には各民族の神々を蔑ろにすることは許されず、五賢帝の一人ハドリアヌスがパンテオン建造の際にそうしたように、必然的に自由で多神教的な宗教観を重んじることとなる。
しかし、皇帝が軍事的な「権力」を常態的に頼みにした「三世紀の危機」以降の外交・経済的混乱の中で、ユダヤ教・キリスト教の一神教が人々の不安を確実に掬い上げることに成功し、迫害に耐えながら遂に「ミラノ勅令」で国教としての立場を確立する。著者はこの多神教から一神教へのスムーズな展開を、犠牲の献上による神々からの救済を崇める古代地中海の精神世界に、神の子イエス・キリストの自己犠牲の構図がうまく合致したからだというが、だとすればローマ古来の「父祖の遺風」や「権力なき権威」はこのキリスト教公認により突き崩された、ということになるのだろうか。
本書全般に言えることだが、特にこの「父祖の遺風」の概念定義が曖昧なまま筆が進められているため、色んなところで都合よくこの概念が使われてしまっている。そのため、自ら冒頭で提起した「ローマの容赦ない攻撃性」に対する回答も明確な輪郭がないままぼやけてしまい、本書の軸も消失してしまっているような気がする。ローマ史を扱った書籍は数多あり、それでもなお知見を世に問おうとするならばそこには新奇性の強い視点が必要になる。本書では問題提起には独自性があり期待が持てたが、残念ながらその後の展開でその問題に首尾良く答えを提示していく、という流れにはなっていないように感じた。
投稿元:
レビューを見る
ローマ人の物語を読破していたので、もっとスムーズに読めるかと思いきや、忘れていることも多く、苦戦した。
投稿元:
レビューを見る
講談社学術文庫
本村凌二 「 地中海世界とローマ帝国 」
ローマ帝国史の本。共和制ファシズム と ハンニバルとの戦いにより、ローマが地中海世界の覇権をとり、平和、政治不安、東西分裂、異民族侵入、一神教へ転換を経て、文明が変貌し 帝国が終焉したという流れ
皇帝を中心に多くの人物を取り上げているが、カエサルとアウグストゥスは別格なページ数の多さ。「あとがき」で取り上げた三人(マルクスアントニウス、ドミティアヌス帝、アンブロシウス)も興味深い
ローマ帝国の始まりと終わりについては、著者の特徴が出ているように思う。ローマ帝国の始まりであるカルタゴ壊滅を ローマ人の「父祖の遺風」の精神から論じ、新しい時代の到来により ローマ帝国が終わったという論調。
帝国だけでなく、人間の営みは全て従来の体制と新しい時代のアンバランスから常に変化を強いられることを実感した
「ローマの道は〜軍道である。戦いに勝っては領土を併合し、個々の都市と同盟関係を結ぶ」