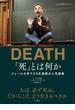読むのに半年かかりましたが、後半は捲ることを厭わなかったです
2021/01/11 22:33
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:わに♂ - この投稿者のレビュー一覧を見る
「死」 直面していないけど、誰もが訪れることを知っている。
「死」 向かって生きているけど、それがゴールではない。
「死」 恐いけど死ねば恐いとも思わない。
「死」 生きているのなら考えて損はない。
どうせ死ぬなら何もしなくてもいいか。
好きなことして死ねばいいか。
では好きなこととは何か。
それが今すぐにできることか。
「遠い」
それが遠くなら行かなくてもいいか。
では遠くに行かないならすることは何か。
それなりに生きてもいいか。
どうせ生きるなら何かしてみようか。
内容が薄く期待外れ。全く答えは得られませんでした。
2020/02/06 00:05
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Sin Kamisiro - この投稿者のレビュー一覧を見る
タイトル・表紙・始めの文体を見て買いましたが、よく読んでいくと、結論も回答も出てこず 仮定と想像のお話ばかり…
これが本当に世界一流大学講義なのかと幻滅しました…
後から私だけなのかと気になり、他の方のAmazonレビューを見てみましたが、やはり同じ感想を持つ人がわりといました。
"なにか概観状況をのべているだけで本人は確信んがないのか自分の言葉の責任が取れないのかなにかはぐらかされているようとても最後まで読む気持ちになりませんタイトルは魅了てきですねタイトルで幻惑します。"
"深みが無い - タイトルや広告の割に、深みが無い本。この程度の内容がアメリカの一流大学の有名講義だという事に驚いた。アカデミックの世界ではエビデンス(実例)が必要ということなのだろうが、そこに限界を見た。"
上記のレビューに全くもって同意で、買う価値はありませんでした。
ちなみに縮尺版であることに異論を唱えるレビュワーさんも多いですが、そこは私は特にありませんでした。なぜなら省かれていた第2項〜第7項はWeb 上にPDF無料公開されていたからです。
「なんだこりゃ?」
2020/07/29 12:08
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:FA - この投稿者のレビュー一覧を見る
私たちに魂があるのか?
私たちのほとんどが何らかの非物質的な魂が存在すると信じていることは確実だ。
私が思うに、欧米の人は非科学的と言われても仕方がないものを信じていたりして、ビックリする。日本人よりも霊とか魂を信じているようだ。バカにする気はないが、見てもいないものを信じることはできないという姿勢である。出てきたら即、信じてしまうと思う。
この作品の帯に、死期が迫った人が、受けたいと願った人気講義云々と書かれてあった。所詮、宣伝文句なのだか、読んでみて、はっきり言って、「なんだこりゃ?」私に死期が迫っていたらこんな講義、死んでも嫌だ。「死」なんて人によって違うものだから、自分で考えてくれって話だと思う。実際に、内容は「死んでしまった方が楽だ」というのは正しいのか、というのをはじめ、未熟な禅問答に感じた。
結論、私には、トンデモ本だった。
投稿元:
レビューを見る
読書記録です。まだの人は読まないでね。
「イェール大学で23年連続の人気講義」なので、「章」ではなく「第1講(義)~9講(義)」になっています。本になったからといって一気に読んでも、難しすぎて理解不能!講義と講義の間にスパンがあることで、人気講義になりえる内容なのかな~と思いました。
「各講義」の後、じっくり時間をかけて自分と向き合い、考える時間が必要なんだと思います。教授から出された命題や疑問に対して、自分なりに考えて答えを探し出す。でも、次の講義でまた新しい命題や疑問が繰り出される…その課程で、それぞれの死に対する向き合い方が見えてくるのかなぁ、と。
若い世代の生徒が、次回の講義ではこういう答えを突きつけて論破してやる!と意気込んだのに、次回の講義でしょっぱなから「うーん、間違いじゃないけどなぁ」「じゃあ、こうだったらどうなる?」と翻弄される姿が目に浮かびます(笑)
投稿元:
レビューを見る
問いの嵐。死ぬことは悪いのか。なぜ死は怖いのか。どの瞬間からが死か。自ら死を選べるのか。
原体験は祖母だった。最後は植物状態だった。果たしてあのときの祖母は生きていたのだろうか。
再読するときが来る。
#death #死とは何か #読書記録2018 #読書記録 #再読候補
投稿元:
レビューを見る
この本は哲学の本。小職は完全版を読んだのだが、完全版では無いこの本の構成が妥当。文章が冗長すぎて読む気が半減する。
投稿元:
レビューを見る
人は必ず死ぬ。だからこそ、どう生きるべきか?
「死」を深く考える。
また、近いうちに再読するだろう。
投稿元:
レビューを見る
死ぬとどうなるのか、死ぬことは果たして悪いことなのか、不死が人を幸せにしないのはなぜが、などを丁寧に考察していく分かりやすい講義だった。
納得できる大部分と、納得できない少しの部分があって、とても興味深く読めたけれども、本を読んだだけで実際に講義を受けたわけではない私としては、これで死の捉え方が変わるとか生き方が変わるみたいな影響は受けなかった。
ところで先日、家に殺人鬼が入ってきてもう次の瞬間殺される…!という夢を見たのだが、そのときに感じた「私はまだ生きたい」という感情が今まで感じたことがないほどに強いものだったことに衝撃を受けた。
私はまだ若いからもう少し生きたいと思うのは当然なのかもしれないが、ならばいつになれば死を受け入れられるのか、そんな心情の変化が起こりうるのか、というのが気になった。
そしてこう言いながらも私はいつか死ぬことをたぶん本当の意味では理解できていないのではないかと思う。きっと誰でも死は目前に迫らないと(または身近な人に降りかからないと)実際にすぐそこにあるとは感じられないのではないだろうか。
でもそれだからこんな些細なことに悩みながら日々を過ごせるわけで、それが人間らしさなのかもしれないなと思った。
投稿元:
レビューを見る
[死]を「存在」や「定義」、「感情・印象」から紐解き、(あくまでも)哲学としての観点で死を考える本。
・人は死は避けれないと思っているが、
本当に死ぬとは思っていない。
・死は悪いと思う正体は[恐れ]ではなく[剥奪]
・死後の無限時間と生まれる前の無限時間は一緒なはず
なのに、残念に思う正体は何か
身近にあるようでないテーマについて、自分の新たな引き出しを増やせる本。
投稿元:
レビューを見る
作者が冒頭に述べている通りあくまでもこの本は哲学書である。つまり、「死」にまつわる作者の考えがひたすら展開されるだけである。
客観的事実も実験も何もない。
しかし、この巡らされる思索が深いゆえに読む者が持つ「死」についての漠然とした靄を少しずつ晴らしていってくれる。
絶対的真実などはなく、あくまでも作者の考える「死」の姿ではあるが、それを共感して捉えることによって「生」の短さ、貴重さを再認識できる一冊となっている。
大学の講義をそのまま書物化したようなので、講義のテーマごとにまとめられているし、作者の視線にはユーモアも感じられてて考えさせられるところもありながらも楽しく読めた。
若いときに読めたらなお良かったかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
日本版は前半部分が省略されているようなので、English Editionを読めるようになろうなろういつかなろう…。
投稿元:
レビューを見る
死についての哲学的な考察。死とは何か、についての明確な解答は出ない。あくまでも、自分で考えることを促す構成になっている。
死について考えるべき点を知れるいい本。
投稿元:
レビューを見る
良書。
だと思うが、読みたい本ではなかったので、拾い読み。
思ったより哲学。理屈。知りたい事は書かれていない。よく読めば書かれているのかも知れない。
哲学にしては、解り易い。難しい言葉は使われていない。
投稿元:
レビューを見る
死はそんなに悪い事じゃないっていう話。
良く言うとわかりやすいけど、悪く言うと長くて退屈。
読んでる間、何度も考え方が西洋的だなぁと思った。
投稿元:
レビューを見る
「死が悪いのは得られたはずの機会が剥奪されるから」が著者の基本の見解。来世も復活も死者の魂もなしという前提で「死」について、本人(遺族や社会でなく)にとって何が良いことなのかを基準に、死への恐れの正体、不死の功罪、自殺の損得など様々なテーマをあらゆる角度から描きつくす感がある。特に反対意見や反論には手数をかけて入念に行い、あたかも独りディベートのよう。イェール大の人気講義というのもうなずける。活字も大きく訳も読みやすいのだが14時間以上かかってしまった。テーマと結論まで見える目次は読み返しに便利そう。