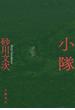「今この時」の小説
2021/04/10 07:57
5人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る
第164回芥川賞候補作。
この回の芥川賞を授賞したのは宇佐見りんさんの『推し、燃ゆ』だったが、その他の候補作も極めてレベルの高い作品が多かった。
元自衛官の砂川文次さんのこの中編も評価が高かった。
特に川上弘美選考委員は「一番に推そうと思い、選考の場に臨」んだという。
それは「突然の理不尽がふりかかった時、人はどのように苦しみ怒り耐え放心しそれでも生きつづけるかを示すために」、この小説が川上さんを揺さぶったからだ。
小説は、北海道にロシア軍が上陸し、日本が第二次大戦後初の「地上戦」を経験することになった様を、自衛隊員である安達の目を通して描かれる「戦争小説」だ。
元自衛官とはいえ砂川さんも「戦争」を経験したわけではない。だから、この作品はもっぱら砂川さんの作った「戦争」である。
ひと昔前であれば、筒井康隆さんが書いたかもしれない世界だが、ここには筒井さんのような毒も笑いもない。あるのは、けだるいような日常から「戦争」という極限の世界に振られるさまだ。
川上さんは、この作品には「コロナ禍」という言葉もその影も出てこないが、極めて「今この時」を感じる作品だと書いている。
確かに私たちはある日突然コロナ禍に巻き込まれた。その姿はこの作品に登場する自衛官によく似ている。
とすれば、この作品が「今この時」のものだということがよくわかる。
バトルオーバー北海道の忠実なフォロワー
2024/03/01 18:42
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:HA - この投稿者のレビュー一覧を見る
バトルオーバー北海道を陸自初級幹部の視点と知識でデコレーションして小説にしてみましたという趣きで、それ以上でも以下でもない。
戦場描写や心理描写はなかなか悪くないものの、戦闘描写や背景となる戦役描写にはリアルさ皆無。そんなところもバトルオーバー北海道そのまんま。
投稿元:
レビューを見る
【「戦場」の現実を描いた芥川賞候補作】第164回芥川賞候補作。北海道にロシア軍が上陸! 元自衛官の作家が、日本人の知らない「戦場」をリアルに描いた衝撃作。
投稿元:
レビューを見る
文体や心理描写の妙なリアリティのせいか、全体を通じた緊迫感に終始圧倒されっぱなしだった。恐怖なのか不安なのか分からないなんとも言えない読後感は初めての感覚かも。
投稿元:
レビューを見る
釧路方面に上陸して侵攻するロシア軍を陸上自衛隊が迎え撃つ。スマホやコンビニが当たり前にある現代の日常の隣で、「西部戦線異常なし」の第一次世界大戦時と大差の無い白兵戦が繰り広げられるリアルさが恐ろしい。見慣れない熟語が多用されることには好みは別れると思うが、硬質な文体と具体的な描写に引き込まれる。
信念や思想的な後ろ盾をもたず、「有事の際に戦闘員となること」をあくまで仕事の一つとして選んだ自衛隊員が、実際の戦闘場面において最後まで闘うことができるのだろうか?と思わずにいられなかった。
投稿元:
レビューを見る
北海道にロシア軍が侵攻してくる。
連隊長以下全ての隊員にとって、初めての実戦。
迎え撃つその最前線を任される小隊長。
訓練通り淡々と戦闘は始まり、圧倒的な戦力の前に蹂躙されていく自衛隊。
その現実の姿、時間の経過を淡々と描いていく。
そして、戦闘が行われている北海道のその最前線を離れると、いつもと変わらぬ生活が営まれている。
大地震に襲われた被災地がある一方、その他の地域では通常の生活が営まれていたあの頃のように。
元自衛官である作者が描く世界はとてもリアル。
投稿元:
レビューを見る
戦争に至る経緯とかの大局を全部差し引いて、現場に入ってる情報だけで現場だけ詳細に描ききる。
そして、最後の最後に、過酷な戦場とラジオの向こうの日常を対比させて、
「生き残った」
感を最大限に表す。
その手があったか。
投稿元:
レビューを見る
作者は、元自衛官で、2014年秋頃、陸上自衛隊操縦学生であった時に書き上げた投稿作「市街戦」で、2016年の第121回文學界新人賞を受賞しデビュー「戦場のレビヤタン」が第160回(2018年下半期)芥川龍之介賞候補作、本作「小隊」が第164回(2020年下半期)芥川龍之介賞候補作となる。「ブラックボックス」で第166回(2022年上半期)芥川龍之介賞受賞。
本作は、元自衛官としての経験と知識を生かした戦闘シーンは、中々のリアリティがあり、時々血生臭いシーンには、ドキリとさせられて、戦闘の虚しさや凄惨さが浮き彫りになり、主人公安達小隊長の人間らしさもここかしこに垣間見えて、人間の生への執着にも同感するが、今の日本が、現実問題として、ロシアの軍隊と戦闘状態に入るまでの設定に展開が安易だし、航空自衛隊の援護もほぼないし、海上自衛隊の登場もないので、この面でのリアリズムに欠けるので、⭐️3個とした。
戦争の経験のない我々には、戦争がどんなものなのか、軍隊とはどういうものなのか、国防とはどう言うことなのか、生と死とは何なのか、考えさせられる。
ただし、ほぼ全編戦闘シーンの連続なので、そう言ったマニアには、テンポの良いストーリー展開は、読者をグイグイ読み進めさせる作者の力量が光る。
投稿元:
レビューを見る
まず感じたのは、専門用語のせいでよく分からない・感情移入できない部分が多かったこと。これは私の知識不足もあるので人によると思う。戦況や作戦は「これはないだろ」感もあったけど戦闘シーンはリアルすぎるほどリアルで、現代日本において日本国内で地上戦が繰り広げられるという私の中での「ありえないこと」と対比されて、読んでて頭がおかしくなりそうだった。身内に彼らと同じような立場の人がいるので他人事とは思えなかった。より一層恐ろしかった。
投稿元:
レビューを見る
ミヤゾンが言ってたけど、5.6割の力で、頑張らないと壊れちゃう。
逃げたほうは負い目を覚え、闘った側は憤る。
芥川賞狙う人はコマ送りのように細かな心理描写を入れるのだろうか。
投稿元:
レビューを見る
今現在行われているロシアとウクライナの兵士に置き換えて読んでいた。
戦わないといけないという義務感となぜ戦わないといけないんだという本能の葛藤がリアルだなと感じた。
会社の年寄りが戦争のニュースをつけっぱなしにしながら仕事をしていると言っていた。理由は、空襲警報や爆撃音の非日常感が面白いからだそうだ。
おそらくその年寄りはその非日常で苦しんでいる人の顔を想像できていない。
想像力の欠如は、こんなにも恐ろしいことを笑顔で言える人間を作り出すのかと怖くなった。
道徳の授業よりも想像力を高める授業を会社員にも学生にも受けさせてほしい。
投稿元:
レビューを見る
北海道釧路に露軍が侵攻。
自衛隊員が本当に戦う、という怖さ。
・・・そうかもしれない、そうなるかもしれない
と思ってしまうほどのリアルさに脱帽。
筆力・リズムとも抜群のセンスだ。
芥川受賞作品も読んでみようと思う。
投稿元:
レビューを見る
ロシアによるウクライナ侵略が行われている最中で読むと、リアル感が違いますね。
元自衛官である著者が描く戦闘描写はかなりリアル。もっとも、著者はヘリパイだったはずなので、陸上戦闘が専門ではなかったはずですが。
それにしても、何がリアルって、避難を求められても避難しない市民とか、これまで戦ったことがない自衛隊が戦う姿とか、そんな感じなんだろうなという気がします。
切ないというか、これまで戦ったことがないことを如実に示しているのが、訓練では負けることがないであろう小隊曹長が、実際の戦闘ではどうであったかという最後の描写。そして、初級幹部が戦闘で鍛え上げられていく描写じゃないんですかね。
こんなことが起きないことを祈ります。
投稿元:
レビューを見る
芥川賞候補ということでかなり前から図書館に予約していてようやく読んだ。戦闘シーンと人物の心境が淡々と描かれている。過去でも未来でもない現在が舞台なのがひたすら不気味だった。
投稿元:
レビューを見る
北海道に攻めてきたロシア軍をなんとか食い止めようと奮戦する小隊のお話です。作者が元自衛官ということで専門用語とその略語のオンパレードで、初めのうちこそ「え、これ何の略だっけ?」とか前ページを繰りなおしたりもしましたが、次第にそんなことはもうどうでもよくなってきて、ひたすら先へ先へと読み進みたくなります。さほど厚い本ではないので遅読の私でも2日で読みましたが、中身は濃厚です。この侵攻がその後どうなっていくのか、ぜひ読んでみたいです。