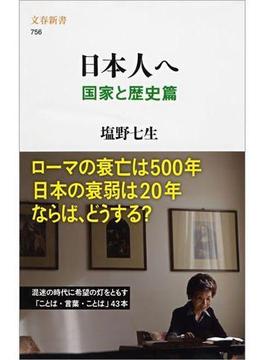日本人へ 国家と歴史篇
著者 塩野七生 (著)
わたしが慣れ親しんできたローマの皇帝たちで“夢の内閣”をつくってみたら──指導者とは、どうあるべきか。すぐれた戦略がなぜ重要か。いま日本が突き当たっている問題は、過去の歴...
日本人へ 国家と歴史篇
商品説明
わたしが慣れ親しんできたローマの皇帝たちで“夢の内閣”をつくってみたら──指導者とは、どうあるべきか。すぐれた戦略がなぜ重要か。いま日本が突き当たっている問題は、過去の歴史にすでに明確な答えがあるのだ。そのほか、小沢一郎ら日本の政治家に思うこと、日本の技術を世界にアピールする方法、執筆とワインの親密な関係、ブランド品について知っておくべきことなど、しなやかな知性があなたを鍛える、大好評『日本人へ リーダー篇』続篇。
著者紹介
塩野七生 (著)
- 略歴
- 1937年東京生まれ。学習院大学文学部哲学科卒業。「海の都の物語」でサントリー学芸賞、菊池寛賞、「わが友マキアヴェッリ」で女流文学賞、司馬遼太郎賞を受賞。2007年文化功労者に。
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
考えることを他人にまかせるな
2010/07/28 08:39
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る
NHKの大河ドラマ「龍馬伝」を面白く観ている。幕末の政治の渦のなかで、若者達が翻弄されていく姿は痛々しくもある。かなりの脚色はあるだろうが、過ぎた時代のそれはやはりドラマチックだ。
どうしてだろうと考えていたところ、本書のなかに「歴史とは、何であろうと求めてやまない、心が狭く、恐怖に駆られやすく人間関係も上手くいかず、落ちついて待つことさえも不得手な、哀れではあっても人間的ではある人々の、人間模様に過ぎない」(「滞日三題噺」)という文章で納得できた
。それはこと幕末のことだけではない。歴史がもっている「人間模様」があるから、面白いのだ。そういう側面をはずしてしまえば、ただの年表になってしまう。
そういうことを理解したうえで、塩野七生のエッセイを読むと、実は人間くさい文章だということに気づかされる。カエサルやアウグストゥスといった歴史上の人物だけでなく、小沢一郎にしても福田康夫といった現代の政治家さえもが、人間くさいのだ。言葉としての彼らの名前に、塩野は実にあざやかに「人生模様」を描いている。だから、塩野のエッセイは生々しい。
新鮮なのが美味しいのは食べ物だけでなく、文章も同じだ。
この「国家と歴史篇」は「事業仕分け」や「密約」のことなど、今年の春に発表されたものまで掲載されている。何百年も遡るのも歴史として面白いが、数ヶ月前をきちんと見直すのも大切だろう。
なにしろ、人間はとても忘れやすい動物だから。
◆この書評のこぼれ話は「本のブログ ほん☆たす」でお読みいただけます。
こんな当たり前のことを書いて売れる、っていうのは、いかに日本のマスコミがまともなことを報道していないのか、そしてそれをうのみにする日本人がいるか、っていうことなんでしょう。それにしても、お金を払って自分の本を読む人以外を読者としては認めない、という奢りたかぶった発言は、塩野の、というか文筆業者の本音なのかも・・・
2011/01/19 20:12
6人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みーちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
カバー折り返しの言葉は、
夢の内閣をつくってみた。大臣たち
は、私が慣れ親しんできたローマの
皇帝にする――治者とは? 戦略と
は何か? 現代日本が突き当たる問
題の答えは、歴史が雄弁に物語ってい
る。大好評『日本人へ リーダー篇』
につづく21世紀の「考えるヒント」。
です。装幀者について表記なし。とりわけ、断るほどのデザインではないのかもしれませんが、書いたら本の価格が上がるとでもいうのでしょうか。そのくらいケチらず書いておけばいいのに。で、この本、初出を見ると、文藝春秋二〇〇六年十月号~一〇年四月号、とあります。この表記について一言。多分、ここでのルールは、年号については二〇〇六というように〇~一まで、月については一~十までの文字を使うということなのでしょう。
これについては何度も繰り返しますが、都筑道夫は一冊の本の中での両者の混用を避け、一つの表記にすることが正しいとしていました。都筑流でいえば、さしづめ今回は
初出 文藝春秋二〇〇六年一〇月号~一〇年四月号 か、初出 文藝春秋二千六年十月号~十年四月号
となるはずです。この本のオリジナルは、自分たち独自のルールに拘ったために「十月号~一〇年」という惨めな結果になっていて、私としてはスマートな
初出 文藝春秋二〇〇六年一〇月号~一〇年四月号
アラビア数字をそのまま漢字に置き換えた表記をとりたいところです。ちなみに、〇は漢字ではないですよね、零が正しくて、それだと様にならない。ここらは、柴田光滋『編集者の仕事 本の魂は細部に宿る』(新潮社2010)の、校正、畏るべし「原稿を整備せよ」に丁寧に書かれている。
で、気になったことがもう一つ。本文中「読者に助けられて」で、塩野は『ローマ人の物語』を書くために他の仕事を断った、とあって、この本の初出を見て、じゃあ、この仕事は何? って思ったわけ。この本はともかく、リーダー篇には「初出 文藝春秋2003年6月号~06年9月号」とあって、『ローマ人の物語 15 ローマ世界の終焉』は2006年に出ているわけです。3年はダブってるじゃん・・・
とはいえ、デビュー当時から殆ど全作品を読んで来たつもりの私としては、塩野の自民党贔屓には疑問を抱くものの、概して共感を持って読みました。ただ、後半に登場する「仕分け」という言葉の使い方は、あまり流行語を使わないという塩野のイメージとは違うかな、と思いました。それと小泉政権への評価、ま、私は小泉なくして公務員改革はなかっただろうと思っているほうなので、それなりに分かるんですが塩野のようにべた褒めまではいきません。
ただ、こうして読むと本当に自民党政権はもう煮詰まっていて、だれが見ても民主党政権への移行というのは必然に近いものだったんだなあと思います。で、そこらについて今回の参院選(2010)の民主の惨敗や、それを予感するような日本人の投票姿勢などの分析がまさに私と同じ意見なので、嬉しくて引用しようと思います。まずは「安倍首相擁護論」から78頁
*
民主主義政体下の有権者とは、「何をやったか」で支持するのではなく、「何かをやってくれそう」という想いで支持を寄せるのである。業績から判断するのではなく、期待感で票を投じる人々なのだ。業績によって評価を下すのは、政治的センスを持ったごく少数の有権者か、それとも歴史家か、でなければ歴史的なセンスも兼ね備えている新聞記者だけと考えた方がよい。
*
その通りです。そして社民や国民新党といった愚かとしか言いようのない政党の暴走ぶりを予見した「拝啓 小沢一郎様」のなかの189頁
*
日本では、次の総選挙では民主党が勝つでしょう。しかし、参院でも連立を組まないと過半数に達しないのに加え、衆院でもおそらく、社民や国民新党と連立を組まないとやっていけないことになるでしょう。
そうすればまず、社民がキャンキャンわめき始める。化石みたいな国民新党も黙ってはいないにちがいない。そしてこれに、民主党内の郷愁派というか守旧派が、浮足立ってくる。結果は、選挙で多く支持された大政党が、ひとにぎりの票しか得なかった小政党に引きずられるという、有権者の意向の反映しない政治に向かってしまうことになる。
*
まさにこれが今回の参院選(2010)直前に民主党政権下でおきた事象です。それと、最近起きたばかりの尖閣列島問題における菅政権の対応を、塩野はどう判断するのでしょう? まだ文藝春秋に連載をしているようであれば、それを読めばいいのでしょうが、『日本人へ 国家と歴史篇』というタイトルには相応しい事件だと思います。できたら文庫化に際してはコメントが欲しいところ。
記事では、「世界史が未履修と知って」の各国の歴史の授業事情についての話、「イタリアが元気な理由」の政権の安定こそが必要だという認識、「円の盛衰」における特に対ユーロの問題、「価格破壊に追従しない理由」あたりを、新鮮な気持ちで読みました。
気になったのは最後の「読者に助けられて」。塩野にとっての読者というのは、あくまで本を買ってくれる人を言うのであって、たとえば図書館で彼女の本を借りて読む人は、読者ではないそうです。身銭を切って読む、印税を彼女にもたらす人が読者。これは予想外の発言でした。そうか、『ローマ人の物語』で、彼女の本を買うことをやめ、図書館で借りるようになった私のような人間は、デビュー以来せっせと高い彼女の本を買ってはいても、読者ではないんだ・・・
最後は目次のコピー。
1
後継人事について
葡萄酒三昧
『ローマ人の物語』を書き終えて
女には冷たいという非難に答えて
世界史が未履修と知って
遺跡と語る
『硫黄島からの手紙』を観て
戦争の本質
靖國に行ってきました
読者に助けられて
夏の夜のおしゃべり
安倍首相擁護論
美神のいる場所
歴史ことはじめ――葡萄酒篇
歴史ことはじめ――チーズ篇
2
滞日三題噺
ブランド品には御注意を
バカになることの大切さ
ローマで成瀬を観る
夢の内閣・ローマ篇
夢の内閣・ローマ篇(続)
漢字の美しさ
福田首相のローマの一日
サミット・雑感
オリンピック・雑感
“劣性”遺伝
開国もクールに!
雑種の時代
3
一人ぼっちの日本
海賊について
拝啓 小沢一郎様
イタリアが元気な理由
地震国・日本ができること
昔・海賊、今・難民
現代の「アポリア」
ソフト・パワーについて
八月十五日に考えたこと
円の盛衰
戦略なくしてチェンジなし
価格破壊に追従しない理由
「仕分け」されちゃった私
仕分けで鍛える説得力
「密約」に想う
後から振り返って、「あぁ、そのとおりだった」と思う記事のなんと多いことか
2010/09/28 14:57
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:YO-SHI - この投稿者のレビュー一覧を見る
1ヶ月前に発行された「日本人へ リーダー篇」の続編、というより上下巻の下巻といった方が的確だろう。「リーダー篇」が月刊誌「文藝春秋」の2003年6月号から2006年9月号までに掲載された著者のエッセイで、この「国家と歴史篇」はそれに続く2010年4月号までに掲載されたものだからだ。
約4年前の2006年9月と10月を挟んで、それ以前と以後でこんなにも臨場感が違うものかと驚いた。前著に比べると本書は圧倒的な迫力で迫ってくる。もちろんそれは、前著は著者の筆が鈍かったということではなく、物事が人の(私の)関心から急速に遠ざかってしまう、ということなのだろう。
そういうわけで、2冊とも読むに越したことはないけれど、どちらか1冊ということであれば、本書の方をオススメする。
マキアヴェッリをよく引き(本書の扉のページも、マキアヴェッリの言葉の引用が記されている)、リアリストでもある著者の主張は、時に切れすぎて怖いぐらいだ。特に戦争や軍備についての考えは、私には受け入れられない。
しかし、著者の考えの方が正しいのかもしれない、と気持ちが揺らぐ。前著で著者が明らかにしているのだが、この連載は「事後に読まれても耐えられるものを書く」という気概で書かれている。そして事後に読んで「あぁ、そのとおりだった」、と思う記事のなんと多いことか。
例えば、民主党への政権交代の雰囲気が盛り上がっていた、2009年4月号の「拝啓・小沢一郎様」では、「単独で過半数を..」と期待と不安を口にしている。理由は、連立内閣では「小政党に引きずられる、有権者の意向の反映しない政治」になるから。異論はあろうが、民主党政権の約1年のある側面を見事に言い表している、と私は思う。
「文藝春秋」の2010年8月号掲載のエッセイのタイトルは「民主党の圧勝を望む」。理由は昨年9月の記事と同じものに加え、政策の継続性のため。著者としてはここ2回の国政選挙は続けて期待を裏切ったことになる。
「自分で自分を守ろうとしない者をだれが助ける気になるか。」
2010/10/10 22:04
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:龍. - この投稿者のレビュー一覧を見る
ページをめくると最初に「自分で自分を守ろうとしない者をだれが助ける気になるか。」というマキアヴェッリの言葉が飛び込んできます。
今の日本を象徴する言葉。
未来に対する戦略が描けないで、その場その場の対応しかできない政治の結果なのでしょうか。
本書は国家と歴史編ということで、国家とはどうあるべきか歴史から、特にローマのそれから学ぼうとするものです。
外から日本を見るということは日本に住んでいる以上、無理なことですが、本書を読むと想像以上に日本の世界での存在感が薄くなっていることを感じさせられます。
軽い文体で書かれているのでとても読みやすいのですが、ほとんどがミクロの事象に言及しているため、そこから「国家」というマクロの事象に考えを発展させながら読むとよいのではないでしょうか。
この国のリーダーがどこに向かって国民を導くのか、そもそもそういう意識をもっているのかなど、考えるきっかけになります。
龍.
http://ameblo.jp/12484/
歴史を振り返りつつ、今を正す
2016/03/19 10:34
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:あや - この投稿者のレビュー一覧を見る
日本史も学んだけど、受験も興味分野も世界史なので読んでいて共感できることはすごく多い。
もっと政治を知ることや自身の意見を表出できるようになりたいと思わせられます。