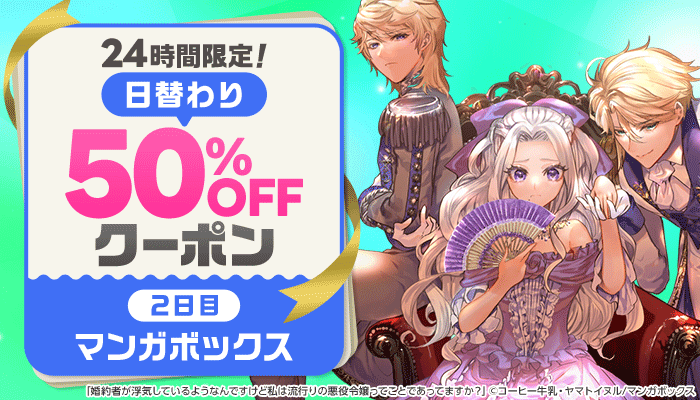パクス・ロマーナ──ローマ人の物語[電子版]VI
著者 塩野七生
志なかばに倒れたカエサルの跡を継いだオクタヴィアヌスは、共和政への復帰を宣言。元老院は感謝の印として「アウグストゥス」の尊称を贈ったが、彼の構造改革の真の意図は別のところ...
パクス・ロマーナ──ローマ人の物語[電子版]VI
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
志なかばに倒れたカエサルの跡を継いだオクタヴィアヌスは、共和政への復帰を宣言。元老院は感謝の印として「アウグストゥス」の尊称を贈ったが、彼の構造改革の真の意図は別のところにあった……。半世紀をかけて静かに帝政を完成させ、広大な版図に平和をもたらした初代皇帝の栄光と苦悩を、あますところなく描いたシリーズ最高傑作。 ※当電子版は単行本第VI巻(新潮文庫第14、15、16巻)と同じ内容です。
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
最後の逸話に思わず涙...
2007/07/26 00:30
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:コーチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
暗殺されたユリウス・カエサルによって後継者に指名されていたオクタヴィアヌス。18歳の彼は、カエサル暗殺後の15年間にブルータスら暗殺者、それから政敵アントニウスを次々と倒す。そして前27年、ただ一人の権力者となった彼は、元老院議員たちの前に立った。
誰もが独裁政治の復活を予想した中で、オクタヴィアヌスの口から発せられたのは、元老院中心の政治、すなわち共和政への復帰宣言だった。これに狂喜した元老院議員たちは、敬意を表して彼に「アウグストゥス(尊厳なるもの)」の称号を送る。しかしこれは、「偽善者」であった彼による独裁権確立のための巧妙な布石であった。新リーダー「アウグストゥス」が始めた政治体制は、市民の第一人者(プリンケプス)による統治という意味で「プリンキピア(元首政)」と呼ばれるが、その実体はプリンケプスによる独裁であり、ローマ帝政の事実上の開始なのであった。
政治権力の集中は、地中海世界を支配するようになったローマにとっては必然的な流れであり、その先陣を切ったのは、カエサルであった。アウグストゥスが目指したのは、この体制をより堅実なものとし、国家の安全と平和を保障することであった。そのために彼は、元老院の反発や警戒を防ぎ、暗殺など不慮の死による事業の中断がないよう細心の注意を払いながら、着実に帝政を整えてゆく。
元来ひ弱で、軍人としての能力にも欠け、カエサルのようなカリスマ性もなかったが、きまじめで一つのことを粘り強く行う性格だけが取り柄だったこの青年の人物を見抜いたカエサルの眼力もさすがだが、それに十二分に応えたアウグストゥスはやはり偉大である。軍事面では、カエサルによってあてがわれた名将アグリッパ、行政面では、メセナ運動の祖といわれるマエケナスに助けられながら、41年という彼の長い治世は、ひたすら上の目標を実現することへと捧げられる。その結果、ローマには比類なき平和と繁栄の時代が訪れる。ここから以後の2世紀を、ひとは「パクス・ロマーナ(ローマの平和)」と呼ぶが、平和の礎を築いた初代皇帝アウグストゥスの功績は、どんなに賞賛してもしきれないであろう。
こんな彼も、長い治世のあいだにはいくつか過ちを犯す。たとえば軍事面では、カエサルがあえて踏み込まなかったゲルマニア(ドイツ)への拡張政策を行い、その結果、3万もの兵隊が全滅するテウトブルグの惨劇を生み、ローマの防衛線を事実上後退させる。
また、自己の血を引く皇統に固執する彼は、再婚相手の連れ子で後に2代皇帝となるティベリウスと、前夫アグリッパに死に別れた実娘ユリアとを結婚させるが、これはそれぞれの男女の不幸を生むだけであった。ティベリウスは最愛の前妻への思いを断ち切れず心をかたくなにし、ユリアも政略の道具にされるだけの身の寂しさから、浮気へ走ってしまうからである。しかもユリアはその結果、アウグストゥス自身が制定した不倫に対する厳しい法律により、流刑に処せられる。
老年期に入ってから起きたこれらの事件は身から出たさびともいえるだけに、アウグストゥスの心をどんなにか苦しめただろう。だが、そんな彼の人知れぬ苦労をねぎらったのは、他ならぬローマの市民たちであった。娘ユリアの不祥事のあと、元老院は彼に『国家の父』の称号を与える。事件で落ち込んでいる彼を慰めるためであった。そして本書は、晩年の彼を「心の底から幸福にした」という次の出来事を伝えて終わっている。
アウグストゥスがポッツォーリという港町に入ったときのこと。船上で休んでいた老皇帝の姿を、別の船の乗員や乗客らが認めた。すると彼らは、合唱をするように彼に向かって叫んだ。
「あなたのおかげです、われわれの生活が成り立つのも
あなたのおかげです、わたしたちが安全に旅をできるのも
あなたのおかげです、われわれの自由で平和に生きてゆけるのも」
これに感激したアウグストゥスは、彼ら全員に金貨40枚ずつをあたえたという。ローマの平和とは、それをあたえる者もまた享受する者も共に理解しあえる時代だったのだろう。
帝政ローマの始まり
2024/08/04 20:45
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:マー君 - この投稿者のレビュー一覧を見る
カエサルの後継者としてアントニウスを倒したオクタヴィアヌス。第一人者アウグストゥスとして静かに帝政に進む。
元老院にとって国王と皇帝とは異なったのだろうか?
ローマ帝国 ― 人類史上、唯一の普遍帝国の完成者
2020/10/02 21:18
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:司馬青史 - この投稿者のレビュー一覧を見る
ローマ帝国・初代皇帝アウグストゥス。
彼は天才ではなかった。
養父カエサルの創造力もなければ、ハンニバルの軍才もない。キケロの弁舌もなければ、スッラの強烈さもない。
彼にあったのは、愚直な責任感と冷徹なまでの自己認識だけだった。
しかし、そんな彼だからこそ、天才たちが成しえなかった偉業を成す事ができた。
あの時代、あの時のローマ帝国には、彼の様な指導者、皇帝が必要だった。
敗者さえ同化し、多民族・多文化が融和した普遍帝国・ローマ。
アウグストゥスなくしてローマ帝国の完成はなく、普遍帝国・ローマの完成も栄光もなかった。
彼は天才ではなかった。
しかし、ローマ帝国がアウグストゥスの様な至高の皇帝を持つ事ができたのは、幸いであった。
魅力的でない世界帝国の創業者
2023/03/18 15:31
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Koukun - この投稿者のレビュー一覧を見る
比類なき世界帝国であった古代ローマ帝国の創業者オクタビアヌス アウグストゥスの一代記である。前巻のユリウス・カエサルと比べていかにも地味で表面的な魅力に乏しい人物の成果、作者塩野七生の筆もずいぶんと抑えられた感じになっている。しかし、振り返ってみると創業者 初代皇帝と言うにふさわしい凄まじいまでの業績を残している。業績や言動ははっきりと残っているが、今ひとつ謎の人物である。

![パクス・ロマーナ──ローマ人の物語[電子版]VI](https://img.honto.jp/item/2/265/360/27169515_1.jpg)