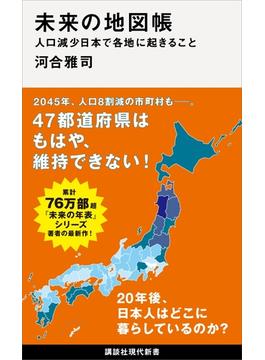3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ワクワク - この投稿者のレビュー一覧を見る
分かっていると思うが、こう具体的に示されて、どうすべきかと考えさせられる。
今こそ、やるべきことを考えて、行動。
よくわかります。
未来の年表シリーズ第3弾
2020/02/02 23:47
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:donden - この投稿者のレビュー一覧を見る
今回はこれまで2作をより具体的にシミュレーションし、各地域ごとに対策案を示しています。
つくづくこれまで続いている東京一極集中政策の弊害が近い将来爆発しそうだと感じた。
無策な政治のつけがそろそろやってくる
2023/12/01 14:07
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
「人口の減少」「少子化対策」が日本で叫ばれようになってからどれだけの時間が経過したことだろう。その間、政治家たちは小手先のバラマキに終始して抜本的な対策をないがしろにしてきた、そのつけが間もなくやってくる、この本を読んで、私が思っているよりもはるかに深刻な状況であることが理解できた
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とりこま - この投稿者のレビュー一覧を見る
未来シリーズの3作目。地域ごとの人口の変化を元に未来に向けた提言をしており、これまで以上に説得力のある内容。
25~39歳の女性が増えなければ少子化は解消しない、人口が増加している大都市でも“高齢者”は増加する、この2点が新鮮に映ってしまうことが、すでにこれまでの少子高齢化対策が間違った方向に進んでいることを示していると感じる。
大都市であっても高齢者が増えていることを念頭においていかなければならないという点は自分の仕事にとっても大事な観点であり、それを踏まえて仕事を進める必要があると感じた。
少子高齢化のペースを下げることは重要だが、それ以上に少子高齢化を受け入れた上で、豊かな街・国づくりを行う、という観点はよく心に留め置きたい。
目指す目標が欲しい
2020/07/05 21:22
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:UMA1001 - この投稿者のレビュー一覧を見る
あんな風になりたいなという目標がないので、日本はぐだぐだになっているのでしょうか。
たくさんのデータを元にそうなんだー、と気付かせてくれるが、若干うざい。
結局、具体的対策は?
2020/06/28 22:47
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ライサ - この投稿者のレビュー一覧を見る
冒頭に「これまでは現状を把握する意識ばかりで具体的対策にはあまり触れられていなかった」「今作は細かい地方ごとの解説とともに対策を書いている」とあるが。
確かに地方ごとの解説は載っている。しかし対策はまたもほとんど書かれていない
いや書かれていなくもないが結局は「今の日本じゃ無理だよね」というものばかりだ
絶望感を強めて終わり
そもそも国民の側が変える気力のある人が少数派って時点でお察しでは。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:キック - この投稿者のレビュー一覧を見る
積読本消化。
現在の人口動勢を活写している第1章は興味深かったです。地方はその中核都市に人口が集まり、さらにその中核都市から東京圏に人口が吸い上げられている様子がよく分かりました。一方、今後の各都道府県の人口の状況を描写した著者の自信作と思われる第2章は、存外退屈で斜め読み。
まず地方から人口減少・高齢化が進み、最後は東京圏にも及ぶという想定内の破滅的な結果でした。少子化対策もやる気のない安倍政権。コロナでも露呈した大局観のない政治に何が期待できるでしょうか。確信犯的な、ゆでガエルは許されないと思いました。
ところで、私が最も心配するのは農業です。農業従事者の平均年齢は70歳くらいであり、人口減少で、まず消滅するのは農業だと思います。担い手が減少する中、自給率の向上なんてまさに絵に描いた餅。地方は既に荒廃しつつありますが、食糧は現状以上に輸入に頼らざるを得なくなるでしょう。
少子化対策も同様ですが、数十年後は自分は存命ではなく、今を凌げば良いというスタンスの高齢の政治家には全く期待できないので、若い世代の方がリーダーシップを取るようにならないと駄目かもしれません。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
少子高齢化についての、警鐘を鳴らしているというのは、わかります。そもそも、若い女性が、少なくなってしまってますから、生まれては来ないわけで……。でも、なんだか、マイナスばかり強調してあって……
投稿元:
レビューを見る
読み終わって、なんというか暗澹たる気持ちになった。。今の生活を今の規模で維持できなくなる地域が数多く発生するのは確実なんだろうな。
出産期にあたる自分にまずできることは子供を産むことくらいだけど、それにしたって命懸けだし、子育てしづらい社会だし、がんがん産むぞーという気持ちにはなれない。環境が整わなくて産みたいと思えない女性がたくさんいるのも理解できる。
こんなことを言っても仕方がないけど、ほんとにこの20年間くらい政治は何していたんだろう、、。
投稿元:
レビューを見る
<目次>
はじめに
第1部 現在の人口減少地図~日本人はこう移動している
第2部 未来の日本ランキング~20年後、日本人はどこに暮らしているか
第3部 それぞれの「王国」の作り方
<内容>
第1部、2部で詳細なデータの分析が行われている。ちょっと気になったのは、現在の行政区分は役に立たなくなる、と言っていながら、この部分の分析は都道府県、市町村を基にしたデータであることだ。もちろん、そういう形でしかデータがないからだが、自分の主張が希薄になっている気がする。第3部は、著者のプランニングだ。曖昧な書き方だが、これは一つの提案として成り立つと思う。行政は「小さい」が、今までのように全部を見る、という考え方を捨て、受益者が必要な時だけ向かう、という考え方。それ以外の時は、小さな「王国」(著者の言い方で、従来の村落単位)で、助け合いながら生活をしていく。出来るなら「王国」ごとに、特徴を出して、生きていく。「王国」ごとに相互協力していく形(今までの行政的な部分も含めて)が、良いだろうという。日本人の、特に年寄りの頭は、発想の転換が難しいので、これの実現はかなり難しいが、妥当な考えだと思う。
投稿元:
レビューを見る
生きていく上で知るべきこと、仕事に行かせること、生き方、家族を考える上で大切な情報。
情報量が多すぎて多少パニクった
投稿元:
レビューを見る
未来シリーズ第3弾
正しいしどうにもならないのかもしれないけれど、単にコンパクトにしていくしかないのかしら?と反発してしまう
投稿元:
レビューを見る
過去の少子化のツケでこれから出産期に入る若い女性がハイレベルで減っていくため、当分の間、出生数は下げ止まらない。人口減少社会は年々酷くなっていくことは避けられない現実なのである
国民の数が減りゆく中で、どこかの市町村やエリアだけがうまく立ち回り、単体で生き残ることは不可能だ。地域ごとの対応策を考えるためにも、他地域の実情を知り、補完関係を作っていくことが不可欠となる
中核都市構想 いささかちゃう種が遅すぎた
国交省 国土のグランドデザイン2050
人口が15万人程度になると、百貨店や救命救急センター施設、先進医療を実施する病院が維持しづらくなる。映画館や、大学、公認会計士事務所が撤退を始める。都市としての風格や機能の衰えは地域経済にも波及するので、人口流出をさらに加速させる要因ともなる
東京の都心への集中以上に、地方圏では各県庁所在地にの便利な市街地への人口集中が進む
東京都の特殊出生率 2017 1.21 全国の1.43に比べて低いが、0-4歳の人口総数で診ると上位10位は東京23区
東京都は、全国から出産できる年齢の女性を多く集めている割には、出生数はこの程度しか伸びなかった
拡大路線による過去の成功モデルで東京圏が日本の経済成長をなんとか牽引しているうちに、人口減少が続く地方の社会基盤を、人口が減ってもやっていけるように根本から作り直すのだ
丸亀商店街の成功
投稿元:
レビューを見る
良い。
人口減少は避けられない。のに、見ない様にしている様だ。政治家はそんな馬鹿じゃないと思いたいが。
住む場所は身軽にして、高齢になったら、便利な場所に住んだ方が良さそうだ。
投稿元:
レビューを見る
ベストセラー「未来の年表」シリーズの著者が、新たな視点として、日本国内の都道府県、市町村の人口動態と今後どのような人口変化が起きるか、そして、避けられない人口減少への対応策を述べています。
相変わらず、データに基づいた、かなり正確な予測を示したうえで、今後の処方箋を描いているわけですが、この世界的にも稀な状況をどのように迎えるのか、厳しい状況ながら、今後の方向性は大変参考になります。多くの方に読んでいただきたいと思います。
▼人口減少は2段階で進む
・第1段階 2042年まで
-若者が減る一方で高齢者は増え続ける。これからの四半世紀、高齢者泰作に追われる
・第2段階 2043年以降
-高齢者も減り、若い世代はもっと減っていく時代
-高齢者も若者も減るから、このころから人口が急落する。
-総人口の4割近くを高齢者が占めるようになるため、社会の担い手が不足し、日常生活がいろいろな形で麻痺する
▼いま、我が国に求められているのは、人口減少を前提として、それでも「豊かさ」を維持できるよう産業構造をシフトさせていくことであり、国民生活が極度の不自由に陥らぬよう社会システムを根本から作り替えていくことである。
▼「戦略的に縮む」
「国土の均衡ある発展」から路線転換し、「拠点型国家」へと移行する必要がある。地図に落とし込めば点描画となるような「ドット型国家」への移行
▼名古屋市の状況
・全国に3つしかない人口200万人を超す政令指定都市の1つ
・大都市のわりに住みやすい街
・人口増の要因は社会増幅が急速に伸びたため
・大企業が集積しているため、人口の流出入は雇用情勢の影響を受けやすい。リーマンショックを乗り越え、経済状況の伸びに引っ張られる形で全国から人が集まってきていることが大きい
・県内からの流入が多く、岐阜県、三重県、静岡県、長野県、北陸3県からも流入が多い
・名古屋市の人口増加は、外国人の存在が大きい
・東京圏へのみ転出超過
・今後の課題
-リニア中央新幹線の開業→ストロー現象の恐れ
-高齢社会に不向きな広すぎる道路
▼国土交通省「国土のグランドデザイン2050」(2014年)
・人口15万人程度→百貨店や救命救急センター施設、先進医療を実施する病院が維持しづらくなる。映画館や大学、公認会計士事務所が撤退を始める。都市としての風格や機能の衰えは地域経済にも波及するので、人口流出をさらに加速させる要因
・人口5万7500人を下回る→結婚式場業が廃業・撤退を始める
・人口3万2500人を下回る→ペット・ペット用品小売業が廃業・撤退を始める
・人口1万7500人を下回る→カラオケボックス業や税理士事務所が廃業・撤退を始める
・人口6500人を下回る→銀行や通所介護事業所まで経営が厳しくなる。一般病院だけでなく、遊戯施設、音楽教室、喫茶店といった住民の「楽しみ」を提供してきたサービスも姿を消し始める
・人口2500人を下回る→お年寄りの憩いの場である喫茶店も持ちこたえられなくなる
▼2030年代に定数を大きく割り込む自治体が相次ぐことが懸念される。2045年を待つまでもなく、行政は公共サービスをどこのエリアまで届けるべきかという「線引き論」が、大きな政治課題となるだろう
▼「東京都は、全国から出産できる年齢の女性を多く集めている割には、出生数はこの程度しか伸びなかった」
▼なぜ地方創生はうまくいかないのか
・出発点からのボタンの掛け違い
①人口ビジョン「2060年に1億人程度の人口を維持」と掲げたこと
②既存の市町村をベースとしていること
▼拡大路線による過去の成功モデルで東京圏が日本の経済成長を何とか牽引しているうちに、人口減少が続く地方の社会基盤を、人口が減ってもやっていけるように根本から作り直す
▼人口が多少減ろうとも、世界の中で「なくてはならない存在」を目指したほうが、豊かさは維持しやすい
▼令和時代に求められる5つの視点
①拠点という「王国」を作る
・人口減少日本では発想を大きく転換し、居住可能なエリアを「王国」として整備すること
・人を中心に据えた出会いの場を用意し、「賑わい」を作っていく。それがエリアの活力となり、仕事が創造され豊かな暮らしを実現していくという好循環を生み出すことに主眼。
・都市部の繁華街や商店街など「すでに賑わっている場所」や既存のインフラをうまく活用しながら展開
・イタリア・ソロメオ村が手本
②基礎自治体の単位を都道府県とする
・「自分で出来ることは、どんなことでも積極的に取り組む」という意識と「行政に多くを頼むことはできない」という覚悟を持つことが不可欠
③働くことに対する価値観を見直す
・日本全体で仕事の総量を減らす。残業がなく生産性が高いオランダを目指す
④「在宅医療・介護」から転換する
・元気なうちから高齢者が集まり住んでおく。交通の便利な中心市街地に高齢者向けの居住スペースを建設するか、その周辺に「王国」を作る
⑤東京圏そのものを「特区」とする
▼「王国」を地方に数多く築き上げていくことが、人口減少日本が豊かさを手放さずに済む唯一の策。
・「豊かさの集積地」を作る:空港(福岡市、長崎空港と大村市)、港、サービスエリア、道の駅など。高齢者向け住宅や福祉施設を街の中心に
<目次>
第1部 現在の人口減少地図―日本人はこう移動している
序 市区町村による「住民の綱引き」に勝者はいない
1―1東京圏 東京は共存の道を探るべき「日本の外国」である
1―2関西圏 三大都市圏の中で減少スピードが最も速いのは、関西圏
1―3大阪市 「西の都」の人口拡大を下支えしているのは、外国人住民
1―4名古屋圏 名古屋市最大の懸念材料は、リニア新幹線と広すぎる道路
1―5北海道 「ところてん式」の札幌市は、200万人を超えるか
1―6東北 政令指定都市なのに通過都市、仙台パッシングの理由とは
1―7中国 周辺から人を集めきれず、「磁力の弱い」広島市
1―8九州 福岡市は北九州市と熊本市の二大都市を吸収か
1―9東京圏 一極集中が続く東京圏、その内側を覗いてみれば
第2部 未来の日本ランキング―20年後、日本人はどこに暮らしているか
序 塗り替えられてゆく日本列島
2―1 都道府県の人口差は30倍超へ
2―2 東京圏という「外国」は、老化に苦しむ
2―3 政令指定都市は、極端に明暗が分かれる
2―4 県庁所在地・地方都市は、不便さの増すエリアが拡大
2―5 出産期の若い女性が減少する地域はここだ
第3部 それぞれの「王国」の作りかた
序 なぜ地方創生はうまくいかないのか?
令和時代に求められる5つの視点