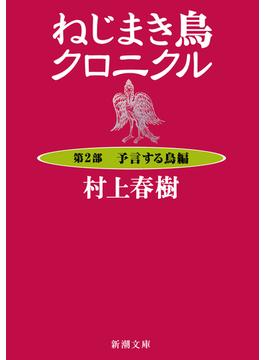読割 50
電子書籍
ねじまき鳥クロニクル―第2部 予言する鳥編―(新潮文庫)
著者 村上春樹
「今はまちがった時間です。あなたは今ここにいてはいけないのです」しかし綿谷ノボルによってもたらされた深い切り傷のような痛みが僕を追いたてた。僕は手をのばして彼を押し退けた...
ねじまき鳥クロニクル―第2部 予言する鳥編―(新潮文庫)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
ねじまき鳥クロニクル 改版 第2部 予言する鳥編 (新潮文庫)
商品説明
「今はまちがった時間です。あなたは今ここにいてはいけないのです」しかし綿谷ノボルによってもたらされた深い切り傷のような痛みが僕を追いたてた。僕は手をのばして彼を押し退けた。「あなたのためです」と顔のない男は僕の背後から言った。「そこから先に進むと、もうあとに戻ることはできません。それでもいいのですか?」(本文より)
関連キーワード
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
「僕」が求めることを決心する「第2部」
2010/07/14 16:58
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:K・I - この投稿者のレビュー一覧を見る
大江健三郎さんが「再読(リ・リード)」の重要性ということをいっていて、それを本で読んでいて、再読のことはずっと頭にあった。
読む本というのは、買ってきた本、図書館から借りてきた本、そして、読み終わり本棚におさまっている本の三種類がある。
よく考えると、それらを組み合わせながら、ほとんどだいたい毎日、何かしらの本には接している、と自分のここ最近を振り返って思う。
そうしたなかで、ふと、本棚の『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』が目に入り、「再読してみるか」と思って、再読してみた。
大江さんは再読では「探索」するような読み方ができるといっている。『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』を読んだときは、鮮明に覚えている冒頭の場面。それから、進んでいく「二つの」世界、それらを読みながら、ところどころ覚えているところもあり、あるいは忘れているところもあり、「ここはああなるんだな」「次はこういう展開だな」と思いながら、再読した。
そして、それを読み終わって、次は、『ねじまき鳥クロニクル』を再読することにした。記録を読むと、ちょうど三年前に読んだようだ。
ただ、どちらかといえば僕は『ねじまき鳥クロニクル』の内容を覚えていなかった。だから、「探索」というような意識的な読み方はできなかった。それでもだからこそ逆に初めて読むように新鮮に読めた。
「第2部」は、主人公が井戸に入り、そこから出てきて、加納クレタとの関わり、それから、最終的に、「電話の女」の正体に気づく。笠原メイの「告白」もこの「第2部」だ。
上で僕は「さほど内容を覚えていなかった」と書いたが、部分的には覚えている部分もあった。そして、おそらく、また何年後か、三度読み返すであろう、ということを予感している。
その前に「第3部」を読む。新装版の文庫で読んでいるのだが、文字も大きく、カバーもかっこうよくなり、個人的にはとても気に入っている。
紙の本
井戸の中に入りたいなあと思う。
2002/07/15 16:22
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ゆうきっく - この投稿者のレビュー一覧を見る
クレタや、笠原メイの助けによって、だんだんと猫の居場所、そして妻の場所が明らかになっていく…。
また、この巻で最も興味深く思えたのは、井戸にこもるということだった。
大佐の戦争の話で聞いた、井戸の中で過ごさざるを得なかった経験というものが印象的で、周りに光もなにもない状態でいったい人はどうなるのか…とか、考え尽くすには、周りに何もなくて、さらに飢えた状態がいちばんイイのかなあとか、イロイロ考えたり、自分も井戸に入りたいと思ってみたり。
主人公が謎の中から、現実の行方不明である猫や妻の場所を探っていくという…。謎から謎を解き出すのですから、物語自体も謎に溢れているわけで…。はまると恐ろしいくらいに、読んでる自分も謎の中に引っ張られて、不思議な感覚が味わえます。それもまた面白いですね。
こんな小説は他では読めません。不思議な体験ができることでしょう。ゆっくり、味わうとさらに効果的だと思います。
電子書籍
読みながら、聞きながら、自分の気づかなかったもの、見ないようにしていたものと向き合う感じがしてくる。 これこそ小説の大きな効能だ。 もう一つの1984年の物語は続いていく。
2023/12/06 10:52
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:mitu - この投稿者のレビュー一覧を見る
Audibleで聞く読書。
個性的な登場人物たちを語り分ける俳優・藤木直人に魅了されながら。
亨の妻・久美子がでていった。
間宮中尉から再び手紙が届く。
亨は家の近くの井戸に潜っていった。
昼間の井戸。
久美子との出会いを思い出す。
越えられない見えない壁のような感覚がよみがえる。
夜の井戸。
久美子との新婚生活を思い出す。
そして、苦い体験も思い起こされる。
亨は、学生時代のガールフレンドを妊娠・堕胎させていた。
結婚後に、久美子とは避妊をしていた。
だが思いもかけず妊娠をしていた。
久美子は一人で堕胎をした。
亨はそれを出張先の札幌で知った。
その札幌で入った二軒目のバーで、ロウソクのパフォーマンスをする男に出会う。
この男の存在は店員も知らなかった。
閉じ込められた井戸に、加納クレタがやってきた。
彼女にも予知能力のようなものがある。
ノモンハンでの中尉の話と重なる。
間宮中尉との、手紙のやり取り。
井戸への思い。
失われた人生の意味を知りたい、と中尉は語った。
読みながら、聞きながら、自分の気づかなかったもの、見ないようにしていたものと向き合う感じがしてくる。
これこそ小説の大きな効能だ。
もう一つの1984年の物語は続いていく。
紙の本
自分の気づかなかったもの、見ないようにしていたものと向き合う感じがしてくる。もう一つの1984年の物語は続いていく。
2023/11/15 09:52
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:mitu - この投稿者のレビュー一覧を見る
Audibleで聞く読書。
個性的な登場人物たちを語り分ける俳優・藤木直人に魅了されながら。
亨の妻・久美子がでていった。
間宮中尉から再び手紙が届く。
亨は家の近くの井戸に潜っていった。
昼間の井戸。
久美子との出会いを思い出す。
越えられない見えない壁のような感覚がよみがえる。
夜の井戸。
久美子との新婚生活を思い出す。
そして、苦い体験も思い起こされる。
亨は、学生時代のガールフレンドを妊娠・堕胎させていた。
結婚後に、久美子とは避妊をしていた。
だが思いもかけず妊娠をしていた。
久美子は一人で堕胎をした。
亨はそれを出張先の札幌で知った。
その札幌で入った二軒目のバーで、ロウソクのパフォーマンスをする男に出会う。
この男の存在は店員も知らなかった。
閉じ込められた井戸に、加納クレタがやってきた。
彼女にも予知能力のようなものがある。
ノモンハンでの中尉の話と重なる。
間宮中尉との、手紙のやり取り。
井戸への思い。
失われた人生の意味を知りたい、と中尉は語った。
読みながら、聞きながら、自分の気づかなかったもの、見ないようにしていたものと向き合う感じがしてくる。
これこそ小説の大きな効能だ。
もう一つの1984年の物語は続いていく。
紙の本
主人公の叔父の意見が心に残った
2020/03/29 22:01
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
複雑にしっかりと絡み合ってしまった問題に対して、主人公・岡田亨の叔父は「まずあまり重要じゃないところから片づけていくことなんだよ」と語る。私にも思い当たることがありなるほどと思ってしまった
紙の本
妻の失踪とノモンハンのつながりかた
2002/06/02 13:44
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:白井道也 - この投稿者のレビュー一覧を見る
最初読んだときにひっかかったのは、この小説の大筋である妻の失踪事件と、間宮中尉の語るノモンハンの体験談の関わり方、である。
「辺境・近境」の中で村上春樹は、ノモンハンを訪れたときの様子を書いている。その中では、「どうしてこんな役にも立たないような土地を争って日本は戦ったりしたのか」というようなことを書いていた。ノモンハンという物語は、それはそれで面白いものを持っているのだけど、間宮中尉の場合は、そこに“井戸”のエピソードが加わる。
間宮中尉は手紙の中でこう述べる。
「私がその井戸の中でいちばん苦しんだのは、その光の中にある何かの姿を見極められない苦しみでした。見るべきものを見ることができない飢えであり、知るべきことを知ることができない渇きでありました。」
主人公は、謎めいた一般論ばかりを述べる加納マルタに対して、「もっと具体的な何かをくれ」という。主人公もまた、見るべきものを見ることができず、知るべきことを知ることができない状態に苛立っている。
妻の失踪事件と、間宮中尉の語るノモンハンの物語。そのつながりは、このあたりにあるのではないかと思った。