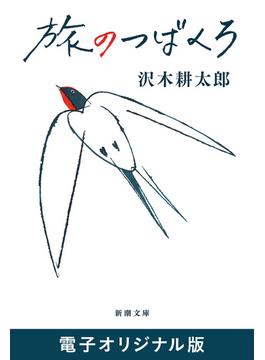なんということでしょう
2025/04/28 10:24
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:a - この投稿者のレビュー一覧を見る
JR東日本の小冊子に連載された日本国内の旅がメインの短い紀行集です。この著者の有名な「深夜特急」が、予定を立てないバックパック旅行でしたが、こちらは国内の短い旅中心ということで落ち着いて楽しめました。
代表的な旅のエッセイ
2025/03/14 08:46
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Koukun - この投稿者のレビュー一覧を見る
「深夜特急」があまりにも有名な作者の東日本の旅のエッセイである。「遊佐」の話が特に印象的であった。旅先でのほとんど一期一会に近い様々な人との出会い。そのような旅を一種の職業としている作者がやや羨ましくもある。
旅に飛ぶ、つばめ
2024/06/15 14:17
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:かずさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
作者の旅に寄せる思いや感慨を書いたエッセイ集。単なる名所への旅ではなく、仕事の途中や若き日に訪れた場所、訪れることができなかった場所への旅。旅好きが読めばその情景とともに思いも伝わってくる。竜飛崎への旅では唐突に「がんばれ、宇都宮線!」から始まるのも面白い。岩手の内陸や海岸部の旅、温泉への旅、若き日の節約旅と飽きさせない。読みやすい文章も魅力か。
投稿元:
レビューを見る
JR東日本の車内誌の連載をまとめたもの。なので、北への旅に関するエピソードが中心。
ふらりとその土地に行って、出会いを楽しむ。目的はあるようでない、そんな旅を疑似体験できた。
深夜特急を寝食忘れて読んだ学生時代、世界に飛び出して行くことを教えてくれた沢木さんが、今度は日本の良さ、面白さを紹介してくれた良エッセイ。
投稿元:
レビューを見る
沢木耕太郎『旅のつばくろ』新潮文庫。
東北新幹線の車内誌『トランヴェール』に連載された国内旅のエッセイから41編を収録。
新型コロナウイルス感染禍が始まる前から『トランヴェール』に連載されたエッセイで、東北地方についても触れていたので、新幹線に乗車する度に楽しみにしていた。2020年1月、いよいよ新型コロナウイルス感染症が猛威をふるい出すと新幹線を利用する機会も無くなり、このエッセイを読む機会も無くなってしまった。
先日、4年振りに新幹線に乗車すると『トランヴェール』の連載エッセイが柚月裕子に変わっていたのを初めて知った。
沢木耕太郎の初めての旅は16歳の時に周遊券を握り締めて回った東北旅行だったという。昔は東北地方の周遊券の他に北海道の周遊券もあり、学割で2万円で1ヶ月乗り放題だった。今でも周遊券はあるのだろうか。
このエッセイを読むと、あらためて旅の面白さが認識出来る。旅先での見知らぬ人との出会いや、受けた優しさ。何十年も前の出来事を今だに覚えている。最近の若者たちは旅をしないらしい。特に海外に向かう若者たちが激減しているのだと言う。旅ほど面白く、人を成長させるものはない。自分も国内外で様々な旅を経験し、様々な体験やトラブルを経験したが、まだまだ旅には行きたいと思っている。
本体価格550円
★★★★★
投稿元:
レビューを見る
JR東日本の雑誌『トランベール』に連載していたエッセイから、著者自ら41編を選んで一冊にまとめたもの。当時、新幹線の車内で読んでいた人が羨ましくなる、素晴らしい内容でした。
例えば「絵馬の向こう側」では、日本人と海外から来た人の書く内容から、視点の違いにドキっとしたり、「旅の長者」では、旅に出て予期しないことに出くわす”旅運”についての記述など、たくさんの興味深いエッセイがありました。
なかでも、一番好きなのは「夜のベンチ」です。著者が、16歳の春に初めての一人旅である、東北一周の旅に出たきっかけが「終着駅」に書かれていますが、そのときに起きたあるエピソードについて書かれています。人っていいなと、心温まる内容でした。
あと、文庫化に際して「文庫版あとがきとして」が追加されており、そちらも素晴らしい内容です。何かしらの自己啓発本を読むよりは、心に響くと思います。文庫化前の四六判を既読の人は、この「文庫版あとがきとして」だけでも読んでみるといいでしょうね。
以下、文中に出てきた本に関する覚え書き。未読のものは、読んでいきたいと思っています。
『津軽』太宰治(他作品『哀蚊(あわれが)』)
『戦艦武蔵』吉村昭
『火宅の人』檀一雄
『奥の細道』松尾芭蕉
『檀』『ハチヤさんの旅』『春に散る』『流星ひとつ』沢木耕太郎
『火花』又吉直樹
『ある華族の昭和史』酒井美意子
『かげろう日記遺文』室生犀星
『今も時だ』立松和平
『方丈記』鴨長明
『菜穂子』堀辰雄
『アレキサンダーの道』『孔子』井上靖
高倉健出演映画『八甲田山』(原作:『八甲田山 死の彷徨』新田次郎)
作家のみは、宮沢賢治(詩:「永訣の朝」)、佐藤春夫、吉行淳之介、横尾忠則、瀬戸内寂聴、小林多喜二、山本周五郎
投稿元:
レビューを見る
以前「トランヴェール」で読んだ「水で拭く」というエッセイがとても印象的だった。今回文庫として手元に置けるようになり歓喜!
更に、「旅先に沢木耕太郎を持って行ったらとても情緒ある雰囲気を醸し出せるはず」と帯同させたのだが、結果旅先で折れ曲がったり表紙が破れたりでぼろぼろに…それもまた味…
そもそも『深夜特急』も全く読んだことがないのに…ミーハー極まり無い…
ちなみに「水で拭く」のはお墓参りのエピソード。花も線香も持たず布で一心にお墓を拭く姿に、澄み切って凛とした空気と、相手へのあたたかな思いを感じた。
旅先での不思議な縁や、共に過ごしてきた人との思い出や。沢木さんほどになれば、日本全国に結び付きの地があるんだなあ。そもそも高校生の時既に東北一周の旅をしていたとか…。そりゃ旅人になるだろうね!強!
あと、遊佐って名字、自分もいいと思います。
小説家は、登場人物の出身地から想定できるのが楽しそう。その土地や知識が無いと深まりが出ないだろうから、知識の量は求められるかもしれないけれど、人物と一緒に旅ができそうで少し羨ましいような気持ちになる。
文末の「〜、だと。」は個人的にある知人を思い出すので笑ってしまう。もしやこれを意識していたのか…?
投稿元:
レビューを見る
70年代の若者は小田実の『何でも見てやろう』に衝撃を受け、80年代は沢木耕太郎の『深夜特急』に触発され、バイトをしてはバックパッカーとして世界中を貧乏旅行していた。
大学4年間ろくすっぽ授業に出ず、世界をリュック担いで世界を巡っても卒業できて社会人に…ある意味では戦後日本の高度成長と繁栄の象徴のひとつだったという見方もできる。
方や今の学生は入学して息つく間もなく就活が口を開けて待っており、ボランティアに資格取得にと社会に巣立つ前の『武装』が求められる時代だけに。
さて本書。その世界中をひとり巡った著者による初の国内旅エッセイ。旅のスタートは東北。沢木耕太郎にとって、東北は『深夜特急』の前哨戦であり、ひとり旅の愉しさと手応えを知った、16歳春 沢木少年の12日間にわたる『みちのくひとり旅』にある。それから約60年。この国内紀行は青春の旅路であった東北から始まる。
いずれの話も『聞かせどころ・読みどころ』が用意されている。通底するのは『宿縁』というか『袖触り合うは多生の縁』に類するエピソードに溢れ、沢木耕太郎はそれを『旅運』という言葉に置換する。
旅先で予期しないことが起きた時、むしろ楽しむ精神が『わらしべ長者』よろしく、良縁を引き寄せる磁力のようなものを育むと語る。う〜ん、ひとり旅の達人ならではの箴言ですな。
沢木耕太郎って〈孤高でコミットしない性向〉と勝手に思いこんでいたけど…なんのなんの実に人なっこい御仁なのだと印象一新。
例えば、キャバクラの客引きから居酒屋の名店を聞き出したり、講演先で訪れた宮城では講演後に熱心な読者の持参した著書にサインした後、その読者の経営する寿司店に流れ一献。その縁が取り持ち良好な付き合いが継続中だったり、軽井沢では駅で知り合った老婦人から紅葉スポットを教えてもらい即その情報に乗っかり足を向ける。そこに待っていたのは息を呑むほどの絶景…。
それもこれもひとり旅の年季の入り方が違うわけで、ひとり旅の手練れなんですな。とは言え、これまで『あっちゃ〜』の失敗の上に成り立っているのは言うまでもなく、ホームラン王に輝いた大谷翔平が今季143の三振を喫してるように、とどのつまり は数なんですな。めげずに振る、懲りずに旅立つ。
そこで、あとがきにはふたつのアドバイスめいた下りが綴られる。
①国内旅行なら失敗をしても容易に回復できるから、ひとり旅をするなら先ずは国内から!
②ネット情報に背を向け、自身の直感と経験を総動員すべし!
後者のアドバイスなんて、ネットなんて無い時代からひとり旅をしてる人だから言える芸当だからで、昭和のアナログ世代の困った時は人に尋ねるといった強引なコミュニュケーション手段が備わっている世代のなせる技で、思わず苦笑。
この本が優れているのは、お手本となる〈ひとり旅の醍醐味をエアー体験できる!〉ってこと。
わずかな路銀で愉しめるひとり旅を探している方なら、この本でまず心得を胸に刻み、旅先を決めるのもいいのかも…。
投稿元:
レビューを見る
思っていた以上に面白かった!
最後のあとがきで、食べログで調べて地元の名店を探す方法もありだけど、それは旅先だからできる失敗の経験をするチャンスを失うということなのだと。自分は結婚してからは、旅行に行くときはいつもカミさんが段取りしてくれて行くから、この沢木さんのいうチャンスをずっと失ってきたのだなと思う。別に残念では無いけれど、この本を読んでたら、日本に住んでいるのに、この本に出てくるところを全然知らないなと思い、今住んでるところと会社の近辺しか知らない人生はかなりつまらないのかもなとしみじみ感じた。まぁ、こういう名文のエッセイを読めば、そこに行った気にはなれないこともないから、読むだけでも良いのかもしれないけれど。
投稿元:
レビューを見る
旅ならぬ出張のお供に持っていった。沢木さんのテンポのよい文章は読みやすい。2時間ほどの飛行機の中で、すっと読めてしまった。
JR東日本の車内誌の連載から何本かピックアップしてまとめたもので、沢木さんにしてはめずらしい、日本国内の旅のエッセイである。沢木ファンとしてはこの連載は楽しみで、ゆっくり読むためよく『トランヴェール』を持ち帰っていた。
本書を読む直前に、司馬遼太郎の『街道をゆく』を読んでいたので、司馬さんと沢木さんの旅のスタイルの違いが面白く感じられた。
司馬さんの『街道をゆく』は、おそらく出版社が行く先々のセッティングをしている。編集者や記者も同行して意外に賑やかである。訪れた先でのエピソードはあまり語られない。むしろその土地を媒介にして、司馬さんは時空を旅して、歴史上の人物たちと語らうのである。
対する沢木さんは、基本的に一人で旅をする。そして、旅自体を楽しんでいる。当然ながら、語られるエピソードは、今を生きる人たちとの偶然の出会いが多い。その偶然の出会いこそが沢木さんの旅の醍醐味でもある。
どちらの旅のほうがいいということでもない。司馬さんほどではないにしろ、土地の記憶を読み込んだうえで、沢木さんのようにガイドブックには手を出さずに旅を楽しむというのもまたいい。仕事抜きで、ゆっくりと旅がしたい。
投稿元:
レビューを見る
著者のはじめてのひとり旅は16歳の時の東北。歳も経験も重ね同じ土地を旅する。
有名無名に関わらず、ひととの出会い、エピソードに心が暖まる。
特に現地で偶然目にした人々の様子、何気ない会話に惹きつけられる。
「失敗」の考え方にも共感できる。
投稿元:
レビューを見る
年末旅行の移動中に読んだ。移動手段と宿だけ押さえた他はノープラン、せめて飯屋くらいは調べておいた方が良いだろうかと悩んでいたが、却って本書で無計画旅行のモチベーションに油を注いだ結果になった。トランヴェールの連載エッセイだからと忖度するわけでもなく、旅先で感じたことが率直に書かれており、各章ごとに一期一会の旅の醍醐味を感じた。
津軽地方について書かれた章は特に、少し前に太宰治の津軽を再読していたので、二人の感じ方の違いが見られて興味深く読んだ。
投稿元:
レビューを見る
時間とお金を考えなくていい旅に行きたくなりました。余裕を持つために会社を変わったのに時間は窮屈になってしまい、旅行もせいぜい2泊まで。去年はコンサートにかこつけてホテルに1泊するだけがほとんど。コロナで次々にダメにしたヨーロッパに行きたいなぁ…
投稿元:
レビューを見る
旅行してるみたいで楽しかった。
沢木さんの本を他にも読みたくなった。
現地に行って自分で感じること。
最後の小さな失敗をする機会を失うのはもったいない、と言うことに共感した。
投稿元:
レビューを見る
つばめのように自由に、気ままにこの日本を歩いてみたい―。世界を歩き尽くしてきた著者の、はじめての旅は16歳の時、行き先は東北だった。(e-honより)