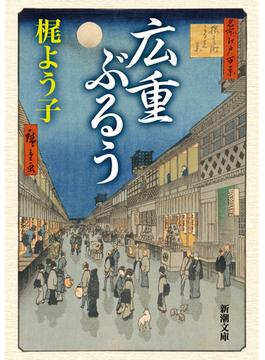広重ぶるう(新潮文庫)
著者 梶よう子
描きたいんだ、江戸の空を、深くて艶のあるこの「藍色」で――。武家に生まれた歌川広重は絵師を志すが、人気を博していたのは葛飾北斎や歌川国貞。広重の美人画や役者絵は酷評され、...
広重ぶるう(新潮文庫)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
描きたいんだ、江戸の空を、深くて艶のあるこの「藍色」で――。武家に生まれた歌川広重は絵師を志すが、人気を博していたのは葛飾北斎や歌川国貞。広重の美人画や役者絵は酷評され、鳴かず飛ばず。切歯扼腕するなかで、広重が出会ったのは、舶来の顔料「ベロ藍」だった。遅咲きの絵師が日本を代表する「名所の広重」になるまでの、意地と涙の人生を鮮やかに描く傑作。新田次郎文学賞受賞。(解説・日野原健司)
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
広重と江戸の町が活き活きと描かれている。
2025/03/26 07:55
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:トッツアン - この投稿者のレビュー一覧を見る
己の才能と絵師としての矜持を持つ広重が、絵描きとして売れない焦燥感の中で活き活きと描かれている。ページから飛び出してきそうな活きの良さ。そして、広重を通して写される江戸の街並みや人々、風俗などが目に浮ぶ。
最初の妻の広重を見る眼差しに深い愛情と広重の才能を信じる慈愛すら感じる。糟糠の妻。
絵師、彫氏、擦師によって錦絵がなりたつことを知った。
読み始めて直ぐに引き込まれ、一気に読んでしまった。
本当に人、町、風俗がこんなに活き活きと描かれてしまうと、自分が側にいる、町中にいるような気分になってしまった。
また、読む。
描きたい絵を描く
2024/03/20 08:42
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:かずさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
東海道五十三次で有名な絵師、歌川広重の絵に対する思いを語った時代小説。
火消同心安藤重右衛門。生活のため画才を発揮して絵を描くが鳴かず飛ばず。
その重右衛門の才能を認めながら苦言をも呈する版元。しかしなかなかその苦言を理解できず時として傲慢になる広重。でも最後は自分が描きたかった江戸百景を描く姿。自分の真に描き残し人の心に残る作品を描き求めた絵師の心情が書かれている。錦絵の制作過程や関わる人々の考えもよく書かれている。
大好きな江戸百景
2024/02/29 12:05
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:BHUTAN - この投稿者のレビュー一覧を見る
202402
広重が安政大地震で壊滅的になった江戸の風景を、以前の姿で書き起こしたものということは知っていた。
が、それまでの広重につていは全くしらなかった。
順風満帆に近かったのかとおもっていたら、大違い。
でも、この本の通りであればコロリと逝けてよかったのかも。
風呂から出て、加代さんに会えたのかな?
面白いのだが広重の人物像に違和感を覚える
2024/05/27 15:42
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:森の爺さん - この投稿者のレビュー一覧を見る
歌川豊春を祖とする歌川派は、第二世代の初代豊国と兄弟弟子の豊広を経て、第三世代の国貞(三代豊国)、国芳、広重で江戸後期の江戸の浮世絵界を席巻しているが、国貞(三代豊国)と国芳が初代豊国門下だったのに対して、広重は豊国に入門を断られた結果、豊広門下になっており、現在の知名度とは逆に若くして歌川派の得意とする美人画と役者絵の第一人者となった国貞(三代豊国)に対して、後進の国芳と広重はそちらでは芽が出ずに国芳は武者絵、広重は名所絵(風景画)でブレイクしている。
本書は歌川派第三世代の巨匠3人のうちで失礼ながら一番地味(北斎や国芳みたいな逸話も無い)な広重を主人公としているが、著者は広重の性格を口が悪く照れ屋でおっちょこちょい気味に描いており、それはそれで面白いのだが、その口の悪さが火消し同心を真面目に勤めて隠居した広重のイメージに合わないのと、広重の死因はコレラなのにラストの描写が面白いのだが症状が違う気がする。
売れない絵師としてあがきながら、ベロ藍(題名である「広重ぶるう」の青色の元となる絵具)による風景画に活路を見出し、ついに東海道五十三次で人気絵師となるが、糟糠の妻や二代目広重と見込んでいた一番弟子(昌吉、歌川重昌)に先立たれ、相次ぐ災害に見舞われながらも絵を描くことは止められない画家の業も書かれている。
また、版元をプロデューサーとして、絵師、彫師、摺師による共同作業により作成される総合芸術としての浮世絵版画の製作という観点から(絵師は現代で言えばデザイナー)、師匠豊広依頼の付き合いで売れない絵師の広重を叱咤する岩戸屋喜三郎、東海道五十三次で広重を一躍人気絵師にする新興版元の保栄堂竹内孫八等、絵師と版元の虚々実々の関係、そして広重の風景画を語るのに欠かせない「ぼかし摺」の摺師として寛治を登場させている。
広重が東海道五十三次を手掛けるきっかけも面白い(広重と竹内孫八との関わりについては諸説あり、また火消し同心の公務で東海道を京に上ったことを否定する説も存在する)し、広重が心ならずも「色重」として枕絵(春画)を書く際に、その分野でも巨匠である国貞(三代豊国)を頼り、その出来の悪い枕絵に対して正月早々版元達が家に押し掛ける下りは非常に面白く、かつ枕絵界の事情、当時における風景画(名所絵)の地位(格)が描写されていて興味深い。
他の絵師との関係では、北斎とのベロ藍を使った風景画の先達として宣戦布告とも言えるやり取り、歌川派の先輩絵師である国貞(三代豊国)との交友(実際に友人関係にあったことは広重の死絵を国貞(三代豊国)が書いていることからも窺える)の中で、同じ歳の国芳をライバル視する余り苦手としている設定で殆ど登場しないのが残念であるが、著者が国貞(三代豊国)の娘婿である四代豊国(清太郎)を描いた「ヨイ豊」と本書でも国貞(三代豊国)が江戸浮世絵界の大御所として存在感を出している。
なお、広重死後の広重一門については「ヨイ豊」でも触れているが、二代広重(鎮平)を主人公とする一ノ関圭著「茶箱広重」がお薦めである。
プロシアンブルーの発色
2024/03/17 17:12
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:nekodanshaku - この投稿者のレビュー一覧を見る
名所絵師といわれた歌川広重の一代記。描く者が眼差しを向けたものがすべて、画になると考え、江戸の町を写生し続ける主人公。役者絵、美人画は得意とせず、ましてや枕絵は描けない主人公は、絵師として売れない日々が続く。東海道の宿場町を描いた錦絵が売れてからは、名が知られ、浮世絵師として生計が立つ。物を手本として写実的に写し取り、これに筆意を加えて初めて画となるのだが、それを理解する版元が少なかったことが、主人公が注目されることが遅れたのだろう。プロシアンブルーの発色にひかれた広重の画力は、確かだった、今に残るから。