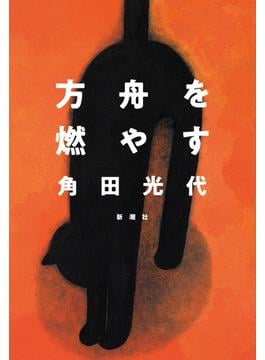0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:はぐらうり - この投稿者のレビュー一覧を見る
吉川英治文学賞。
"大勢を救うことがどだい無理でも、でも、近くにいるだれかが助けを求めて手をのばしていたら、それに向かって手をさしのべることくらいは、自分にもできるのだろうか。"
善意で信じて、騙されたり、迷惑になったりしてしまうんだな。大変面白かった。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
ねたばれ
タイトルに使われている「方舟」は聖書に登場する「ノアの方舟」からきている、主人公の一人、飛馬は「ノアは方舟は神を信じている人しか助けないのか、信じていない人も助けるべきじゃなかったのか」と考える、その考えは地震から多くの人を救ったという祖父の行動(どうも眉唾ものらしいが)に起因しているのかもしれない、作品のテーマは「デマ」、もう一人の主人公、不三子は勝沼という女性と知り合い「玄米を食べればつわりはおさまる」「白い食べ物は体に悪い」と教わって健康食品や自然療法を家族に取り入れる、しかし家族は崩壊してゆく、彼女の主張は他の家族には「デマ」としか聞こえない、ノストラダムス、コックリさん、災害に関するフェイクニュース(動画)と確かに「デマ」とは長いこと付き合わされている
正しいと思う情報が、正しいことも誤りであることも
2024/04/22 21:47
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:nekodanshaku - この投稿者のレビュー一覧を見る
二人の主人公が過ごした生活の場は、場所や時が異なる場であったが、自らが得た情報を、正しいと判断したがために、心に刻み、信じたその結果は、読む人の判断にゆだねられるのだろう。私たちは、予測不能な世界に生きるのだから、何が正しいことであることは、本当のところ、わからない。信じたい世界を身にまとい、生きていくことを、作り話にまみれた生き方など、どうしていえよう。方舟を作り乗り込んだノアは、後世に物語として語り継がれたが、方舟に乗り込まなかった人で、生き残った人が、いたかもしれないと思うと、正しい情報とは、何か?
投稿元:
レビューを見る
2024年 28冊目
1960年代〜今日のコロナ禍において男女2人が、信仰や噂に翻弄され、苦しみもがきながらも正解を求めて生きる姿が描かれた1冊。家族のためを思って尽力するが、結果として結びつかない歯痒さが、フィクションだがリアルに感じられた。
投稿元:
レビューを見る
角田さんらしいなぁと思いつつ読む。
昭和、懐かしい…
というか、すでに昔感あり過ぎでヤバいwww
投稿元:
レビューを見る
アナタは何を信じていますか?
信じる事の強さと壊さ
みんなそれぞれ信じるものがある
宗教だったり信念だったりSNSだったり
人によってどれも本当でどれも嘘になる
昭和、平成、令和を生きた人達ならあの出来事全て覚えてるだろう
そんな歴史的系列に沿いながら進む2人のお話にとても引き込まれた
投稿元:
レビューを見る
うーん、角田光代さんすごく好きなんだけどこれは刺さらなかった。
時代背景はすんなり入ってきたけれど、登場人物の思考にかな。
投稿元:
レビューを見る
自分が信じてきたことが本当に正しかったのか。
溢れる情報の中でどれを信じて進むのか人それぞれ。何が正しくて何が間違っているのか、自分で考えでいかないといけない。
信じるものしか救わない方舟はいらない。
投稿元:
レビューを見る
昭和50年代生まれの不三子と60年代後半生まれの飛馬。昭和の時代から令和の時代を生きる2人の姿を追っている内に読み終わったが、少し疲れたという感想。
良くも悪くも劇的な出来事は起こらない。不三子については、マクロビオティックな食生活にこだわりを持っていたり、子どもとの関係性が上手く行ってなかったりしていたが、こういう家庭はよくありそうだ。今、自身が妊娠中でもあるため、食べ物に多少気を使うようにはなったが、不三子のレベルは度を超えていて私には無理だ。
本書のひとつのテーマでもある"何を信じるか?"。
そんなの自分の決断を信じるしかないと思う。ワクチン接種だって子に与える食事だって、誰かに決めて貰うわけにはいかない。
ただ、周りが余計なことを言ってきたり、やたら疑心暗鬼になったりで、自分の信じるべきものを見失ってしまうこともあるだろう。それは仕方の無いこと。
全てを完璧にやろうとするのではなく、自分が納得できるようにやることが一番だ。
本編とあまり関係ない感想になってしまった。読んでいて疲れたのは、あまりにも現実世界そのままの内容だったからかもしれない。コロナが流行していた時代のことはあまり思い出したくもないし…。ただ、遠い未来、本書を読む人が昭和から令和初期にかけての日本を知るに良いだろうな。その人(未来人)は読んだあと何を思うのだろうか。日本人は幸せだったと思うか、それとも惑わされてばかりだと思うのだろうか。
投稿元:
レビューを見る
2024/02/29リクエスト17
平成、令和と世の中の流行、事件や災害が出てきて、自分のその時と重ね合わせ懐かしい気持ちにもなった。
杉並区役所勤務の飛馬と不三子が物語をすすめていく。
杉並区役所というのが土地勘があるため読んでいて親近感が湧く。
不三子が義母だったら確かに疎遠になる。悪い人ではないと思うが自分の正当性を一番声高に叫んでいる。そして私は鬱陶しい義母にはならない、息子夫婦とはいい距離を保っている、と思いこんでいる。
その母親に子供時代にワクチン接種を受けさせてもらえなかったために家出していた娘は、どうして氷解したのだろう。私ならそのまま離れる。
登場人物誰にも共感できなかったが、全員が自分の意志、意見を持ち行動しているのでその点には好意を抱く。
評価に悩むかな…
投稿元:
レビューを見る
信じるとはどういうことか、何を信じるのかということを畳み掛けるように問われている気がした。
だまされまいとするあまり、べつのものにだまされているということはないか。(p.388)
ただしいはずの真実が、覆ることもあれば、消えることも、にせものだと暴露されることもある。(p.392)
読了後、じわじわと深みにハマっていく感じ。
投稿元:
レビューを見る
主人公2人の人生が年毎に書かれていて、2人の接点はどこで生まれるのかと思いながら読んだ。
様々な経験を経て、2人とも自分のこれから進むべき道を見出したのではないかと思えたラストは良かったと思う。
投稿元:
レビューを見る
(2024/8/13読了)
久しぶりに読んだ角田光代さん、そしてどこを開いても字で埋め尽くされた長編も久しぶり。
主人公二人の人生が年ごとに書かれている。
第一部は飛馬が1967年から1986年、不二子は1967年から1984年、第二部は飛馬が2016年から2022年、不二子は2016年から2021年。一部二部を通して、飛馬は小学生から進学、就職、結婚離婚を経て定年前まで、不二子は独身の会社員から結婚、子育て、夫との死別でおひとり様となった老年までが書かれている。
口裂け女やノストラダムス、阪神や東日本の大震災、コロナウィルスなど、その時々の情勢の中、迷いながら自分の考えに則って生きていく二人。二人が出会うのは第二部の子供食堂で仲間として。
ふたりとも根底には、例えるならノアの方舟のような思いがある。
飛馬の方が自分の背景と近く、思い込みが激しく、そんな行動はしてはいけないのにやってしまう思考回路も似ていて共感。
それにしても角田さんの人物の描き方はすごい。その人の人となりが入ってくる。現実に飛馬や不二子がいるようだ。
読後、達成感はあるけどスッキリはしないので、星は四つ。
投稿元:
レビューを見る
大きな事件は何も起きない。
どこにでもいるような
少年Aと主婦Bの55年間が
昭和、平成、令和の
3つの時代の出来事を交えながら
淡々と描かれていく。
出会いや別れ、成長と挫折
家族との確執…
結局、この世の中は
誰かが適当に作り出したまがいもので
あふれていると言いたかったのかな?
それでも人は何かにすがり
何かを信じ、何かを選んで生きていく。
ありふれた人生のようでも
一人ひとり特別なものなのだと思う。
投稿元:
レビューを見る
壮大な作品だった。時間軸が長いけれど、途中からは自分の生きた時代と重なってきて、ああそうそう、あの頃はこうだったよなあ、こんな事件あったよなあと頷きながら、一気に読んでしまった。コロナの頃の話が、つい最近なのに、こうして作品として文章化されると、物凄く昔の話で、しかもフィクションのように思えてしまう。
角田さんの作品の登場人物は、自分とは違うし、周りに同じような人がいたわけでもないのに、ああ、こういう人いるよな、知ってる。自分にもこういうところ、あるなあ、といつも思わされることが多い。