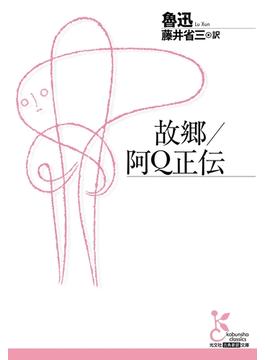故郷/阿Q正伝
久しぶりに再会した幼なじみは、かつて僕の英雄だった頃の輝きを失っていた……切なさと次世代への期待に溢れる「故郷」。定職も学もない男が、革命の噂に憧れを抱いた顛末を描く「阿...
故郷/阿Q正伝
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
久しぶりに再会した幼なじみは、かつて僕の英雄だった頃の輝きを失っていた……切なさと次世代への期待に溢れる「故郷」。定職も学もない男が、革命の噂に憧れを抱いた顛末を描く「阿Q正伝」。周りの者がみな僕を食おうとしている! 狂気の所在を追求する「狂人日記」など、文学で革命を起こした中国現代文学の父、魯迅の代表作『吶喊』『朝花夕拾』から16篇を収録。
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
やっと魯迅を読めた!
2019/01/13 22:08
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
魯迅は19世紀末の生まれで、20世紀初頭に活躍した中国人作家である。この作品集に収録されている作品の中では、やはり表題の「故郷」「阿Q正伝」そして「狂人日記」が突出しておもしろい、「故郷」におけるあこがれていた先輩がただの小汚い貧乏人にしか見えなくなってしまっていたという喪失感、「阿Q正伝」の俺はコテンパンに虐げられているけれど俺の方が血統がいいから俺の勝ちという脳内勝利という何だか自分に置き換えると笑えない話になってしまう辛辣な内容、「狂人日記」は俺はみんなに食べられてしまうと恐れ、狂ってしまう男の話なのだが、本当に狂っていたのか狂っているふりをして俺だけは違うと叫びたっかのか
面白い!
2017/02/05 10:35
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:だーしま - この投稿者のレビュー一覧を見る
授業で「故郷」をやったので、違う作品も読んでみたいと思い、また「故郷」の違う訳も読んでみたいと思い購入。「故郷」やあとがきを読んで、この人の訳の忠実さがわかりました。
職場にも阿Qのような人が結構いる
2020/12/19 20:24
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:うさぎさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
学生時代に読んだことがあった。もう一度読み返した。当時、阿Qのような人はまぬけだなあとだけ思って気に留めることはなかった。ところが、社会にでるとわんさか存在するのだ。他人事ではない。あせると誰でもこうなるかもしれない。 自戒もこめて、再読必須だ。
中国の小説家、魯迅の深い思想が垣間見られる短編集です!
2020/05/11 10:42
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、19世紀から20世紀に活躍した中国の小説家であり、翻訳家でもあり、思想家でもあった魯迅の短篇小説集です。表題の「故郷」は、主人公の生家の没落、故郷からの退去が話の中心となっており、これは魯迅本人の経験がもととなっていると言われています。また、当時の社会に残存する封建的な身分慣習に対する悲痛な慨嘆が込められてた作品としても高い評価が与えられています。また、「阿Q正伝」も、これ以下はないであろうと思われる最下層の人間を主人公に設定し、それを縦横無尽に活躍させることにより、巧みな布置の中に農村社会ひいては全体社会のさまざまな人間タイプの思考や行動の様式を浮き彫りにしている作品です。同書には、その他秀作14篇が収録されており、魯迅の思想や考えを目の当たりにできます。
本書の訳について少し思ったこと
2010/05/14 20:16
11人中、10人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:K・I - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書には魯迅の短編小説と、自伝的エッセイがおさめられている。
僕個人の話をすれば、魯迅は高校のときの教科書で読んだだけだ。
なぜ、再び読んでみようかと思ったのかはよくわからないが、この本の訳者の藤井省三氏が、
魯迅の「阿Q正伝」と村上春樹の『1Q84』を関連付ける発言をして、それを報じた新聞記事を読んだからかもしれない。
魯迅が影響を受けた作家として、夏目漱石、芥川龍之介、ロシアの作家のアンドレーエフ、チリコフの名が挙げられている。上記のロシアの作家は僕は知らないのだが、夏目漱石、芥川龍之介の名が挙げられているように、ここに収められているのは、「近代文学」のオーソドックスなスタイルだ。
その意味では、日本の近代文学を好む読者にとっては受け入れられやすいとも思う。
基本的にどの作品も楽しめたのだが、訳者は「あとがき」で魯迅の竹内好訳の訳文をかなりしつこく批判している。
まず、アメリカの「翻訳理論家のロレンス・ヴェヌティ」が翻訳を外国語・外国文化の土着化、本土化を意味するdomesticatinと土着文化・本土文化の外国化を意味するforignizatinの両面から分析していることをふまえ、竹内好の翻訳は魯迅を過度に「土着化、本土化」している、と非難している。正直言って、この論難が適当なのかどうかは僕には判断できない。しかし、「魯迅の文体は屈折した長文による迷路のような思考表現を特徴とする」からといって、直訳を基本的に試み、その結果として、「本書新訳では多くの文章が長く屈折しており、明快な論旨からは遠い訳文となっている」となるのは、少し納得がいかない。
たしかに読んでいてよく理解できない部分がまま見受けられたのは事実だ。それは、単に僕の理解力が足りないという理由もあるだろうが、本書の訳によるところもあるのだろう。
個人的には訳者の竹内好訳への執拗な批判はあまり読んでいて気持ちのよいものではない。また、訳者の批判の根拠付けもこちらの理解力が足りないせいか、完全に腑に落ちるとはいえない。
訳者は翻訳というものに関して、先のロレンス・ヴェヌティの分析を借りれば、土着文化・本土文化の「外国化」であるべきだ、と思っているようだ。しかし、それゆえに、意訳を可能な限り廃して、ゆえに、よく意味の通じない訳文になってしまっている部分もある(と少なくとも個人的には感じる)という翻訳というのは、どうなのだろう。
もちろん、学者に文句を言えるほどの立場ではないが、僕はある程度の意訳というものは必要ではないかとも思う。うまく自分の思っていることを表現できないのだが、僕が感じる翻訳というものは、外国文化の土着化に重心を置いている。その意味で、訳者の翻訳理解と僕の翻訳理解とは食い違っている。
そういうことを考えると、そもそも光文社古典新訳文庫という企画自体に少し疑問がわく。この本の帯には、「真の魯迅像を忠実に再現」「画期的新訳ついに登場!!」と書かれている。
「真の魯迅像」ということは、直訳を心がけた訳者の訳のことを言っているのだろう。
しかし、光文社古典新訳文庫のいくつかの既刊については、他の学者からその翻訳の「質」に関して、疑問がかなり提出されているのも事実である。
一般の読者としては、「新しい訳」ということで、「読みやすい」「近づきやすい」という感覚を持つだろう。そして、出版社もそういうイメージで売ろうとしているのだろう。しかし、少なくともこの本の訳に関しては、部分的にはよく分からない部分もある(と個人的には感じる)。
この小文において、翻訳とは何かという大きな問題について述べることは難しいし、それに僕にそれだけの力はないのだが、少なくとも、今回、藤井省三訳の魯迅を読んで、岩波文庫の竹内好訳の魯迅も読んでみようと思った。