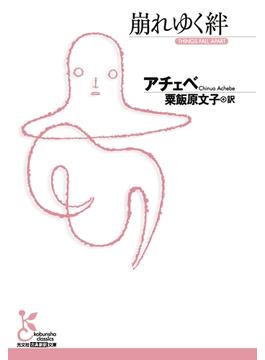0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:令和4年・寅年 - この投稿者のレビュー一覧を見る
アフリカの部族の暮らしが変わりゆく時代の風景。風習によって維持されてきた一つの社会が崩壊していく。キリスト教が入ってきた時の森と教会の役割もまた印象深かかった。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:H2A - この投稿者のレビュー一覧を見る
巻末にボリュームある解説があってかなり参考になる。それに丁寧な注釈はそのページにあって、イボ族の歌詞も日本語に訳され、付属の栞には登場人物まで載っていて良心的な本作り。慣れないアフリカ文学という敷居の高そうな本だが、その丁寧さには好感。ウォムフィア村のオコンクウォという男が、村の中で声望を得て財をなし妻も3人と子供たちといちおう平和に暮らしているが、その男性的な権威と力に頼る頑なさのために罪を犯して転落していき、最後には(この文化の中では忌み嫌われる)自殺を遂げる。当時のアミニズムの世界観での人々の暮らしと、迫りくるヨーロッパのキリスト教による侵略との対比の中で簡潔に描いて力強い。その文化は異様にも映り始めはとっつきづらいが、読み進むうちに独自の一貫した論理もあって洗練されていることがわかり、この小説が垣間見せてくれたその世界は忘れ難い。
これが3部作の最初の小説なら、その後の作品も合わせて訳してくれたらと思うのは贅沢というものだろうか。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Todoslo - この投稿者のレビュー一覧を見る
アフリカ固有の文化や風習が失われていく過程が、淡々と描かれています。すべてを手にした後で破滅へ向かう、主人公・オコンクゥワに現代の成功者を重ねてしまいます。
アフリカから西洋を批判した作品
2019/01/26 23:26
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
ナイジェリアの作家、アチェベの作品。未開の地を舞台にした作品というと想像してしまうのが「アラビアのロレンス」のように、知恵も勇気もなくて、ただ列強のされるがままになっている現地人を率いて戦う白人という図式しか想像できなかったのだが、この作品ではイギリスに支配されているナイジェリアのあっても、イギリス人が野蛮としか理解できない(キリスト教以外は野蛮な邪宗だと思い込んでいる)崇高な宗教が存在し、その宗教を基盤とした村社会が成立していたという前提から話が始まる。主人公・オコンクウォは戦士として死んでいきたいという苦悩の末に自殺という村では隠避といわれる方法を選択してしまう。その過程でのイギリス人(白人)の狡猾さは、なぜもっと後世に批判されないのか
民俗学的な語りのおもしろさ
2015/12/19 22:01
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:アトレーユ - この投稿者のレビュー一覧を見る
大好きな民話の語りのような話の流れ、そして少しダレそうになるあたりから一気に、起承転結の“転・結”がくる。小説としての完成度が高いというのかな。アト的に一部(アフリカの地域住民の慣習・伝承という基礎の上に成り立っている日常生活のお話。民俗学的)だけでも満足だけど。日本でもアイヌや蝦夷の話がある。同じように征討されて終わるのかと思いきや、意外な結末。だが、きちんと行く末を描かないことが、あからさまな政治臭を消し、小説としての浄化させてる、と思った。
解り合う努力を放棄して力で押さえつける安易さ…
2017/01/18 11:00
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:sin - この投稿者のレビュー一覧を見る
自然と共に生きるすべを呪術信仰に昇華したアフリカ人と、民族の衝突と私利私欲により洗練された宗教を持つ白人の、各々の神の正当性の主張はその背景にある武力の差によって優劣を決定された。白人は博愛の神の代弁者として圧政を敷きアフリカの風習を野蛮として退けたが、悲しいかな主張の隔たりが或る場合のお定まりの成り行きとは云えないだろうか?解り合う努力を放棄して力で押さえつける安易さ…
投稿元:
レビューを見る
キリスト教の流入と植民地化により、アフリカの部族社会が崩壊していく様子が、1人の男の目を通して描かれる。
とは言え物語が大きく動き出すのは半ばを過ぎてからで、前半は馴染みのない風習や儀礼に代表される土着文化が生き生きと描かれ、非常に興味深い。
余談だが、久々に登場人物の名前がなかなか覚えられない……という体験をしたw
投稿元:
レビューを見る
小説の前半に描かれる、呪術と迷信が跋扈する19世紀のアフリカ社会を描く筆致、その異様な迫力に圧倒される。年代的にはアチェベはそれら時代から少し隔たっており、本書を読むことは、作者が自らの拠り所としてのアフリカ社会の伝統を手繰り寄せる行為に立ち会う作業とも云えそう。
旧社会を代表するオコンクォの破滅を描くところで小説は終わるが、その先を描かないところにアフリカの深い自問があるのか、と思う。アフリカ現代を知りたいと感じる。
新訳を出版した光文社に拍手。
投稿元:
レビューを見る
チヌア・アチェベ『崩れゆく絆』光文社古典新訳文庫、読了。呪術と慣習の根深い伝統社会で生きる人々とそこに忍び寄る「文明」としてのキリスト教の植民地支配。
伝統的な価値観の崩壊と変化に抗あらがう男の悲劇を描く本作は、「アフリカ文学の父」と呼ばれる著者の代表作。
著者のコンラッド批判は有名だが、ただ著者の筆致は単純な否定と肯定でもない。カウンターとは違うそのたたずまいに多元主義の徴が光る。
投稿元:
レビューを見る
アフリカ伝統社会が西欧文明の流入により壊れてゆく様子を描いた小説。前半は伝統社会の描写で入り込むまで時間がかかるが、それでも読み進むねうちはある。映画「セデック・バレ」や、明治日本の近代化、さらには高度経済成長以後の日本の変化にも重ね合わせて読んでみたい。
投稿元:
レビューを見る
「アフリカ文学の父」チヌア・アチェベ。
まだ当時、イギリス植民地だったナイジェリアの出身。
キリスト教徒の熱心な教育を受けると共に、土地の慣習や文化にも慣れ親しんでいた。
そんな作家が、植民地化前夜にあたる時期のナイジェリア(イボランド)を描いた作品。
読んでよかった。本当に読んでよかった。
第1部のイボ語のことわざや口伝の慣習、その土地の宗教観は読んでいるだけでもワクワクする。
特に音楽的な描写は本当に楽しくて、「太鼓奏者がスティックを持つと、大気が震え、ぴんと張った弓のように緊迫した。」(p.84)や「心の耳をすませば、エクウェ、ウドゥ、オゲネが奏でる、血の沸き立つような入り組んだリズムが聞こえてくる。そして自分の笛の音もそのリズムと絡み合い、華やかで哀愁漂う旋律を添える。全体としては陽気で快活な調子。しかし、笛の音が抑揚をつけて響き、ついで短い断片になっていくのを聞きとると、そこに悲しみや嘆きの趣を感じることができるのだ。」(p.21)「太鼓が奏でているのは、紛れもなく、格闘のダンスだ。速く軽快で、陽気なリズムが、風にのって運ばれてくる」(p.75)など、読んでいるだけで体の底からリズムを感じるようなアフリカンミュージックの鼓動!
第2部と第3部。
キリスト教宣教師。
元の土地の宗教では救われなかったり弱者であった人々を筆頭に、改宗していく…その気持ちはよくわかる。
でも、宗教の善し悪しを話しちゃいけない。温厚に話し合っている場面ですら、その壁を越えたり壊したりしちゃだめだと、苦しくなる。
しかも「宗教は政治と一緒にやってきた。」
そして第3部のラスト1行の、この衝撃。
チヌア・アチェベは、コンラッドの「闇の奥」を批判した人であるらしい。
アチェベを読んだ後に「闇の奥」を再読したら、また何か変わるかな。
今は、アチェベの他の作品や、紹介されているアフリカ文学を読んでいきたい。
投稿元:
レビューを見る
ヤムイモのリアリズム。アチュべはナイジェリア出身の作家。ナイジェリアはヤムイモ産出量世界1位。なによりもまず重要なのはイモであり、あらゆる食事にヤムイモなのである。
客人がやってきてに「コーラあるよ」ともてなすのだが、これはコカコーラの原料の「コーラの実」のようである。覚醒作用があるようなのでやっぱりお酒かドラッグみたいなものなのか。
ナイジェリアの生活様式が興味深い。村で生活するためのシキタリ。それを決めるのは長老かお告げ師である。長生きできることが尊敬に値する、というのは子供の生存率が低いということからも分かる。
コミュニティでは親分から種イモをもらって小作は畑を肥やしそれが生活の糧となる。一夫多妻制で、主人公の妻は3人いる。家屋は主人を中心とし放射線状に離れがあり、妻はそこで子供と暮し、毎日主人の食事を用意する。家長はとても威張っている。作ってくれた食事に文句を言うし、安易に妻へ暴力もふるう。いろいろとしょうがない。
村の余興はレスリング。もちろん強い男が評価される。村人たちはそれを見るのが娯楽。村には巫女がいて「憑かれていない」ときは普通に生活している。(←これはあとで豹変する)
近隣のコミュニティとの軋轢もある。おそらく生贄状態でやってきたよその村の子供を囲って主人公は息子同然に育てるが、村の長からお告げによりそいつは殺すべしと指示され、親代わりだった男が自ら手をくだすことになる。ひどい。それは成長した他所の男が女を孕ませることができる歳になっているという危機感による、原始的な男らしさでもある。
女性は16歳で嫁に行く。婿希望者は持参金を持って女性の父親とかけあう。男同士は椰子酒を飲んで仲良くなる。嗅ぎ煙草を入れている「山羊の革の袋」がよく出てくるが、これはおそらく山羊の胃袋で携帯するポーチのような役割として使われているのではないだろうか。
一夫多妻なので、男子を生むことが女性の地位をあげることになる。子供をたくさん産んでも成長させることが難しいのは悪霊のせいなのであったりする。あるいは大事な石をどこかに埋めてしまったからであったりする。
(登場人物がどんどん増えていく。舞台はアフリカなので「ン」ではじまる名前も多く、慣れないと覚えるのが難しい)
そして後半、突如外部から白人が宗教を布教しにやってきて、長く続いていた土着コミュニティはもろく崩れていく……。ここからですよキモは。キリスト教と白人の欺瞞が。ああ、アフリカの文学。コンラッド『闇の奥』が苦手だった人にもお勧め。今の時代、わたしたちが知るべきはこっちの世界だ。
投稿元:
レビューを見る
19世紀のアフリカを舞台とした、欧州の植民地支配によって分断されていく家族と共同体の物語。あらすじはシンプルだけど、実際にはとても重層的な意図の込められた、にもかかわらず単純に物語としても面白く読めてしまう本だった。語り口の変化は近代化のメタファーとして機能しているし、支配の過程も単純な二元論では収まらない。そもそも著者が植民地支配の教育を受けて育つことで、その支配以前の文化を書き留められたこと自体が逆説なのだろう。その上で、個人の弱さを軸とした物語は時代も文化も飛び越えて、こんなにも普遍的に届いてくる。
投稿元:
レビューを見る
少し前に文庫化されぜひ読みたいと思っていた一冊。アフリカ文学の父といわれる、チヌア・アチェベの記念碑的一冊ということ。アフリカ文学には聡くないので、そういう意味での評価はできないが、歴史的背景も合わせて様々な学びを与え、人間と歴史の気づかない側面を教えてくれた。
未開のアフリカ、一部族を取り巻く現代の侵入とりわけ西洋、キリスト教の侵入を描いている。レヴィ=ストロースをはじめとする文化人類学の発展は、未開の兄弟たちに対する人権的な意味での理解を進めてくれた。キリスト教主義からの絶対史観がよろめいてしばらくたったところに新たに相対的な視点を与えてくれた。この作品はそういう視点に立っているといえば少し違うのかと思う。文化人類学はあくまでも西洋が見た未開の人間に対する学であるが、アチェベは現地イボ人の作家であるのだから。アチェベ自身はキリスト教化の後のアフリカに生まれ、熱心な信徒である両親の愛を受け育った文化人であるが、この作品から漂う土と血と鉄の臭いは、アフリカの血を受け、人と信仰と歴史の交差路に悩む生きた人間の生臭さがある。
一様にキリスト教を非難しているわけではない。土着の文化の非人道的な解釈も痛々しさは隠せない。こういう文化の中には明確に人間個人に先んじる価値が存在していて、それを守るためなら人間を殺すことにも躊躇はしない。しかしイケメフナを神託を持って殺したオコンクォには抑えることの出来ない葛藤と後悔があふれていた。
『崩れゆく絆』とはよく作品を表したタイトルである。部族の伝統と宗教が西洋の侵入によって崩れていく。しかしそこに描かれるのは、人間自体が持っている悲しさである。部族の価値にとどまるも、キリスト教に染まるも、悲しき人間の生き方、歴史である。
15/3/26
投稿元:
レビューを見る
ひとことで言うと部族の価値観をやや過剰に体現していた男がそれ故に居場所を失う話。出来事は突然に起こる(銃が暴発するがごとく)、但しその予兆、萌芽が十分に感じさせられるのでオコンクウォ、ウムオフィアの運命に必然性を感じられる。
部ごとの変奏がすばらしく、ラストは美しく冷徹。
作者やイボの実存を問う作品で歴史的な作品なのだと思う。
訳も原書と比較したわけではないが、とても丁寧で愛を感じる。訳者あとがきも同様。ただ本編読了後早く読みすぎないほうがいい気がする。素晴らしいので自分の感想が抑圧されてしまう気さえする。