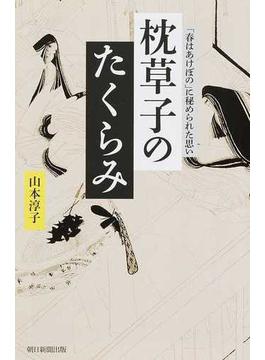「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
読割 50
紙の本
枕草子のたくらみ 「春はあけぼの」に秘められた思い (朝日選書)
著者 山本淳子 (著)
清少納言が中宮定子に捧げた作品「枕草子」。定子の死後、その敵方であった藤原道長の権勢極まる世で潰されることなく、作品として生き残ることができたのはなぜか。その謎を解明する...
枕草子のたくらみ 「春はあけぼの」に秘められた思い (朝日選書)
枕草子のたくらみ 「春はあけぼの」に秘められた思い
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
清少納言が中宮定子に捧げた作品「枕草子」。定子の死後、その敵方であった藤原道長の権勢極まる世で潰されることなく、作品として生き残ることができたのはなぜか。その謎を解明する。【「TRC MARC」の商品解説】
【文学/日本文学評論随筆その他】藤原道長が恐れ、紫式部を苛立たせた書。それが随筆の傑作「枕草子」だ。権勢を極めてなお道長はなぜこの書を潰さなかったのか。冒頭「春はあけぼの」に秘められた清少納言の思いとは? あらゆる謎を解き明かす、全く新しい「枕草子」論。【商品解説】
藤原道長が恐れ、紫式部を苛立たせた書。それが随筆の傑作「枕草子」だ。権勢を極めてなお道長はなぜこの書を潰さなかったのか。冒頭「春はあけぼの」に秘められた清少納言の思いとは? あらゆる謎を解き明かす、全く新しい「枕草子」論。【本の内容】
著者紹介
山本淳子
- 略歴
- 〈山本淳子〉1960年金沢市生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科修了、博士号取得(人間・環境学)。平安文学研究者。京都学園大学人文学部歴史文化学科教授。著書に「源氏物語の時代」など。
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
清少納言の想いに涙しました
2017/06/15 00:34
7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:bluemonkey - この投稿者のレビュー一覧を見る
清少納言の定子への想いに自然と涙が出ました。
失意の中屈辱的な日々を送る定子の心を癒し、一条に愛されながらも力尽きて逝った定子の魂を慰めるため、清少納言は書いた。
時には涙しながら書いていたかもしれない。
定子は枕草子の中で、明るく知性にあふれ思いやりのある気遣いができる魅力的な中宮として輝き続ける。
そんな清少納言の健気な想いに心が震えました。
切なくも爽やかな読後感を与えてくれた作者の山本淳子先生に感謝します。
紙の本
とても面白く新鮮な驚きに満ちている
2018/05/21 21:42
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:たあまる - この投稿者のレビュー一覧を見る
「枕草子」といえば、小学生の教科書にも載っている、古典中の古典。
だれでも知っているでしょう。
私も古文の授業で教わったし、参考書や問題集では一部を読んでいたけど、読書としては読んでいませんでした。
それでもなんとなく、「枕草子」や清少納言のイメージは持っていたのですが、『枕草子のたくらみ』(山本淳子・朝日新聞出版)を読んで、ずいぶんそのイメージが変わりました。
この本自体がとても面白く新鮮な驚きに満ちていて、そこに描かれる「枕草子」がとても興味深いのです。
何より「平安時代のお堅い才女」みたいだった清少納言のキャラ(これ、完全に誤解でしたね)が、賢くもあり、かわいくもある女性に見えてきたのです。
そして清少納言が仕えていた中宮定子も魅力的です。
彼女らを取りまく、藤原氏を中心とした平安貴族の社会のようすもよくわかります。
こんな本を学生時代に読んでいたら、古文の学習がもっと楽しめたのになあ。
技術の進歩に直接役立つ自然科学と違い、文学なんて「役に立たない」と思われたりもするようですが、昔の書物がこんなに面白くよみがえり、楽しめるなんて、文学の研究って、なんて実り多く豊かなものなんだろうと思いました。
文部科学省は、こういう研究にちゃんと予算を出してよ。
紙の本
枕草子の見方が変わる
2020/11/05 09:38
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:pizzaco - この投稿者のレビュー一覧を見る
学生時代、教科書に載っていた『春はあけぼの』の美しい描写。
自分の好きなものや宮中の生活を描いた随筆。
というイメージしかなかった枕草子。
だが、その時代の歴史と照らしてみると矛盾が生じる。
中宮定子とその一族の栄華と悲劇の歴史、道長との権力争い、一条天皇の思い、それらを清少納言という才気あふれる女性の筆が、描いたものだった。定子という稀有な貴人を守るため、周到なたくらみを持って。
文学好きにも歴史好きにもおすすめの一冊。
紙の本
定子皇后への
2020/01/10 13:50
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:earosmith - この投稿者のレビュー一覧を見る
田辺聖子さんの「むかし、あけぼの」を読んでいたので、とても興味深く楽しめました。枕草子に込められた、清少納言の定子皇后への言葉には尽くせない思いに心打たれました。
紙の本
古典の見方が激変しました
2017/12/14 11:42
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:フィン - この投稿者のレビュー一覧を見る
枕草子は学生時代に授業で読みました。源氏物語に比べて平坦な印象であまり好きではなかったのですが。「たくらみ」というタイトルに惹かれて手にして、ホントに良かったと思います。
才気煥発のイメージがあった清少納言が実は劣等感に悩まされていた知って、一気に親しみがわいたこと。そんな彼女がなぜ必死にこの作品を書き続けていたのか、なぜ彼女がこんな書き方をしていたのか。まるで大河ドラマを観ているようでした。
古典を読むには、その時代背景をしらなければ半分も理解できないのだとつくづく思いました。次は同じ著者の「源氏物語」についてほ本を読みます!
電子書籍
文句なく面白かった!
2020/04/16 16:23
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:qima - この投稿者のレビュー一覧を見る
ネットでおすすめされていたので手に取りましたが、期待に違わぬおもしろさでした。やっぱり物語はその背景や歴史まで含めて楽しむものですね。満足。
紙の本
本当の賢さ
2017/06/03 14:13
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:nobita - この投稿者のレビュー一覧を見る
今でも光る彼女の天才さとゆたかな感性および趣深さ。いつ読んでも最高!