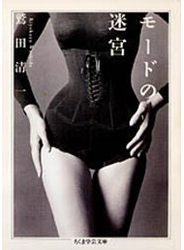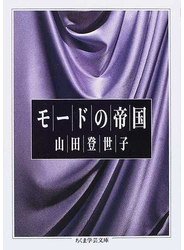ブックキュレーターhonto編集員
ブックキュレーターhonto編集員
「装う」ということとは?ファッションを哲学するための本
認識が追いつかないほどに日々刻々と軽やかに移り変わるファッション。この浮薄なゲームを言葉で追いかけ分析することに、はたして意味があるのか・・・。実は分析の道具である言葉、ひいては思考そのものに、ファッションと似たところがあるのです。装うことが人間の本質だとすれば、「本当の私」なんて存在しないのかも?と思えてくる本を紹介します。
- 12
- お気に入り
- 8386
- 閲覧数
-

モードの体系 その言語表現による記号学的分析
ロラン・バルト(著) , 佐藤 信夫(訳)
記号学者のロラン・バルトが、モード雑誌に書かれたテキストがいかに流行を生み出すのか、そのメカニズムに記号論的に迫った大著です。もともとは身体を覆うためのものであった衣服がその機能性を超えてファッションとなる上で、いかに言葉が重要な役割をはたしているのかを解説しています。流行にはそのつど新たな言葉が必要なのです。
-

モードの迷宮
鷲田 清一(著)
「人間の身体」という視点からファッションに迫った好著です。衣服を身体の一部、ひいては身体を作るものとして捉え、ファッションがつねに変化をその本質とし「不均衡」であるからには、それに規定される「わたし」という存在もまた、頼りなく不安定な存在でしかありえないと本書はいいます。「本当のわたし」について考えさせられる一冊です。
-
まるで「衣服」を哲学しているように思えるタイトルですが、実は逆です。制度や道徳というものはそのつど着脱する衣服のようなものである、と本書では主張しています。つまり、人間の思考のクセもまた時代に規定されたファッションに過ぎない、と看破していて、思想は衣服に似ているのかも?と思えてきます。
-
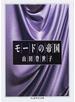
モードの帝国
山田 登世子(著)
「装う」とは何か?ファッションに関するその根源的な問いを、エロスと結びつけて論じたのが本書です。モードの歴史を振り返りながら衣服の変遷とともに、私たち人間のエロスがいかに衣服に規定されてきたかが、強い説得力をもって示されています。
-

ファッションは語りはじめた 現代日本のファッション批評
西谷 真理子(編)
刻々と移り変わるファッションという現象に、言葉が追いつくための画期的な試みともいえる一冊です。新進気鋭の批評家・哲学者・デザイナーらが、現代日本におけるファッションの可能性を論じています。ある流行が生じる文脈を探ることで、ファッションという一過性の現象をより豊かなものにすることができるようになるかもしれません。
![]()
ブックキュレーター
honto編集員ブックツリーとは?
ブックツリーは、本に精通したブックキュレーターが独自のテーマで集めた数千の本を、あなたの"関心・興味"や"気分"に沿って紹介するサービスです。
会員登録を行い、丸善・ジュンク堂・文教堂を含む提携書店やhontoでの購入、ほしい本・Myブックツリーに追加等を行うことで、思いがけない本が次々と提案されます。
Facebook、Twitterから人気・話題のブックツリーをチェックしませんか?
テーマ募集中!
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを募集中です。あなたのリクエスト通りのブックツリーが現れるかも?
テーマ応募フォーム
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを入力してください。
ご応募ありがとうございました。
このテーマにおける、あなたの”6冊目の本”は?
※投稿された内容は、このページの「みんなのコメント」に掲載されます。
コメントを入力するにはログインが必要です