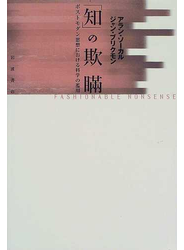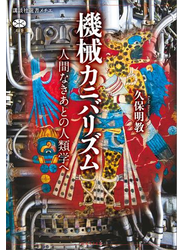ブックキュレーター哲学読書室
ブックキュレーター哲学読書室
文系的思考をその根っこから科学技術へと開くために
科学技術は現代社会に大きな影響を与えていると言われますが、社会や人間を対象とする「文系」学問(人文・社会科学)の主要なトピックとはされていません。何故こうした分割が生じており、いかにそれを乗り越えることができるかを考えるための5冊を選びました。【選者:久保明教(くぼ・あきのり:1978-:一橋大学准教授)】
- 131
- お気に入り
- 8391
- 閲覧数
-

文系と理系はなぜ分かれたのか
隠岐さや香(著)
文/理の区別は学問を分類する19世紀以降の考え方の一つであり、決して固定的なものではないこと、でもそこには、近代的な学問が宗教的/世俗的な権威から自律していく過程で生じた「人間をバイアスの源と捉える立場」と「人間を価値の源泉と捉える立場」の違いが息づいていることがバランスよく論じられています。
-

科学論の現在
金森 修(編著) , 中島 秀人(編著)
人間をバイアスの源と捉えて数学など形式的な論理を重視する発想に基づく科学技術が社会に甚大な影響を与えるようになった20世紀後半、人間を価値の源泉として捉える立場から科学や技術もまた社会的に構成されると論じたのが、科学(技術)社会学でした。この本の第一部では、その有効性と限界が多角的に検討されています。
-

「知」の欺瞞 ポストモダン思想における科学の濫用
アラン・ソーカル(著) , ジャン・ブリクモン(著) , 田崎 晴明(訳) , 大野 克嗣(訳) , 堀 茂樹(訳)
ポストモダン思想における物理学/数学用語の濫用を自然科学者が批判した書として有名ですが、筆者たちのもう一つの標的は、科学的知識の社会的構成を論じる科学社会学でした。人間を価値の源泉とする立場から科学を捉えることが、人間をバイアスの源と捉える立場からいかに不当なものに見えてしまうかを鮮明に示す一冊です。
-

ブルーノ・ラトゥールの取説 アクターネットワーク論から存在様態探求へ
久保 明教(著)
科学は人間というバイアスを排して自然の事実を的確に捉えるものか。それとも、人間という価値の源泉に根ざして社会的に構成されるものか。この二つの立場を同時に否定し、科学技術も社会的実践も人間と人間以外の存在が絡まりあうネットワークの動態として捉えるラトゥールの議論を平明に解説しながら検討した本です。
-
将棋ソフトやSNSをめぐる具体的事例から、「近い将来AIが人間の知的能力を超える」という未来予測が広まる現代における人間と機械の関係を捉え直し、文系的思考の根っこにある近代的な人間観から離脱することで、それを科学技術に開いていく道筋を構想した本です。ラトゥールの議論が方法論的基礎の一つになっています。
![]()
ブックキュレーター
哲学読書室知の更新へと向かう終わりなき対話のための、人文書編集者と若手研究者の連携による開放アカウント。コーディネーターは小林浩(月曜社取締役)が務めます。アイコンはエティエンヌ・ルイ・ブレ(1728-1799)による有名な「ニュートン記念堂」より。
ブックツリーとは?
ブックツリーは、本に精通したブックキュレーターが独自のテーマで集めた数千の本を、あなたの"関心・興味"や"気分"に沿って紹介するサービスです。
会員登録を行い、丸善・ジュンク堂・文教堂を含む提携書店やhontoでの購入、ほしい本・Myブックツリーに追加等を行うことで、思いがけない本が次々と提案されます。
Facebook、Twitterから人気・話題のブックツリーをチェックしませんか?
テーマ募集中!
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを募集中です。あなたのリクエスト通りのブックツリーが現れるかも?
テーマ応募フォーム
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを入力してください。
ご応募ありがとうございました。
このテーマにおける、あなたの”6冊目の本”は?
※投稿された内容は、このページの「みんなのコメント」に掲載されます。
コメントを入力するにはログインが必要です