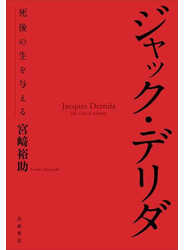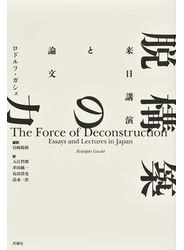ブックキュレーター哲学読書室
ブックキュレーター哲学読書室
「死後の生」を考える、永遠の生を希求することなく
死んだらどうなるのだろう?──誰もが抱くこの素朴な疑問に対して古代の哲学者は、現世の生そのものが孕む「死」の意味を説くことを通じ、此岸の生の倫理を示した。デリダは決して「魂の不死」も「永遠の哲学」も主張しないが、ソクラテスと同様、私たちの有限な生を、いまここにある「死後の生」、此岸において死と対峙することで肯定されるべき生として探究した。デリダの思想から「死後の生」を考えるための五冊。【選者:宮崎裕助(みやざき・ゆうすけ:1974-:新潟大学准教授)】
- 64
- お気に入り
- 8898
- 閲覧数
-
脱構築はその言葉からしばしば破壊的なニヒリズム、生を否定する死の哲学とみなされてきた。しかしデリダが生涯追究していたのは、死の哲学どころか、死が折り込まれた生、いまここで生を超えてゆく生、そうして死後になお生き延びる生の肯定の思想であった。そこから出てくる多様な展開を、言語、立法、労働、動物、友愛、家族、民主主義といった後期思想の諸テーマに即して論じた一冊。
-
「死後の生」の考えを求めて哲学史を遡るとすれば、まずはこの本を挙げたい。ソクラテスが死刑執行当日に語った、「魂」をめぐるあまりにも有名な問答。その重要なテーゼのひとつは、哲学とは「死の練習」であるというものだった。威厳をたたえた晴朗さのなかで死を受け容れるソクラテスの姿は、現世への諦念であるどころか、此岸において「死後の生」を肯定する哲学の原光景を提示している。
-

ベンヤミン・コレクション 2 エッセイの思想
ヴァルター・ベンヤミン(著) , 浅井 健二郎(編訳) , 三宅 晶子(ほか訳)
デリダの「死後の生」が参照するのは、ベンヤミンの「翻訳者の使命」に出てくる Überleben(生を超える生)と Fortleben(生以後の生)という言葉である。「死後の生」とは、有機体の生命のみならず、なにより歴史的にみられた生であり、芸術作品の生を含んでいる。翻訳は意味や文脈を移し替えることで作品の生を損なうが、そのことでこそ作品を当の生以上に生きながらえさせるのである。
-

動物を追う、ゆえに私は〈動物で〉ある
ジャック・デリダ(著) , マリ=ルイーズ・マレ(編) , 鵜飼 哲(訳)
「死後の生」は人間の生だけではない。デリダのいう「死後の生」は人間主義から見られた生の概念を問い質し、人間と動物の境界をも脱構築するにいたるだろう。デリダがバスルームで飼い猫のまなざしから受け取った恥の感情、それは、種差や個体差を超えて交錯する生の有限性と特異性の痕跡である。人間/動物、生/死のリミトロフィー(境界培養)の書。
-

脱構築の力 来日講演と論文
ロドルフ・ガシェ(著) , 宮崎 裕助(編訳) , 入江 哲朗(訳) , 串田 純一(訳) , 島田 貴史(訳) , 清水 一浩(訳)
デリダの死後、脱構築そのものの「死後の生」はどうなるのだろうか。ド・マン、デリダの衣鉢を継ぎ、脱構築思想のフロンティアを開拓してきた第一人者による日本版論集。デリダ以後、デリダなき脱構築は、脱構築をキーワードとして特権化すらしない思考の厳戒態勢のもと、秘密裡かつ複数形でその遺産を相続し散種するのである。
![]()
ブックキュレーター
哲学読書室知の更新へと向かう終わりなき対話のための、人文書編集者と若手研究者の連携による開放アカウント。コーディネーターは小林浩(月曜社取締役)が務めます。アイコンはエティエンヌ・ルイ・ブレ(1728-1799)による有名な「ニュートン記念堂」より。
ブックツリーとは?
ブックツリーは、本に精通したブックキュレーターが独自のテーマで集めた数千の本を、あなたの"関心・興味"や"気分"に沿って紹介するサービスです。
会員登録を行い、丸善・ジュンク堂・文教堂を含む提携書店やhontoでの購入、ほしい本・Myブックツリーに追加等を行うことで、思いがけない本が次々と提案されます。
Facebook、Twitterから人気・話題のブックツリーをチェックしませんか?
テーマ募集中!
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを募集中です。あなたのリクエスト通りのブックツリーが現れるかも?
テーマ応募フォーム
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを入力してください。
ご応募ありがとうございました。
このテーマにおける、あなたの”6冊目の本”は?
※投稿された内容は、このページの「みんなのコメント」に掲載されます。
コメントを入力するにはログインが必要です