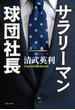映画化したら面白いのに
2020/10/17 08:23
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る
読売新聞社会部記者を経て、読売巨人軍球団代表になるもその後解任。その後、山一証券の破綻を描いた『しんがり 山一証券最後の12人』で講談社ノンフィクション賞を受賞とノンフィクション作家に転身した清武英利さんが、2019年から2020年にかけて「週刊文春」に連載したノンフィクション作品。
週刊誌の連載時につけられた副題の方がこの作品の内容をよく伝えている。
すなわち、「阪神と広島を変えた男たち」。
阪神、いうまでもなく巨人の永遠のライバル「阪神タイガース」。そして、広島は今でこそ強いイメージがあるがかつてはお荷物球団ともいわれた「広島東洋カープ」。
かつてこの2つの球団に親会社のサラリーマンから出向させられ、のちに球団社長かそれに匹敵する地位にまでなった男たちがいる。
この二つの球団だけが「サラリーマン球団社長」ということはない。
多くの球団が元々普通のサラリーマンであったのが「球団社長」になっている。
ただ、この作品で取り上げられている二人の場合は、常にフロントと現場で問題が発生する阪神であったり、弱小球団だった広島の「球団社長」として、その活動が著しかったということだ。
清武さんは彼らの活動が2つのことを証明したという。
1つは変革が異端者によって成し遂げられることが多いということ。
もう1つは、素人であっても情熱があれば理想球団の夢が描けるということ。
ビジネスの観点からも参考になるし、野球の裏話としての面白さも楽しめる、そんなノンフィクション作品だ。
カープの鈴木さん
2023/10/08 20:25
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:陽だまり - この投稿者のレビュー一覧を見る
広島東洋カープの鈴木さんの存在は随分前から知っていました。
一読して、いままで随分ご苦労されたことがよく分かります。
黒田さんや秋山さんをカープに入団(復帰)させたのは、間違いなく鈴木さん!
著者は新聞社ご出身とあって、文章の書き方が流石に上手いと思います。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なま - この投稿者のレビュー一覧を見る
プロ野球の球団社長をするなどということは、ほとんどの人とは縁のない事だろう。しかし、実際にやってみたらどれほど大変な事なのだろうと思わせる話ばかりだった。
『サラリーマン球団社長』
2020/12/24 19:03
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:百書繚乱 - この投稿者のレビュー一覧を見る
お家騒動がお家芸の万年Bクラス“ダメ虎”阪神タイガース
主力がFAで流出する赤貧球団の“赤ヘル”広島東洋カープ
「来月から、タイガースの常務取締役として働いてもらおうと思ってね」
「東洋工業を辞めて、うちの球団に来んか」
本社から球団に出向した二人のサラリーマンが球団の体質や機構の旧弊に抗いながら改革に挑戦する
《たとえ素人であっても、頑固な情熱があれば理想球団の夢が描ける》──「プロローグ」より
野村、星野、黒田、金本……脚光を浴びた監督や選手をつくりだしたフロントに光を当て、ナベツネにジャイアンツを追われた同じ“サラリーマン球団社長”の清武英利が克明に描いたノンフィクション
阪神ファン、広島ファンだけでなく、すべてのプロ野球ファンに
「週刊文春」2019年12月〜2020年5月の連載に加筆修正して単行本化、2020年8月刊
一気に読んでしまいました
2020/11/18 16:30
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:キュリオ船長 - この投稿者のレビュー一覧を見る
内容は「プロ野球」という業態を扱っていますが、
「プロ野球」を知らずとも純粋に入り込めるものになっています。
著者自身が球団関係者ということもあり、「プロ野球」が興行である以上、
他の人では表現できないような細部が丁寧に描かれています。
加えて「プロ野球」に興味ある方なら、「おぉ」というようなエピソードも
あり、一気読みできました。
老舗球団・弱小球団の体質であったり、財務状況であったり、
人事抗争であったりと、いわゆるサラリーマン本の定番を
踏んでいますが、どの世界も一緒だとの印象を受けました。
投稿元:
レビューを見る
【無名の組織人に光をあてた傑作ノンフィクション】どん底に喘ぐ阪神タイガースと広島カープの優勝。そこには野球とは無縁な傍流者2人の奮闘があった。週刊文春の人気連載を1冊に。
投稿元:
レビューを見る
球界再編当時に現場に関わった筆者だからこそ書けるドキュメント。当時の広島市民の焦燥感を思い出します。阪神の野崎さんには足を向けて寝れない。m(__)m
投稿元:
レビューを見る
かなり読み応えがあり一気に読むことができた。阪神と広島の内部の構造の違いがかなり明確に語られており特にどっちのファンでもないが面白かった。特に阪神って想像してたより酷い体質なんやと思ったし、今でもこうなんやろうなって感じる。
あとは2人のフロントマンとしての経験の話が面白かったけど、野崎さんはこんな形で球団去るようになって悔しかったんやろなぁって思う。
プロ野球好きやったら読んでみて損はない1冊やと思う。
投稿元:
レビューを見る
本書の主役は、阪神タイガース 野崎勝義氏と広島東洋カープ 鈴木清明氏。いずれも元選手ではなく、行きがかり上、プロ野球界に背広組の一員として入ったバリバリのサラリーマン。
野崎氏は阪神電鉄の海外旅行部門一筋のエキスパート、鈴木氏は東洋工業経理マン。この話は門外漢のふたりが球団改革に駆り出されていくところから話はスタートする。
著者は読売新聞社からジャイアンツに転身、GMを務めた。同一リーグのライバル球団のフロントマンとしてシノギを削った間柄。ゆえに親会社と現場の板挟み、オーナーの朝令暮改な指示に翻弄される中間管理職の悲哀…理解し合える、謂わば同士のような関係だけに文中にも時折「私」として登場し、見解を添える。
【広島東洋カープ 鈴木清明 氏の奮闘】
主催ゲームの売店で販売するちくわの仕入本数に悩み、フィットネスクラブの店長の辞令を受けたり、南米ドミニカ共和国でのカープアカデミーの担当者として派遣されたり、とにかくオーナーからの無理難題を押し付けられ、球団の基礎固めに奔走。球団運営に回ればエースと四番の高騰する年俸に対応できず、毎年の様にFA宣言され他球団へ流出。そう、育てては去られるの繰り返し。それでも鈴木氏は前を向きに『大木がなくなれば、そこに陽が差し、また新しい芽が出る』と語る。そんな苦境を乗り越え、念願のスタジアムの完成、大リーグの高額年俸を蹴りカープに電撃復帰した黒田博樹の男気、刃折れ矢尽き果てた新井の復帰、そして2016年の25年ぶりとなるリーグ優勝…。この裏には、鈴木氏の慈愛の精神と情熱、鈴木氏の手腕を信じ任せたオーナーの胆力が揃い、大団円を迎える。現在は常務取締役球団本部長として辣腕を振る。
【阪神タイガース 野崎勝義 氏の奮闘】
球団役員と言っても親会社の部長クラス。改革しようにもそこに立ちはだかる社内に巣食う営業・編成・スカウト各部門の既得権益者たち。様々な抵抗に遭いながら地道に社内の風土改革に励む。一番の難敵は野崎を抜擢した阪神電鉄会長兼球団オーナーの久万氏。対米追従の日本政府よろしく巨人の動向を気にし、日和見主義な言動を繰り返す。92年の2位を最後に10年間下位を低迷。観客動員も200万人を切る惨状ながら、大ナタと振ることは監督の首のすげ替えと信じて疑わない旧態依然の電鉄本社、群盲の守旧派が席巻する球団スタッフ。やがて野崎氏は社長に就任し、手を緩めることなく大胆な球団改革に着手する。それはベースボール・オペレーション・システム(BOS)の球界初の導入。
しかしながら、ここでも守旧派の抵抗に遭い、野崎氏の目論見は露と消える。システムの推進役は日ハムにヘッドハンティングされ、それを導入するや日ハムは常勝集団に突き進むという実に皮肉な結末をたどる。在任中二度のリーグ優勝を果たすも、その後野崎氏は球団を退任。
著者は野崎氏の肝いりで導入しようとしたBOSの頓挫について、ある事例を用いて解説する。
トヨタの生産システムである『カンバン方式』を導入・定着させた大野工場長は、自身の合理性と洞察力に加え、システムを徹底させるために時に『怒鳴り声』を上げた。従わない社員を怒鳴り上げてもやらせる気迫が加��ってこそ初めて実現したシステムだったと。
翻ってタイガースには、その怒鳴り声を発する工場長がいなかった。本来なら球団本部長が陣頭指揮すべき者が守旧派のスカウト側に立って反対している有様。
当時を知る球団要職者は坦懐する。
『本社は2回優勝して満足してしまった。野崎さんはドラスティックに球団を変えました。彼の球団本部改革やスカウト改革を、私たちが推進することができなかったという自省があります。特に編成部長やその下のスカウトや現場の抵抗が強かった』。
昔、ある清廉な政治家が首相就任を打診された際に語った『表紙だけを変えたところで何も変わらない』。優勝から15年も遠ざかり、相も変わらず監督の首のすげ替えを繰り返し、功労者への労う言葉を持たない阪神球団。
この言葉ほど、この球団を言い得たものはない。
久々にトホホな読後感に苛まれた一冊。
投稿元:
レビューを見る
芦屋 高級住宅地だけでない 埋め立ての方
p61 極限状態では運が命を左右する
p76 スパーキー 敗者からの教訓
p118 川上哲治 遺言
p208 大曽根幸三
ある副社長の語録
上がファジーだと下はビジーになる
部下は上司の言うとおりに育たず、上司のやる通り育つもの
出る杭を叩いて上司上をみる
共存共栄は最後には強存強栄にしかならない
偏屈な人間を嫌ってはいけない。偏屈な人が、意外と大きな仕事をやりとげるのだ。偏屈な人ほど、しっかりした中心がある。その中心が一芸の芯となる。その芯を見出してあげ、見守るマネージメントがでる人は、実は全員の人間性も大事にできるマネージャなのである
耐雪梅花麗 ゆきにたえてばいかうるわし
p309 東洋工業 ある旅人が石を運んでいる人々に、なにをしているんですかと訪ねた。一人が私は石を運んでいますといい、二人目は塀を造っていますとこたえた。ところが3人目の男は、私は寺を作っています、みんなの心がやすまるような、と答えたというんだ。
同じ仕事でも、3人目の男は、目的をはっきり持って石を運んでいる。単調な仕事でも、いつも何のためにやっているのか、というkとおを考えなくてはいけない。寺を造って人々に喜んでもらうために働いている、というような意識だよ
投稿元:
レビューを見る
あの清武氏だからこそ書けた!低迷する阪神、広島の改革に奮闘するサラリーマンのフロントを描いた、プロ野球の内情に詳しい筆者ならではの傑作。
巨人の球団代表兼編成本部長を務めた筆者。ナベツネの逆鱗に触れ、読売を追われ今はノンフィクション作家。長いサラリーマン生活で培った独自の視点が素晴らしい作家。そんな筆者が今回のテーマに選んだのがプロ野球の球団の運営。阪神タイガース、広島カープという二つの低迷する球団。ぬるま湯体質であったり保守的な環境など、苦労しつつも結果を残していく。その過程、サラリーマンの悲哀をこめた感動的な作品。
星野監督の下でのタイガース優勝。その前のノムさんの監督勝地など。カープについては黒田、新井のカープ復帰など。劇的な場面を創るまでのフロントの奮闘が見事に描かれている。
本書は週刊文春の連載をまとめたもの。筆者は現在文藝春秋に「後列のひと」を連載中。こちらも目立たぬサラリーマンの奮闘を描いた傑作。筆者のサラリーマン経験が作品に反映されている。
プロ野球の内情を描いたノンフィクションとして屈指の出来でしょう。
投稿元:
レビューを見る
2020.11.12読了。
広島ファンにとって謎の人、鈴木本部長にかねて興味があり面白く読んだ。中南米にアカデミーを作ろうと追随する球団がなんで現れないのか不思議だったが、想像を絶する困難の数々にそれもむべなるかなと納得。
ロッテがサブローを放出に至る経緯、阪神の藤田平監督解任と幻に終わった外国人監督招聘計画、一場の裏金問題が球界にとって決定的なターニングポイントだったことなど、色々な事件と驚くべき内幕を知れるので、広島・阪神ファン以外にも一読の価値ありと思う。
著者が、いわゆる清武の乱でナベツネに反旗を翻した御仁であることを差し引いても、しょうもないオーナー(特に久万とナベツネ)ほど害悪をなすものは無いという訴えには説得力がある。
野球ファンたるもの、贔屓のチームに物申す時は、監督だけでなく、オーナーや親会社にまで視野を拡げるべきと胸に刻んだ。
時系列が入り組んでいたり、文脈が取りづらかったりで、読みにくいところがあるので、星一つ減じた。
投稿元:
レビューを見る
もったいないと思いました。
これだけの材料があればもっと一杯書けたんじゃないのかな。
もっと細かいところが読みたかったですね。
投稿元:
レビューを見る
元ジャイアンツ球団代表によるノンフィクション。阪神の野崎球団社長、カープの鈴木本部長の奮闘が描かれる。それにしても旧態依然とした阪神の体質にはトホホ感しかない…。近代経営のIT企業が親会社をいているチームが強いのが納得!
投稿元:
レビューを見る
旅行マンから阪神タイガースに出向した野崎。経理部員から広島カープに転職した鈴木。彼らは野球の素人だった。営業収益アップ、商品販売の効率化、上司の理不尽な命令、異例の人事異動…“どん底”球団の優勝にむけて2人のサラリーマンが行った改革とは!?『しんがり』『石つぶて』の著者が放つ渾身の企業ノンフィクション!
会社側の苦労はなかなか知る機会がないだけに、貴重な一冊。スマートにはいかないのですね。