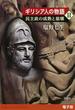0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Koukun - この投稿者のレビュー一覧を見る
日本では義務教育の段階から「民主主義」の長所や、人権の大事さ、自由 平等 博愛のと音さを教えられる。そしてその民主主義の古典的なお手本が本書で取り上げられたペリクレス時代のギリシア アテネである。しかし本書を読むと本当にこれが手本とすべき民主制なのか という疑問を抱かざるを得ない。ペリクレス亡き後のアテネの崩壊を見るとさらにその思いがつのる。
民主政治のお手本とされるが。
2018/08/23 11:41
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:名取の姫小松 - この投稿者のレビュー一覧を見る
アテネのペリクレスとその時代を描く。ペリクレスは民衆の移ろいやすい、深く考えない性質を理解しきっていた人間なのだろう。だからこそ、長年民主制の主導権を握り続けられた。同時にペルシア帝国、スパルタを治める有力者たちとの相互の協力があったとしても、足を掬われずに過せた能力は素晴らしい。
しかし、ペリクレスの退場とともに衆愚政治が始まったとされるのはなぜなのか。これは作者ではなく、読者が考えるべきなのだろう。
二人の偉大な哲学者を生んだ精神的緊張の時代
2018/02/28 23:40
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:コーチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
『ギリシア人の物語』第2巻の前半は、ペリクレスの時代におけるアテネのデモクラシー全盛期が、後半は、ペリクレスの死後、衆愚政治に陥るアテネとペロポネソス戦争の悲劇が描かれる。
ペリクレス時代-アテネ民主政の理想とされるこの時代は、実際にはペリクレスというただ一人の政治家が支配した時代であった。
塩野は、彼の政治家としての手腕を次のように要約する。「これこれの理由でこの政策が最も適切であると、彼自身の考えをはっきりと示す。こうして...現状を明確に見せたうえで、ただしこの政策への可否を決めるのは、あくまで君たちだと明言する...」さらに「ペリクレスの演説を聴く人は、最後は常に将来への希望を抱いて聴きおわる...なるほどこういう見方もあるのかと感心しながら政策の説明を聴き...積極的で明るい気分になって家路につける」これこそが、33年もの間ただ一人の支配者としてアテネを率いたペリクレスの人心掌握術であったという。
国家防衛を用意周到に行う一方、諸外国特にスパルタとの友好関係の構築には気を配り、その王とも親友関係にあったという。また外国からは芸術家や劇作家など能力のある者が移り住み、アテネは絢爛たる文化の熟成が見られたのだった。
ペリクレスの死後、アテネは急速に分裂への道を進む。武将としては、アルキビアデスなど有能な人材も出たが、政治の実権がデマゴギーグに牛耳られたアテネに、もはや自浄能力はなかった。ペリクレスの晩年に発生したペロポネソス戦争はその流れを決定づけ、多くの悲劇をアテネにもたらす。とりわけ、シラクサ攻撃の失敗による、多くのアテネ兵の運命はあまりに悲惨である。
紀元前461年から紀元前404年までのわずか57年という短い期間に、まさにアテネの光と影2つの時代が、見事な対比をもって語られている本書は、現代にも通ずる民主政治の光と影を描いた書でもある。さらに、ペリクレス時代の理想と衆愚政治の暗黒という大きな矛盾に満ちた50年は、ソクラテス、プラトンという偉大な哲学者を立て続けに生むことになる精神的緊張の時代でもあった。だが、本書にはそのような角度からの描写はなかったことが残念といえば、残念ではある。著者の塩野七生が学習院の哲学科出身であるだけに...
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぽんた - この投稿者のレビュー一覧を見る
ペルシャ帝国を破ったギリシャ(特にアテネ)がペリクレス時代(アテネの最盛期)からペロポネソス戦争に敗れるまでを書いてます。後半のアテネが没落する様が読み応えあります。アテネとスパルタの戦いと裏で糸を引く黒幕。
よくダメになるのはあっという間と言いますが、ピッタリ当てはまります。
失敗の見本や民主主義のマイナス面として読んでも面白いです。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:るう - この投稿者のレビュー一覧を見る
ペリクレスの死後から坂道を転がるように衰退していくアテネの姿には愕然とするしかない。テミストクレス、ペリクレスと同じ国の人間とは思えないほど。特にシチリア戦役後の惨たらしさは読むのも疲れた。国が枯れていく道のりは読んでいるだけでエネルギーを消耗するものなんだなあ。
投稿元:
レビューを見る
光と影がともにあってこそ、物のかたちをはっきりと認識できるように、国家の隆盛と衰退は、その国家のかたちを明確に浮かびあがらせる。本書では、エーゲ海におけるアテネの覇権の確立からその失墜までが一冊にまとめられているだけに、明暗はいっそう際だって見える。
アテネの繁栄を支える要因は四つあった。民主政体、強力な海軍、アテネ市街と外港ピレウスの一体化、そしてデロス同盟である。これらは互いに密接にして不可分の関係にあった。どれか一つでも失おうものなら、残りすべての維持もおぼつかなくなるのである。
このことを正しく理解し、これらの維持・強化に努めたのが、稀代の政治家ペリクレスである。彼は優れたリーダーだったが、国民のニーズをくみ上げ調整をはかるタイプの政治家ではなかった。国が進むべき道を自ら指し示し、国民にはその賛否のみを問う。一見、非民主的にも見えるが、このようなリーダーの下でこそ、民主政体はよく機能すると著者は説く。
やがてこのペリクレスが死去すると、民衆の漠たる不安を煽るデマゴーグ(扇動者)が幅を利かせるようになる。27年にもおよぶスパルタとの戦争でも、アテネはいつも不安を抱えて右へ左へと揺れ動き、一貫した方針を持つことができないのだ。デロス同盟の盟主の迷走は、同盟下の国々の相次ぐ離反を招く。海軍を支える有能な船乗りたちは、スパルタに引き抜かれる。結果は、アテネの無条件降伏。アテネは、先に挙げた四つのすべてを、手放すことを余儀なくされるのである。
民衆の不安は、いつの時代にも多かれ少なかれ存在するものだろう。だがデマゴーグは、不安というものが持つマイナス面を露わにする。デマゴーグとなる者は、何も政治家に限られない。ウェブなどを通じて我々もまた、自覚しないうちにデマゴーグとなりうるという著者の指摘に、はっとさせられた。「デモクラシー」と「デマゴジー」、いずれの言葉も「衆」(demos)に由来することの意味は重い。
投稿元:
レビューを見る
ギリシア3部作のアテネの民主制の成熟から崩壊までの第2部。前半はアテネって、スパルタって、ギリシアって、って同じようなフレーズが頻出して、それもうわかったからーってなるんだけど、後半の崩壊期に入ると史実に動きが出てくるから、それなりに塩野節にもリズムが出てくる。それだけ成熟期の前半は、派手な動きがなく、資料も乏しく、持て余している感があるんかなと。
また塩野さんには、ローマ後の中世モノを期待したい。
投稿元:
レビューを見る
ギリシア人の物語の第II巻はペルシア戦役の後のペリクレスの時代とその後のペロポネソス戦役の時代の話です。
アテネの黄金期をもたらしたペリクレスはどのようにして繁栄に結びつけたのか,そしてその後のペロポネソス戦役でアテネはどのようにしてすべてを失って行くのか,この一連の流れを読んでいると,組織としての継続性を確保する仕組みとそれを牽引して行く指導者の重要性を強く感じました。
ペロポネソス戦役におけるアテネの戦略の一貫性のなさと,一貫性のない中でどのような経緯で迷走して行ったのか,そしてその迷走を牽引した煽動者は何に目をつけて煽動して行ったのか,そのようなことに注目しながら読み進めていました。一方で,外的環境の変化に適切に対応できるように,全体の戦略機能を担う機関の柔軟性も大切だと,ペロポネソス戦役における主役の都市国家であるアテネとスパルタの対応を読んでいると感じます。
戦略を立てる人,戦略に関わる人がどのように一貫性を持つのか,一貫性を確保するシステムと外的環境の変化に対応した柔軟性をどのように確保するのか,それとともに,扇動などの不安をかき立てる情報に対してどういう姿勢に臨むのか,ということを考えるヒントになると思います。
最後の三巻でアレクサンドロス大王とギリシアの最後をどのように記述されるのか,今から楽しみです。
投稿元:
レビューを見る
第II巻はペロポネソス戦役。
デロス同盟のアテネ 対 ペロポネソス同盟のスパルタで、
国、民衆としてすぐれていた(先進的だった)と思われるアテネが敗れてしまう。民主制の自壊。
スパルタの意固地さ、頑なさ、融通の無さは笑ってしまうが勝利するもはスパルタ。
I巻は少々飽きたところもあったが、II巻は面白く、一気に読んだ。ギリシャ人の名前が覚えづらいのは変わらないが。
第3巻はアレクサンダー大王だ。
投稿元:
レビューを見る
塩野氏さんが描く、アテネの繁栄と凋落の物語。
世界史の教科書だと、3ページくらいで済んでしまうが、塩野氏にかかれば、いとも鮮やかに、その時代に生きた人々の姿が浮かび上がる。
一つの物語になる。人物だけでなく、国家も。
塩野七生さんが描く、アテネの繁栄と凋落の物語。
デロス同盟によって支えられ、海洋国家として覇権を握り、繁栄を極めたアテネ。
しかし、それらを支えたのは「民主政」。
繁栄も衰退も「民主政」になるとは、なんたる皮肉か。
いかに生きたかという人間ドラマだけでなく、都市国家アテネの「国家としての物語」も面白かった。
民衆の漠然とした将来への不安をリーダー(扇動者)が巧みに煽り、利用すると、民主政はたちまち衆愚政に突入してしまう可能性がある。
投稿元:
レビューを見る
ギリシャのペリクレス時代の巻。面白いがやはりローマ人には負けローマの方がダイナミックですね。民主制は良いが体制に流される。そこが難しいところ。
投稿元:
レビューを見る
ギリシア人の物語3冊中の2冊目。なんでだかずるずると衆愚政へとなっていく理由はもっと掘り下げてほしかった。しかしまあローマ人と比べるとギリシア人はちょっとな…という感じが強いのは著者の好みによるものだけではないように思われる。
投稿元:
レビューを見る
ようやく読み終わり。
ロングライドシーズンに入り、読書時間が後回し気味。
そんな中でも、ペロポネソス戦役に始まるアテネの自滅までの25年の中盤から、読みたいという気持ちが強くなる感じでした。
投稿元:
レビューを見る
古代ギリシア人世界を描く歴史物語の2巻目。
本巻ではペルシア戦争後のペリクレスによる最盛期からペロポネソス戦争を経ての自滅というアテネを中心に描かれています。
民主制をうまく運営していくのは難しいし、責任の所在も分かりにくいものになる事が良くわかりましたし、民主制を採用する以上は参画する民衆のレベルが問われると思いました。
作者は女性を愛する政治家が好きなようで、ペリクレスとアルキビアデスは魅力的に描かれていたと思います。
次巻は予告では最終巻でアレクサンドロス大王の物語になりそうで、期待したいと思います。
投稿元:
レビューを見る
民主制が定着したペリクレス時代、そしてその後のペロポネソス戦争の時代のアテネ。デロス同盟の中心国としてスパルタ、コリント、テーベなどペロポネソス同盟と対峙する。スパルタは一方の中心国でありながら、一国独立主義で、しかも貿易にも文化にも関心がない国。27年にも及ぶ両同盟の戦争において、今一つ戦争に積極的でないアテネ・スパルタが、同盟国の戦争に巻き込まれ、盟主として参戦せざるを得ない歴史がまるで現代を思い起こさせる。そしてアテネに難民が押し寄せ、ペリクレスが批判を浴びる状況も、今のドイツなどの欧州諸国そのもので、苦笑いである。古代3大美男というアルキビアデスがアテネ、スパルタ、ペルシャと渡り歩いた姿には、意外とこの3国が疎遠な関係ではなかったことを感じさせるものだった。アテネがシチリア島シラクサ征伐の遠征の大敗北から勢いを失っていく歴史は、超大国アメリカに重ねてみざるを得なかった。ペリクレスが愛した女性アスバシア、そして若いソクラテス。そのソクラテスに愛されたアルキビアデス、ペリクレスの親友ソフォクレス。彼らの時代関係がよく理解できた。ペリクレス、スパルタ王アルキダモス、そしてペルシャ王アルタ・クセルクセスの3者の信頼関係の深さなどは想像もつかないテーマだった。