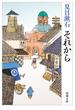- 予約購入について
-
- 「予約購入する」をクリックすると予約が完了します。
- ご予約いただいた商品は発売日にダウンロード可能となります。
- ご購入金額は、発売日にお客様のクレジットカードにご請求されます。
- 商品の発売日は変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。
紙の本
いつの日だったろう。
2008/12/07 11:58
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:サムシングブルー - この投稿者のレビュー一覧を見る
「どんな人生を送りたいですか?」
「高等遊民」
「高等遊民って何?」
「『高等遊民』は漱石の小説に出てくる言葉で仕事もしないでぶらぶらしてる人。僕の憧れかな。」
同級生とメールで話したことを思い出しました。『それから』を読み終え、本との出合いは人生に深く関わっているように思えてなりません。
代助と旧友の平岡との再会、代助と平岡の妻三千代の再会により、代助の人生は大きく揺らいでいきます。代助は自然の昔に帰るために、部屋中に大きな白百合の花を飾り、三千代と会います。
「彼等は愛の刑と愛の賚(たまもの)とを同時に享けて、同時に双方を切実に味わった。」(240頁)
究極の愛にしばらく茫然となりました。漱石作品のヒロインはたいそう潔く思います。『三四郎』の美禰子もそうでした。代助の兄誠吾が訪ねてきて「貴様は馬鹿だ」「愚図だ」「おれも、もう逢わんから」と云い捨てて出ていきます。
代助と三千代の『それから』を思う。そして、この連載小説を読んでいた明治の知識人は何を思ったのだろうと。明治42年漱石42歳の作品です。
紙の本
玄妙な夏目漱石
2010/07/19 22:06
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ホキー - この投稿者のレビュー一覧を見る
p.21で、ニートを貫く主人公代助に、旧友平岡が「困るよ」と言う。「困るよ」とは、p.12で、すでに代助が、ニートを貫く門野君に対して2度言っている言葉である。
【門野君にニートは「困るよ」という代助が、平岡にニートは「困るよ」と言われる】というパラレル関係によって、代助の立ち位置が鮮明になっている。
このパラレル関係が、代助自身も、あとのp.40で代助自身が「まるで門野のようになっちまうから困る」と言うように、自分自身の「困る」という自意識を生じさせる。
このように、『それから』では、代助が、いつでも自分の心情・立ち位置を客観的に語るのではなく、さまざまな他者とのかかわりによって、その姿を自然と映し出す手法を採っている。すなわち、代助の自己を、他者が『代』わりに映し出す、あるいは、自己認識を他者に『代』わってもらって『助』けられるのが『それから』の基調である。その意味で、映し出される側の「代助」というネーミングは絶妙である。
この人物描写の手法と、『三四朗』の比較は面白い。
『三四朗』では、前半の各章で、野々宮・与次郎・美禰子・広田といった重要人物がおおむね一人ずつ新登場して、それまで登場していた主要人物とその新登場の一人との各関係が描かれていく、という構成だった。
その時の人物関係図は、主要人物がたしか6人でありので、6角形の各頂点から、他の全ての頂点に線が延びているような図になる。学園恋愛小説である『三四朗』に相応しい相関図である。
対して『それから』では、各登場人物が、全て代助との関係によってとらえられている。人物関係図は、中心点に代助がいて、放射状の各線が各登場人物とのつながり、といった図である。そして、周辺の人物が、いくつかずつ「実家」、「家」、「平岡関係者」という塊を形成しているのである。
ところが、代助の「実家」、「家」、「平岡関係者」のすべてに絡むのが、「三千代」である。そこで、「三千代」のネーミングは、「実家」、「家」、「平岡関係者」の『三』っつの局面で『代』助を映し出す、という役回りを、絶妙に表している。
三千代のネーミングは、もう一つのさらに巧妙な含意がある。
p.24で、平岡が、部下の不正会計の補てんについて、「千にたらない金だったから僕が出しておいた。」と強がっている。
しかし、その千円が平岡を結局苦しめ、ストーリーの基調になっている。
三千代が、代助に5百円の援助を頼み、代助が嫂(あによめ)からそのうちの200円を又借りして三千代に渡すことで、平岡と三千代が代助に、代助が嫂とひいては実家の面々に、それぞれ大きな借りを作ることになった。
この借りのために、平岡は代助に対して、代助は実家に対して、それぞれ、それまでの距離をおいた態度を取るわけにいかなくなり、相手に対して自己を開示し、葛藤や矛盾が生じたのである。
ちなみに、誠太郎を「相撲」に連れていく羽目になったのは、代助が、実家の「土俵」に引きずり込まれはじめたことを示している。
このように、ストーリーを進ませる大きな原動力の1つである「お金」の返済における、「借り」の連鎖は、『三』箇所で『千』円の『代』金を工面することであり、それをスタートさせた三千代のネーミングが、その役割を先取りしている。
『三』つの局面で『代』助の姿を映し出す役回りとの、二重の含意をもつ玄妙なるネーミングである。
それよりも玄妙なのは、そうして三分割されてなお、各人に越えられない壁として立ちはだかった元凶の負債である『千円』に、貨幣価値の変わった後代であるとはいえ、著者の夏目漱石自身が収まっていたことであろう。
★
『三四朗』との対比で面白かった箇所をもう一つ。
p.77 平岡の新居を、代助が、自分が紹介したにもかかわらず内心で、東京に増えてきた狭小住宅を「目下の日本を代表する最好の象徴」と言っている。
これと、『三四朗』1章の「富士山」とは好対照である。「これからは日本も発展するでしょう」と言った三四朗と、「滅びるね」と言った男の意見を合わせると、『それから』での代助の「敗北の発展」と同じ意味になるだろう。
などと考えながら読んでいると、p.85に、『三四朗』の「男」そっくりな日本対西洋論が出てくるのである。
このような漱石の文明論は、『私の個人主義』に総括されている。
紙の本
頭を整理させようと、書いているうちに・・・。
2009/06/09 22:51
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:wildcat - この投稿者のレビュー一覧を見る
最初は、とってもやりきれなかった。
心臓の辺りに鉛があって、ぎゅーっと押されるような感じ。
どうしてこうなってしまったんだろう?
もうちょっとどうにかならなかったんだろうか?
いったいどうすればよかったんだろう?
しまったこれは、引きずるかもしれない!
『ダンサー・イン・ザ・ダーク』を見終わったときと
同じ感覚だぞと思った。
私は、主人公とは近い立場では決してないのに、
気づくととてもミクロな視点で読んでしまっていた。
明治という時代とか、現代との相関とか、高級遊民的立場の生活とか、
社会対個人とか、この作品の文学的意義とか、
漱石は何を描きたかったのだろうとか・・・
そちらの視点には、なかなか行けず・・・。
彼の「世の中」に出ない理由は、
結局のところ自分だけがきれいに生きたいだけの理屈で、
自分は何もしないままに、
お金だけは、現実にまみれている親からもらっているという矛盾。
それでも、一歩踏み出し、「生きる」ことができない。
追い込まれていないから。
自分の気持ちに気づいてしまったときから、
引き返せないところまで進んでしまうのだけど、
それでも、むしろ何もしていないよりも
この人は生きているんじゃないかなと思った。
もしかして、幸せだったんじゃないだろうかと思ってしまった。
愛する人と共有する記憶が視覚的に描かれていたのが『三四郎』だが、
本作では、白百合を使って嗅覚的に描かれていることが
とても印象的だった。
より近感覚に近いその記憶は、視覚的な恋よりも官能的なように思えた。
最後の方は、熱に浮かされたように、破滅しかないのだろうと思いながら、
それでも破滅に突っ込んでいくように、読んでいた。
最初は、結末を狂気としか読めなかったのだけど。
救いようのない結末としか思えなかったのだけど。
そのうちだんだんなんだか違うような気がしてきたのだ。
彼は、破滅を最後まで個人的なレベルでしか想像しえなかった。
だが、破滅は社会的な形
(といっても職を持たない彼の社会は小さな世界でもある。)で
訪れている。
彼が想像した最悪ではなかったのだ。
だからそこに救いがあるような気がした。
最後に追い込まれたときに取った主人公の行動、
そして、彼の頭の中に見えたもの。
それは、この人がはじめて自分で立とうとした瞬間の
命のほとばしりなんじゃないだろうか。
彼は追い込まれるまで、生きるとは心臓が鼓動していることで、
死ぬとは心臓が止まることでしかなかったのではないか。
冒頭と終幕の赤の使い方がその対比を、
そして、命の意味を表しているように思えてならない。
一度壊れてみた先のこの人のそれからを、私は見てみたい。
ずっとのらくら生きながらえていたときよりも、
むしろ壊れてみてからが人生なのだと思うから。
紙の本
いつから?
2019/07/24 22:18
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Yo - この投稿者のレビュー一覧を見る
自由を謳歌しているようで自縄自縛。自分に誠実でないものは、決して他人に誠実であり得ない、とはいうものの、主人公は本当に「自分に誠実」だったといえるのかな。
紙の本
代助は三千代のことを、本当に昔から好きだったのだろうか
2019/04/23 21:29
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
この小説で一番疑問に思うことは、主人公の代助が平岡の妻・三千代のことを平岡と三千代の仲をを代助が取り持ったころから本当に好きだったのかということ。私は、代助が生活力がなく三千代に苦労ばかりかける平岡(自力では生活できない代助も偉そうなことはいえないのだが)に腹を立てて、三千代さんのことをずっと好きだったという筋書きを自分で建ててしまったのではないかと思う。そこには二人をくっつけたのは私だという罪悪感があったのかもしれない。「相当の地位を有っているの不実と、零落の極に達した人の親切とは、結果において大した差異はない」という作品中のことばがなぜか心に残っている
紙の本
最高!
2016/10/02 11:09
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:鶴 - この投稿者のレビュー一覧を見る
それからのうたい文句にある「三角関係」はおまけのように、
いつもの漱石の「自己とは?」という問題が山積し、押しつぶしてくるようだ。
紙の本
前期三部作のなかで一番秀作か?
2015/12/19 18:45
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:森のくまさんか? - この投稿者のレビュー一覧を見る
三四郎、それから、門と漱石先生の前期三部作と言われていますが、
それからがこの三つの中で 秀でているように 私は思います。
読んでいて主人公の煮え切れなさに ハラハラドキドキさせられました。
最後は ファイヤーブレードに主人公はなってしまったと私は勝手に思っています。
これは 三部作の中でもっともよかったと思います。
紙の本
ふしぎのひと、代助
2004/03/04 20:17
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:けんいち - この投稿者のレビュー一覧を見る
漱石の、というより、近代日本文学の代表的作品の1つ、なのかもしれない。では、そこから、漱石という名前の偉大さを引いたとき残る、小説それ自体の魅力とは何だろう?
それは、恋愛小説としての側面にも、高等遊民物語(明治知識人の苦悩のも)としての側面にもないだろう。また、当時の社会的事件との関わりについても、『それから』を現代小説として読む限りにおいては、一般読者の埒外にあるといってよい。
では、何がおもしろいのか?
もちろん、つまらないという答えもある。
いずれにせよ、『それから』の核は、主人公である代助その人の「ふしぎさ」にかかっているといってよい。この「ふしぎさ」は、思い切って翻訳してしまうならば、そのあまりにも都合のよさ、といってもよい。
代助は都合がいい男である。
しかも、都合が悪くなると「男」であることすら回避しようとする。
だからといって消極的なばかりではない。
三千代との恋愛には、はたからみて、不自然なほどに、自己演出をしながら積極的に踏み込んでいく。
これを要するに、代助はふしぎのひとである。
そこから、ドラマが起こり、物語が始まる。
こんな人物を書いた夏目漱石という人も、また不思議な人なのであろう。
紙の本
究極の選択
2002/06/05 23:22
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:やまたのおろち - この投稿者のレビュー一覧を見る
社会の子となるか、自然の子となるか。つまり、社会の要求する価値観や道徳と、自分の内面から沸き上がる本然的な感情とどちらを優先すべきかを問いかける小説である。両者がうまく調和できれば、それに越したことがないのであるが、もし両者が決定的に相反したら? 自分の感情を偽って社会に伍するのか、社会から見捨てられても自らの意思を貫くのか? 明治と言う社会を舞台にし、恋愛を題材にしているが、決定的に現代に生きる我々の生き方を根本から問いかける名作である。
紙の本
今の時代であれば
2021/03/01 14:41
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Todoslo - この投稿者のレビュー一覧を見る
ニートや引きこもりといって切り捨てられそうなところを、敢えて「高等遊民」と豪語する代助が憎めません。経済的な安定か、自由と愛か。終盤に突き付けられる選択も悩ましいです。
紙の本
漱石から100年、ここまで、と、それから。
2004/06/27 12:13
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Ryosuke Nishida - この投稿者のレビュー一覧を見る
江藤淳の夏目漱石に関する評論を読んでいる関係で、
最近、夏目漱石の作品を読み返している。
漱石は作品を通じて、初期近代知識人(=文学的な言葉では高等遊民)の隘路=富国強兵という有形財の大量生産や学問等々様々な西洋近代の産物の輸入を通じて、急速な近代化を志向する後発国日本の社会の中で、有形財を生産しない知識人(=高等遊民)という近代社会特有の、前衛的な視点と身分を有する者の非肉、苦悩を描く。
しかし、果たして、その時代から僕らはどこまで進んだのか。
中学高校時代に読書感想文の題材として漱石の作品を読んだ人も多いだろう。だが、改めて読み返すとつくづく漱石が浮き彫りにした日本の近代化過程の問題点は平成の今においても過去のできごととは思えない。
また、明治の時代に、近代化が今日に至るまで連綿と、とりわけ知識人に対して(日本においてその階層があいまいになってしまったにせよ)、もたらし続けている非肉、苦悩をここまで鋭敏に感じ取り描いた漱石の作品は読書感想文の課題として読むだけではもったいない。
紙の本
日本に西欧が押し寄せてきて、「それから」。
2004/10/03 23:47
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:中堅 - この投稿者のレビュー一覧を見る
この小説は前半、主人公・代助を中心とした情景・性格描写に終始していながら、後半から突然「姦通小説」の形をとりだす。
代助はなにもしない。父の家からお金をもらい続ける、今でいえばパラサイトの生活をしており、(貴族であるから同じではないが。)働くことになんの意義も認めていない。
生活のために働くことを「労力のための労力」つまり消費といいきり、「互を腹の中で侮辱することなしには、互に接触を敢てし得ぬ、現代の社会を、二十世紀の堕落」と呼ぶ。また、親友であった平岡は、「僕は僕の意志を現実社会に働き掛けて、その現実社会が、僕の意志の為に、幾分でも、僕の思い通りになったと云う確証を握らなくっちゃ、生きていられないね。」といいながら、事業に失敗し、酒に溺れるようになっている。そして、「普通の都会人」を評して代助は、「より少なき程度に於て、みんな芸妓ではないか。」という。
現代は、「それから」の「それから」であることをひしひしと感じる。
主人公の代助が三千代への「愛」を思い出す場面があるが、これを私は唐突すぎると思う。この事件は、クライマックスに至って「世間」から暴力的にはじき出される際に鮮明になる、個人と社会の対立をより先鋭化させるための強力な仕掛けであったのではないだろうか。
平岡も兄も父も社会的制裁はあっても各々の欺瞞性について裁かれはしない。代助の愛の欺瞞だけが裁かれるのである。この小説は、正常な社会と、それに対立する罪びと、という構図をとらず、社会(代助に対する父、兄、平岡)というものの欺瞞性が明らかに示され、それに対立して愛のために全てを失う代助、という構図において、欺瞞の人と真実に気づいた人という対立を描いているように思われる。
道徳的にどうか、社会的にどうか、とその行為を尋ねると「同時に」人間は存在するし、生きている。社会なしには個人は存在しないが、個人なしに社会は存在しない。しかし現実は、最大多数の最大幸福のために一人の人間は沈黙させられる。この社会は、「個人の自由と情実をごうも斟酌してくれない器械の様な社会」なのである。
------
岩波文庫の「それから」は、中村びわさんの書評によると、「脚注がマニアックなぐらい丁寧で楽しめ」るらしい。(漱石に関して、中村さんの書評は全て岩波文庫版にあるようである。)
新潮文庫は、脚注は最低限度、といった感じである。ちくまのものは分からない。