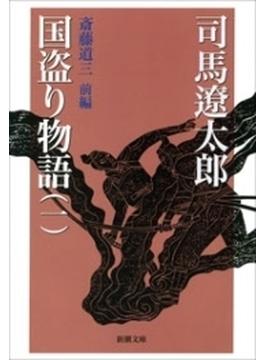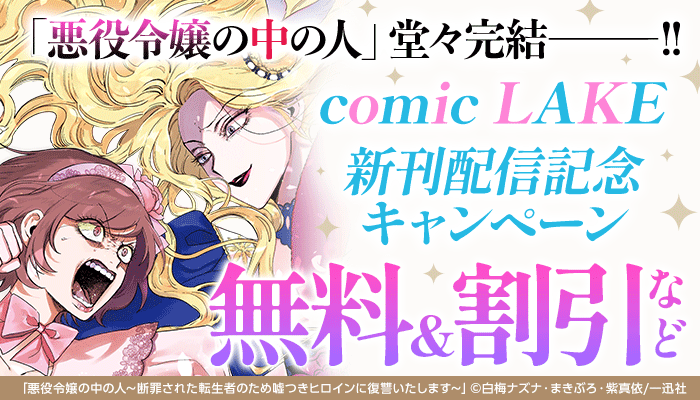- みんなの評価
 11件
11件
国盗り物語
著者 司馬遼太郎
世は戦国の初頭。松波庄九郎は妙覚寺で「知恵第一の法蓮房」と呼ばれたが、発心して還俗した。京の油商奈良屋の莫大な身代を乗っ取り、精力的かつ緻密な踏査によって、美濃ノ国を〈国盗り〉の拠点と定めた! 戦国の革命児斎藤道三が、一介の牢人から美濃国守土岐頼芸の腹心として寵遇されるまでの若き日の策謀と活躍を、独自の史観と人間洞察によって描いた壮大な歴史物語の緒編。
国盗り物語(四)(新潮文庫)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
2017/05/21 00:32
面白かった
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:読書灯 - この投稿者のレビュー一覧を見る
司馬遼太郎の作品でこの本のこの第一巻が一番好きだ。
まるでライトノベルのような詩的な書き出しだが、熱気が伝わってくる。
巻を追うにつれて淡々とした歴史小説のような文体に落ち着いてしまうけれども、私はこの巻の熱さがやっぱり忘れられない。
国盗り物語 改版 2 斎藤道三 後編
2020/06/24 17:25
斎藤道三はいい蝮だったのか
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る
新潮文庫版で4冊となっている長編歴史小説の2巻め、「斎藤道三 後篇」である。
最初に断っておくと、新潮文庫版で1、2巻が「斎藤道三」で3、4巻が「織田信長」となっているが、この2巻めで斎藤道三が姿を消す訳ではない。
この巻でようやく幼いうつけ者信長が登場し、道三の娘である帰蝶の婚礼が整う前夜あたりまでが描かれているから、このあともまだ道三は描かれることになる。
司馬遼太郎さんはこの長い物語を雑誌に連載するに際して、道三のことを「妙な人物をかく」と記した。続けて、「奇人ではない。どこにでもいる。われわれの性根の内部にもいる」と書いた。
この巻では、自分の主人であった国守土岐頼芸を美濃の国から追いやる「蝮」の道三の姿を描いているが、そういう悪のような部分も「われわれ」の内部にあると司馬さんは見ていたのかもしれない。
さらにいえば、この歴史小説の合間に「斎藤道三という苛烈な「悪人屋」を書こうとしたのは、自分へのけいべつから出発しているらしい」と、自身の内情まで吐露している。
斎藤道三には悪だけではない、人間としての魅力が濃厚にある。
斎藤道三という人物が面白いのは、彼ひとりではなく、彼の「国盗り」がふたりの「弟子」によって引き継がれていく点にもある。
ふたりの「弟子」。すなわち娘婿の織田信長と、道三の妻の甥の明智光秀である。
この二人がその未来においてどう交わるか歴史の事実として知っている読者にとって、わくわくしないはずはない。
いずれにいても、この巻ではまだ道三は生きている。
国盗り物語 改版 4 織田信長 後編
2020/07/24 08:37
光秀は「麒麟」か
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る
新潮文庫版で4冊となっている長編歴史小説もいよいよ最後の巻、「織田信長 後編」である。
そしていよいよこの巻のクライマックスで「本能寺の変」が描かれている。
そこからすれば、「織田信長編」というより「明智光秀編」といった方がいいかもしれない。自らの主家であった信長に何故光秀は謀反を起こしたのか。
おそらくそれは光秀しかわからない、あるいは光秀自身にも解けない謎であったかもしれない。
この長編小説にはたびたび信長に対する光秀の妬みのようなものが書かれている。
妬み、というのは、自分の方が生まれもいいし能力もある、という愚かな考えから出ている。
あるいは、濃姫と結婚したかもしれない自分を想像したこともあったやもしれない。
どんな組織でも、光秀のような考えをもつ人物は現れる。ただ光秀の場合、そんな考えを持つほどに能力も高かったのも事実だ。
ただ残念なことに、光秀は信長のことが嫌いであった。
好き嫌いの問題はどうしようもない。
精神が病んでいくように見える光秀だが、信長の仕打ちも目に余る。
現代ではパワハラであるには違いないが、戦国時代、ましてや下克上といわれている時代に信長のような強烈な個性がなければ天下などとれるはずもない。
道三、信長、光秀、三人の武将の長い物語はここで完結したが、一体誰が本当の「国盗り」だったのだろう。
秀吉なのか家康なのか。
あるいは光秀の謀反に組みしなかった、光秀の友細川藤孝だったのだろうか。