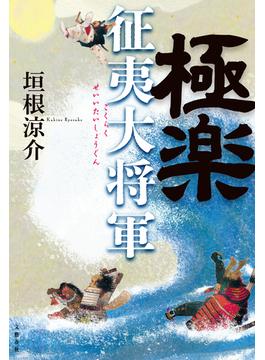紙の本
足利尊氏を主人公とした一代記
2023/06/26 21:57
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:nekodanshaku - この投稿者のレビュー一覧を見る
足利尊氏を主人公とした一代記であるが、主人公を取り巻く弟・直義、足利氏家宰・高師直らの視点から主人公を描く形になっている。茫洋としたとらえようのない人物であったようだ。世間の欲望の上にぽっかりと浮かび上がる化身のようなものだという表現が作中にあるが、鎌倉幕府執権北条一門を滅ぼし、幕府を起こすために、直義や師直らにより神輿として担ぎ上げる人物としての主人公は、担ぎ上げてくれた人々を、内ゲバのような戦いの中で失い、自らは遅ればせながら自立していったようだ。室町幕府成立前後の世の流れが、よく理解できた。
紙の本
読みにくいのに引き込まれる
2023/12/03 10:20
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぶっちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
人物名が通り名など、歴史物特有のややこしさがあり、文章も分割表記で読みにくいな…と思った。
ところが!読み始めるとどんどん引き込まれて寝る間も惜しんで読みたくなる。
鎌倉幕府滅亡から室町幕府創立という、誰もが知っている時代背景たが、今までの尊氏像や一族に拘る武家の認識が一変する掘り下げ方。
是非、じっくりと読み耽ってほしい一冊。
紙の本
鎌倉末期から室町初期
2023/11/05 17:26
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:咲耶子 - この投稿者のレビュー一覧を見る
足利尊氏の一生を、弟直義と高師直の視点から語られる。
庶子に生まれ、家督から遠いところにいた尊氏が嫡兄の早逝で当主となり、後醍醐天皇の討幕行動に巻き込まれつつ転戦し、やがて室町幕府を樹立していきますが、その姿は無欲で何事も他人事で仕事のできないこ「極楽殿」として描かれています。
室町幕府はその成立頃から終始人間関係が複雑で、っていうか勢力図が目まぐるしく入れ替わり、煩雑だけど反面とても面白い。
紙の本
後半ダレた
2023/11/13 11:19
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:hid - この投稿者のレビュー一覧を見る
室町幕府を開くまでは面白かったんだけど。
その後は、ずっと内輪もめ。
描写も、史実にちょこっとフィクションを加えたくらいの感じで。
面白みがなかった。
電子書籍
長編でした…
2023/08/25 17:32
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:さくら - この投稿者のレビュー一覧を見る
足利尊氏の人となり、足利幕府のありようが分かった気がする。尊氏と直義兄弟の境遇と才能が足利幕府を作った、鎌倉で幼少期を過ごした幼い兄弟が二人で成した征夷大将軍だった。
投稿元:
レビューを見る
【史上最も無能な征夷大将軍】民への使命感も権力への執着もなく天下を統一した足利尊氏。明確な意思を欠いたまま権力を極めた男の謎を解く、歴史群像劇。
投稿元:
レビューを見る
歴史って面白い。個性とその組み合わせ、意図したこと、時流、第三者が割り込んできて、と色んなことが積み重なって歴史になる。
尊氏、弟の直義、そして師直。この3人が長所短所ありつつ、室町幕府を開くけれど、そのあとの維持のむずかしさ!
投稿元:
レビューを見る
昔NHK大河ドラマで「太平記」をやっていて観ていた。
調べてみたら1991年とのこと。
尊氏が真田広之、直義に高嶋政伸、師直に柄本明
懐かしい。
鎌倉幕府で執権の北条氏を滅ぼし、
その後も色々ありながら九州から攻め登って幕府を開くまでは団結していた三者(尊氏、直義、師直)。それが幕府の運営を巡って軋みが生じて同族相争う骨肉の闘いとなる。実に愚かしいが周りを見渡せばそんな例は沢山ある。
そんな人物像を垣根涼介はどう描くか。
読んでいて実に楽しかったが、これもう少し字を大きくして上下巻に分ければ良かったのにと思いながら読んだ。
寄る年波で小さい字を長時間読んでいると目が疲れる。
人気の垣根涼介なら上下巻にして売り上げを上げれば良いのにと内容に関係無いことを思ってしまった。
作品紹介・あらすじ
やる気なし
使命感なし
執着なし
なぜこんな人間が天下を獲れてしまったのか?
動乱前夜、北条家の独裁政権が続いて、鎌倉府の信用は地に堕ちていた。
足利直義は、怠惰な兄・尊氏を常に励まし、幕府の粛清から足利家を守ろうとする。やがて後醍醐天皇から北条家討伐の勅命が下り、一族を挙げて反旗を翻した。
一方、足利家の重臣・高師直は倒幕後、朝廷の世が来たことに愕然とする。後醍醐天皇には、武士に政権を委ねるつもりなどなかったのだ。怒り狂う直義と共に、尊氏を抜きにして新生幕府の樹立を画策し始める。
混迷する時代に、尊氏のような意志を欠いた人間が、何度も失脚の窮地に立たされながらも権力の頂点へと登り詰められたのはなぜか?
幕府の祖でありながら、謎に包まれた初代将軍・足利尊氏の秘密を解き明かす歴史群像劇。
投稿元:
レビューを見る
読了まで非常に時間がかかってしまった。序盤の波打ち際での出来事が晩年に回収されるんだと容易に推測できたが、その回収された時の満足度の低さが今回の私の評価そのものなのかなと感じる。とても好きな作者だけに今回は残念でした。極楽というワードのこだわりがむしろ逆効果で史実が歪曲されてミスリードされていく感覚に陥ってしまう。(何が史実かということは関係なく)
投稿元:
レビューを見る
直木賞受賞おめでとうございます。
読んでも読んでも終わらない作品ではあるが、読後感は一応スッキリ☆
南北朝終焉から室町勃興、そしてその後
に至るまでの流れが描かれた作品を他に知らないので、とても勉強になった。
もっと内容の濃い感想を書きたいけれど、楠木正成の武勇がなぜ歴史に残ったのか分かった気がする。
投稿元:
レビューを見る
すごい1冊。室町幕府創設の立役者たちの時代背景、生い立ち、人物関係そしてドラマが全て詰まった1冊。
室町時代には、イメージとして何か釈然としないものがまとわりつく。応仁の乱などはその象徴だろう。では何が釈然としないかと言えば、それは善悪の対立構造の分かりにくさと、当事者の打ち出す理想への共鳴の無さではないだろうか?正確には、大した理想や理念もないのかもしれない。源平の戦い以降の流れを汲んでいることは間違いないだろう。鎌倉殿以降の歴史は、泥々の内輪の権力闘争の歴史で、特に時代をどうこうするイデオロギーには乏しい。
その流れを汲んで、室町時代もそのイメージが付き纏うなか、作者は良くぞこの足利兄弟に着目したなぁと感心せざるを得ない。この兄弟の面白さには、本流じゃないところから成り上がった成功の興奮、兄弟で力を合わせた美談など、人々を魅了するストーリーに溢れている。兄弟のキャラもわかりやすく、惹きつけやすい。北斗の拳で言えば、雲のジュウザ、ドカベンで言えば殿馬、例えが古いが、飄々キャラの兄と頭がキレる弟の組み合わせ。そして支える高兄弟などもキャラがわかりやすい。
歴史のうねりの中で登場する人物たちもキャラが濃くわかりやすい。赤松円心、楠木正成、新田義貞、そして何より後醍醐天皇だろう。
本前半の足利兄弟中心に旧体制である執権制度北条鎌倉幕府を倒していく過程と、後醍醐天皇という悪質なやり手に向かっていくそのスピード感と高揚感の描き下ろしはとにかく圧巻で面白い!
しかし残念ながら、この兄弟の歴史は、鎌倉殿の13人と同じ方向をなぞって行ってしまう。そこからは、人の恨みつらみや面子や立場や対話の欠如からの誤解ばかりからの対立が蔓延り、誰と誰が何のために争っているのか、分かりにくくなる。それは歴史がそうだったのだから仕方がない。足利兄弟には、時代と人の心を掴む理念とそれを広めるプロデュース力が足りなかったのかもしれない。
しかしこの本は、そんな歴史を凌駕するほど濃く、そして面白い1冊だった。足利尊氏と直義兄弟のことをより知りたくなり、赤松円心や楠木正成も然り。そして高兄弟も今後より新たな歴史的発見と解釈が増えてくるのでないか?と推測する。応仁の乱には気が向かないが、作者は今まであまり陽の光が当たらない室町時代の一番興味深く面白い部分にスポットライトを当てられたのではないだろうか?今後ここにより注目が当たるのではないだろうか?分厚い一冊だったが、あっという間に読み終わった。鎌倉幕府の終焉と室町幕府の始まりについてもよく分かるようになった。
投稿元:
レビューを見る
まさに大作。
いやはや、長かった。
尊氏の人物像を、その「両輪」の視点から描く仕掛けが巧み。
他の登場人物も魅力的で、時代の転換期の「これでもか」というほどの権力争いの闘いの日々が、いろんな人々の思惑と絡んで面白く描かれている。
投稿元:
レビューを見る
何か垣根氏は時代小説の大家になったなあ。足利尊氏・直義と高師直の3人を軸に、鎌倉幕府滅亡期から観音の擾乱までの歴史が物凄く親近感をもって迫ってくる感じで、大長編にも関わらずスイスイ読めてしまった。大枠は知っていたが、改めて細部まで勉強できた。垣根氏の尊氏・直義・師直の人間性解釈が大変興味深い。そして室町幕府の成立時点から、応仁の乱・戦国時代が必然だった背景が手に取るように理解できる(そもそも室町時代成立時点から下克上があまりない戦国時代とも思える)。赤松円心の存在の大きさは全く知らなかったので大変勉強になった。
投稿元:
レビューを見る
足利直義と、兄の尊氏の兄弟の歴史小説。
名前くらいしか知らず詳しくなかったが。この一冊を読んですっかり好きになってしまった。
大河ドラマ「鎌倉殿の13人」を見てたので、その後の時代の話なんだなと、想像しやすくて良かった。
後醍醐天皇のアグレッシブさに驚くわー。
そんでもって、政治って難しいんだな、と思った。
面白かったー。
垣根涼介さんの歴史小説は、非常に好きだわ。
投稿元:
レビューを見る
室町幕府を開いた足利尊氏についての小説は少なく、その人となりは謎に包まれている。
本作では意思もなく、欲も執着心もない尊氏が何度も窮地を迎えながらも弟直義、執事高師直に支えられ、幕府を開く姿が描かれている。幕府成立後に起こった高師直と足利直義の内紛を通しても変わらない尊氏が両名の死後、将軍としての才能を開花させる様子はやはり立場や環境が人を作るというところに通じる。