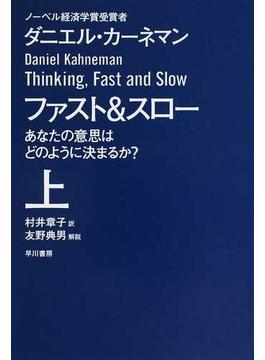「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
読割 50
紙の本
ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか? 上 (ハヤカワ文庫 NF)
心理学者にしてノーベル経済学賞を受賞した著者が、直感的・感情的な「速い思考」と、意識的・論理的な「遅い思考」の比喩を巧みに使い、意思決定の仕組みを解き明かす。上はヒューリ...
ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか? 上 (ハヤカワ文庫 NF)
ファスト&スロー (上)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
紙の本 |
セット商品 |
ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか? (ハヤカワ文庫 NF)セット
- 税込価格:2,112円(19pt)
- 発送可能日:購入できません
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
心理学者にしてノーベル経済学賞を受賞した著者が、直感的・感情的な「速い思考」と、意識的・論理的な「遅い思考」の比喩を巧みに使い、意思決定の仕組みを解き明かす。上はヒューリスティクスとバイアスなどを取り上げる。【「TRC MARC」の商品解説】
直感的「速い思考」と論理的「遅い思考」による人間の意思決定メカニズムを徹底解剖。【商品解説】
関連キーワード
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
気づきとアイデアの宝庫
2016/01/27 21:09
9人中、8人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:アリョーシャ - この投稿者のレビュー一覧を見る
ノーベル経済学賞受賞者による行動経済学の本であるが、本質的には経済学よりも心理学である。さまざまな実験によって、速い(fast)思考であるシステム1と、遅い(slow)思考であるシステム2に着目して、意思決定のメカニズムを探究していく。とりわけ、システム1を中心にあつかいながら、意思決定の際に起こりうる誤謬を、これでもかと列挙してくれる。日々の生活の中に意思決定はあふれているから、本書は多くの人にとって気づきとアイデアの宝庫だと思われる。
紙の本
行動経済学に興味があるなら、目を通しておきたい本
2015/09/26 23:43
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:chibi - この投稿者のレビュー一覧を見る
最近、テレビでも随分と「行動経済学」と言う言葉を耳にするようになってきた。損失回避、ヒューリスティクス、フレーミング効果・・・などがそれにあたる。平済みになっている本でも、書かれている内容だ。
もちろん、本書でも書かれているが、やはり本家は違う。冒頭からの「システム1」と「システム2」の話などは、目から鱗であった。
行動経済学に関心のある方は、是非とも読んでいただきたい1冊と言えるだろう。
電子書籍
経済学に風穴を開けた著者
2015/08/31 02:43
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ほん太 - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者は心理学を応用し2002年にノーベル経済学賞。
大雑把に言うとそれまでの経済学は人は合理的に判断するということを前提にしてたが
そうでないことが広く知れ渡った。
不合理な選択をしたくない人は読むべし。
紙の本
判断の非合理性
2016/10/28 15:14
5人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:くまごろう - この投稿者のレビュー一覧を見る
人間の意思決定システムは非常に誤謬を犯しやすく、単純な影響を受けやすく出来ているということが様々な実験で明らかにされている。人間は考えられている以上にずっと非合理的な判断をし、その誤りに気付いてすらおらず、それは一般人だけでなく各分野の専門家も例外ではない。本書を読んだ前後では物の見方、考え方が変わるだろう。
紙の本
人間の行動は果たして合理的なのか、を改めて考えさせてくれる良書です!
2017/11/20 09:36
4人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、心理学者でありながらノーベル経済学賞を受賞したカールマン氏による渾身の書です。「人間は果たして合理的に判断して、行動しているのだろうか?」。このような素朴な疑問を徹底的に検討し、私たちが間違った判断を行い、間違った行動に出る理由を解明してくれます。ここには行動心理学や認知心理学の研究成果がちりばめられていますが、決して内容は難しくありません。その面に関して素人の方々でも興味深く読むことができます。
紙の本
バイアスと数字を扱うのが苦手な人間
2022/01/10 08:46
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:病身の孤独な読者 - この投稿者のレビュー一覧を見る
行動経済学の言わずと知れた名作であるが、上巻では行動経済学で研究されている認知バイアスについての紹介が行われている。認知バイアスは様々なあるが、総じて言えるのが、人間は合理的に数字をそのまま処理するのが苦手だということである。著者らのそもそもの問いが、「人間は統計的・数学的に物事を考えられるか?」というものだった。この問いの答えとして、「否」と答えられるかもしれない。その実例がまじまじと研究を交えて説得力あるかたちで記述されている、認知バイアスという癖があり、数字を基に客観的に判断するのがあまり得意でない。これまでの合理的人間を想定する経済学へのアンチテーゼにもなる。
紙の本
ウムムの心理
2019/05/24 17:22
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:保母札布 - この投稿者のレビュー一覧を見る
行動経済学といっても、経済だけでなく生活全般に影響している私たちの行動原理をわかりやすく、実験から見る根拠を添えて示されている。
これを逆手にとって悪用されないよう、騙されないよう、自分を守るためのバイブルとして何回読み直しても、新たな発見がある。
紙の本
サッと読むのもいいかもです・・・
2017/01/30 19:53
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:K - この投稿者のレビュー一覧を見る
違う角度から切り込んでいるのもありますが、重複内容も多く思え、まとめをさっと読むだけでも内容が掴める気がしました・・・
紙の本
義務教育で教えて欲しい
2017/01/15 10:31
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みーやん - この投稿者のレビュー一覧を見る
人間の意思決定が様々な種類のバイアスによって歪められ、合理的な行動がとれなくなるという事実が解説されています。
科学的な実証実験のデータも提示されています。
自分の思い込みを補強するために都合のいい事実だけを選び出す確証バイアスなど、本書で明らかにされていることこそ、義務教育できちんと教えておくべき価値のあることだと思います。
紙の本
私には難しい本でした。
2023/02/21 16:41
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぽち - この投稿者のレビュー一覧を見る
字も小さく、量も多い。
読み進めるのが大変でしたが、思考に2つの種類があるというのは新しい気づきでした。