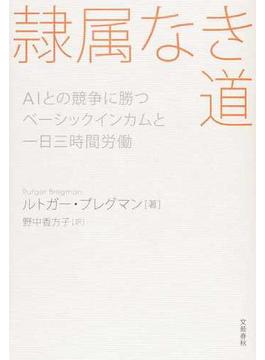「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
- カテゴリ:一般
- 発売日:2017/05/25
- 出版社: 文藝春秋
- サイズ:20cm/308p
- 利用対象:一般
- ISBN:978-4-16-390657-7
紙の本
隷属なき道 AIとの競争に勝つ ベーシックインカムと一日三時間労働
【ビジネス書大賞準大賞(2018)】人間がAIとロボットとの競争に負けると、「中流」は崩壊し、貧富の差は広がる。人々にただでお金を配る、週の労働時間を15時間にする…。オ...
隷属なき道 AIとの競争に勝つ ベーシックインカムと一日三時間労働
隷属なき道 AIとの競争に勝つ ベーシックインカムと一日三時間労働
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
【ビジネス書大賞準大賞(2018)】人間がAIとロボットとの競争に負けると、「中流」は崩壊し、貧富の差は広がる。人々にただでお金を配る、週の労働時間を15時間にする…。オランダの新星ブレグマンが、機械への「隷属なき道」を行くための処方箋を示す。【「TRC MARC」の商品解説】
◎ピケティに次ぐ欧州の新しい知性の誕生◎
オランダの29歳の新星ブレグマンが、「デ・コレスポンデント」という
広告を一切とらない先鋭的なウェブメディアで描いた
新しい時代への処方箋は、大きな共感を呼び、全世界に広がりつつある。
最大の問題は、人間がAIとロボットとの競争に負けつつあること。
その結果「中流」は崩壊し、貧富の差は有史上、もっとも広がる。
それに対する処方箋は、人々にただでお金を配ること、週の労働時間を15時間にすること、
そして国境線を開放することである。
それこそが、機械への『隷属なき道』となる。
【目次】
■第1章 過去最大の繁栄の中、最大の不幸に苦しむのはなぜか?
産業革命以降の2世紀で、長く停滞していた世界経済は250倍、1人当たり
の実質所得は10倍に増えた。これは中世の人々が夢見た「ユートピア」なのか?
ではなぜ、うつ病が歴史上かつてないほどの健康問題になっているのか?
■第2章 福祉はいらない、直接お金を与えればいい
生活保護や母子家庭手当て、就学援助、幾多ある福祉プログラムを全てやめる。
そのかわりに全ての国民に、例えば一律年間150万円の金を与える。それが
ベーシックインカム。ニクソン大統領はその実施をもくろんでいた
■第3章 貧困は個人のIQを13ポイントも低下させる
ベーシックインカムがなぜ有効なのかは、貧困がもたらす欠乏の害を調査する
とわかる。貧困はIQを13ポイントも下げる。奨学金や有効な教育プログラム
にいくら投資しても、そもそも貧困層にいる人は申し込まないのだ
■第4章 ニクソンの大いなる撤退
60年代初頭、ベーシックインカムは、フリードマンのような右派から
ガルブレイスのような左派まで大きな支持を得ていた。それを潰したのは一部の
保守派が持ち出してきた19世紀英国での失敗だった。ニクソンに渡された報告書
■第5章 GDPの大いなる詐術
ロシア人教授クズネッツが80年前に基礎を築いたGDPは進歩を表す神聖なる
指標だ。だがGDPは多くの労働を見逃し、医療や教育のサービス分野でも
効率と収益に目を向ける。人生を価値あるものにする新しい計器盤を検討する
■第6章 ケインズが予測した週15時間労働の時代
ケインズは1930年の講演で、「2030年には人々の労働時間は週15時間になる」
と予測した。ところが、産業革命以来続いていた労働時間の短縮は70年代に
突然ストップした。借金によって消費を拡大させる資本主義の登場
■第7章 優秀な人間が、銀行家ではなく研究者を選べば
「空飛ぶ車が欲しかったのに、得たのは140文字」とピーター・ティールは
揶揄する。過去30年の革新は富の移動に投資されてきた。優秀な頭脳が【商品解説】
著者紹介
ルトガー・ブレグマン
- 略歴
- 〈ルトガー・ブレグマン〉1988年生まれ。オランダ出身。ユトレヒト大学などで歴史学を専攻。歴史家、ジャーナリスト。広告収入に一切頼らないジャーナリストプラットフォーム「デ・コレスポンデント」創立メンバー。
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
オランダの29歳の新星による新しい時代の処方箋です!
2017/12/09 10:16
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、オランダの新星ルトガー・ブレグマンによって書かれたこれから始まる新しい時代の処方箋を示してくれる書です。彼によれば、人工知能やロボットに人間は完全に負けてしまうと説きます。その結果、社会の中流階級は崩壊し、貧富の差が増すまず広がる社会になっていくと警告を鳴らします。これを食い止めるには、ただでお金を配ること、労働時間を週15時間にすること、などなど、驚きの処方箋が開示されます。巷ではピケティに次ぐ新しい知性の誕生、と騒がれている驚異の書です!
電子書籍
賢い人の文章はわかりやすい
2020/03/03 00:48
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:わびすけ - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者の主張の一つでもある、左派主張は平易な言葉でわかりやすく(十二歳の子供に説明できるくらい)でなければならないというルールをきちんと守っていて、読んでる自分が賢くなったような気がする。ピケティと被るところもあるが、累進課税とタックスヘイブンの抑止、公的扶助ではなくベーシックインカムによる生活の底上げが貧富の増大の楔となるというシンプルな主張と、それを行う上での様々な妨害も想定しているのがすごい。ウィルス騒ぎでできた余暇の過ごし方としては最高の贈り物だった。我々は余暇を有効に使える!自信を持てる一冊。
紙の本
こういう議論をもっと聞きたい
2017/05/30 10:42
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:tomoaki - この投稿者のレビュー一覧を見る
NHKだったか、”日本の若手学者らと経済学を考える”という番組を見た。
このとき、経済学者という人が「経済学は(現在の日本で大きな問題と言われる)格差にはあまり興味ないんですよね」という発言をしていて、この人は何のために学問をしているのだろうとあきれてしまった。
ただ、この番組で唯一といえる収穫は、この書籍を紹介していたことだ。
ベーシックインカムや労働時間短縮(3時間!)などの議論を、著者なりに描いた「ユートピア」を主張しながら展開している。
別番組だが「欲望の資本主義」ではトマス・セドラチェック、「欲望の民主主義」ではマルクス・ガブリエルやヤシャ・モンクなど、海外の学者らの知見のほうが聞いていて刺激的だ。それは彼らが社会や政治に緊張感や批判精神、当事者性を持って対峙しているからだろう。
”過剰な消費主義社会、資本主義社会によって、新しい価値を生まない、くだらない仕事が増えた”という問題意識は、毎日会社勤めをしている身にはつまされる指摘だ。
「会社が給料をやるんだからいわれた仕事をしろ」「政府が(最低限の)生活費を負担するから社会のために何かしろ」ではどちらが、個人と社会の幸せのためになるだろうか。後者の場合、今の日本政府では徴兵制をしかねないので楽天的に考えることはできないが、多くの国民は家族で保育や介護などを担当したり、地域ボランティアに勤しむことを選ぶ気もする。
英語ができる方はぜひ、本人の議論を直接フォローすることをオススメする。
紙の本
一つの道
2017/09/07 07:09
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:病身の孤独な読者 - この投稿者のレビュー一覧を見る
広がる格差。そして人工知能(AI)による労働への脅威。これらが迫る未来で我々はどのような対策を取ればよいのか?
この問いへの一つの答えを提示しているのが本書である。貧困層やホームレスのへの「自由に使える」現金の給付を行うことで、それらに属していた人々の救済に成功してきた研究事例を豊富に紹介して、ベーシックインカムの導入を著者は強く主張している。
全世帯へのベーシックインカム導入は、特に所得下層においては確かに格差解消には期待できるかもしれない。また、AIによって働ける人口が限られてくる未来では、人間の生活保障の有力候補として挙げられるだろう。
しかし、本書の重大な短所は、研究事例が貧困層に偏っていることである。所得中間層や上位層に、下層と同様の現金給付を行うことで、所得下層と同様な経済的効果が得られるかどうかは断定することができない。
この点は注意する必要があるが、説得力のある書籍であり読む価値はあると考えられる。
紙の本
BIに賛成だけど…
2019/07/08 00:14
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:コアラ - この投稿者のレビュー一覧を見る
評者はBI賛成論者である。BIでは有名な本らしいので読んでみた。残念というのが感想だ。第7章と第8章だけあればよい。他は不要だ。特に第1章は自分がいかにすぐれた知識人であるかをひけらかしているだけの無意味な章だ。第1章があれで,よく人々は続きを読む気になったと感心する。井上智洋の「人工知能と経済の未来」のほうが安いし短いしすぐれている。自分の意見は絶対に正しくて反対するやつらはみんな馬鹿という態度には嫌悪感しか湧かない。こういう人が権力側につくとスターリニズムが実現するのだなと思った。