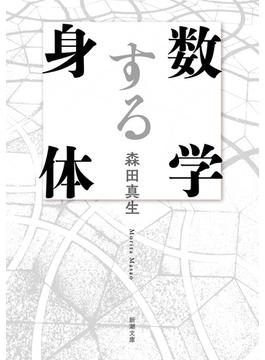紙の本
数学の営みの新たな風景を切り拓いてくれる書です!
2019/02/04 09:34
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、数学という学問をもっと人間のための存在するものとなり得ないのかということをテーマに考察した書です。数学は、あたかも数字という無味乾燥な記号を操作し、私たち人間の生活とは切り離されたところで発展してきた学問という印象が強いのですが、今一度、数学というものを再考し、数学に身体や心の居所はあるのかということを真剣に深く考えています。そして、そうした思考を経て、著者はアラン・チューリングと岡潔という二人に行きつきます。数学の見方を根本から変えてくれる画期的な一冊です。
紙の本
今まで読んだ数学関係の本で、一番面白いかも。
2022/06/17 09:01
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:L療法 - この投稿者のレビュー一覧を見る
文系、いや身体系?
数学者なのか思想家なのか、スマートニュースにも関わっていた若き学者による、数学の本。
数学史についての本であり、数学史の一部でもある様な数学思想なんだろうか。
とにかく読みやすい。
数式を使わず、ちょっとやばい領域に片足突っ込むくらい、数学の根源的な部分につれってくれる。
今まで読んだ数学関係の本で、一番面白いかも。
ただ、ちょっとスピ的な、論理を超えていく、あるいは、一般的な論理とは別の視点には、ちょっとばかし抵抗があり、騙されないぞと警戒してしまう。
いかにも新潮文庫な、尻ポケットサイズですが、昔の本より紙が薄いらしく、思ったよりページ数がある。
(どれだけ新潮文庫離れてたんだってことでもある)
とにかくすこぶる面白い。
数学に息吹を取り戻す、魔術的本。
そういや、作者の名前は、真生である。
これは自然としての、あるいは、心身を含む環境としての数学の本かもしれない。
紙の本
算数ではなく
2018/05/03 09:33
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
自然法則に従う一つの「機械」に過ぎない人間にどうして自由な意思を持つ「魂」が宿るのか、これからも数学を研究し続けるぞ、という決意表明とそれに至った過程の書。
紙の本
数学の身体
2022/02/10 19:57
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:H2A - この投稿者のレビュー一覧を見る
こういった方向から数学を扱った本は知らない。数学が生存に直結した手段からギリシャで証明を重んじるようになり、しだいに記号そのもので記述されるようになり、本来あったはずの「身体」をなくしていったと述べる。後半はチューリング、岡潔という人物の足跡が中心になり、それはそれでいいのだけれど第1,2章の方がおもしろく読めた。
投稿元:
レビューを見る
本書は、東大工学部・理学部数学科を出た(文Ⅱから理転)独立研究者・森田真生(1985年~)が2015年に発表した初の単著で、史上最年少で小林秀雄賞を受賞したもの。(2018年文庫化) 著者は現在、数学をテーマとした著作・講演活動などを行う。
本書で著者は、古代ギリシアからの数学史、ナチスドイツの「エニグマ暗号」を解読し「人工知能の父」とも言われる英国人アラン・チューリング(1912~54年)、そして、多変数解析関数論の研究で世界的な業績を残した数学者・岡潔(1901~78年)を語りながら、「数学とは何か」、「数学にとって身体とは何か」、「数学とは何であり得るのか」を問うている。その過程では、数多の数学者のほか、建築家の荒川修作、『生物から見た世界』のフォン・ユクスキュル、脳科学者のラマチャンドランなどにも話は及ぶ。
しかし、解説で鈴木健氏が言っているように、著者の関心は明らかに岡潔に注がれており、著者が岡潔の『日本のこころ』に出会ったときに、「私は、岡潔のことをもっと知りたいと思った。彼が見つめる先に、自分が本当に知りたい何かがあるのではないかとも思った。簡単に言えば、「この人の言葉は信用できる」と直観したのだ。」という確信に基づいて語る言葉は、私には強い印象を残すものであった。
「「情」や「情緒」という言葉を中心に据えて数学や学問を語り直すことで、岡潔は脳や肉体という窮屈な場所から、「心」を解放していこうとした。・・・岡潔は確かに偉大な数学者であったが、生み出そうとしていたのは数学以上の何かである。」
「岡は科学を丸ごと否定しているのではない。彼は「零まで」をわかるためには「零から」をわかるのとは違う方法が必要であると言っているのだ。」
「自他の間を行き交う「情」の宿る個々の肉体は狭い。人はその狭い肉体を背負って、大きな宇宙の小さな場所を引き受ける。その小さな場所は、どこまでも具体的である。友情もあるだろう。恋愛もあるだろう。人と交わした約束や、密かな誓いもあるだろう。苦しい離別もあれば、胸に秘められた愛もあるだろう。そうしたすべてが、ひとつひとつの情緒に、彩りを与える、そこに並々ならぬ集注が伴うと、それが形となって現れる。岡潔の場合、数学となって咲いた。」等々
私は、岡潔の『春宵十話』は以前読んでおり、その中にあった「数学とはどういうものかというと、自らの情緒を外に表現することによって作り出す学問芸術の一つであって、知性の文字板に、欧米人が数学と呼んでいる形式に表現するものである。」という表現に衝撃を受けたが、その真意は十分には分からなかったし、本書についても、一読しただけで著者の言わんとすることが消化できたとは思えない。
しかし、著者が「あとがき」に記している「よく生きるために数学をする。そういう数学があってもいいはずである。この直感に、私は形を与えていきたい。」という思いには直感的にシンパシーを覚えるし(更に、岡潔も著者も「よく生きるために●●をする」の●●は「数学」である必要は必ずしもないとも言っているのだ)、それを少しでも身体で感じられるように、今後時間をかけて思索してみたいと思うのである。
(2018年5月了)
投稿元:
レビューを見る
数学と数学者の話ししか出てこないのに、爽やかで清涼な残り香。なんとも不思議なエッセイだった。
大学の教養課程で「数学」の授業が「論理」についての授業だった時におぼえた解放感を思い出した。本書は言葉をつくして「考えること」「考える手続き」「思考の道具」「考えたことを共有する方法」など思わぬところで「生きることと数学」がつながっているのだと語りかけてくれる。
素晴らしい読書体験だった。
投稿元:
レビューを見る
快著である。チューリングに至る、身体性にからめた数学史のさらい方に唸るものがあるが、岡潔を通して、逆方面から数学を大きく、深く写し出した思索も見事である。文も美しい。
投稿元:
レビューを見る
数学することと生命活動を営むことの間の関係性を,数学の歴史を繙き,チューリングと岡潔の生を顧みることにより明文化する.明確な解が存在するかも分からないが,何はともあれやってみて,それから思考すればよいではないか,という姿勢は,研究者に通底する.
投稿元:
レビューを見る
第1章 数学する身体
第2章 計算する機械
第3章 風景の始原
第4章 零の場所
終章 生成する風景
第15回小林秀雄賞
著者:森田真生(1985-、東京都、数学)
解説:鈴木健(1975-、エンジニア)
投稿元:
レビューを見る
最初はチンプンカンプンだったが、アランチューリングが出て来て、面白くなった。
「イミテーションゲーム」という映画を見ていたので、馴染みがあったのだ。
そして、岡潔が出て来て、こちらも小林秀雄との対談で知っていた。
今まで読んだことのないジャンルの本に、興味を持たせる本である。
投稿元:
レビューを見る
大学には属さない在野の数学研究者であり、数学の魅力を伝える様々な講演活動等も行う若き著者が、数学の歴史を紐解きながら、数学との距離が遠くなってしまった身体をいかに数学に取り戻せるか、というテーマの元に、数学という学問の面白さを語る随筆。小林秀雄賞の受賞作という点からも明らかなように、文体は極めて理路整然としており、かつ静かな熱量を帯びた語り口が魅力的に映る。
読み手に一定の解釈の自由度を与える(良い意味で、特定の意味を読み手のおしつけない)文章であるが故に、読む人によってどこを面白いと感じるかは恐らく大きく違うだろう。僕個人としては、作図や数学的記号を用いた演算といった「道具」を数学が手に入れることで、「意味」を超えるものがそこから生み出されるという点に改めて「道具」というもののもたらす可能性を感じた次第。人間がその時点で知覚できる「意味」には常に限度があり、その本当の意味はむしろ事後に遅れて解釈されるようになる。虚数の概念のように、数学ではそうした事象が顕著に見られるという点が面白い。
投稿元:
レビューを見る
岡潔とアランチューリングという2人の数学者を引き合いに出しながら、「考えること」に関して向き合った本。考えるということは、個人の脳の中では完結せず、脳から身体へ、そして公共へと拡張されることによって実現される行為であるというのが要旨だと読み取った。
・古代ギリシアより、数学をするには「証明」という思惟の公共性が必要とされた。内にてひとりぼっちで思索にふけるのではなく、証明という外部表出によってはじめて思惟たりうるという考え方。
・ハイデガーも言っている通り、学ぶという行為は、すでに知っているものを知ることである。
・いかなる生物も、客観的な「環境」を生きているわけではなく、自分の主観に基づいて再編集された「環世界」を生きている。その環世界の中で、思考と行為を繰り返し、「自分の思惟」が完成されていく。
・岡潔においては、何かに取り組むことというのはそのものと主客二分されずに一体となるという瞬間が必要だと語る。
投稿元:
レビューを見る
【数学する身体】
森田真生著、新潮社、2016年
著者は1985年生まれだから10歳年下の33歳の数学者。
東大文二在学中にベンチャー企業を設立するためにシリコンバレーに行っていた著者が、戦中戦後に天才数学者と言われた岡潔の本を読んで数学に目覚めて「数転」(文系から数学科に転じる)した著者。
もともとが文系だけあって、文章がとにかくうまい。
人間が数学というものをどのように作ってきたのか、がとてもわかりやすく書かれている。
例えば、僕らは数を数える時に「10」を一つの単位としていることに異存はないだろう。これを「10進法」と呼んでいる。
では、なぜ「10」が基本単位なのだろうか?ということがこの本には書かれている。
そんなこと、考えたことも無かったが、森田は以下のように説明する。
--
指を使って数えるのもそうである 。指はもともと 、モノを掴むために使われてきたのであって 、数えるための器官ではない 。実際 、人間の長い進化の来歴の中で 、 「数える 」必要に迫られることはごく最近までなかっただろう 。だからこそ 、いざその必要に迫られたときには 、それまでモノを掴むために使っていた指を 「転用 」するほかなかったのだ 。あくまでその場凌ぎの方法だから 、これにもしわよせがある 。普通に指を使って数えると 、十までしか数えることができない 。だから 、 「十 」が数えるときの単位として定着した 。無限にある数の中で 、 「十 」が特別扱いされなければならない数学的な理由など 、どこにもないのにである 。実際 、コンピュ ータの中で数字は 、二進法で表現される 。何と言っても 、二つの記号だけですべての数を表せるのが魅力である 。その点 、二進法は十進法よりもはるかにエレガントだが 、世界中の大部分の人は十進法を使う 。それは 、身体を使って数を扱う人間にとって 、十進法がたまたま運用上 、もっとも合理的であったというだけのことである 。
--
この他にも、第二次大戦中にナチスドイツの最強暗号といわれた「エニグマ」を、解読する方法を編み出したイギリス人の天才数学者チューリングのこともページを割いて紹介されている。チューリングはその後、それまでの「人間が行う計算」から「計算そのものを行う計算」という概念を打ち出して、それこそがコンピューターの基礎理論となったことなどを紹介する。
今こうして、フェイスブックを通じて読書日記をUPすることも、インターネットで世界中にシェアできることも、まさにこのチューリングの発想から始まったことだ。もっと言えば、現代社会の殆どがチューリングの発想から始まっていることに驚嘆する。
高校にいると「数学なんて、役に立たない」というセリフを聞くことがままあるが、現実は的には「数学の恩恵を得ない生活は成り立たない」ということだ。
6割くらいしか理解していないかもしれない。
でも、むっちゃ面白かった。
せっかくの夏休み、高校生は背伸びをして、こういう本に挑戦してほしい。
#優読書
投稿元:
レビューを見る
数学という学問が数学という体裁を手に入れてから今日までの進化の道程を辿りつつ、
一見相反する「数学」と「情緒」を繋ぎ合わせていく。
チューリング、岡潔が対照的でありながら心へと向かう試みという点で共通している、という洞察は非常に面白い。
数式が出てくるでもなく、細かい解説がなされるわけではないが数学という学問の意外ともいえるしなやかさに触れることができる刺激的な一冊。
投稿元:
レビューを見る
数学は哲学。世界を、心を理解する方法から、世界に、心に「なる」ことへ。チューリングと岡潔(と芭蕉)を通して語られる森田さんの哲学。チューリングは偉大でありつつ悪役で、岡潔に大きく傾倒している様が読み取れる。私はまだまだ「理解」の側にしか立てないな。岡潔の著作を読んでみたくなった。