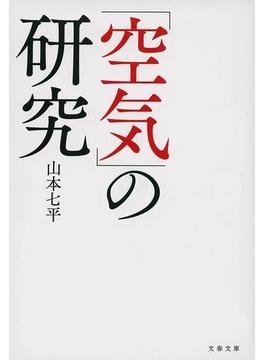「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
紙の本
「空気」の研究 新装版 (文春文庫)
著者 山本七平 (著)
日本において「空気」はある種の絶対権力を握っている−。著者の指摘は、誰もが空気を読み「忖度」する現代を予見していた。いまだに数多くのメディアに引用され論ぜられる名著にして...
「空気」の研究 新装版 (文春文庫)
「空気」の研究
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
日本において「空気」はある種の絶対権力を握っている−。著者の指摘は、誰もが空気を読み「忖度」する現代を予見していた。いまだに数多くのメディアに引用され論ぜられる名著にして、日本人論の決定版。【「TRC MARC」の商品解説】
昭和52年の発表以来、40年を経ていまだに多くの論者に引用、紹介される名著。今年3月も、NHK Eテレ「100分deメディア論」で、社会学者・大澤真幸氏が本書を紹介し、大きな反響があった。日本には、誰でもないのに誰よりも強い「空気」というものが存在し、人々も行動を規定している・・・。これは、昨今の政治スキャンダルのなかで流行語となった「忖度」そのものではないか!
山本七平は本書で「「空気」とはまことに大きな絶対権を持った妖怪である。一種の『超能力』かも知れない。」「この『空気』なるものの正体を把握しておかないと、将来なにが起るやら、皆目見当がつかないことになる。」と論じている。それから40年、著者の分析は古びるどころか、ますます現代社会の現実を鋭く言い当てている。「空気を読め」「アイツは空気が読めない」という言葉が当たり前に使われ、誰もが「空気」という権力を怖れて右往左往している。そんな今こそ、日本人の行動様式を鋭く抉った本書が必要とされている。
『「水=通常性」の研究』『日本的根本主義(ファンダメンタル)について』と続き、日本人の心の中にかつても今も深く根ざしている思想が明らかにされていくのは圧巻。
日本人に独特の伝統的発想、心的秩序、体制を探った、不朽の傑作を、文字の大きな新装版で。【商品解説】
誰でもないのに誰よりも強い「空気」。これは「忖度」そのものだ。発表から40年を経て、今こそ読まれるべき日本人論の名著。【本の内容】
関連キーワード
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
山本七平氏による、空気に関する深い考察が書かれた本
2023/01/24 22:27
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:デーモン - この投稿者のレビュー一覧を見る
山本七平による、日本独特の、いわゆる、空気、もしくは、ムードと呼ばれるものの、正体について、本の編集者とのやり取りを、端緒として、戦前の日本軍の事例、自動車の問題を題材に、興味深い考察が描かれています。会社組織について、考える際にも、ためになる本だと思います。
紙の本
「空気」読まないことも!
2019/01/25 22:53
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オカリナ吹き - この投稿者のレビュー一覧を見る
産経新聞のコラムにこの本が紹介された。それを内科医院の待合室でたまたま読んで、その足でジュンク堂へ。さっそく読んでみた。厚労省の不正統計、森友の「忖度」は「空気」を読んだ結果です。それが日本にだけあること。聖書の影響の大きい欧米では考えられないことのようです。「空気」を読まないことが必要なこともあるのです。
紙の本
空気を自覚しているのに見ないふりをする日本人
2018/12/18 09:31
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:tomoaki - この投稿者のレビュー一覧を見る
会議で想定外の意見や議論を嫌がる、
根回しのみでの出来レースを好む、
「周りのことを考えて」という、、、、
日本に暮らしているとこういう場面が本当に多い。
どの社会でもある程度はこういう場面はあるのだろうが、日本人は過剰に周りの空気を読み、忖度する。百歩譲って、それが日本社会で生きるスキルなのだとしても、そのうちに周りの意見=自分の意見といつの間にか同化してしまったりしている。これは外国人とは違う点ではないだろうか。
日本人の変な空気に疑問をもったときには読んだほうがよい本だろう。
紙の本
「空気」と「水」
2022/11/11 04:22
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:かずさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
この「空気」と「水」は空気を読め、水を差すな。このことを論理的に考えている。物事を決める議論や会議の時、空気を読め、あの空気では仕方がなかった。と言われたり、流されたり、疑問を持った時に素直に疑問を発した時に「水を差すな」と言われたことはないだろうか。日本人独特な思考形態かもしれない。何故、そのような思考が全体を覆うのか。研究された時代の出来事を例に取り上げながら考察している。繰り返しの部分が多くあるので難解な文脈が続くこともある。じっくりと読むことが必要。
紙の本
日本論
2020/01/21 06:10
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:七無齋 - この投稿者のレビュー一覧を見る
場の空気についての論述だが複数雑誌掲載の形態からとりとめのない話も入っていて焦点がぼけがちだ。空気の支配についてはかなりうなずけることがある。
紙の本
私たちの判断基準となっている「空気」とは
2019/11/30 10:28
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ゲイリーゲイリー - この投稿者のレビュー一覧を見る
常日頃から場の「空気」を読み行動をしている人は大勢いるだろう。
かくいう私も、場の「空気」に合わせて行動をしていることは否めない。
その「空気」とは何かと問われると誰しもが答えに詰まるのではなかろうか。
本書は、その「空気」について深く掘り下げていた。
今までどれ程の人々が「空気」に基づいて判断していたかを、様々な事例を基に分かりやすく書いていた。
「空気」が醸成される原理原則も非常に分かりやすく書かれていた。
個人的には、「空気」の原因でもある臨在感的把握にとても強く興味を持った。
対象への一方的な感情移入による自己と対象の一体化により、対象への分析を拒否する心的態度である臨在感的把握。これは誰しも心当たりがあるのではないか。
また、本書は「空気」だけでなく「空気」を崩壊させうる「水」についても書かれている。
「空気」=虚構の異常性、「水」=通常性という関係性も様々な事例を基に分かりやすく書かれていた。
本書では、太平洋戦争や戦後の政治情勢、キリスト教に関する歴史などが多々書かれている。
私自身の知識不足も相まって、それらが記述されている部分は分かりづらかった。
ただ、日本という国の独自性や臨在感的把握の事例など分かりやすい部分も多くあるので、世の中を覆う「空気」に違和感を持っている人には本書をオススメする。
電子書籍
時を超えた”空気”の存在
2019/09/13 14:13
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:姫路ねこ研究所 - この投稿者のレビュー一覧を見る
HPVワクチンの有効性は医学的に認められている。しかし、我が国での普及は燦々たるものである。
最近、あるジャーナリストの厚労省の官僚にインタビューした記事を目にした。HPVワクチン接種の推進についての記事である。インタビュアーは“何でワクチン接種を推進してこなかった?科学的根拠をもってやるべきでは?”という問いかけに対して、官僚は“当時の空気ではできなかったですよ”と返していた。
厚労省の官僚すら贖えない“空気”、なんだ?これ?いったい?
著者は“空気”の説明に“臨在感的把握”という単語を使っている。簡単に言うと、ある出来事や物に対して感情移入してしまう、ということか。臨在感的把握をしてしまうと、出来事や物を絶対化し、判断を支配されてしまう。
これは日本人独特のようだ。西欧では絶対的なものは神のみである。その他のものは全て相対的に把握する。なので、出来事や物に対して臨在感的把握をしない。行き着く先は合理的把握することである。
日本の場合、古来、多神教だった。なので、様々な出来事や物に対して臨在感的把握をして、絶対化してきた。一つの絶対化が崩れたとしても、別の出来事や物に対して臨在的把握をして絶対化をすればよい。ものごとの可否の判断に着いても、それぞれを絶対化してしまう。特に日本では、相対化して考えるより、絶対化して考える方が、はるかに楽なんだ。
すると、“この社会”はどんな社会?逆説的だが、構成しているメンバーは、絶対化された対象の前では、皆平等である。絶対化された対象を君とする。ここに一君万民の社会ができる。君を覗いたメンバー同士の関係性は、家族的となる。一君万民に対して矛盾に見える出来事が起こると、メンバー間で出来事そのものの存在を否定する。メンバーは互いに家族なんで、これができる。こうやって秩序を保持する。“この社会”のメンバー間の関係性が“空気”である。
“この社会”が一旦確立してしまうと、方向転換ができず、“鎖国”となる。最終的には自滅する。しかし、自滅後も“この社会”は別の出来事や物を臨在的把握し、絶対化するだけである。
では“空気”がなくなるのは?その一つに“水を差す”行為がある。定義は困難なようで、著者も、少しずつ浸み込んで行って腐食させるもの、とだけ書いているが、つまりは“それを言っちゃあ、おしまいよ”てなことである。ただ、これが通用するのは空気が形成されたごく初期なんだろう。
HPVワクチンに当てはめて考えると、臨在感的把握を行い、“空気”を形成しているのは、反ワクチン派である。ワクチン非接種という“出来事”を絶対化し、“この社会”を形成している。
解決には、反ワクチン派の意見に“水を差す”ことができるかもしれない。しかし、もはや水すら効果がないところに来ている。
最終的には、反ワクチン派の自滅を待つしかない、というのが、著者の意見になる。
ただ、もう一つだけ、本書では少ししか触れられていなかったが、可能性がある。日本人が“この社会”を形成するには、同じ出来事や物に対して、同じように臨在感的把握を行う必要がある。でも、そんなにうまくいくだろうか?多くの場合は、典型的日本人ではない、非典型的日本人による恣意的な誘導ではないか?
つまり、自らが非典型的日本人となり、出来事や物を臨在感的把握を行うように仕向ける、ということである。
ただ、厚労省の役人ですらできなかったこと。できる人は・・・日本で数十人レベルかも・・・