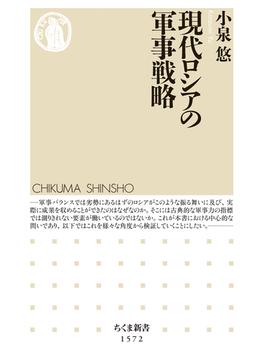現代ロシアの軍事戦略
著者 小泉悠
冷戦後、軍事的にも経済的にも超大国の座から滑り落ちたロシアは、なぜ世界的な大国であり続けられるのか。NATO、旧ソ連諸国、中国、米国を向こうに回し、宇宙、ドローン、サイバ...
現代ロシアの軍事戦略
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
冷戦後、軍事的にも経済的にも超大国の座から滑り落ちたロシアは、なぜ世界的な大国であり続けられるのか。NATO、旧ソ連諸国、中国、米国を向こうに回し、宇宙、ドローン、サイバー攻撃などの最新の戦略を駆使するロシア。劣勢下の旧超大国は、戦争と平和の隙間を衝くハイブリッドな戦争観を磨き上げて返り咲いた。メディアでも活躍する異能の研究者が、ウクライナ、中東での紛争から極東での軍事演習まで、ロシアの「新しい戦争」を読み解き、未来の世界情勢を占う。
目次
- はじめに──不確実性の時代におけるロシアの軍事戦略/「ポスト冷戦」時代の終わり──揺らぐ国際秩序/軍事力の「効用」/非軍事的闘争論/テクノロジーは戦争を変えるか/本書を理解するための基礎知識/第1章 ウクライナ危機と「ハイブリッド戦争」/1 NATO拡大──東欧でのオセロ・ゲーム/リガ空港の「バックファイア」/倉敷に人民解放軍の基地ができたら/後退する「戦略縦深」/小さな軍事大国/「アフガニスタンのことを考えて眠る」/「勢力圏」と「大国」/2 ウクライナで起きたこと/瞬く間に失われたクリミアとドンバス/人間の「認識」をめぐる戦い/ドローン戦争/米海兵隊も舌を巻くロシアの電磁波作戦能力/ウクライナのインフラを麻痺させたサイバー攻撃/3 「ハイブリッド戦争」をめぐって/非クラウゼヴィッツ戦争?/「360度同盟」へ/「ハイブリッド戦争」論の起源/戦争の「特徴」と「性質」/古くて新しいハイブリッド戦争/ハイブリッド戦争に関する3つの論点/第2章 現代ロシアの軍事思想──「ハイブリッド戦争」論を再検討する/1 非軍事的闘争論の系譜/ロシア軍参謀総長が語る21世紀の戦争/レーニンとクラウゼヴィッツの戦争理解/スリプチェンコの「非接触戦争」論/情報の力──メッスネルの「非線形戦争」論/パナーリンの「情報地政学」理論/ロシアの疑心暗鬼/軍隊は役立たずに?/2 「永続戦争」の下にあるロシア/「カラー革命」への脅威認識/戦場としての言論空間/NGOを「外国の手先」と認定/若者の心を掴め/プーチンの市民社会論/ロシアはなぜ米国大統領選に介入したか/3 「カラー革命」に備えて──ロシア国内を睨む軍事力/プーチンの「親衛隊」/国家親衛軍をめぐる権力関係/ゲラシモフ演説に見る脅威認識/コロナ危機とプーチン政権/4 それでも戦争の中心に留まる軍事力/思想と実践の間/ゲラシモフ演説を読み直す/ドクトリンではなくハッパ/予測の困難性を超えて/第3章 ロシアの介入と軍事力の役割/1 ウクライナ紛争に見る軍事力行使の実際/クリミア半島での電撃戦/二転三転するドンバス紛争/軍隊は強い/親露派武装勢力の「戦う理由」/「ハイブリッド戦争」と「ハイブリッドな戦争」/2 中東での「限定行動戦略」/シリア紛争を一変させたロシアの介入/愛国者公園にて/「第6世代戦争」の入り口/「精密攻撃」と残虐性の価値/介入戦争を可能にした限定行動戦略/3 特殊作戦部隊と民間軍事会社/シリアに送り込まれたロシアの秘密部隊/平時と有事の間で戦う特殊作戦部隊/砂漠に咲くひまわり/民間軍事会社「ワグネル」の誕生/ワルキューレの騎行──ドンバス紛争とワグネル/ワグネルの「事業モデル」/リビアでの敗北/「ワグネルって何ですか?」/4 「状況」を作り出すための軍事力/「勝たないように戦う」/「解凍」されたナゴルノ・カラバフ紛争/ドローンは「ゲーム・チェンジャー」か?/「意志のせめぎ合い」としての戦争/アゼルバイジャンの「読み勝ち」/エスカレーションを抑止する/暴力の行使という溝/第4章 ロシアが備える未来の戦争/1 大演習を見る視角/秋は演習の季節/そもそも演習とは/ほか
関連キーワード
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
軍事的なことは不案内だけれど
2022/04/10 15:56
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:qima - この投稿者のレビュー一覧を見る
とにかく読みやすくて、わかりやすくて助かります。しかも、すごく興味深い内容ばかりで。残念なタイムリーになりましたが、こういう専門書があって幸運でした。
ある意味、ウクライナ侵攻の預言書。ロシアの軍事思想を知る上でも役立つ。
2024/05/26 20:53
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:瀬戸内在住の猫 - この投稿者のレビュー一覧を見る
この本、ロシアのウクライナ侵攻の前年に出版された本だが、内容的に2022年のウクライナ侵攻を預言したかの様な内容になった。
それと言うのも、当時分かる限りでロシアの軍事戦略を分析したからで、その点では現在でも充分参考になる。
ロシア軍が核戦力を実戦使用する事を前提条件として戦略を練っている事も分かるので、今後のロシアとウクライナの戦争を分析する上でも有用だろう。
リアリスティックで冷静に、ロシア観点での考えや軍事状況がわかります
2022/10/17 09:20
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とらとら - この投稿者のレビュー一覧を見る
出版されたのは2021年ですが、2022年のロシアのウクライナ侵攻までの経緯や、ロシア側からの観点での思いなどまでもわかる、冷静な分析を事実に基づいて書かれています。情報戦の意味と、それでも昔からの強制力を持つ軍事的な能力の重要性が決して減じているわけではないことなどもよくわかります。
侵攻後に起きていることの分析や解釈などについても、読みたくなります。
時節をとらえた重要書
2022/08/10 13:53
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:見張りを見張るのが私の仕事 - この投稿者のレビュー一覧を見る
題名の通り現代ロシアの軍事戦略について分析した本。はじめに現代ロシアの軍事力は、軍事力を支える経済力という点を踏まえてもNATOに対して劣勢である、というところから述べられる。軍事力で劣勢にあるロシアは非軍事的闘争論という考え方を編み出してきた。単純な軍事力なら負けてしまうが、敵国の大衆の心理に訴える情報戦や、政治体制をゆるがす政治運動の利用、といった情報面での闘争を通じて、暴力によらず政治的目的を達成しようとするのが非軍事的闘争の要点である。ただし、そういった思潮の中でも通常軍事力の影響力は依然として重要でありつづけていることも指摘されている。
ロシア軍の軍事演習の分析も述べられている。以前はテロ組織といった非国家的勢力を念頭に演習が行われてきたが、ここ最近では大国との大規模戦争が想定されるようになっている、という指摘が貴重。
現代ロシアの軍事戦略では核兵器についてはどのように位置づけられているのか。かつてワルシャワ条約機構がNATOにたいして通常戦力で優位であったときは、核の先制不使用、つまるところ伝統的な核抑止論をいうだけで事足りたのが、現在ではロシアが通常戦力下で劣勢にあるために限定的核使用によるエスカレーション抑止論という具体的にどのように使用するのかを想定した理論が組み立てられているという指摘は興味深い。もっとも、核使用については資料が非公開とされ不明な部分が多く確かなことは言えないらしいが、それでもエスカレーション抑止に相当する考え方をロシアが持っている可能性は高いと言う。
中国を封じ込めるためにロシアと手を組む(あるいはロシアを封じ込めるために中国と仲良くする)というような政治的態度にくぎを刺している。中国とロシアは権威主義体制の国同士でウマが合い、西側の自由主義は権威主義体制を揺るがすものである。日本は西側の一員としての自覚を持って事に当たるべし、とのことである。
丁寧な説明です
2022/05/12 20:32
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:飛行白秋男 - この投稿者のレビュー一覧を見る
ロシアのウクライナ侵攻後、ロシアの専門家として多くのTV番組に出演され
解りやすい説明と、誠実に違いないお人柄、頭の良さがにじみ出ている方の著書を初めて読みました。
濃い内容ですが、私には少し難しいようでした。
基礎知識のある方にはお勧めです。
ロシアのウクライナ侵略以前に出版された書籍だが陳腐化していない
2022/07/19 15:06
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:巴里倫敦塔 - この投稿者のレビュー一覧を見る
ロシアの軍事・安全保障の研究者が、軍事的にも経済的にも「弱いロシア」が体面と大国意識を保つために、どのような軍事戦略を採っているのかを分析した書。ロシアのウクライナ侵略以前(2021年5月)に出版された書籍だが、さほど陳腐化していない。ウクライナ侵略の現状を理解するのに役立つ指摘もあり、読み応えがある。著者の専門家としての眼は確かで、テレビに引っ張りだこになっている理由がよく分かる。ウクライナ侵略の背景を知る上で必読の書だろう。
筆者はロシアの軍事・安全保障戦略の中核を「ハイブリッド戦争」と位置づける。直接軍事力を行使するクラシカルな戦略だけではなく、非軍事的手段を組み合わせる。すなわち、サイバースペースでの攻撃、電磁波を用いた電子機器への攻撃、人の認識を操作し侵略を正当化する情報戦(プロパガンダ)を織り交ぜて、NATOや米国と対峙する訳だ。
一方の欧米(NATO)もハイブリッド戦争を前提に戦略を組み立てる。実際クライナの現状を見ると、クリミア占拠(2014年)とシリアへの軍事介入(2015年)におけるロシアのハイブリッド戦争を参考に、NATOや米国が対応している様子もうかがえる。
戦術核兵器使用に関する分析も注目に値する。いわゆる「エスカレーション抑止」である。限定的な核使用によって敵に「加減された被害」を与え、戦闘の停止を強要したり、域外国の参戦を思いとどまらせるというものである。
ロシアの軍事力
2021/06/13 09:02
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なつめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
現代ロシアの軍事力について、いろいろな角度から分析されていて、よかったです。日本との関係も、興味深かったです。
今読むべき本のひとつ
2022/05/28 14:45
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぷー - この投稿者のレビュー一覧を見る
サントリー学芸賞を受賞しているイズムィコ先生の新書。このタイミングで読まねばいつ読むのだ、と思って購入したが、しばらく寝かせてしまった。
自らを半ば卑下するようにも聞こえる「軍事オタク」と称するその文章は、確かに膨大な情報量をとめどなくアウトプットするオタク的要素も含みながらも、その構成はクリアで明快、読んでいて気持ちいい。著者の語り口そのもののように思える。
ウクライナ侵攻が始まって、早くも3ヶ月が経過した。その背景を手っ取り早く知ることができる良書。
現在のウクライナ戦争下のロシアの軍事思考を知ることが出来る。
2022/05/09 12:52
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:いけたろう - この投稿者のレビュー一覧を見る
どちらかと言うと、2022年5月9日においてはロシア軍の時代遅れさをとらえたものが多いが、この本を読めばその行動は納得出来る。
しかし、実際は概してそのようにならないことのオンパレードだ。
戦術核の使用をちらつかせながら恫喝する行動など、事前に決められた方針に則っており、追い詰められているという様には思えなくなった。
ただ、初期の軍事行動はまさにクリミア半島制圧通りの行動であった様に思われ、裏をかかれて失敗した様に思われる。
その失敗に鑑み、長期化はロシアの方針通りの行動だがいかにこれを挫折させるかが平和に至るプロセスなのだろうと思った。
ロシア
2021/06/21 16:11
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:中村 - この投稿者のレビュー一覧を見る
プーチンの戦略性には、日本人では、太刀打ち出来無いかも?
と思いました!
今こそ……
2022/03/16 02:19
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
タイムリーな内容で、現代のロシアのこと、プーチンの本性など詳細に書かれています。しかし、これが、ロシアの実体であり、プーチンがそうならば、日本はとてもとても……。北方領土なんてとんでもない……ってことに……