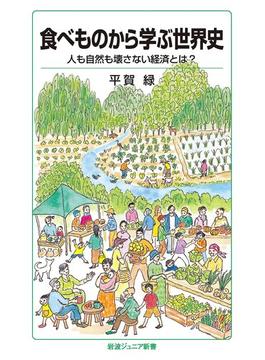「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
紙の本
食べものから学ぶ世界史 人も自然も壊さない経済とは? (岩波ジュニア新書)
著者 平賀 緑 (著)
食べものから世界経済の歴史を学べば、人も自然も壊さない「経世済民」が見えてくる。すべての問題の根底にある資本主義のカラクリを、小麦粉や砂糖、油、トウモロコシ、豚肉などの食...
食べものから学ぶ世界史 人も自然も壊さない経済とは? (岩波ジュニア新書)
食べものから学ぶ世界史
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
食べものから世界経済の歴史を学べば、人も自然も壊さない「経世済民」が見えてくる。すべての問題の根底にある資本主義のカラクリを、小麦粉や砂糖、油、トウモロコシ、豚肉などの食べものから解き明かす。【「TRC MARC」の商品解説】
砂糖や小麦粉など身近な食べものから「資本主義」を解き明かす! 産業革命、世界恐慌、戦争、そしてグローバリゼーションと「金融化」まで、食べものを「商品」に変えた経済の歴史を紹介。気候危機とパンデミックを生き延びる「経世済民」を考え直すために。【商品解説】
身近な食べものから「資本主義」を解き明かす! 食べものを「商品」に変えた経済の歴史を紹介。【本の内容】
目次
- はじめに
- 序章●食べものから資本主義を学ぶとは
- 食と農の現実
- 食べるための働き方も変わった
- 資本主義とは
- 食べものから世界経済の成り立ちを学ぶ
- 1章●農耕の始まりから近代世界システムの形成まで
- 農耕の「神話」と穀物の役割
- 大航海時代と重商主義
- 資本主義と産業革命の始まり
著者紹介
平賀 緑
- 略歴
- 〈平賀緑〉広島出身。京都橘大学経済学部准教授。立命館大学BKC社系研究機構客員協力研究員。京都大学博士(経済学)。著書に「植物油の政治経済学」がある。
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
あの『砂糖の世界史』に並ぶ名著。
2022/12/09 18:46
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぴんさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
食というテーマから、資本主義の歴史と現在を振り返り、未来を模索する。あえて言います。必読、と。中高生から大人まで、ぜひ。平易な語り口、食という理解しやすい題材で、バッサリと資本主義を切った大人の読み物。食べものから世界経済の歴史を学べば、人も自然も壊さない「経世済民」が見えてくるだろう。
紙の本
提言が手厳しい1冊です
2021/08/03 07:37
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:広島の中日ファン - この投稿者のレビュー一覧を見る
現代の「食」をビジネス・経済に取り入れる社会はいかがなものか?という提言に基づく、紙幅は薄いですが、読んで考えさせる1冊です。昔から現代までの「食」を順に振り返る、タイトル通り世界史のストーリーで構成されています。
著者の、「食」をビジネスにすることで、食糧の貧富の差、フードロス問題、環境問題に大きな悪影響を与えている現実に対する、提言が本当に手厳しいです。
どのような世代にも読んでいただきたい良書です。私も考えさせられました。
紙の本
今までとは違った視点での、世界史がある!
2023/03/04 14:53
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:野間丸男 - この投稿者のレビュー一覧を見る
「身近な田畑や自然環境から日々の食を得ていた」から、
大航海時代を経て、重商主義の金銀がお金の時代になり、
その後の産業革命により労働者が発生し、
そのための生活・食べるモノが変化し、市場が変化・発展していく。
小麦粉や油を多用する食品産業の発展のよる「食生活の変化」が、
どのように資本主義に影響を与えてきているかが、よく理解できる。
食べものから資本主義を学ぶとは
農耕から近代世界システムの形成まで
山積み小麦と失業者たち
世界の半分が飢えるのはなぜ?
日本における食と資本主義の歴史
中国のブタとグローバリゼーション
農耕と資本主義とを結び付けて考えることは無かったが、
「なるほど~!」と、納得の本である。
紙の本
大人の学び直しにもよい
2023/08/10 15:03
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:くまを - この投稿者のレビュー一覧を見る
人生半ばの年齢になって恥ずかしながら知らないことばかりで、とても興味深く読みました。こういうことを義務教育の期間に体系的に学べるといいのにな。
紙の本
資本主義経済と食料
2022/07/26 09:17
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:かずさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
読み始めると資本主義の発達が食べ物にも大きく影響しグローバル化から「北」と「南」、貧困問題まで関連し資本主義経済を否定するかのように思うかもしれないが、それは大きな誤り。読んでいる自分自身がどっぷりと資本主義経済の食料システムに浸かっているのを感じてしまった。本来人間が生きる為、健康と自然環境のための食と農が軽んじられていること。ビジネス利益第一主義が何も考えずに三食たべている現実。ちょっとでも現在の食料事情を考えた時には読んでおくべき。ジュニア新書だが大人が読んでも十分に考えさせられ、何か自分でもできないか。と思う。「命か経済か」より「命のための経済」この著者の言葉は食べ物だけでなくコロナ禍の政治家や資本家が心に刻む言葉。
紙の本
ほんとうのことは知らされないもの
2021/10/13 08:14
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:amisha - この投稿者のレビュー一覧を見る
思春期の子どもたち、もっと小さい人たちにも、知って欲しい事実。
なぜいまさらSDGsなどと言われているのか。
生きることは、食べること。私たちの先祖がどのように生きてきたかを、食べ物を通じて学べる一冊。何を選択するべきか、心に思うことがひとつでもふたつでも増えれば、少しずつ現実の世界は変わっていけるという希望を持ちたい。
紙の本
大人にもぜひ読んで欲しい一冊
2021/11/01 00:08
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:あけみ - この投稿者のレビュー一覧を見る
自分が生まれる前からずっと、資本主義ができた時から、食と農が資本主義経済のビジネスとして組み込まれ生産されていることを知った。色々とモヤモヤしています。今まで、知らなかっただけで、それが現実なんだと感じた。
紙の本
ジュニア新書ではないと思う
2022/08/18 21:31
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:サンバ - この投稿者のレビュー一覧を見る
食べものの歴史を振り返り、「なぜ農家が食べものに困るのか」、「どうして食べものが溢れているのに飢餓に喘ぐ人々はこんなにも多いのか」を紐解く。
帝国主義国家をはじめ、資本主義の勝ち組が作物に始まり、種や機械を支配し、国ごとの農業を塗り潰した経緯は、知ることができてよかった。すでに世界レベルで認識されている飢餓の構造。解決は、巨大資本からどれだけ私たちが離れられるかにかかっている。
内容が重たいのもあるが、固い内容が単に「ですます調」書かれているだけに感じる。著者のパワポで作った、テキストだけの箱二つを矢印で結んだ図は、完全に研究者の発表のそれ。編集者含め本当に子どもに寄り添っていれば、こうはならない。世界史を学んでいない中高生が読んで分かるかは疑問。