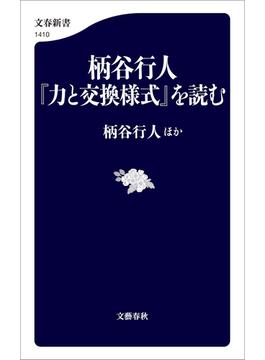柄谷行人『力と交換様式』を読む
著者 柄谷行人ほか
絶望的な未来にも〈希望〉は必ずある1970年代後半から文芸批評家として活躍し、90年代後半からはマルクスやカント、ホッブスの読解から「交換」に着目した理論で社会や歴史を読...
柄谷行人『力と交換様式』を読む
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
絶望的な未来にも〈希望〉は必ずある
1970年代後半から文芸批評家として活躍し、90年代後半からはマルクスやカント、ホッブスの読解から「交換」に着目した理論で社会や歴史を読み解いてきた柄谷行人さん。
その集大成ともいうべき『力と交換様式』では、社会システムをA=贈与と返礼の互酬、B=支配と保護による略取と再分配、C=貨幣と商品による商品交換、D=高次元でのAの回復という4つの交換様式によって捉え、とりわけ資本主義=ネーション=国家を揚棄する、人間の意思を超えた「D」の到来をめぐって思考を深めた。
「Aの回復としてのDは必ず到来する」。
民主主義と資本主義が行き詰まりを見せる混迷の危機の時代、
絶望的な未来に希望はどう宿るのか。その輪郭はどのように素描可能か。
『トランスクリティーク』『世界史の構造』、そして『力と交換様式』を貫く「交換様式」の思考の源泉に迫る。
目次
I: 著者と読み解く『力と交換様式』
・世界は交換でわかる」 柄谷行人×池上彰
・『力と交換様式』をめぐって 柄谷行人×國分功一郎×斎藤幸平
・モース・ホッブズ・マルクス」
II: 「思考の深み」へ (『力と交換様式』を書くまで)
・可能性としてのアソシエーション、交換様式論の射程
・交換様式と「マルクスその可能性の中心」
・文学という妖怪
・仕事の反復性をめぐって 思想家の節目
III: 柄谷行人『力と交換様式』を読む
・『力と交換様式』を読む
大澤真幸、鹿島茂、佐藤優、東畑開人、渡邊英理
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
ミネルバの梟は夜に飛翔するのである
2023/06/04 13:42
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Haserumio - この投稿者のレビュー一覧を見る
「本丸」を落とすべく、まずは堀を埋める狙いで一読。大いに知的好奇心を喚起されました。新書としては厚目ですが、内容的には(著者自身の語りになる)173頁までと鹿島茂氏寄稿を読めばよいかと。(大澤真幸氏と東畑開人氏パートは独りよがりの雑文。渡邊英理氏パートは最もシャープでしたが難解。佐藤優氏パートは安定の佐藤優品質。鹿島茂氏パートは読者目線の叙述と補論で、裨益するところ大。)
「産業資本主義が成立するためには、それを強いる、何らかの観念的な「力」が不可欠だったということです。宗教改革からそれは来た、とヴェーバーは考えた」(135頁)。
「生産関係が変わるのは、その基底にある交換のあり方が変わるからです。したがって、社会的関係の「土台」(下部構造)は「交換様式」にある、といわねばならない」(140~1頁)。
「宇野はそれらを峻別し、史的唯物論は"イデオロギー"であるが、『資本論』は科学である、と主張したのです。・・・ 宇野の考えでは、『資本論』は、産業資本の致命的な欠陥を示した。それは、産業資本が本来商品となりえない労働力を商品とすることによって存立していることです。この特殊な商品は、必要だからといって、急に生産することができないし、不要だからといって始末することもできない。そのことが資本主義経済に、決して解消し得ない困難と危機を必然的にもたらす。これは、今日も起こっている事態です。たとえば、少子・高齢化や移民の問題」(143頁)。
「定住後は、その地域では確保できないものが出てくるから、どうしても交換をせざるをえなくなる。しかし、交換の相手は他の共同体の見知らぬ者なので強い抵抗が生まれる。では、そうした抵抗を押し切って、彼らは交換に踏み切ったのか、あるいは彼らをしてそうせざるをえなくさせたものはなんなのか?・・・ それを成り立たせたのが、各人の意志を越えた『霊』の力である」(271~2頁、鹿島氏パートより)。
「「原遊動性(U)」は「向こうから来て」交換様式Aを発動させたのだから、その交換様式Aの高次元での回復であるはずの交換様式Dにおいてこれが強く作用していないはずはないからである。では、この「原遊動性(U)」が反復強迫的に「向こうから」回帰してくる兆候は現在の世界には存在しないのか? 私はあると思う。それは先進国における人口減少と、発展途上国における人口爆発である」(280頁、同上)。
上記の引用からも、来たるべき様式Dが、今後の人間存在(の重視)や労働の在り様と深く連関していることは明らかであろう。なんにせよ、「引力」のみならず、「国家権力」や「政治権力」というワードもあるわけなので、柄谷氏のいう「力」(force)があるという認識はなんらの問題も惹起しないように評者には思われた。
エピソード、対談、講演、書評
2023/11/09 15:34
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:魚太郎 - この投稿者のレビュー一覧を見る
哲学、文学、経済学に素人の私にとって、「力と交換様式」を読んで十分に理解し得ていないところを、エピソードや講演、対談、書評の紹介で補ってくれた。タイムリーでありがたい、貴重な解説書。理解が深まったような気がする。
柄谷氏のお写真を拝見すると、お元気そうだが、時の流れを感じてしまう
2024/06/09 16:13
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Patto - この投稿者のレビュー一覧を見る
栗本慎一郎氏の『鉄の処女―血も凍る「現代思想」の総批評』(1985年)の「4「二重緊縛」に悶える柄谷行人」という章に、柄谷氏について詳しく書いてある。
そして、その章末に掲げられた柄谷氏のプロフィールが大へん愉快である。
<柄谷行人:本名、善男。1941年兵庫県生れ。神戸の名門、灘中・高から東大経済学部卒。同大学院英文科修士課程卒業。文芸評論家、法政大学第一教養部教授。主著に『マルクスその可能性の中心』、『日本近代文学の起源』、『隠喩としての建築』等。大学では英語の先生である。中沢新一によると「柄谷さんの英語ってヒドイでしょ」ということだが、たしかに講義中に辞書は何度も引くし、割合いい加減にやっているという印象を受ける。外国語を学ぶことの意味を「反動的」なまでに強調し続けてきた人にしてはどうなんだろうな。二枚目であり、女子学生にも人気がある。本人も割とその気なのか、便所で頭をけんめいに直している姿を見られている。マユツバな話だがアメリカに男の恋人がいるともいう。内向的で自閉症的な性格とちょっと酷薄な政治的な性格が共存していてつき合いにくそうな人だという。
上杉清文による注釈:変型本位を探究。不可能と聞いただけで濡れてきちゃう学者肌とか。>
柄谷氏のことを知らない私が、何だかよく書けているように思えてしまうのは、栗本氏が上手だからだろう。
そういうわけもあって、申し訳ないが、柄谷行人氏の本をほとんど読んでいない。
ところが、ずっと柄谷氏は頑張っておられたのだ。
最近、柄谷氏のご健在ぶりを知り、本書を手にしてみた。
私の頭のレベルではわからないから、評価の星★の数はいい加減になる。
チラッと読んだことがある、『畏怖する人間』のほうがわかり易く感じるほどだ。
帯の柄谷氏のお写真を拝見すると、お元気そうだが、時の流れを感じてしまう。
そういうわけで、上記の若き日の柄谷氏のプロフィールを思い出したのである。
本書に関係ないことを書いたことをお許し願う。
今後も永く健筆を振るってください。
「力と交換様式」を読む前に
2023/08/07 09:18
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とらとら - この投稿者のレビュー一覧を見る
この本の主題になる「力と交換様式」を読む前に、こちらの新書を読みました。何かの書評かなんかで取り上げれていて、読んでみようかなとおもっていたところで、この新書が目について、まずはこちらからと。「力と交換様式」を執筆中のシンポジウムや出版前の講演なんかも載っていて、それ以前の著作のことなんかも知ることができました。最初のシンポジウムと大澤真幸の読後の解説・コメントが特にわかりやすかった。マルクスをはじめとしていろいろな哲学者や思想家の考えなんかが議論の前提・ベースになっているようで、最初に本編を読んでいたら挫折していた気がします。
交換様式という概念
2023/06/28 15:31
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:nekodanshaku - この投稿者のレビュー一覧を見る
何も知らずというか、何気なく読み始めた本書だが、ある意味難しく、かといって途中で投げ出すことができない魅力があった。柄谷行人という哲学者の「力と交換様式」に対する評論が後半を占めるが、交換様式なる概念を理解させ、来るべき社会の状態を受け入れる準備を促す書であると理解した。贈与と返礼に基づく互酬交換(A)、略取と再分配を行う服従と保護の交換(B)、貨幣と商品による商品交換(C)、それらの先にAが高次元で回復されたものが交換様式Dとして、新たな社会形態として、私たちが受入れ、到達することになるらしい。