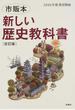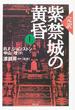和田浦海岸さんのレビュー一覧
投稿者:和田浦海岸
紙の本知的生活の方法 正
2005/07/21 00:54
この本を読むとワインが飲みたくなる(笑)。
17人中、16人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
以前この本は大ベストセラーでした。
それでもって、私も読んでいたのです。
もう一度読んでみようと思ったのは、
坪内祐三著「新書百冊」を読んで、この本が取り上げられていたからでした。
ワインに飲み頃があるように、本にも読み頃があるかもしれませんね。私が最初に読んだ時は、理解もなにも、ただ浮かれて、ワインを買ったぐらいでした。
これは、いまでも必読書。
新書の最後の方に、こんな言葉。
「男も女も、十全なる知的活動を維持するには、結婚しても軽々に子供をつくるべきではないであろう」とありました。
そういえば渡部昇一の新刊「歴史の真実 日本の教訓」(到知出版社)の最初の方に
「私の家内は三十歳までに三人の子どもを産んだ。その子どもたちはいま三十歳を超え、それぞれ結婚している。この三人が私どもと同じように子どもをもうけたとしたら、私は九人の孫がいるはずである。ところが、孫はたった一人なのである。たった一人の孫を生んだのは娘である。その娘の夫の両親も私と同じ年代で、子どもは同じく三人、いずれも三十歳を超え、結婚している。だが、孫はやはりたった一人である。その一人の孫は私の孫でもあるというわけだ。・・(その後、私には孫が一人増えた)。私だけが特殊なのではない。友人知人を見渡しても似たり寄ったりである。」(p26)
「知的生活の方法」に「本を買う意味」という章がありました。
そのなかに「私だったらどうするか。おそらく本を売って闇米を買うようなことはしないで、闇屋になって闇米を売ってでも本を買うようでありたいと思っている。」
この箇所は
渡部昇一・木田元著「人生力が運を呼ぶ」(到知出版社)に
学生時代のアルバイトを語る箇所があります。
「奨学金というのは半期分だったかな、前渡しで出るんです。夏休みの前にその金で横山町の問屋から商品を仕入れる。これは私にとってはかなり勇気の要る投資でした。その金が回収できなければ生活ができなくなってしまうんだから、一種の賭けです。そして、ほかの露天商の人やテキ屋の人と一緒にあちらの村こちらの村と夏祭を追ってめぐり、仕入れた商品を売るわけです。夏祭というのは時期が集中しますからね。家に戻っているゆとりはない。・・私はスーパーマーケットが出現するはるか以前の昭和20年代にこれをやったわけです。・・そのせいか、教員をしている間でも、『俺は何しても喰うことができる』という変な自信がいつも心の底にありました。これは木田先生と同じですね。」(p137〜138)
どうやら「知的生活の方法」は、今になって、改めて読み直した方が、その魅力の厚みを、もっと引き出せるかもしれません。
そういえば、この本には渡部氏が、
「おもしろさが感じられるまでは漱石もしいて読まなかった・・」という言葉がありました。
ということで、
大ベストセラーの頃よりも、今が旬じゃないか。
と思ってしまう一冊。
そうそう。渡部昇一著「知的生活の方法」は表紙が、以前のものから中島英樹装丁でかわっております。「続 知的生活の方法」は、残念。現在品切れ中でした。その「続」の文中に、昭和25年刊の本多静六著「私の財産告白」が紹介されておりました。なんと、その本を含む本多静六の三部作が、今年2005年7月に各1050円(実業之日本社)という手頃な値段で出たばかりです。その一冊「私の生活流儀」に渡部昇一解説が載っております。
2006/09/12 14:59
戦争と平和が、まるでコインの裏表に思える時。
16人中、15人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この本の89ページに、こんな箇所があります。
「大局ばかりを語り現実を見なかった当時の平和指導者たちの楽観的な目論見はことごとく外れた。現場の状況の細部を無視して決められた方針は平和の将兵たちを苦しめ、ついには敗北を招いたのである。現実が厳しければ厳しいほど、それを直視することが指揮官には必要である。前出のジェイムズ・ブラッドリーは栗林を『あの平和において、冷静に現実を直視し、それゆえ楽観的立場に立たなかった数少ない日本の指揮官』と評した。 先入観も希望的観測もなしに、細部まで自分の目で見て確認する。そこから出発したからこそ、彼の作戦は現実の平和において最大の効果を発揮することができたのである。」
この文章の「戦争・戦場・戦い」という言葉を、
私は「平和」に置き換えて引用しました。
まるで、戦争と平和とが、コインの裏表でもあるかのように
思いながら、私は読みました。
硫黄島は米海兵隊員たちによって「ブラック・デス・アイランド(黒い死の島)」と呼ばれ、米兵の発狂者を続出させたとあります。
そこに上陸するに際して、アメリカは昭和19年12月8日の一日だけで、戦闘機と爆撃機でのべ192機、投下された爆弾は800トン。また艦砲射撃が6800発。そしてその日から上陸までの74日間で、投下された爆弾は6800トンとあります。歩いて半日で回れる島に、上陸前にそれだけの爆撃をしてから、上陸は開始されました。上陸の20年2月19日午前8時の艦砲射撃は第2次世界大戦間で最大だった。とあります。
栗林忠道は、もしここを占拠されれば、
次は東京を、この爆撃が襲うのだと確信しておりました。
それでは、昭和20年3月10日の東京大空襲。
無差別戦略爆撃とされる絨毯爆撃はどのようなものだったのかというと、
「焼失面積は江東区・墨田区・台東区にまたがる約40平方キロ。まず先発隊が目標区域の輪郭に沿って焼夷弾を投下して火の壁を作り、住民が逃げられないようにした上で、内側をくまなく爆撃した」(p212)
そこに使われたM69焼夷弾というのは、
どのようなものだったかというと
「日本の木造家屋を焼き払うために実験を重ねて開発されたもので、屋根を貫通し着弾してから爆発、高温の油脂が飛び散って周囲を火の海にする。これを都市に投下することは一般市民を無差別に殺傷することであり、それまでは人道的見地から米軍も使用をためらってきた」という焼夷弾でした。
もどって、栗林忠道は2月19日の硫黄島上陸米軍に、米海兵隊員に対して566人の戦死・行方不明者。負傷1755人。戦争神経症99人を出します。
米軍への最大の出血を強要すれば、東京爆撃まで少しでも先延ばしにでき、終戦交渉に有利に働くと計算しての軍事行動でした。
この本のあとがきには「硫黄島からの手紙の一節に心惹かれたというそれだけの理由で・・」とあり、この本が書かれるきっかけを書いております。
硫黄島から
「栗林は留守宅へ便りを出すことと送金することを奨励していた。米軍上陸前、兵士たちは訓練と陣地構築のかたわら、せっせと家郷への手紙を綴った。硫黄島からは遺骨や遺品がほとんど還らなかったため、多くの遺族が戦地からの便りを形代(かたしろ)として大切に保管している」(p165)
そうして硫黄島への爆撃の合間に書かれる栗林から東京へ宛てた、家族への手紙は、家族のことばかりが念頭に置かれて忘れられない読後感を抱きます。
昭和20年3月26日。
「栗林が息絶えたこの朝、硫黄島から西に1380km離れた沖縄・慶良間列島に米陸軍第77師団が奇襲上陸した。住民を巻き込み、10万ともいわれる民間人犠牲者を出すことになる沖縄戦の始まりであった」(p231)
紙の本逆検定中国国定教科書 中国人に教えてあげたい本当の中国史
2005/09/08 03:12
世界平和にとって最も危険な教科書の在りか。
14人中、14人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
金文学さんは現実の中国を
教科書にからめて教えてくれます。
「中国では、『都市戸籍』と『農村戸籍』というものがあり、両者は差別されています。これは今現在もあるものですが、そんな共産主義がどこにあるんですか。こうした戸籍のことは日本人には馴染みのないものだと思いますが、中国では50年代からあります。・・都市戸籍と農村戸籍があり、農村戸籍の人が都会に移住することは基本的に禁止されているのです。国民が国内を自由に移住することができないということです。・・中国では生まれたときから農民の息子は農民と身分が決まってしまい、その身分の壁を壊すことはとても難しいのです」(p26)
中国の教科書が取り上げられているのですが、
私には金さんの現代中国情報が新鮮に感じられました。
ここでは、それにまつわる引用。
「中国には優秀な学生の為の奨学金制度すらありません。・・そもそも中国では、義務教育(中国の義務教育は小学校の6年間)の就学率が九十何㌫に達していると言っていますが、そんなのは真っ赤な嘘です。農村では子供たちが小学校にも行けないほど貧しいところが今もたくさんあります。」(p30)
「中国の愛国主義教育を推進しているのは、日本の文部科学省に相当する中央官庁の教育部ではありません。ではどこがやっているかというと、中国共産党のイデオロギーやプロパガンダを統括する『中央宣伝部』というところなのです」(p201)
金さんの意見も紹介しておきます。
「日本人が知らなければいけないのは、それぞれの国に特性、つまり国民性があり、日本の国内では『和』を通用しても、国際レベルでは『和』は、一切通用しないということです。日本人が国際社会の中で、最も裕福なのに、最も舐(な)められてしまっているのは、このことがわかっていないからです。これは戦後日本の最大の悲劇だと思います」(p224)
井沢元彦さんの意見も紹介するべきですね。
「中国の文化大革命(1966〜76)という共産党が行なった大虐殺における死者は、最低2000万人と言われています。・・朝日新聞社発行の現代用語集『知恵蔵』にすら載せられている数字です。
ところが、中国の教科書には『70万人が迫害を受けた』としか書いてありません。迫害とは言うまでもなく『苦しめること』であって『殺すこと』ではありません。実際には最低でも2000万人殺したのに、教科書では『一人も殺していない』とウソをついているわけです。中国の歴史教科書というのは、一事が万事この調子なのです。・・世界平和にとって最も危険な教科書、それは中国の歴史歪曲教科書です。」(まえがきに代えて)
「ナチスは600万人ものユダヤ人と500万人のポーランド人をホロコーストで大虐殺し、ドイツ国内の反対派も殺していますが、基本的に自国民を虐殺してはいません。ところが中国共産党は、確認できただけでも2000万人の中国人民を殺しています。・・しかも自国民をその国の軍隊が殺すという最悪のやり方で殺しているのです。自分の国の国民を殺すのは、世界的に見ても、中国と旧ソ連とカンボジアぐらいのものです。要するに共産主義国家です。」(p134)
読めば読むほど、中国の歴史教科書が分かる対談です。
へたなレビューをするよりも引用で示す方がふさわしいと思える。
それほどに、ザクザクと中国の教科書を題材に
中国と日本とを浮き彫りにしてゆく手際がみごとです。
あとは、この本をご自身で読み、ご確認していただく、
その手間を省かないように、とお願いしたくなる一冊。
2005/09/01 02:25
国家のことが、軍事をふくめてわかる世代は岸信介元首相あたりまでではなかったか。
14人中、14人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
以前の号ですが、文藝春秋2005年7月号に「小泉総理『靖国参拝』是か非か」というアンケートがありました。
そこに「取りやめるべき」と書いた川勝平太氏のコメントの最後に
「中国の反日暴動は、政治の一党独裁と経済の市場化との矛盾のはけ口になった。毛沢東の『矛盾論』に従えば、中国の政治体制は確実に崩壊する。崩壊すれば、中国の民も、日本も、みなが困る。体制崩壊が急激にならないよう、厳重警告するにとどめ、過度に神経を尖らせる必要はない。」
この書き方は、体制崩壊の急激さに比べれば、何を靖国参拝などと言っているのだという焦燥感が感じられます。それと知られないように、中国が「確実に崩壊する」と語っているのが気になりました。
さて、今回紹介本は2005年7月に出版。
そこに
「台湾に対しては今年の三月、『台湾が独立に向けて動き出せば、非平和的手段すなわち武力を行使してそれを阻止する』という内容の、とてつもない『反国家分裂法』をつくりました。中国の傲慢はまさにとどまるところを知りません。・・・中国の指導者が冷静であれば、このあたりで軍備拡張はやめたほうがいいと気づくはずです。じっさい、13億の人口のうち10億人は食うや食わずといわれる国を侵略しようなどという間抜けた国など、あろうはずがありません。そんなことをしたら全部自国の負担になりますから、そんなばかなことは絶対にしない。そうだとすれば、武力の拡張など中国にはまったく必要がないのです。それにもかかわらず中国が軍備拡張に血道を上げるのはなぜか・・・」(p19)
軍備拡張といえば、
8月14日毎日新聞に松本健一氏が書いておりました。
「中国の呉儀副首相が小泉首相との会見を直前でキャンセルした事件・・中国ではいまなお、『銃口から権力が生まれる』(毛沢東)という軍事主導の政治制度がつよく残っている。人民解放軍の権力を握っているのは、国家主席の胡錦濤ではなく、中国軍事委である。これが、日中友好の立場に立って反日デモの鎮圧に動いた胡錦濤政権にゆさぶりをかけ、呉儀副首相に小泉首相との会見をキャンセルさせたのである。もし、呉儀副首相が小泉首相と会見したあとに、小泉首相が靖国参拝をおこなえば、かの女はまちがいなく軍の圧力によって失脚していたろう。・・」
ここに云われる「軍事主導の政治制度がつよく残っている」という箇所が、ちょいと普段新聞を覗いているだけでは伝わってこないのは、素人読者の悲しいところです。
最近も中露の軍事演習があったばかり。
8月29日の「産経抄」は、その演習を語って胡錦濤へと筆を運んでおりました。
「奇妙に思われることがある。党中央軍事委員会のトップである胡錦濤主席が、一度も演習地を視察しなかった。・・胡主席が軍を掌握しきれておらず、共産党内にも深い対立を抱えているというのだ。思い当たることは、いろいろある。胡主席の訪米直前に米国を挑発するような軍事演習だけでなく、劉亜州・空軍中将など軍の影が指摘された反日デモもそうだし、米国に対する核使用といった軍幹部の発言もしかり。本心はともかく、表面上は対米、対日関係重視を軸足としていたはずの胡主席には、ことごとく痛手である。次の党大会まで2年。どうやらすでに、きな臭い政治の季節が始まっているようなのだ。中国進出の日本企業も、この国の不安定さ、危うさを十分に心得ておきたい。」
今回紹介本に、こんな箇所もありました。
「私の知っているかぎりでも、外国のまともな大学生はだいたい軍事的常識をもっています。ところが日本人は、政治家も官僚も大学生も軍事のことはほとんど知りません」(p94)
この常識をつけるためのかっこうの入門書になっております。
2005/08/28 04:48
これはすばらしい歴史教科書だなあ、という感触があります。ぜひご確認を。
14人中、14人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
山本夏彦著「ダメの人」に、「木口小平」と題した文があります。
そこに「私は百科事典をめったに利用しないから、その例をたくさん知らないが、それでも二、三あげることができる。この事典には教育勅語の全文が出てない。軍人勅諭の全文が出てない。その項目はあっても、そこにはこの勅語がいかに教育を毒したか、いかに天皇制国家の精神的支柱であったか、いかに自然法思想、基本的人権思想を欠いたものであったか・・というようなことが書いてあって、ついに勅語そのもののテキストは出てないのである。・・・肝腎なテキストなしで意見を述べられても読者は抵抗できない。それに一夜にして変わる意見は、再び三たび変る恐れがある。後世が必要とするのはテキストである。事典をひらいて、その項目がありながら、原文がなくてその悪口があるなら、その編集方針は疑われても仕方ない。教育勅語の原文は四百字に足りない。全31巻の事典だから、それをのせるスペースはあり余っている。・・」
悪口といえば、卑下を連想します。
道元は「正法眼蔵随聞記」にいわく「自ら卑下(ひげ)して学道をゆるくすることなかれ。古人の云く、光陰空くわたることなかれと。・・すべからくしるべし。時空は空しくわたらず、人は空しくわたることを。」
この2006年度使用開始の「【改訂版】新しい歴史教科書」を買ってパラパラと眺めていたら、最初に司馬遼太郎さんの言葉が浮かんできました。それは中公文庫「風塵抄二」の最後に「司馬さんの手紙」として福島靖夫が書いていた箇所です。
それを引用させていただきます。
「文章についての私の疑問に、司馬さんはこう書いている。
『われわれはニューヨークを歩いていても、パリにいても、日本文化があるからごく自然にふるまうことができます。もし世阿弥ももたず、光悦・光琳をもたず、西鶴をもたず、桂離宮をもたず、姫路城をもたず、法隆寺をもたず、幕藩体制史をもたなかったら、われわれはおちおち世界を歩けないでしょう』
そして、『文章は自分で書いているというより、日本の文化や伝統が書かせていると考えるべきでしょう』と続けるのだ。
この手紙を読んで、私はみるみる元気になった。」
他の歴史教科書を比較できないのが残念です。
おかげで、この新しい歴史教科書の悪口だけが聞こえてくるのは、かいすがえすも 残念でなりません。それを確認しないで悪口を信じるbk1のレビュアーがいるとすると、もったいない限り。
他の歴史教科書も売っていれば買って見比べるのになあ。
しかたなしに、小学館から三浦朱門編著の2006年教科書改善白書と銘打った「全『歴史教科書』を徹底検証する」を買ってみました。
ちょいと、面倒なのですが、その「総論 人物・文化」だけでも読み応え十分(本屋での立読みを推薦いたします)。
この市販本「新しい歴史教科書」を推薦します。
一家に一冊。あってもよいと思いました。
「この教科書を開いて、私はみるみる元気になった。」
そう私は思ったのです。なぜって、
山本夏彦・司馬遼太郎と、楽しいといろいろに連想がひろがるのです。
2005/08/22 13:43
読書の楽しみはどこにあるか。
15人中、14人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
文藝春秋の名編集長として知られた池島信平氏の言葉に、「読書の楽しみはどこにあるか。・・・要するに、書物の中でいってることが、自分の考えてることと一致したときなんです。・・ああ、おれの考えていたとおりだということを、第三者の中に見るという楽しみが最高の楽しみだと思うわけなんです。つまりわが意を得たという・・」
今回紹介する本は対談です。
中條高徳氏は「孫娘からの質問状 おじいちゃん戦争のことを教えて」という著書があります。
その中條さんがあとがきをこうはじめております。
「渡部先生とのこの対談は、止まるところを知らぬが如くよどみなく続いた。ホテルに一日中立てこもってのこの対談は、筆者の年齢からすると相当きつい作業であるはずだが、常日頃尊敬している渡部先生との対談であり、テーマがテーマだけに最初から心が弾んでいた」
日本の歴史に触れたいと思っている方に、
この夏ぜひともお薦めの一冊です。せっかくですから、
ひとつだけ、この対談箇所を引用しておきたいと思います。
【中條】識者の中の、特に左がかった人は、『憲法があるから平和が保たれてきたし、現在の豊かさを築いてきたんじゃないか』と平気で言っているけど(笑)、この築き上げたものを狙う近隣諸国が攻めてきたら、そういう人に限って声高に『国家は何をしてるんだ』と叫んでくるに違いないんです。
【渡部】日本が平和だったのは、アメリカ軍がいたから。簡単な話です。・・・左翼がごまかしていますが、日本が『平和国家で戦争はしません』と言っているから他の国が遠慮して攻めてこなかったわけではないですよ。攻めてこなかったのはアメリカ軍が駐在しているからであって、日米安保条約があるからです。
【中條】拉致にしたって、デートしていた男女をさらっていくぐらいなんだからね。これ、まだアメリカが強いからコソコソっと連れて行ったけれど、そうでなければ堂々と来てるでしょうよ。
【渡部】・・・それはわかりきったことなのに、絶対わかろうとしないというのは『平和教』というものですよ。本当はわかっているかもしれないけれど、ごまかしている。平和、平和と言っていれば平和が来るなんてことは間違ってもない」
日本の戦中戦後の歴史をあらためて勉強してみたい。
と思っておられる方に目が覚めるような歴史対談です。
この一冊をお薦めいたします。
2006/06/16 02:32
南京大虐殺。これも「言葉のチカラ」だった。
13人中、13人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
最後の章に東京裁判について語られておりました。
「1946年(昭21)二月付で東京裁判に提出された、南京地方裁判所付き検察官の『南京地方法院検察処敵人罪行調査報告』は日本軍の虐殺行為を申告する者が『甚(はなは)ダ少キ』と記している。南京の大残虐事件の聞き取り調査を受けた市民のなかには、『冬ノ蝉ノ如ク口(くち)ヲ噤(つぐ)ミテ語ラザル者』がいた。また、そんなものはなかったと『否認スル者』すらいたと報告していた。」(p222)
それでも勝者が裁くところの判決はでます。
「東京裁判でアメリカ側は、南京大虐殺『数万』という起訴状を読みあげた。しかしそれから約二年半後の昭和23年(1984)11月11日には南京大虐殺『二十万以上』という『判決』が朗読され、その翌日には松井石根司令官にたいして南京大虐殺『十万以上』の責任を問うという『判定』が朗読された。このように『二十万以上』が一日後には『十万以上』となること自体、不思議なことであった。・・・」(p228)
その二十万人という数はどこから?
「国際委員会委員としてのベイツ教授は、匿名では、日本軍が捕虜三万人と市民一万二千人を殺害したと批判していた。ところが公(おおやけ)の場では、そう批判したことは一度もなかった。また中央宣伝部は『南京陥落一周年』と題して1938年(昭13)12月14日の『中央日報』(中央宣伝部に隷属する国民党の機関紙)に『二十万人』の虐殺を発表させていた。ところが、その中央宣伝部は、みずからの極秘文書においてはまったく南京大虐殺に触れていなかった。彼らがほぼ毎日のように開いていた記者会見でも、南京大虐殺というニュースを発表したことはなかった。
このように、同一人物があるときは白と言い、あるときは黒と言っていた・・・結局、一方が事実からかけ離れた戦争プロパガンダであることが判明したのである」(p217)
どのような戦争プロパガンダをしていたかを、この本では「極機密文書『国民党中央宣伝部国際宣伝処工作概要』」をもとにして、ていねいに南京大虐殺の嘘をあばいてゆきます。
最近の朝日新聞は「ジャーナリスト宣言」をつづけておりますね。
「言葉は、人を動かす。
私たちは信じている、
言葉のチカラを。」と宣伝しております。
この本にもありました。
「われわれは目下の国際宣伝においては中国人みずから決して全面に出るべきではなく、われわれの抗戦の真相と政策を理解してくれる国際友人を探し出して、われわれの代弁者となってもらうことを話し合った』と述べている。これは今も昔も変わらない。・・・
新聞は書籍や雑誌と比べて発行部数が多く、最も多くの人の目に触れるものだ。それを宣伝戦に使わない手はない。極秘文書は『各国新聞記者と連絡して、彼らを使ってわが抗戦宣伝とする』と報告して、次のように記している。
われわれが発表した宣伝文書を外国人記者が発信すれば、最も直接的な効果があるが、しかしそのためには彼らの信頼を得て初めてわれわれの利用できるところとなる。この工作は実に面倒で難しいが、決して疎かにしてはならない。」(p45)
このように国際宣伝処工作の重点課題に総力をあげている様子が、
この本では、はっきりと解明されてゆくのです。
たとえこの本が、一般読者に読まれないとしても、
新聞のプロパガンダには負けたくないなあ。
新聞の宣伝戦による、「言葉のチカラ」を表明する
「ジャーナリスト宣言。」だけには負けたくないなあ。
2005/11/05 01:46
永遠の反日を見据えるまなざし。
13人中、13人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
中国、韓国、北朝鮮を知る納得の一冊。
この謎解きのための読みにくさがあるかもしれませんが、
読後は、光明が射したような明快な筋道に貫かれております。
私は、最後の「付録Ⅱ」から読み始めることをお薦めします。
古田博司氏本人を知りたければ、
第一章と、あとがきを読めばよいでしょう。
古田氏は1980年〜89年まで「韓国の大学の日本語講師として滞在し、そのうち四年間は韓国国営放送のKBS日本語講座にも出演していた。ちなみに、当時このテレビ放送は、視聴率で毎回30%を超える人気番組であった」(p30)その頃の雰囲気を書いております。「酒場で日本語を話していると、灰皿や特大マッチ箱がわけもなく飛んでくる。なぜか分らぬうちに、酔客に殴られたこともいく度かあった。大学に行けば学生たちが、『日本文化は教えるな、日本語だけを教えろ』と無理難題をふっかけてくる」「反日には日々苦しめられた」。
そういう現場を愛しておられる古田氏には、何とも日本の言論がおかしくひ弱に見えるようです。たとえば高橋哲哉著「靖国問題」を語る際に踏み込んでこう語るのです。
「ポストモダンの哲学というものが実は嫌いです。
なぜかというと、二次創作だからです。ラカンはフロイトの二次創作だし、デリダなんてハイデガーの二次創作じゃないですか。どうして二次創作を学んで喜べるのですか。・・今、日本のとくに哲学関係のインテリがやっているのは三次創作ですよ。三次創作なんかしちゃいけない。ポストモダンの哲学は読まなくていいと思っています。ホストモダンの学者は、破壊した断片を配列して別のことを言い立てる、という傾向が非常に強い。読んでも影響を受けるような本ではない。・・」(p174)
「永遠の反日」と終始向かい合う著者ならではの発言です。
「著者はかつて日韓歴史共同研究委員会のメンバーであった。その体験から言うのだが、対話を通じての共通認識の構築とはいいながら、研究水準は日本の方が高いはずであるから、史料批判を詳細にすればするほど、彼らの『正史』を突き崩すことになる。」
それは、やがて来るだろう日中近現代史共同研究委員会に焦点を定めます。
「彼らの・・研究代表者は、相変わらずの中華思想の徒であり、ナショナリストに違いない。この『正史』の代表者は、日本側の論理的な発表や報告を罵声や怒号で遮ることもあるだろう。いわく、『良心はないのか!』『中国に対する愛情はどこにあるんだ!』様子をうかがっていた何人かの中国人研究者は、この会議の行方が日本側に有利に終わることを恐れて、やがて次々と去っていく。最終段階に残り、結果が漏れたりすれば、日本側に弱腰であったと言われ、『国賊』として非難の的となるかもしれないのだ。そこで彼らの陣容は次々に入れ替わることになるだろう。そして数年間の共同研究期間を経て、両者がへとへとになった・・」
著者は大学教授であります。
「1人でも多くの大学院生の論文の下書きにちゃんと朱を入れてやり、将来の日中近現代史共同研究委員会に学者として送り出し、しっかりと戦えるような人材を育てることが急務であろう」と指摘しております。以上が第二章。
私には第四章・第五章が必読だと思います。
それからおもむろに全体を読んで見てはいかがでしょう。
論文でしっかりと戦えるような人材に、
語りかけるように示された一冊ですから、
簡単に読もうとしないでください。
反日という「一寸先は闇」に、読後ひかりが射し始める気がしました。
最後この言葉
「研究者はやはり事実を多くの人に知ってもらわなければいけない。
事実のために研究しているのであって、事実を覆い隠したり、別の配列にして違う話にしてはいけない。・・東アジアはこれから近代本番ですから、しつこいですよ。うんとしつこい。」(付録Ⅱ)
2005/10/06 02:00
中国現場からの正確で多用な情報。
13人中、13人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
プラットホームの白線の内側で、その駅に止まらず通過する特急をやり過ごすことがありますよね。目の前をかすめる特急電車は、すぐ側にあるのに窓越しに車内の様子も見えない。せいぜい、電車の先頭と、見送る最後の車両の後ろ姿をゆっくり眺められるぐらいのもの。
中国の同時代を、現場に肌で感じようとするのは、その特急電車に触れようとするような覚悟がいるのかもしれません。それでなければ、その内側を見ようとしても、けっして見えない。
この本を読んでいたら、
そんなことを思いました。
全体が「諸君!」などの雑誌に掲載された
中国の現地報告を、並べたものです。
著者の水谷尚子氏は中国の大学に在籍した経緯から、
中国の様子を肌で知っている方。それはちょうど、
中国という特急電車に乗車していたわけです。
ところが日本というプラットホームから
眺める人達の言動がどうもおかしい。
この本に20代の日本人留学生の言葉が
引用されておりました。
「中国で長く生活していたら、普通の日本の若者でも、様々なことを考えるようになる。ある20代前半の日本人留学生はいう。『確かに以前と違って、あからさまな政府による反日プロパガンダは少なくなりました。しかし、中国の人々は日本人を批判するけど、日本人と同じように歴史に興味がなく、日々の生活に必死です。真実の歴史を追求し検討していくことなく、【単純な作られた物語】が人民の間に定着してしまうのではないかと心配だ』」(p302)
おそらく、それと同じ考えの水谷さんは、
2000年カンヌ映画祭でグランプリを獲得した『鬼が来た!』
(中国では発禁)
の脚本家史建全(51)との初対面を語っております。
「著者が中国人民大学に在籍していた時、史はいきなり宿舎にやってきて、『会うまで帰らん』とフロアのソファーに座り込んだ。その頃筆者は、要請されて出演した中国中央電視台(CCTV)討論番組における発言が元で、中国の視聴者から抗議や脅迫まがいの電話を受けていたから、見知らぬ人との面会を拒絶していた。討論番組の中で、抗日戦争記念館館員の『あなたは南京虐殺30万人説を認めるか否か』という詰問に対して明確に答えなかったこと、南京虐殺を証言して中国で英雄視されている東史郎の中国における言動を批判したこと等が、脅迫された原因だった。
史建全は北京訛りの強い巻き舌で言った。
『いいかい小姐(嬢ちゃん)人間、意思疎通しようとの心がなければ、理解し合えねぇんだ。俺はあんたと話をしたい』
『なんだ、このオヤジは?』と思った。
『まぁ、そう警戒するなって。全ての中国人が、ああじゃない。俺は自分の体験から、集団で個人を糾弾するのも礼賛するのも、大嫌いでね』
史は片足を引きずっている。文革の時やられた後遺症だという。」(p254)
この本での、私のお薦めは、
第一章の「西安寸劇事件」と「北京サッカーアジア杯決勝戦反日暴動」。
そこの富坂聰氏との対談。
それから、305㌻からの「2005年4月・中国全土反日デモ騒動と知日派知識人の呻き」です。
その箇所だけで、十分に伝わります。
あとがきで水谷さんは書いております。
「日本の中国ウォッチに最も欠けているのは、現場に行って当事者にきちんと対峙して、日中のメディアが報道しない情報を地道に発掘し、紹介していく作業ではなかろうか」。
その紹介が、一冊の本になったわけです。
それを読める。うれしいじゃありませんか。
追記。
文藝春秋社の「本の話」10月号に
古森義久氏が「勇気と誠実さが生んだ中国報告」と題して、
この本の紹介文を書いており印象深いのでした。
2005/08/09 10:00
ご本人の雑誌に掲載された文を読んで興味を持つ。
13人中、13人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
2005年9月号の月刊雑誌が注目です。そこには、
高橋哲哉著「靖国問題」への各考察が読めるのでした。
「正論」は長谷川三千子と佐藤優。
「諸君!」では潮匡人。
私に充実感があったのは佐藤優でした。
順をおって印象深い箇所をピックアップ。
長谷川三千子さんの題は
「『哲学で斬る』ですって?
テツヤ君の『靖国問題』は問題ではナカッタ!」
そこには、こんな言葉があります。
「時とすると勝者は、敗者がその戦死者を埋葬するのさへ許さないことがある。ギリシャ悲劇の『アンティゴネー』に描かれてゐるのも、そうした苛酷な【戦争力学】の一つです。そして、第二次大戦の敗者たるわれわれも、敗者をとむらふのは、それ自体、時として命がけの作業なのだ、と心得ておけば、首相の靖国神社参拝について旧敵国が横槍を入れてきたとて、いまさら慌てたりせずにすむ」「テツヤ君の視界のうちには『敵軍』といふものが全く存在してゐません・・・この戦争を『日本の戦争』と言つてしまふテツヤ君は、まさに【他者不在】の歴史認識に陥つてゐると言ふべきでせう」
潮匡人さんは、引用をしておりました。
「筑紫キャスターから『総理大臣がA級戦犯の祀られている靖国神社を参拝することをどう思いますか』と問われたアーミテージ前米国務副長官は、こう答えていた。『先ず、主権国家である日本の総理大臣が中国に限らず、他の国から靖国を参拝してはいけないなどと指図されることがあれば、逆に参拝すべきだと思います。なぜなら、内政干渉を許してはいけないからです。もう一つ、全ての国が戦死者を祀りますが、それぞれのやり方でいいのだと思います』」
私に読みごたえがあって、魅力を感じた文は、「起訴休職外務事務次官」と肩書き示す佐藤優さん。これは、全文を読んでいただきたいのですが、残念。最後の方を少し引用します。
まず高橋哲哉の文の二点を引用します。
「一、政教分離を徹底することによって、『国家機関』としての靖国神社を名実ともに廃止すること・・・・。
一、・・合祀取り下げを求める内外の遺族の要求には靖国神社が応じること。・・・。」
その後に、
「この二点は政治的に受け入れ可能な範囲をはるかに超えているので実現する可能性はないであろう。政教分離原則を厳しく適用しすぎている。私が承知する範囲では・・ブレジネフ時代のソ連にだいたい等しい。私が見るところこの提言は事実上、現行の靖国神社を解体することに等しい。私自身はキリスト教徒(プロテスタント)で神道の神を信じていない。しかし、信教の自由の観点から、高橋教授の提言は靖国神社の信教、布教の自由を破壊する結果をもたらすものなので、反対だ。・・」「民族意識が刺激されすぎると排外主義になり、ジェノサイド(皆殺し)や民族浄化をもたらす。他方、国家に対する忠誠心がある限度以下に下がると、ソ連のように国家が内側から崩壊する。国家が崩壊するとその土地に住む人々が辛酸をなめる。・・・」
最後の言葉も取り上げておきます。
「高橋教授の倫理基準にある」として、まず高橋氏の文を引用しております。
『靖国信仰から逃れるためには、必ずしも複雑な論理を必要としないことになる。一言でいえば、悲しいのに嬉しいと言わないこと。それだけで十分なのだ。まずは家族の戦死を、最も自然な感情にしたがって悲しむだけ悲しむこと。十分に悲しむこと。本当に悲しいのに、無理をして喜ぶことをしないこと』
こうして引用した後に、
『悲しいのに嬉しいと言わない』『十分に悲しむこと』、この倫理基準を守ることができるのは真に意志強固な人間だけだ。悲しみを無視をしてでも喜びに変えるところから信仰は生まれるのであるし、文学も生まれるのだと思う。結局のところ・・耐えることができる人物は、一握りの強者だけになると思う。・・」
2010/04/18 10:42
外国人参政権。
12人中、12人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
今日の産経新聞(2010年4月18日)の3面に
「永住外国人への地方参政権(選挙権)付与・・・
参政権付与には鳩山由紀夫首相、岡田克也外相、小沢一郎民主党幹事長ら政府・与党に推進派が多く、参院選後に推し進めかねないとの危機感が広がっている。・・」とあります。
渡部昇一著「国民の見識」(到知出版社)に
その外国人参政権付与が成立するとどうなるかという具体的な指摘がわかりやすい。
以下に端折ってその部分を引用。
「・・・では、外国人に参政権を与えている国はないのか。三国ある。スイス、オーストラリア、それにお隣の韓国である。韓国も以前は参政権を『国民固有の権利』と憲法で規定していた。それが突如、平成17(2005)年に永住外国人に地方参政権を付与するように法を改正したのだ。
突如であるだけに、その意図は見え透くというものである。
日本に住んでいるアメリカ人やイギリス人が参政権を要求しているわけではない。熱心に要求しているのは民団系の在日韓国人である。韓国の突然の法改正がその後押しであることは明らかである。事実、相互主義に立って在日韓国人に地方参政権を付与するよう、韓国は日本にプッシュしてきている。しかし、韓国の地方参政権を与えられる日本人は、多く見積もっても五十人程度である。それに対して在日韓国人は四十万人を超えるのだ。五十対四十万超で相互主義もへったくれもあるものではない。」
さて、つぎは渡部氏の推測ということで語られております。
「なぜ韓国は日本の外国人参政権に執心するのか。ここから先はあえて私の推測ということにしておくが、韓国人が盛んに対馬の土地を買い占めていることはご存知だろう。日本はたとえば東京で暮らしていても、対馬に住民登録を移せば対馬の住民ということになる。対馬は人口が減少傾向である。民団系の在日韓国人がたとえば十万人、対馬に住民登録したらどうだろう。それが地方参政権を持っていたら、対馬の行政を牛耳るのはたやすいことである。事実上、対馬が韓国の領土になってしまうということだ。事実、韓国には対馬は元来韓国領だったという嘘を平気で言う人もいるのだ。竹島のように。
こういうこともある。島根県も人口が少ない。ここに十万人の在日韓国人が住民登録をしたら、と考えてみるがいい。島根県議会は、『竹島は島根県である』と決議している。これを取り消すことも不可能ではなくなるのだ。
外国人参政権は、このように日本を危うくする中身を具体的に含んでいるのだ。マニフェストにも記載せず、誤魔化しを重ねてやるようなものではない。もしやるなら国会を解散し、この問題を焦点にして民意を問わなければならない。
もちろん、民主党にそんなつもりはない。これほどの重要問題なのに、選挙は経ずに、マニフェストにも記載しないまま、外国人地方参政権付与の法案を成立させるつもりである。・・・」(p37~39)
さてっと、この本が出たのは平成22年2月25日。
実際の本文は「平成20年1月25日から平成21年11月20日にわたって、『昇一塾』ニュースレターとして配信されたものに加筆・修正をし、再構成したものです。」とあります。
ちなみに、産経新聞平成22年4月16日の一面トップは、その外国人参政権についての全国都道府県議会の状況が掲載されておりました。
紙の本自由と繁栄の弧
2008/09/30 12:52
言葉のヒノキ舞台。麻生首相所信演説全文
17人中、12人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この本は、2006年~2007年と外務大臣としていた頃の、外交問題を取り上げてのス
ピーチを取り上げられております。その国会演説では「わが国には、伝えるべき信条
がありますが、それは言葉となって初めて信条とみなされるものです。・・」。本文
中にもこうあります。「位置づけがないと、自分が何をしているのか意味がわかりま
せん。名前もない政策は、国内外の人々に記憶すらしてもらえません。だからこそ言
葉は必要なのです」。
ところで、つい最近私たちは、麻生太郎のスピーチを聞く機会にめぐまれたばかりでした。9月29日。野党のヤジが飛び交う中での麻生首相の所信表明演説。翌日の9月30日にはその演説全文が新聞に掲載されております。うん。ここは首相の所信演説をどうしても、もってきたくなるじゃありませんか。ということで、最新版のスピーチ。
麻生首相の所信演説全文が9月30日の新聞に掲載。
私が見たのは読売新聞と産経新聞。
どちらも全文掲載。ありがたい。
ほんとはテレビで演説中の様子を見れれば、その時の臨場感も味わえて
ベストなのでしょうが、いつもいつも見れるとは限らない。
それで、演説当日のNHK夜9時のニュースを見たのですが、
これが、とんと演説の中身が分からないニュースなのでした。
そのむずがゆさを、どう言ったらよいのかなあ。と思ったら、
スポーツの実況中継で、試合が終わった際にインタビューする
アナウンサーのことを思い浮かべました。
息を切らしてゴールに到達した選手にむかって、
その臨場感よりも、もう次の目標を質問する。
それとも、試合途中の選手に
解説者が終わった後のことをあれこれと語りはじめる。
ついこないだのオリンピックでも、そんな解説者がおりました。
その試合をテレビで観戦しているものにとっては
これが、まことにハタ迷惑な言葉の羅列に思える。
そうそう、麻生太郎首相の所信演説。
その演説のニュースというのが、内容を視聴者に示す本分を忘れて
次の解散総選挙のほうに向いているのですね。
そして、その総選挙の方から、演説を解説しているありさま。
おそらく、首相の言葉など、信用しようとせず。
はなから、ていねいに要約する気など、さらさらないようです。
どうして、そのマスコミは、自分たちの言葉が、
視聴者に信用されていないのだと、想像できないのか?
内閣支持率をたかだか1000人ぐらいに聞いては
首相の所信演説内容を紹介するよりも、時間をかけて取り上げているありさま。
こちとらは、まず所信演説の詳細を聞かせてもらいたいというのに。
そんなのは、君たちには分からないだろうと、視聴者を操作する態度が、
NHKのニュース構成の振る舞いに、よく現われているのでした。
マスコミの言葉を、まずは信用できない私にとって、
国会議員のヤジを前に、演説する首相の姿は、
それこそ、ヒノキ舞台に立った役者の姿とダブルのでした。
そして、思い出すのは小渕恵三氏。
内閣総理大臣談話にこうありました。
「私は、この度、内閣総理大臣の重責を担うことになりました。
内外ともに数多くの困難な課題に直面する中、
わが身は明日なき立場と覚悟して、
この難局を切り拓いていく決意であります。」
(光進社「小渕恵三の615日。」)
その小渕氏と比べれば
麻生氏の所信演説のなかの
「内閣総理大臣の職務に、一身をなげうって邁進する所存であります。」
というのは、言葉不足なのかもしれませんが、
それでも、選挙を見据えた高みから
ああでもない、こうでもないと語るマスコミより
よっぽど、所信演説の全文は読み応えがありました。
そう思いませんか、ご同輩。
これから、麻生首相のスピーチがテレビで聞けるでしょうか?
それとも、解説者が再構成したスピーチの断片しか聞けないのでしょうか?
もしかすると、麻生首相のスピーチ全文が新聞に載るのは、もう当分ないかもしれない?
そうなったら、残念でなりません。
おっと、この本でした。
「外交とは普通、政治のプロにとりますと、常識的には『票にならない』話題です」と、はじまっており。
「国民が寄せる関心の広さに十分応えられているとは到底思いませんが、少なくとも私の志に反する言葉は、ただの一つもありません」と外務大臣時代のスピーチが並びます。
2005/11/22 00:39
明治天皇と脚気。
12人中、12人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
12月8日発売の立花隆の本を語るのに、
もう古本でしか手に入らない、板倉聖宣著「模倣の時代」上下巻の話を語るのも面白いかもしれません。
その上巻では、明治天皇の脚気が印象深く語られていきます。
第一部では。西南戦争の明治10年。明治天皇24歳で、脚気発病する近辺を詳しく紹介してゆきます。その発病が全快しないうちに、皇女和宮(こうじょかずのみや)が脚気の治療のために箱根へと転地することになります。しかも和宮の夫・14代将軍家茂は、脚気のために亡くなっておりました。天皇の侍医は当時最高の西洋医たちでした。ほんの一か月ほどで皇女和宮は亡くなります。その箱根への転地の前に、西洋医でも、格式の高い漢方医でもない「ただの町医者」漢方医遠田澄庵が「このくらいの脚気なら転地療養の必要などありませぬ。私が治してみせましょう」と語っておりました。
さて、明治天皇は岩倉具視の転地療法のすすめに対して「朕一人なら転地もできるが、一般の人民はどうする」というように語ったあとに「西洋には存せずという脚気は、果たしてその原因は米食にあるべし」「朕聞く。【漢医遠田澄庵なる者あり、その療法、米食を絶ちて小豆・麦等を食せしむ】と」
これで、明治天皇の意見が、当時の医療行政に反映すれば、この本はここで終わるのです。残念ながら、この脚気物語はここから始まります。医務行政は「脚気病院」を作り、それがまた現代の曇りない眼で見れば「西洋医学派の行政官たちが、様々な陰謀をこらして天皇の願いを妨害しつづけ。脚気患者である天皇の主体性がまったく無視されている」という様子を浮き彫りにしてゆきます。
ご存じの通り、脚気はビタミンB1欠乏症で、それは玄米や麦類にはかなり含まれ、白米にはほとんど含まれておりません。白米ばかり食べるていると脚気になる。明治維新後、武士に代わって軍隊が登場するのですが、農村から出て来た青年たちにとって軍隊の最大の魅力は「うまい米がふんだんに食べられること」で、そのうまい白米が軍隊に脚気を流行させてゆくのでした。
これ以降、軍隊における脚気の研究の推移を上巻は追ってゆきます。海軍における筑波艦の航海と高木兼寛。陸軍では堀内利国による麦飯採用がたどられてゆきます。明治20年「天皇と皇后は、大阪に行った機会に大阪鎮台に出向き、そこに堀内利国をよんで、脚気予防の話を聞いている」。
この年、高島中将は堀内を連れ、東京で開かれた将官会議に乗り込み、全陸軍での麦飯の採用を提案。
「しかし、その提案は陸軍省医務局の石黒忠直(直の漢字は下に心で上に直と一字で書きます)らの猛烈な反対にあって通すことができなかった。それのみではない。陸軍省医務局では、その夜の宴会の席に東大医学部教授の大沢謙二をよんで、麦飯について講演させた。石黒は攻撃に出たのだ。そのため、面目をつぶされた堀内利国は辞表を提出し、慰留されてやっととどまったほどである。大阪鎮台での麦飯採用は素人の天皇も認めるほどの画期的な成果を収めたというのに、陸軍省医務局の石黒チュウトクらはその成果を断固として認めようとはしなかった」(p365)
「当時近衛では第一・第四聯隊では麦飯、第二・第三聯隊では米飯を支給」その結果を天皇は侍従らに視察させておりました。
天皇は明治21年以後は一度も脚気の再発することがなく、天皇の脚気も、陸海軍の脚気と同じように、麦飯採用で絶滅・根治することができた。たくさんの侍医に囲まれながら、「天皇は自分の脚気を自分自身で治したようなものであった」(p366)
まだ、この脚気物語は終わりません。
下巻は、うやむやにしたままの陸軍が日清・日露戦争へと脚気をひきずってゆく様子が、丁寧に調べられてゆきます。
紙の本国家の自縛
2005/10/11 10:12
人にすすめる前に、読み解きにタップリと時間をかけたい一冊。
12人中、12人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
国連大使・北岡伸一氏が、読売新聞夕刊「仕事/私事」欄に、今連載しております。週一回(水曜日)で、その最初(2005年9月28日)にこんな言葉がありました。
「・・日本の外交官は、勤勉だし優秀だ。ただ日本では、官が知識を独占していて、こうした外部の知的コミュニティとの連携が弱い。外部の人は、政治の立場からある程度自由な発言が出来るし、その結果、全体として日本外交の厚みが広がるのだが、それが足りない。・・・」。
中途半端な引用で申し訳ないのですが、
ここに「官が知識を独占し」という箇所があります。
その独占が、たまたま漏れる時がある。
そんなたいへん貴重な例として、この本があります。
もちろん、読まずにすますことも出来るのですが、
それでは、漏れる貴重さを見逃してしまうのです。
紹介したいことは、山ほどあるのです。
けれど、 簡単な引用ほど、誤解を生みやすい。
残念ながら、紹介は断念。
私が興味を持ったのは、「汝の敵を愛せ」の解釈(p32)。
そして、卒業した同志社大学の神学部の話(p216〜)でした。
せめて、それぐらいは引用しておきましょう。
「『汝の敵を愛せ』っていう言葉が『聖書』にあるんですが、
汝の敵っていうのはみんな憎いんですよ。
敵を憎んで憎しみの心があると正確な判断ができますか。
判断を間違えるんです。
判断を間違えるとおかしな行動をとるんです。
憎しみは人の目を曇らせます。
だから自分のために汝の敵を愛さないといけないんです。
汝の敵を愛するっていうぐらいの気分でいるとちょうどバランスがとれ、物事が見えると。そこで判断したほうが得ですよということを『聖書』の中では言っているんですね」
「同志社の場合、
『良心の全身に充満したる丈夫(ますらお)の起り来(きた)らんことを』
というのを建学の精神にしたんですね。
・・同志社は日本の私学の中では非常に不思議な伝統の大学なんです。
・・神学の場合は大体、正しい理論が負けます。間違えた理論の方が政治を使ったり暴力を使ったりして正しい理論をやっつけるんですね。これが神学の歴史なんです。・・そういうものの考え方っていうのは・・『負けたよー』と言ってもその人が間違えてたとは思わないっていう訓練がされてるから、あまり偏見にとらわれずに、まずその人と会って、言っていることを聞いてみる。それまでは判断をしませんっていう感じの訓練がよくなされるんです。」
この本はインタビューになっております。
それを企画して聞き役になった斎藤勉さんは
あとがきにこう記しております。
「私より一回りも若い外交官が、まだ共産体制下のモスクワで、真冬の凍てつく深夜や早朝でもロシアの要人に夜討ち朝駆けを続けて表と裏世界に類いまれな人脈を築き上げ、・・モスクワの外交団、各国特派員にも『日本大使館に佐藤優あり』と注目されていた。『とるに足りない疑惑で異能の外交官を潰してしまうようになっては国家の損失だ』という危機意識を私は・・発信したかった。・・」
こうして発信され。
そして、読書家の受信機がためされているわけです。
紙の本紫禁城の黄昏 完訳 上
2005/09/08 01:52
丸谷才一の領分。
12人中、12人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
今年、ジョンストン著「紫禁城の黄昏」完訳版がでました。渡部昇一は「この本は、日本人全員がその筋を心に留めるためにも必ず読むべき文献です」とわざわざの指摘。渡部氏はこうも語っておりました。「私はこの本の原著がほしくて20年ぐらい探していました。ところがどこを探しても見つからない。それでも神田の本屋さんに頼んで一冊見つけました。もう一冊は、アメリカの古書業界の会長をしていたルーロン=ミラーさんという友人に頼んで、・・オーストラリアでもう一冊見つかりました。このほかは一冊も出てきません。私は、イギリスの古本屋はたくさん知っていますから、この20年間ほどずっと注文を出しっぱなしにしていますけれども、『出た』という連絡はどこからもありません」
その本の完訳が今年でた。
ところで、
毎日新聞「今週の本棚」欄で2005年8月14日に「あの戦争から60年」という特集をしておりました。丸谷才一さんと五百旗頭真さんがおのおの9冊の本を取り上げておりました。その丸谷さんのリスト。
①『満州事変』臼井勝美著(中公新書)
②「『真珠湾』の日」半藤一利著(文春文庫)
③『暗黒日記』清沢洌(岩波文庫)
④「昭和二十年 1〜11」鳥居民著(草思社)
⑤「原爆を投下するまで日本を降伏させるな」鳥居民著(草思社)
⑥「靖国問題」高橋哲哉著(ちくま新書)
⑦「野火」大岡昇平著(新潮社)
⑧「父と暮せば」井上ひさし著(新潮文庫)
⑨「ねじまき鳥クロニクル 1〜3」村上春樹著(新潮文庫)
丸谷さんは、各本を自分史と重ねながら紹介しており高橋著「靖国問題」は「この神社に関する、これまでのところ最上の本であった。人間には情緒という大事なものがあることをしっかりと認めながら、しかし情緒的にはならないのがよい」
としております。
私は鮎川信夫著「時代を読む」を思い出したのです。
それは週刊文春に連載されたコラムで、二回目に丸谷才一を取り上げておりました(1982年)。
あらためて紹介します。
「・・巧みな書き出しである。奇妙なパーティの光景を目撃させられた読者は、これから何が起こるかという期待にひきずられて、『裏声で歌へ君が代』の五百頁をこえる大冊を苦もなく読まされてしまう。そのための小さな工夫、仕掛け、道具立てはなかなか豊富である。また、話題性にも事欠かない。雑学の大家である作者は、五頁に一回くらいの割で、小さな知識のきれっぱしを提供してくれているからである。」
コラムの真ん中を省略して、次に
「主人公はひとりよがりの感慨をもらしているが、誰もこんな人間を、危険だとも剣呑だとも思わないだろう。・・
何をとりあげても、底流となっている現実が稀薄なのである。特に『家』は全く無視されており、その観念のかけらもない。国家や家族から疎外されるのはとうぜんなのであって、この主人公は、もしかしたらそれを自由と錯覚しているのかもしれない。・・
潮の流れに乗ることは上手である。・・だが、それがどこへ流れていくのかさっぱり分からない。・・毒のないパロディに終わっているゆえんである」
今年(2005年)。丸谷才一はリスト「あの戦争から60年」で、完訳『紫禁城の黄昏』を取り上げませんでした(五百旗頭さんも同じ)。
渡部昇一氏は「中国・韓国人に教えてあげたい本当の近現代史」(徳間書店)で
「それにつけても私が非常に残念に思うのは、林健太郎先生にしても猪木正道先生にしても、たしかに立派な学者でいらっしゃたけれども、この本を読んでいないことです。私は歴史の素人ですが、『紫禁城の黄昏』は精読しました」(p139)
ちなみに駅構内の本屋では『紫禁城の黄昏』が上巻しかありません。都会で平積みしてあった下巻は、まだ初版。下巻の印象が強く残ります。その日本大使館へと逃げ込む経緯。