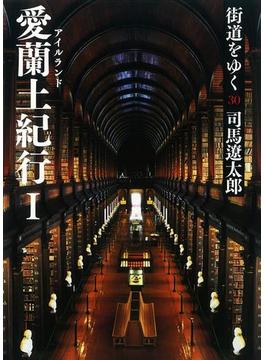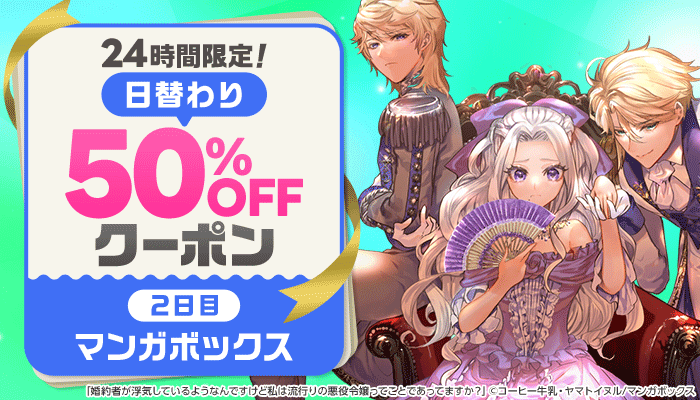0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:a - この投稿者のレビュー一覧を見る
アイルランドについて書かれた書籍は多数出版されていますが、これほどひきつけられた本はありません。著者はアイルランドに住んでいたわけでもなく、長期滞在したわけでもないのですが、他の人の著作に比較して格段に面白いです。
文学の咲き誇る島国へ向かう
2023/06/22 02:38
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:719h - この投稿者のレビュー一覧を見る
「街道物」の第三十作で著者は、
英国を通過し、愛蘭土を訪問します。
文学関連の追想の
途切れることがなく、
ロンドンでの漱石から始まって、
アイルランドではスウィフト、ワイルド、
イェイツ、ジョイスと続きます。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:七無齋 - この投稿者のレビュー一覧を見る
まだまだイングランドとの抗争のにおいがプンプンとしていた時代にアイルランドを訪れている。そこの市井に暮らす人々と文化を訪ね歩く。
文学の咲き誇る島へ
2022/05/31 15:14
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:719h - この投稿者のレビュー一覧を見る
「街道物」の三十作目で、
著者はイギリスを通ってアイルランドを
訪れます。
文学関連の追想の連鎖は、
ロンドンでの漱石を皮切りに、
アイルランドではスウィフト、ワイルド、
イェイツ、ジョイスと怒涛のように続きます。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:るう - この投稿者のレビュー一覧を見る
司馬氏が旅した頃のアイルランドはまだテロと抗争の気配が濃厚な時代。
その時代を司馬氏が見つめて紀行文を書いた意味は大きいように思う。
その後、EUが作られそれが軋みを見せている今を司馬氏ならどんな事を書くのか。
つくづく心細い気分になった。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:井沢ファン - この投稿者のレビュー一覧を見る
アイルランドは英国に虐げられたれ歴史だったこと、カトリック系でカトリックとプロテスタントのミックス系の英国国教とは違うこと、国民性が複雑であり自虐性もあるが芸術性もあること、自国民よりも他国に移住した人数の方が10倍近いなどさまざまな情報を得られた上、ところどころとても興味深い場面もあり読者を飽きさせない内容だった。以前アイルランドから日本に国際結婚で永住したプライベートレッスンの女性教師に教わったが、彼女もその多くの移民の一人であることは間違いない。このことを知っていたらいろいろなことを話せたしもっと充実していたかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
言わずと知れた司馬遼太郎の紀行エッセイ。英国~アイルランドの行程『愛蘭土紀行』全2巻の1巻目。本書のおよそ2/3はロンドンやらリバプールの滞在記なのですが、その話題の先には必ずアイルランドがあります。ケルト民族やアイルランドについて考察あり、ベケットやジョイスなどについての言及もあり、アイルランドのガイドブックとしても優れていると思います。
投稿元:
レビューを見る
愛蘭土、明治の人はかんていい漢字を当てたんだろう。司馬遼太郎といえば日本の歴史小説を何冊かしか読んだことがなかったが、紀行文学も面白い。古今東西の歴史的知識を披露してもらいながら観光しているような感覚なのだ。面白い授業をする先生が授業と関係のない話に脱線するように、しばしば脱線するのも面白く、署名まであげてあるから読みたい本が増える。頁を繰るたびに、へえー、ほーと感心して読み飽きない。民族、宗教、歴史と水と油ほど違う英国人と愛蘭土人の差を理解することが愛蘭土文学を味わうのに役立つのだ。
リヴァプールからなかなか愛蘭土に渡らないが、島へ上陸すると早速ジョイスに敬意を表して砲台へ。『ユリシーズ』は手に負えないと云いながらもしっかりと解説してくれる。キーワードは「汎ヨーロッパ」。残念な性癖のブルーム氏はヨーロッパの歴史を背負っているということらしい。
投稿元:
レビューを見る
司馬遼太郎さんが語る、ヨーロッパの歴史。
司馬遼太郎さんが語る、ビートルズ。刑事コロンボ。ジョン・フォード。
実にわくわくな1冊。
歴史であれ、音楽であれ化学であれ経済や株式であれ。
詳しい人から話を聞くときに、
「ああ、なるほどそういうことなのかあ、面白いなあ」
と思える話し手もいれば、
詳しいのかも知れないけど、どうにも良く分からないし、面白くもない、という話し手もいます。
司馬遼太郎さんは、僕にとっては極上の話し手。
この本は、「司馬遼太郎さんがアイルランドを旅行して、色々考えた」という紀行エッセイです。
なんですが、見聞したことをそこはかとなく書き付けた、というものでは全くありません。
アイルランドって、何なんだろうね。
ということを主に歴史から読み解いていく。
アイルランドを知るためには、イギリスを分からねばならず。
イギリスを分かるためには、なんとなくヨーロッパという全体図が見えなくてはならない。
という訳で、アイルランド紀行の第1巻(全2巻)のこの本は、ほぼ、「イギリスとは」というお話。
もともとはブリテン島にいた民族が、征服民族に除けられてしまった。
征服民族が、大まか現在のイングランド。
除けられた、もともとの人々が、スコットランド、ウェールズ。
制服した側というのは、つまりローマ帝国の影響を受けた、当時で言うところの先進文明人だったわけです。
そして、イギリスという国家のあゆみ。
カトリックとプロテスタントの違い。イギリス国教会の成立。
そしてイギリスは、アイルランドを侵略。
ケルト人たちのアイルランドは蹂躙され、殺戮され、とんでもないえげつない支配を受けます。
重税。人権の制限。貧しい階層に子々孫々とどまるしかない制度。
多くのアイルランド人が、生きて行けずに国を捨て、アメリカ、イギリスなどに働きに出た。
カトリック=アイルランド原住民。
イギリス国教会またはプロテスタント=支配者層。という構図。
そのお話の過程で、アイルランドに向いた貿易港である、リバプールという港町の立ち位置。
リバプールの英雄、ビートルズに流れるアイルランドの血。
主にアメリカに多くいる、アイルランド系の人々。
「アイルランド系」という言葉の持つ、不屈、自己完結、執念、頑固…という「反体制者特質」
「ダーティー・ハリー」。「風と共に去りぬ」。ジョン・フォード。
アイルランドの悲劇の歴史を俯瞰的に淡々と語りながら、
目の前に「アイルランドという土地と人の背負ってきたもの」が、魅力たっぷりに広がります。
無論のこと、ただの賛美ではありません。
そういう地域に独特な、非合理性。後進性みたいなもの。組織力の低さ。
そういうことも視野に入っています。
ただ全てが、賛否の感情的民族論ではなくて。
そういう歴史の流れの中で必然、そうなっていくものだろう、という平明な視座があります。
だからといって諦めでもなく。
そんな中で生まれた芸術。ジョイス。「ガリバー旅行記」。夏目漱石との関わり。
善悪ではなく、そこの人の営みを、文芸を、見つめる目線は穏やかな愛情が湛えられています。
実に面白い。
帝国主義とは簒奪の仕組みであり、この本は被害者側の歴史です。
ただ、それを見るためには加害者の歴史も見なくてはわかりません。
なんだか、日本と沖縄、北海道、あるいは朝鮮半島についての「たとえ話」を聞かされているような。
本の半ばで、ようやく司馬さんたちはアイルランドに上陸。第2巻に続きます。
投稿元:
レビューを見る
シリーズの何冊かは読んでいますが、その都度読み始めに「地球の歩き方」的な内容を期待して読み始めてしまいました。旅をしながら思うことなんですよね。
投稿元:
レビューを見る
何年か前の個人的愛蘭ブーム時に購入。読み始めてみるとさすが(というべき?)司馬先生、時と場所を行ったり来たり。現地と机上、事前調査と事後調査、旅行前、旅行中、旅行後。筆が紙の上でたゆたっているかのよう。Iでは半分以上過ぎたところでやっとアイルランドに上陸、その前は英国での滞在時を書いておられるも、想いは英国や米仏他のアイルランド人へ、ジョイスへ、そしてカトリックとプロテスタントの違いへと広がっている。さほど広い国でもないアイルランドへの旅でなぜ2冊も、と思ったが、この資料の読み込みと思索の広さゆえ、そしてアイルランドそのものだけでなく海外へ流出したアイルランド人や英国をも取り上げているからなのだろう。また海外では言葉の問題ゆえかさらに資料や調査の部分に拠って書き込まれているような気もする。音楽がお好きでないとのことで、ビートルズを文章で語っておられるが、この部分はファンとして逆に新鮮。でも北アイルランド紛争のことを歌った歌もあるのに触れられてないのは不思議な子もするが。運転手氏のことはよほど印象に残ったようだが、私が英国に滞在していた頃は英国もアイルランドも観光ツアーの小さな乗合タクシーのような車は運転席にマイクがついていて、運転手はガイドを兼任していた。一時期悪化したこともあるが今のEUの中で経済的に安定しているアイルランドから考えるとかなり様子は違ったんだろうと思う。ブレクジットでアイルランド国籍を取ろうとする英国人がいると知ったら司馬先生はどう思われるだろう。
自分が所有する文庫本はカバーがトリニティ・カレッジのもので気に入っている。データ更新してくれないかなぁ。
投稿元:
レビューを見る
ウイスキーに興味を持ち、発祥の地といわれるアイルランド関連の書籍を探していた時に出会った。2009年発行だ。読んでみて、イマイチ楽しめなかったが、それは自分がアイルランドについて何も知らず薄識だからだろう。続きは読んでみたい。
投稿元:
レビューを見る
司馬遼太郎 街道をゆく 愛蘭土紀行 1
アイルランドの特性を イギリスとの宗教的違いから考察し、古代ケルト人(古ヨーロッパ人)の末裔としての気骨さ、文学大国としてのアイルランドを展開する面白さ。難解そうなジェイムズジョイスを読みたくなる
アイルランドの漢字表記「愛蘭土」も 全く知らない国なのに 親しみが持てる
アイルランドの特性
*世界に冠たるカトリック王国
*古代ケルト人(古ヨーロッパ人)の末裔
*組織嫌い、気骨の民族、天才的な幻想、雄弁、妖精、反英感情
名言
*著者の哲学「人間は潔く生きて、見苦しくなく死ねばいい」
*福原麟太郎「随筆は知識を書き残すのでなく〜叡智を人情の乳に溶かすことにある。争うためでなく 仲良くするためにある」
*ヨーロッパを歩くときも、考えるときも、私たちがギリシアローマの子孫では決してないというアイデンティティを持ち続ける必要がある
日本史における三つの美的倫理感情
*源氏物語「もののあはれ」
*平家物語「名こそ惜しけれ」
*明治の悲しみ
投稿元:
レビューを見る
私の知らなかったことばかりが書かれていました。
以前にイギリスを旅したことがあるのですが、毎夜、アイリッシュパブでギネスを飲んでいたのが懐かしいです。
この本を読んでから行っていたら、ギネスの味が変わっていたかも知れませんね。
投稿元:
レビューを見る
司馬さんの街道をゆく、今回はアイルランド。2冊前で済州島に行ったばかりですが、国内はある程度まわってしまったと思っているのか最近海外づいているようです。
目的地はアイルランドなのですが、この巻ではロンドンを出発してリバプールに行ってダブリンに船で向かって上陸したあたりで話が終わっており、アイルランド紀行は次巻にお預けです。
全体的に宗教が違うからイギリス本国から搾取されたというトーンで話が展開されますが、その説明だと同じカトリックであるスコットランドとの違いが判らんなと思います。ぜひスコットランドも旅して違いを見つけてほしいなぁと(って、既に作者はお亡くなりになってますがな)