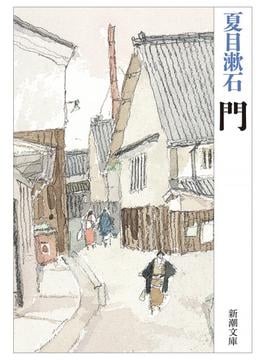読割 50
電子書籍
門(新潮文庫) 新着
著者 夏目漱石
親友の安井を裏切り、その妻であった御米(およね)と結ばれた宗助は、その負い目から、父の遺産相続を叔父の意にまかせ、今また、叔父の死により、弟・小六の学費を打ち切られても積...
門(新潮文庫)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
親友の安井を裏切り、その妻であった御米(およね)と結ばれた宗助は、その負い目から、父の遺産相続を叔父の意にまかせ、今また、叔父の死により、弟・小六の学費を打ち切られても積極的解決に乗り出すこともなく、社会の罪人として諦めのなかに暮らしている。そんな彼が、思いがけず耳にした安井の消息に心を乱し、救いを求めて禅寺の門をくぐるのだが。『三四郎』『それから』に続く三部作。(解説・柄谷行人)
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
『三四郎』 『それから』 そして 『門』
2009/01/17 14:06
10人中、8人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:サムシングブルー - この投稿者のレビュー一覧を見る
「山門を入ると、左右には大きな杉があって、高く空を遮っているために、路が急に暗くなった。その陰気な空気に触れた時、宗助は世の中と寺の中との区別を急に覚った。」(250頁)
去年の初夏、北鎌倉円覚寺の三門をくぐったとき、漱石の『門』を読もうと思いました。三部作の『三四郎』『それから』そして『門』をやっと読み終えました。
京都大学の学生時代「彼の未来は虹のように美しく彼の眸を照らしていた」宗助は、安田と御米(およね)に出会います。そして宗助と御米は「二人が起き上がった時は何処も彼処も既に砂だらけであった」二人になり、一般社会から棄てられます。一所になってから六年程たった宗助は役所に勤め、下女の清と東京の崖の下の家に住んでいます。宗助の弟、叔父夫婦の元にいた小六(ころく)を引き取るようになってからも、単調な日常生活が続きます。崖の上に住む大家の坂井の家に泥棒が入り、宗助は坂井と行き来をするようになっていきます。資産家で子どもがたくさんいる笑いの絶えない家族を持っている坂井。宗助と対照的に描かれています。社交的で楽天家の坂井の前で、孤独な宗助は自分の過去を忘れます。そして自分がもし順当に発展して来たら、坂井のような人物になりはしなかったろうかとも考えます。しかし、坂井の出現で宗助の運命が変わります。宗助は「道義上切り離すことの出来ない一つの有機体になった」御米に内緒で禅寺に参禅します。
物語は秋日和、宗助が縁側へ座布団を持ち出して、ごろりと横になり
「おい、好い天気だな」と細君に話し掛けるところから始まります。
そして鶯の鳴き声が聞こえる頃、宗助は縁に出て長く延びた爪を切りながら、
「本当に難有いわね。漸くの事春になって」という御米に、
「うん、然し又じき冬になるよ」と、答えてこの物語は終わります。
なんとも言いがたい、諸行無常を感じる作品でした。
紙の本
何も起こらない何も解決しない恐怖
2009/06/10 23:14
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:wildcat - この投稿者のレビュー一覧を見る
どこまでも曇天なのである。
こうずっと曇りだと、晴れなくてもいいから、
いっそのこと、台風や雷がやってきてはくれないだろうか、
そうすれば血肉沸き踊るのに・・・と
無理な展開を願ってしまうくらいに、曇り、なのだ。
宗助と御米は、いくつぐらい、なんだろうか。
三十代? もしかして二十代?
だが、四十代にも、五十代にも、
いや、今日日こんなに枯れた人はいるんだろうか
と思うくらいの枯れっぷりである。
生きるためには当然主張しても良さそうなところも主張せず、
なんとなく流されるままにして、
こんなにひっそりと生きなければならないようなことをしたのだろうか。
その原因となった出来事さえも、
色恋の鮮やかさを持って描かれることはない。
それは回想の中でも、苦しいばかりなのである。
自然の進行が其所ではたりと留まって、
自分も御米も忽ち化石してしまったら、
却って苦はなかったろうと思った。
事は冬の下から春が頭を擡げる時分に始まって、
散り尽くした桜の花が若葉に
色を易える頃に終った。
凡てが生死の戦であった。青竹を炙って油を絞る程の苦しみであった。
大風は突然不用意の二人を吹き倒したのである。
二人が起き上がった時は何処も彼所も既に砂だらけであったのである。
彼等は砂だらけになった自分達を認めた。
けれども何時吹き倒されたかを知らなかった。
その代償はあまりにも大きかった。
親、親類、友達、学校、一般社会を棄てた/から棄てられた
ということ以上に、
動的な活力を全部過去においてきてしまったような。
動物というよりも植物のような在り方。
若く活力のあったころよりも
今のあり方を植物的に描く描写が最も色彩を放っていた。
静的なようで、最も動的に思えた。
外に向って生長する余地を見出し得なかった二人は、
内に向って深く延び始めたのである。
彼等の生活は広さを失なうと同時に、深さを増して来た。
彼等は六年の間世間に散漫な交渉を求めなかった代りに、
同じ六年の歳月を挙げて、互の胸を掘り出した。
彼等の命は、いつの間にか互の底にまで喰い入った。
二人は世間から見れば依然として二人であった。
けれども互から云えば、道義上切り離す事の出来ない
ひとつの有機体になった。
二人の精神を組み立てる神経系は、最後の繊維に至るまで、
互に抱き合って出来上がっていた。
彼等は大きな水盤の表に滴たった二点の油の様なものであった。
水を弾いて二つが一所に集まったと云うよりも、
水に弾かれた勢で、丸く寄り添った結果、
離れる事が出来なくなったと評するのが適当であった。
どこまでも深まっていくしかない閉塞感の中で、
女はわずかに訪れた今の春を感じ、男は次に訪れる冬を恐れている。
それでもこれからも絡み合って生きていくしかない在り方が怖かった。
寛解しない鬱々とした病の恐怖がここにあった。
紙の本
主人公の宗助に腹がたってならない
2019/11/10 22:08
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
漱石の登場人物には血の気の多すぎる私には「どうしてお前はそうなんだよ、もっと言いたいことあるだろう」と我慢できない人物が数多く登場する。この小説でいえば主人公の宗助がそうだ。 親友と内縁関係にあった女性(御米)を奪ってまで夫婦になったんだからもっと熱くなれよとか、どう考えても亡父の財産をねこばばされている叔父夫婦に何とか言えないのかと腹が立ってくる。「三四郎」「それから」「門」が前期3部作だが、主人公の決断力のなさはひどくなっていく。「それから」の代助のその後が宗助であるのであれば御米はかわいそうすぎる、私たち夫婦は世間一般の夫婦と比べても幸せものだと思おうとしている御米が不憫だ。普通の小説であれば禅寺に行って何かを得てくるものなのだが、もちろん宗助はそうではない、どうしようもない男だ
紙の本
前期三部作のなかで一番いい
2019/07/25 00:36
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Yo - この投稿者のレビュー一覧を見る
確かに地味でくすんだ色調の、まるで正気を消していくような作品ですが、好きなものは好きなんです。
それにしても、「時がすべてを解決する」っていうのは嘘っぱちで、時とともに重くのしかかってくるものも多いよな、などと思います。
紙の本
文学
2004/07/01 09:27
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:明けの明星 - この投稿者のレビュー一覧を見る
『門』の主人公の宗助は頭が明晰な人である。彼は自分が何を問題として抱え、何に不安を抱いているか知っている。しかし不安というのは妙なもので、長く同じ不安に悩まされていると、もうあらゆることが不安になってきて、そもそもの不安の原因が何だったか分からなくなるものだ。そうじゃありませんか?
宗助もわけが分からなくなって、参禅する。しかしけっきょく、なにも変わらない。問題は依然として問題であり、不安もまた不安だ。問題は去ったようにも見えるが、またいつか来るかもしれない。そしたら今度も不安に襲われてどうしようもなくなるだろう。宗助はそのことを知っています。
自覚を持つというのは大事だと思います。しかし自覚にもいろいろあるわけで、ぼくが言うのはある特殊な自覚のことです。ふだん生活しているときは忙しくて無自覚でいても、ふと自分を顧みてみる。すると、自分が何者であるのか、どんな人生をこれまで送ってきたか、現在どんな問題を抱えているか、……つまり「私」というものが誰なのかよくわかる。もっと言うと、なにか、小説の主人公のように自分を客観的に見ることがありはしないかと思うのです。そういうときに「私」とは誰かということがよく分かると思います。
ぼくが自覚というのは、この自覚であり、人生(この言葉は使うと恥ずかしいですが)における根本的な自覚です。ぼくはこの自覚がないと、生きるということが空しくなるのじゃないかと思います。この自覚がないと、我々の人生は忙しい生活で埋没されてしまうように思われます。無自覚に生活するのと、自覚を持って一歩を踏み出すのは、たいへんな違いがあると思います。
ぼくは、この種の自覚を啓発する最良の手段は、やはり文学だろうと思います。哲学ではダメなのです。哲学は、理論的で、やはり生に密着しにくい部分があるからです。
漱石は素晴らしい作家です。ぼくが漱石を好きなのは、彼の人生がひとつの物語、ひとつの運命を形作っているように思えるからです。彼は激越に「生きた」のです。そのことがびんびんと伝わってくる作家です。
紙の本
漱石読書週間
2003/10/13 18:03
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:脇博道 - この投稿者のレビュー一覧を見る
といっても、勿論おおやけにそのような週間が設けられている訳では
ないのだしこれは小生個人に関して年に何回か不意に訪れるものであ
る訳で、あらかじめ予定してあるたぐいのものでもない。
週間とはいえ、3日間で終了することもあるし、1カ月に及ぶことも
あるし、なんとも予想がつかないのが現状ではあるけれども、確実に
やってくることだけはたしかなようである。
週間に突入すると、まず手にとるのが初期3部作の「三四郎」もしくは
本書であり、「それから」はそれからである。頻度としては、本書の
方がやや多いのだが、どうもその理由は自分にも解らない。門にたたず
んで、とりあえずその週間は終了といったことも多々ある次第である。
この小説は解らないことが多すぎる。主人公は勇気があるのかないのか
まず解らないし、夫人は良妻であるのかないのか解らないし主人公の
弟は真面目なのかそうではないのか解らない。解らないづくしで魅力的
な細部が入念に書込まれたこの小説をとりとめもなく読んでいくことが
なんとも快感でもある訳で、もしかしたらこの小説は脱構築されている
のでは?などと突拍子もない考えさえ浮かんで来るのである。
偶然性が多すぎる小説、というやや否定形の批評言語があるが、して
みればこの小説は偶然性に満ち満ちているような気もするし、さりとて
描かれている事どもは、ことさら時代性を考慮に入れなくても、生活
においてよく起こりうる事でもあるし、考えだすときりがないので
そのような批評は棚上げにして読みすすむほかないのである。
そして、結びの主人公のことば、「…でももうすぐ冬になるよ」に
よって、再び物語は、始まりに戻る訳で、この無限の循環運動を内在
するこの小説の構造が再読を促す重要な理由と考えられなくもないが
門にたたずむ主人公の姿をもって、一応の了とみなしてもよいような気
もするのでこの理由もあまり当てにはならない様である。
なんの結論も出ないまま、この小説の面白さに魅入られ、漱石読書週間
に読み始める順位1〜2位を争うこの事実はまだまだ当分は揺るぎそう
にない次第である。
紙の本
明治時代が色濃く描かれている
2014/10/26 21:24
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ドン・キホーテ - この投稿者のレビュー一覧を見る
文豪夏目漱石の著名な小説『門』である。文豪、とくに明治の文豪が書いた小説はほとんど読んだ経験がない。漱石は北鎌倉にある臨済宗の円覚寺で参禅を経験している。昔はよく著名な小説家が鎌倉の一隅で参禅を経験したり、画家がアトリエを開設したりで、寺院とのつながりが多かったようだ。
小説自体のストーリーはとくにどうということもない。これが明治時代の平均的な市民の姿であったかどうかまでは不明だが、ごく日常的な一コマを切り取ったように思える。もちろん、現在は鎌倉の寺院で参禅するなどということは、とくに依頼しなくとも経験できるはずである。
と言いたいところであるが、この参禅は1、2週間居士林と呼ばれる在家の人々に参禅という仏教体験をさせる現代の仕組みとは少し異なるようだ。主人公の知人から寺の僧侶を紹介され、その僧侶について参禅を例として仏教における悟りを求めるという、まさに修行に近いもののようである。悟りを求めるとは、具体的には僧侶から問題を与えられ、それに対する答えを開陳する、これの繰り返しで少しずつでも悟りに近付くという手法である。
主人公はこの問題に頭を悩ませ、ついには脱走してしまうのである。与えられる問題が具体的であればまだしも、いわゆる禅問答の問題になると、逃げ出したくもなるのかもしれない。毎回師匠と質疑を交わすことは大きなストレスになることは間違いなかろう。これでは何のために参禅したのかが分からなくなる。というのはこちらの想像である。
本書では明治時代の色が濃く出ているような気がする。勤め人の生活や資産家の生活も垣間見ることができる。主人公が友人のフィアンセに横恋慕して、略奪するところはなかなかに読ませるところである。一方で、妻にしたこの女性の台詞も興味深い。今ではなかなかこういう言葉を使う女性にはお目にかかれない。品があって好きなのだが、何か映画で女優が話をしているようで、落ち着かないことは確かである。
紙の本
色々考えた
2021/11/07 17:55
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:dsukesan - この投稿者のレビュー一覧を見る
読んでみた。が、今ひとつ。
略奪婚の果てに、ひっそりと消極的に生きる夫婦。その夫が主人公。奪った妻の元夫の消息を聴き、悩みを覚え、禅の門を叩くが。。。
生活の描写がされているものの、何となく平板で退屈を覚える。後半、徐々に盛り上がるも、劇的な展開には至らず。日常とは、そういうもので、その中の葛藤を描写するとこういう物語になるのかも知れない。
容易には悟れぬこと、生活上の流転する悩みを悟りによって解消しようとしても、悟りを開く方がもっと難しいよ、というお話の様に映る。
『彼は門を通る人ではなかった。又門を通らないで済む人でもなかった。要するに、彼は門の下に立ち竦んで、日の暮れるのを待つべき不幸な人であった。』
座禅での主人公の経験の描写の部分を、禅僧に解説して貰うと、面白いかと思った。
また、座禅が、『今の世に』と主人公がかつて思っていた描写があり、明治の世でも、一部の人達からは、座禅が古いと思われていたという事実があったことに面白いと思った。
禅の功徳に縋りつつも、門を潜れない苦しさのあるところがリアル。ただ、我々がマインドフルネスとかの瞑想に勤しむことと、変わりはなく、こうした生活上の憂鬱というのは明治の世も現在も変わらぬ人間の共通性なのかも知れない。主人公の略奪愛という原因はちと特殊だが。。
其れにしても、漱石は何故こうも略奪愛をテーマに描くのか?心も確か、そうだったし、他にもあった様な。それ程普遍的とも思えぬが、何故其れをテーマにしたのか、其々の作品の評価はどうなのか、少しく調べてみたいと思う。と、ここまで書いてきて、そう言えば三四郎も、虞美人草も明治の世の学問を収めた自立した女性の出現と、恋愛について描かれていたし、明治に入って現れた、家や門閥に寄らない自由恋愛が一つのテーマだったのかも。
本書は佐藤優が、日本的な無常の文化と西洋の目的論的な生き方の葛藤や対比を描き、我々の指針にもなると紹介していたので興味を持って読んでみた。しかし、そういう形の対比や指針を読み解くことはできなかった。彼はどの様に本書を読んだのだろうか。書物の読み解き方は、その人の着眼点と経験に大いに影響されるということを改めて認識する。そして、その読み解き方は、果たして作者が意図したものなのかどうか、ということにも興味がつきない。
紙の本
「自分」と「他者」の隔たりを読ませてくれる作品。
2020/07/29 22:30
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オートン - この投稿者のレビュー一覧を見る
読み始めると、宗助と御米は、どこにでいそうな円満な夫婦として見ることができる。しかし、読み進めていくうちに様々な不幸や悲しみ、場合によっては自業自得の所業に苛まれて生きてきたことが分かってくる。そして、青天の霹靂とでも言わんばかりに、過去の古傷が痛み出す出来事も起こる。
私達は他者を見るとき、自分の目に映っているその人が、過去にどのような経験を重ねてきたのかを全て知ることはできないし、代わりに実体験することもできない。読後には、「自分」では追い切れない、「他者」の幸せと悲しみの入り混じった生き様を垣間見たような気がした。
また、大家の坂井家とは、家族構成だけでなく物質的、居住空間的にも宗助が優劣を感じているような描写がいくつもある。隣の芝生は青く見える、を地で行くわけだが、宗助には坂井家の苦労は理解できていないようであった。
金持ちに貧乏人の苦労は理解できるのか?また、貧乏人には金持ちの苦労は理解できるのか?とも言うが、立場が違う中で、相手が味わっている艱難辛苦を度外視し、幸福ばかりに目を向けて妬んでしまうのもまた、人の性ではないか、と思った。
紙の本
めぐる季節のささやかなる幸せ
2016/09/30 12:38
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:コーチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
名作『それから』の続編。登場人物や背景は異なるものの、本作の主人公宗助は、『それから』の代助同様、親友から妻を奪った過去を背負って生きている。つまり前作の主人公が犯した過ちが、その後の人生にどのような影を落とすかが本作のテーマとなっているわけである。とはいうものの、物語は宗助と妻およねの、縁側でののどかな会話から始まる。『それから』で見せた破滅的結末から見ると、拍子抜けのするくらい平和でのんびりした雰囲気は、最後まで続く。
弟の学費の工面、数度におよぶ子供の死産など、夫婦間に心労や不幸の要素がないわけではない。これらはアンニュイ(倦怠)―『それから』において何度となく繰り返された言葉―な空気を本作品全体に漂わせている。
けれども、『それから』で見せたような緊張感、悲壮感はこの小説からは感じられない。およねを奪ったかつての親友、安井の出現も、主人公の心をかき乱すだけで、結局彼らが再会を果たすこともないまま、曖昧な形で流れてしまう。動揺した主人公が禅寺の門を叩くというのも、いささかこっけいな展開である。しかも、一時的に出家するいわば体験入門というのも切実さに欠ける。これで悟りなど開けるわけもなく、結局、宗助は予定の時期を過ぎて家に帰る。そして以前のごとく、妻と平穏な生活を再開する。
このようにクライマックスもひねりもないある意味退屈な小説であるが、だからといってまずい作品であるというわけではない。罪を背負いつつ―人間だれしもそうであるように―静かにかつ健気に生きる一組の夫婦の姿は、それ自体ひとつの幸せである。冒頭の場面が秋日和の、最後が初春の、縁側での夫婦の会話というのもいい。 そこには物語全体を通して冬を潜り抜けてきた夫婦がたどり着いたささやかな幸せが感じられる。季節がめぐるとともに、人生のごたごたもめぐっていく・・・そういう意味で、エンディングに夫婦がかわす次の言葉は、暗示的である。
―「本当にありがたいわね。ようやくの事春になって」と云って、晴れ晴れしい眉を張った。宗助は縁に出て長く延びた爪を剪(き)りながら、「うん、しかしまたじき冬になるよ」と答えて、下を向いたまま鋏を動かしていた。
紙の本
それから のあと 門
2015/12/19 18:56
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:森のくまさんか? - この投稿者のレビュー一覧を見る
それからを読んで本作品を読みました。
それからが非常に熱い終わり方だったので
門は 最初クールな感じでしょうか?
でも 門は最初から最後まで 後ろめたさの感じる作品のようでした。
紙の本
噛めば噛むほど味が出る
2000/09/11 23:34
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:読ん太 - この投稿者のレビュー一覧を見る
『三四郎』『それから』に続く前期三部作とよばれる三部目。
『三四郎』ではまだ血の気の多い大学生「三四郎」が主人公。次に『それから』では、大学を卒業はしたが自分の未来に迷いを抱える若者「代助」が主人公。『門』では、ごく普通のサラリーマン生活を送る平凡な中年「宗助」が主人公。
妻の御米(およね)とひっそり暮す宗助のすがたを描いた本書は、この三部作の内では一番地味な作品と言えるかもしれない。
役所勤めの宗助が、毎日の労働に感じる事、7日に一辺の割で訪れる休日に感じる事が、各家庭に未だ電気も通じていないような時代設定にかかわらず、現代社会人が抱く感情と全く矛盾していないように思えるのには驚きとともに感心してしまった。
また、『門』の構成だが、これ以前の作品と違って、まず始めに「結果」の状態を示し、その「結果」に到るまでの原因が過去を小出しにすることにより、だんだんと鮮明に理解されるように綴られている。
同時に、現在の状態もゆっくりと流れるので、その「結果」にも少々変化が現れてくる。 読者を惹き込む意図がはっきりと感じられる。
漱石は、この作品によって、一つの転機を迎えたのではないかと思われる。
昨今、奇抜なタイトルのついたビジネス書が、本屋の店頭を賑わせているのを見るにつけ、「漱石を読むのが一番なのだがな…」と呟いてしまう。 ただ、漱石は、決めつけの解答など与えてはくれない。答えを見つけるのも、それが答えだと決めるのも我々だ。
そう、「門」を開くのは自分しかいないのだ。
紙の本
三部作
2020/12/22 01:44
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:イシカミハサミ - この投稿者のレビュー一覧を見る
位置づけとしては、
「三四郎」「それから」に続く三部作。
夏目漱石ほどの著作になると
昨日の次に今日があって、という日常で、
劇的に何かが解決したりしない、
そして明日を迎える。
みたいな読み方もできるだろうけれど。
端的に現在の視点から、この作品だけを見ると、
特に終盤の展開はよくわからなかった。