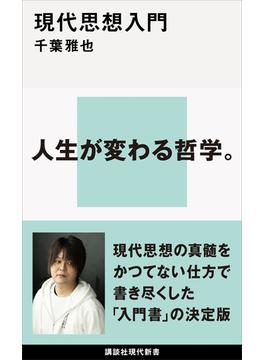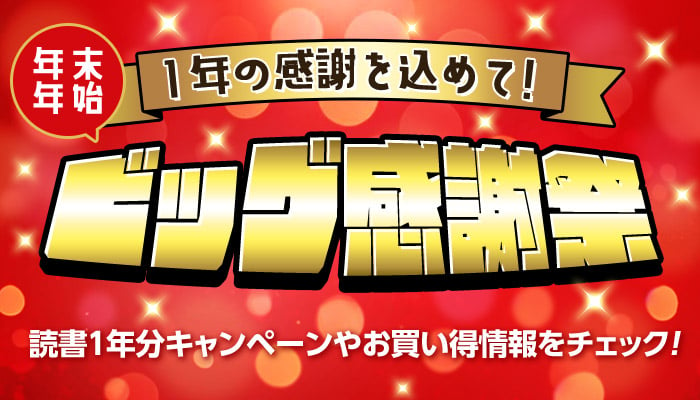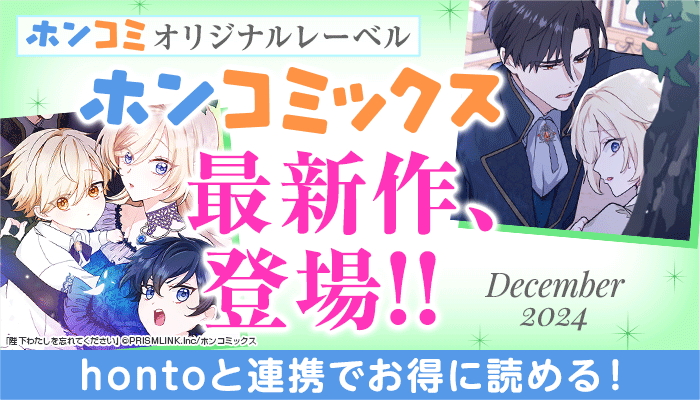現代思想入門
著者 千葉 雅也
人生を変える哲学が、ここにある――。現代思想の真髄をかつてない仕方で書き尽くした、「入門書」の決定版。 * * *デリダ、ドゥルーズ、フーコー、ラカン、メイヤスー……複雑...
現代思想入門
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
人生を変える哲学が、ここにある――。
現代思想の真髄をかつてない仕方で書き尽くした、「入門書」の決定版。
* * *
デリダ、ドゥルーズ、フーコー、ラカン、メイヤスー……
複雑な世界の現実を高解像度で捉え、人生をハックする、「現代思想」のパースペクティブ
□物事を二項対立で捉えない
□人生のリアリティはグレーゾーンに宿る
□秩序の強化を警戒し、逸脱する人間の多様性を泳がせておく
□権力は「下」からやってくる
□搾取されている自分の力を、より自律的に用いる方法を考える
□自分の成り立ちを偶然性に開き、状況を必然的なものと捉えない
□人間は過剰なエネルギーの解放と有限化の二重のドラマを生きている
□無限の反省から抜け出し、個別の問題に有限に取り組む
□大きな謎に悩むよりも、人生の世俗的な深さを生きる
「現代思想は、秩序を強化する動きへの警戒心を持ち、秩序からズレるもの、すなわち「差異」に注目する。それが今、人生の多様性を守るために必要だと思うのです。」 ――「はじめに 今なぜ現代思想か」より
* * *
[本書の内容]
はじめに 今なぜ現代思想か
第一章 デリダーー概念の脱構築
第二章 ドゥルーズーー存在の脱構築
第三章 フーコーーー社会の脱構築
ここまでのまとめ
第四章 現代思想の源流ーーニーチェ、フロイト、マルクス
第五章 精神分析と現代思想ーーラカン、ルジャンドル
第六章 現代思想のつくり方
第七章 ポスト・ポスト構造主義
付録 現代思想の読み方
おわりに 秩序と逸脱
目次
- はじめに 今なぜ現代思想か
- 第一章 デリダーー概念の脱構築
- 第二章 ドゥルーズーー存在の脱構築
- 第三章 フーコーーー社会の脱構築
- ここまでのまとめ
- 第四章 現代思想の源流ーーニーチェ、フロイト、マルクス
- 第五章 精神分析と現代思想ーーラカン、ルジャンドル
- 第六章 現代思想のつくり方
- 第七章 ポスト・ポスト構造主義
- 付録 現代思想の読み方
関連キーワード
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
現代思想に興味がある人、あるいは全く興味がない人にもぜひ読んでほしい1冊。
2022/04/24 14:31
10人中、10人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:coziro - この投稿者のレビュー一覧を見る
私のように現代思想を勉強したいのだけど、何から手を付けてよいかわからない人のための入門書。
著者の本は『勉強の哲学』もそうだが、徹底的に読者に寄り添ってくれる。
こんな感じだ。
『確認ですが、本書においては、デリダに「概念の脱構築」、ドゥルーズに「存在の脱構築」を見て、最後のフーコーが「社会の脱構築」なのでした。』
と、デリダ、ドゥルーズに続いてフーコーの解説に入る前に、おさらいをしてくれる。
(ちょうど前の記述を忘れかけている頃合いを見計らって)
あるいはまた、『ここ、かなり難しい話だと思います。ですが(中略)「否定神学批判と合わさることで理解できると思いますので(中略)大丈夫です』と、迷路に入りかけて不安な読者を安心させてくれる。
この1冊で「現代思想が分かった!」とはとてもならないし、「なんとなくわかった」までも難しいかもしれない。
けれども、近代以降の思想の流れはざっくりつかめるし、その中で入門書の紹介があり「よし、ほかの入門書も読んでみよう!」という気にさせる。
おまけに付録として哲学書の読み方のレクチャーまである。(これがまた秀逸)
まさに手取り足取りで、恐る恐る現代思想の入り口をのぞき込んでいる初学者を導いてくれる。
「おわりに」にある次の一文に、著者の熱い思いが吐露されていて、私など、涙ぐんでしまった。
『本書は、「こうでなければならない」という枠から外れていくエネルギーを自分に感じ、それゆえこの世界において孤独を感じている人たちに、それを芸術的に展開してみよう、と励ますために書かれたのでしょう。』
理想的な、入門のための入門書。
かつて「現代思想」にかぶれた人も楽しめる書
2023/03/27 02:42
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぶんてつ - この投稿者のレビュー一覧を見る
2002年の内田樹による『寝ながら学べる構造主義』では、フーコー・バルト・レヴィ=ストロース・ラカンが構造主義の「四銃士」だった。
その後、フーコーはポスト構造主義のメンバーにも入れられていたが、フランスの「現代思想」は、構造主義とポスト構造主義を合わせたものというのが私の認識だった。
それが2022年のこの本では、「現代思想」の代表者として、デリダ・ドゥルーズ・フーコーが挙げられている。ラカンはルジャンドルと共に、「精神分析と現代思想」として、1章が与えられている。
取り上げられるメンバーの違いからもわかる通り、この本では、ポスト構造主義が「現代思想」とされている。
そして、デリダは「概念の脱構築」、ドゥルーズは「存在の脱構築」、フーコーは「社会の脱構築」と、極めて明快に解説してくれる。
また、この本の面白いところは、第6章に「現代思想のつくり方」という章が設けられているところだ。自分で作ってこそ、本当に理解できたと言えるということだろう。
構造主義の面白さから「現代思想」にかぶれた私でも、著者のわかりやすい解説で、充分に楽しめた「現代思想」入門でした。
大学生におすすめ
2022/07/21 16:44
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:さくらの - この投稿者のレビュー一覧を見る
『現代思想は差異の哲学である』とある。この差異の哲学(必ずしも定義に当てはまらないようなズレや変化を重視する思考)というものがとても重要な考え方だと思った。また、脱構築の基本的発想はフィールドワークにおいてよく使われるものと同じだと思った。こんな感じのよく分かんないけどなるほどって思うような所が多く面白かった。
二項対立を使いこなす
2022/06/05 11:02
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:サンバ - この投稿者のレビュー一覧を見る
二項対立は善悪のように、+対-で語られることが多い。本書は、-で語られる部分の重要性を指摘し、マイナスとされる方にも相応のエネルギーがあり、時にはプラス側を支えていると指摘。その上で二項対立からの逃走を指南する。物事の複雑性を認め、共通認識を仮固定しながら、相対的に生きることが見えてくる。
入門の入門
2023/01/21 21:19
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:H2A - この投稿者のレビュー一覧を見る
デリダ、ドゥルーズの章だけでも読む価値ありだと思う。目から鱗だった。音声中心主義、差異、とかそういう解釈があるのかと今さら納得。無意識のもんだいにもそんなに関心あったわけではないが、ドゥルーズにおいてどういう意味があったのか少し蒙が拓いたような気がする。これほどくだいて書けるのも著者の地に足のついた理解のおかげ。それから終章のポスト・ポストモダンもおもしろく読んだ。
前半=Very Good、後半=Not So Good
2022/04/13 19:06
9人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Haserumio - この投稿者のレビュー一覧を見る
評者如きが内容を云々出来る筈もないのだが、前半の判りやすさと明晰さは素晴らしい。(この世は差異ないしは多様性の「海」なので、多くの言説類が「仮固定」であって、そうでもしないと前に進めないことはそりゃ一般常識からも理解できる。また、ドグマを壊すのに、二項対立を揺るがす(=脱構築する)というのも、ビジネスなどではよくある話。)が、第5章から第7章はイマイチで、こなれていない。もっと工夫が必要かと。末尾の「付録 現代思想の読み方」にきて判りやすさと明晰さが復活しましたが、結局、評価としては星4つとさせて頂きました。
人生観が変わるかもしれない
2022/05/12 19:49
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:nekodanshaku - この投稿者のレビュー一覧を見る
「読書はすべて不完全である」この言葉に救われた。デリダ、ドゥルーズ、フーコーを中心にポスト構造主義の現代思想家の概念を読み解くことができた。実際には前半だけが理解したつもりになったにすぎず、後半のラカンなどの話題にはついていけなかった。複雑なことを単純化しないで考えること、文章を理解するときは二項対立を意識すべきであり、思考する場合は、その二項対立を揺るがして脱構築することが重要であること、などなど、確かに人生が変わる読書経験であった。
世俗性と偶然性。
2022/05/26 00:26
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ゲイリーゲイリー - この投稿者のレビュー一覧を見る
本作は、難解な現代思想を懇切丁寧に解説している。
デリダ、ドゥルーズ、フーコーを中心に二項対立からの脱構築とはどういうことなのかを段階的に取り上げていく。
そこで述べられるのは、秩序の中にある攪乱要因や同一性を絶対視しないことの重要性である。
白か黒かではなく、グレーゾーンをグレーゾーンとして受け入れることが如何に重要であるかを述べているわけだ。
また本作は現代思想を解説するだけでなく、なぜ今現代思想が必要なのかということにまで触れていく。
更に巻末には現代思想をどういう風に読みこむべきか、といったレクチャーまで記載しているのだから、タイトル通り現代思想の入門書として最適と言う他ない。
秩序を何よりも重んじ、必然性を求めてやまない今の世の中だからこそ、本書の様に世俗性や偶然性を肯定する作品は読まれるべきだ。
無限の反省から脱却し、自らの人生において今ここで何をするかに注力することを後押ししてくれる一冊。
入門書
2023/07/12 20:16
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
入門というには、むずかしいです。というか、知らない用語がけっこう出てきたせいかもしれません。自分は、哲学は、大学生のとき、一年間だけ一般教養で学んだだけで……、と、言い訳しときますが。