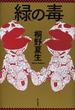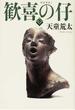あまでうすさんのレビュー一覧
投稿者:あまでうす
紙の本キルリアン
2009/10/22 13:29
これって「似非小説」ではないでしょうか?
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ひとりの中年の自称鎌倉文士が市内の名所旧跡、たとえば夜の円覚寺の山門や化粧坂、あるいはまた亀ヶ谷のおのれのあばらや、北鎌倉の居酒屋、さらには若き日に身に覚えの道玄坂界隈などで、やたらひとりよがりな物思いにふける私小説的感慨小説です。
まず冒頭の蝶の描写が妙ですよ。
「一匹の蝶がその風に翻弄されつつも、絶命的なバランスで宙を泳いでいく。」
というのですが、およその意味はわかるけれど、この一行においてプロの文章として「絶命的」はないでしょう。せっかく勢い込んで読もうとしていたのに、この奇怪な形容動詞に面喰って「絶望的」な気分になりました。
しかし心を動かされる個所がないではありません。たとえば突然文士の陋屋を前触れもなく訪れる謎の美女。
「薄手の黒いストッキングの細い足首が見え、三和土(たたきと読む)に残ったもう一方に足が太腿の奥まで露わにしていた。茶封筒とバッグを框(かまちと読む)に置いたまま、畳を軽やかに揺らして入ってくると、布団に頽(くずお)れてくる」
なあんて、なかなかうまいもんです。おまけに文士は、こんな官能的な美女にいきなり唇を重ねられたりするのです。いいなあ。
それからこの文士の風呂場には巨大な「鎌倉蜘蛛」が棲息していて、昼でもそうとう不気味な雰囲気を醸し出しています。さらには文士の故郷新潟の友人からはなにやら幼友達の不穏なうわさ話を伝えてきます。
しかしながら、これらの諸要素がよってたかってなにか小説的核心を構成していくのかと思ってじっと我慢して読み続けていたのですが、結局はなんにも起こらない。なにもない。なにももたらされない。このサントリーの山崎的状況はいったいどういうことなのでしょう。
不得要領のまま読み終わったのですが、タイトルの意味すらわからない。仕方なくネットで調べてみると、キルリアンとは旧ソ連の科学者が唱えた「似非科学」で、高周波電界中に置かれた生物体の表面に起こるコロナ放電現象のことらしいのですが、それならこの芥川賞作家の小説って「似非小説」ではないでしょうか?
ちょうどその時でした。しかしちょっと待てよ。主題の喪失と描法の混乱こそ現代小説の2大特徴とすれば、この作家のこの作品こそは、げにそれらの特性を全開させた秀逸な収穫ではないのか?という不埒な思いつきが、私の鈍い爬虫類の脳内にあたかも天啓のように閃いたのでした。
♪不埒な女のラチもないプラチナジュエリー 茫洋
2009/05/11 20:12
頼朝という人のほんとうは、結局この程度の者であった
8人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
我が国に初めて武家政権を樹ち立てた二品頼朝に対する評価は高いようだが、吾妻鏡を読み進むとこの武士の人間性がだんだん厭になるような気がするのは、後に源家を簒奪した悪辣非道な北条氏がこの歴史書を編纂したからだろう。
しかし平家追討、殲滅に多大の貢献をした弟の伊予守義経や、それほどの武勲はなかったが義理の兄の代理として西国を連戦した範頼への冷酷極まりない処遇には、冷徹非情な政治家の決断を褒めそやす以前に、大いなる違和を覚える。
所詮この男は老獪な北条時政や梶原景時などの側近に目を眩まされ、己の真の敵と味方とを弁別できず、己の内部に異端や外様や取り込んで清濁併せ呑むことができなかった悲劇の将軍ではなかっただろうか。
とりわけ平家掃討戦に軍の矢面に立たなかったくせに、伊予守の殺戮を命じてやむを得ず実行した藤原泰衡の追討には中央軍の陣頭指揮を取っており、なにもそこまでしなくとも、という気がするのである。
藤原氏征討直後の文治五年一一月一七日、二品は藤沢市の大庭御厨の近くで一匹の狐に遭遇する。数十騎で取り囲み、頼朝が弓矢を番えてヒョウと射たところ、彼の矢は当たらず、傍から射た弓矢の名人篠山丹三の矢が狐の腰に当たった。頼朝はそのことを知りながら、「命中した!」と声を発した。
すると丹三は忽ち馬より降りるや頼朝の矢を己の矢と入れ替えて狐に立て、これを掲げて二品に奉った。翌日御所に帰還した頼朝は、丹三を召し出して側近く使えるように命じたというのであるが、これほど嫌な話もない。
頼朝という人のほんとうは、結局この程度の者であったと思わないわけにはいかない。
♪亡き人の胸に塞がる菊の花 茫洋
紙の本正義で地球は救えない
2009/05/11 19:46
いまどきの環境ブームに冷水を浴びせかける問題作
5人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
地球における二酸化炭素の急増と温暖化の相関関係に疑問を投げかけることからはじまって、環境問題の本質は、食糧とエネルギー問題にあると喝破し、もろもろの「地球にやさしい」環境運動の虚偽と虚妄を鋭くえぐる問題提起の書である。環境原理主義者に対する反環境原理主義者の弾劾の書でもある。
例えばここ2年間くらいの企業の広告活動をみると、その中心的なテーマは環境問題であって、その一極集中ぶりは異常なものがある。環境さえPRしておけばそれで良し、とする体制順応型の対消費者コミュニケーション活動そのものが、この国の産業活動の疲弊と腐敗と堕落を物語っているようだ。
それでは企業や消費者にとってそれほど環境問題、とりわけ地球温暖化問題がどれほど切実な課題として認識されているのかといえば、それらは極めて表層的なものにすぎない。
たとえば先の洞爺湖サミットで我が国はじめ世界各国は「50年までに排出量半減」することを認めたが、具体的な行動計画については誰もなにも言わなかった。しかし養老氏が説くように、二酸化炭素排出の最大の要因は石油の使用なので、本気で温暖化を抑えたければ、石油生産を抑止するのがもっとも効果的だ。
これを年々計画的に抑制すれば多少経済活動は弱まるが「50年までに排出量半減」など簡単に実行できてしまう。ところがそれがわかっているくせに手もつけず、同じサミットで逆に産油国に対して石油増産を要請するというのは矛盾そのものである。
つまりはおそらく(日本国をのぞいて)世界中の国々が本当に本気で二酸化炭素の削減に取り組んでいるわきゃあない。ここは思案のしどころだよと著者たちは警告するのである。
確かに気象変動の要因は複雑怪奇だから、二酸化炭素の増減だけで地球温暖化を説明することはできないだろう。もしもあるパラメーターを恣意的に導入することによって過去100年間の気候変動を上手に説明することができたとしても、一歩先の未来について確信の持てる予測をすることは困難だろう。
肝心要の二酸化炭素の増減や地球温暖化の因果関係についても最終的にはまだ学問的な決着はついていない。にもかかわらずそれを己の金もうけや政治的野心の道具として利用しようとする輩が陸続と登場し、科学的真実の探求そっちのけでわれがちに世界崩壊だの人類絶滅の未曾有の危機だの目の色変えて叫んでいるようだ。科学と論理に弱い(どうでもよい?)私には、いずれが正かいずれが邪か今やそれすら見分けがつかなくなってきたので、この問題からはしばらく降りて様子を見ることにしよう。いまわあわあ叫んでいる連中がみんな死んじまったころにはおのずと結着がつくだろう。
しかしだからといって池田が言うように、京都議定書に始まる世界各国の取り組みがまったくナンセンスであり、こんな愚かな活動に全国民を巻き込むのは愚の骨頂であるばかりか税の無駄遣いであり、アメリカ帝国主義の大陰謀である、と偉そうに説くのはいかがなものであろうか。(日本だけが損をする)排出量取引が排出量低下自体につながらないことはいうまでもないが、それでもあの漫画的なクールビズだのエコバッグだのエコカーだって、印税稼ぎの駄弁を弄するだけで何もやらないよりは多少はましではないのではなかろうか。
しかし事の重大さからすれば、著者たちが力説するとおり、石油の産出が終了する前に代替エネルギーを開発して全世界の持続を可能にするとともに、極力世界人口を低減させていくことは、ツバルやベネチアやオランダの陥没やホッキョクグマの絶滅を心配することよりもはるかに重要な「地球人の使命」であろう。
♪さらばベネチア沈みゆく関東ローム層で弔鐘を鳴らすのは誰 茫洋
紙の本歓喜の仔 上
2013/02/07 10:57
あまりにも「普遍的な」メッセージでありすぎるための陳腐さ
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「歓喜」というタイトル通り、ベートーヴェンの第9交響曲の第4楽章の後半でうたわれ、「歓喜に寄す」の歌が重要な伏線であり、ライトモチーフともなっている。
人間の友愛とその喜びを神に向かって感謝する詩は、無神論者からみればナンセンスな面はあっても、人と人の絆が重要だと説くシラーの熱い叫びは現在でも一定の意味を失ってはいないだろう。
しかしそれがあまりにも時代を超越した「普遍的な」メッセージでありすぎるために、作曲者のメロディと相俟って完全に陳腐な音楽として届けられてしまう危険性がある。かのフルトヴェングラーを除く今日のベートーヴェン音楽の演奏と同様に。
紙の本緑の毒
2011/10/16 14:59
奇妙な失敗作というべきか
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
タイトルに魅せられて読んだが、奇妙な失敗作というべきか。
開業医が水曜日の夜に手当たり次第に住居に不法侵入してスタンガンで気絶させ、麻酔薬を注射して婦女暴行するという話には大いに興味を抱いたのであるが、いったいどうしてそういう事に及ぼうとしたのかという動機が最後まで不明であった。
もしかするとそれは「当方の不明」によるものかもしれないが、いくら同業の医師である妻との関係がおもわしくないからといって、この若くて、お洒落で、金離れのよい東京の開業医が、なにを血迷ってだか連続レイプ事件を引き起こす「遺伝子異常」以外のなんらの必然性も感じられず、そんなことは頭の良い著者だって充分分かったうえで書いているに違いない。
だとすれば、これは暴行された女性たちの被害者同盟や復讐を誓う者たちの怒りや悲しみがいちおうもっともらしく描かれているとはいうものの、お話の本質は医師や病院を舞台にした一種の通俗娯楽小説であって、ここには最近著者が提起した「東京島」や「ナニカアル」などの文学的人生的サムシングは皆無なのであった。
2009/11/14 21:21
マルコ・ポーロもフビライもはたして実在したのか?
7人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
これは池澤夏樹編集による河出書房新社の世界文学全集の1冊です。
ユーゴスラビアのキシュが書いたのは現実と幻想がごった煮になった父親の思い出とそれに付随するビルダングスロマン。ユダヤ人の父親はアウシュビッツで帰らぬ人となりましたが、誰にせよ父にまつわるさまざまな記憶と物語はあるわけで、それらと比べてこの小説が格別劣るわけでもすぐれているわけでもありません。
イタリアのカルヴィーノが書いたのはこれとは正反対の幻想小説です。マルコ・ポーロの「東方見聞録」を下敷きにした偉大なる旅行者と偉大なる征服者フビライ・ハーンとの世界の都市をめぐる対話です。
それらすべて女性の名前がつけられた都市はベネツイアをのぞいて実在しない空想の都市であり、したがってそれらの都市をめぐってさまざまな視点から繰り返される対話自体も空想的な性質のものです。
第7部に至って、フビライはポーロが一歩も静謐な庭を動いて形跡がないにもかかわらず、いつそれらの数多くの都市を訪問する暇があったのかと疑い、「朕もまたここにおるということが確かなこととは思えないのだ」と自問します。
万里の長城やヴェネツィアははたして本当に実在していたのか? マルコ・ポーロもフビライもはたして実在したのか? 歴史的事実も人物もその存在の根底が激しく疑われたままこのいかにももっともらしい小説は終わりを告げるのです。
♪われ描くゆえに都市ありカルヴィーノ語りき 茫洋
紙の本歓喜の仔 下
2013/02/07 10:59
♪おお、友よ、もっと別な真理の歌をうたおうではないか!
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
作者はこの小説の展開についてなみなみならぬ周到な構成を凝らして臨んではいる。日本と外国、2つの異なる場所と場面で自由と独立のために戦う人々の同心円世界を同時進行で描きだそうとする意欲的な試みもそう。
だが、「どんな社会や人世の苦悩や闘争があろうとも、それを勇気と友愛の絆で潜り抜けた暁には遥かなる天空の彼方に救い主たる神が待ち受けている」、という余りにも紋切り型の大団円が、多くの読者にとっていささか鼻白むお寒い着地点に収斂するのも無理からぬ話なのである。
♪おお、友よ、このような安易な物語ではない。
我々はもっと心地よい、もっと歓喜なぞを忘れた別な真理の歌をうたおうではないか。
紙の本花酔ひ
2013/02/01 17:51
あきれはてあなはずかしくあじきなし
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
京都の葬儀会社と東京のきもの販売会社の2組の夫婦が巡り合い、ひょんなことからスワッピングするようになるという通俗小説にありがちなよろめきドラマであるが、こういう主題をさかんにとりあげている渡辺淳一と違って、このひとの文章は日本語としてちゃんとしているので、「そういう意味では」安心して読める。
渡辺淳一といえば最近日経に連載している「私の履歴書」のなかで、自分と出来てしまった看護婦を堕胎させたうえに、その逆恨みを懼れつつ他の女性と厳戒体制の中で結婚したなどと得々と述べているが、そんな破廉恥な行状といい、そんな告白をこのような場所で面白おかしく公開するという非常識さといい、その人間性を疑わずにはいられない。
さて話が大きく逸れたが、今回著者が殊の外ちからを入れたのはSMの描写である。最近海外でも女性が描くソフトSM小説がはやっているようなので、さっそく売らんかなとばかりに耳学問でとりこんだのであろうが、マゾに目覚めた男がサドに目覚めた女と激しく行為するシーンは、著者の実体験から「湧出」したものではないにしても、なかなか迫力がある。
それはよいのだが、お互いの浮気によって生じた肉の喜びの落とし所をどこに求めて良いのかに窮した挙句、突如漫画的な事件で無理矢理本編を終わらせたのは問題だ。SMよりも性のむきだしに発情し発条した男女の生の行方は、この小説ではまったくつきつめられてはいないからである。
あきれはてあなはずかしくあじきなしおんなとおとこのせいのむきだし ちょうじん
紙の本日本小説技術史
2012/11/15 10:01
ほんの断片すらも理会することが出来なかった
6人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
題名の面白さに惹かれて一読してはみたものの、わたくしの生まれながらの脳力の弱さも手伝って本邦の小説の歴史をその構成技術をつうじて論じるという前人未踏、空前の快挙の詳細のほんの断片すらも理会することが出来なかったのはまことに残念無念、痛恨の極みでありました。
小説は膨大な言葉から形づくられているが、確かに著者がボルヘスにならっていうように、その創作の手法の定型や技巧をテーマに歴史的に研究されたことは、わたくしの知る限りでは島田雅彦の「小説作法ABC」を除いてあまりなかったような気がします。
本書では馬琴から逍遥、紅葉、亭四迷、鴎外、一葉、独歩、藤村、花袋、泡鳴、漱石、秋声、龍之介、利一、翠などの作家の諸作品が、著者の博学を誇示するように縦横無尽に引用され、彼らの小説技術が高踏的に論じられるのですが、冒頭に述べたようなお恥ずかしい理由で、わたくしにはその「高尚なる理屈」がいくら読んでもてんで腑に落ちませんでした。橋本治氏が説くように日本の小説の源流は江戸時代の人形浄瑠璃にあるにもかかわらず、これを無視して馬琴から開始する手法も納得できません。
このように本書の前半は、暗愚なわたくしには取りつく島もない難解な原理論の連続だったのですが、後半から末尾にかけては著者が高踏的な小説技術論をどこかへうっちゃって、漱石が「トリストラム・シャンディ」の影響を深く受けたとか、尾崎翠の「第七官界彷徨」がどうしたこうした、とかの単なる文芸ひよーろん風のお話が続くので、それなりに面白く読めたのでした。
著者の、日頃のお勉強の成果をこの時とばかりに披露したいという青臭い思いや、衒学趣味が嵩じて超難解な用字用語を教壇の高みから下々に呉れてやりたいというエリート意識も分からないではありませんが、もしもおのれが説こうとする思想や内容にいささかでも自信があれば、この本は小西甚一の「日本文藝史」やドナルド・キーンの「日本文学史」のように、もっともっと分かりやすい日本語で書くことができたはず。今は亡き井上ひさしがいみじくも言い遺したように、「難しいことは分かりやすく」書くのが書き手の作法というものではないでしょうか。
自分にもよくは判らぬことだから超難解の言辞を一発 蝶人
紙の本信長私記
2012/02/27 11:00
やさぐれのごんたくれ作家のでっち上げ
2人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
太田牛一の「信長広記」の向こうを張って、やさぐれのごんたくれ作家がいっちょでっち上げたる「信長私記」である。どうせ編集者の推挽で無理矢理書かされた連載小説なのだろうが、彼の血湧き肉踊る京都を舞台にした肉弾自叙伝と違っていまいち、いま二、いま三乗りが悪く愉しめなかった。
ごんたくれが尾張織田家のごんたくれになり代わって一族のみそっかすを打倒したり、斎藤道三の娘濃姫と濡れ場を演じたり、後年の前田利家の尻の穴を破ったり、後年の秀吉や家康の人となりを見抜いたりする戦国青春ヤッホーホイサッサのアホ馬鹿噺であるが、例に因ってくだんのごとし。面白くもおかしゅうもない。
竹千代、すなわち当時織田家の人質になっていた家康が、「永久に戦のない世界を作ることが自分の願いである」、と語って、そんなことは阿呆鱈経の絵空事と考えている信長親子を驚かせるところが出てくるが、この家康流の信条って昔からNHKの大河ドラマの女流脚本家の決まり文句であるなあ、と思って軽くのけぞってしまいましたよ。まる。
青空に孤蝶消えゆく寒さかな 蝶人
紙の本放蕩記
2012/01/31 09:48
いったいどこが放蕩なの?
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
挑発的な題名に惹かれて手に取ってみたが、いったいこの小説の主人公のどこが放蕩なのかさっぱり分からなかった。
放蕩とは広辞苑によればほしいままにふるまうこと。特に酒食に耽って品行が修まらないこと等とあるが、ヒロインは少女時代にちょっぴりレスビアンの真似をしたり、高校時代に2人のクラスメイトと先輩と致したり、大学時代に出版社勤務のリーマンとラブホテルへ行ったりするくらいで、この定義のいずれにもあてはまらない。
その後もいろんな男と寝まくったというのだが、よしんば彼女が毎晩違う男と床入りしたからといってそれを色情狂と称しても放蕩娘とは言えないだろう。それはこのヒロインンがきわめて意志強固な倫理的な志操の持ち主であり、肉欲に溺れて男を漁らざるをえないマンイーターとは鋭く一線を画しているからである。
それでも彼女は粋がって自分を放蕩娘と命名したいのかもしれないが、彼女が放蕩するのはより深く人世を知り生き抜くための方法的放蕩であって、肉が肉に溺れるほんたうの放蕩とは似て非なるものである。
本作では関西弁で饒舌に自己表現する主人公の母親が登場して大活躍するが、どこの家庭でも母と娘とはまあこんな関係だろう。そう大騒ぎして書きこむほどのことはない。花村萬月ばりの波乱万丈の放蕩記を期待したのに、出てきたのは世間でよくある母娘の葛藤話。これを凡庸な文体で延々と書き連ねられると読むほうもうんざりしてくる。こんな作家がよく直木賞をもらったものだ。
紙の本バット・ビューティフル
2011/11/02 21:01
著者が勝手に空想してでっちあげた8つのショート・ショート・ストーリー
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
レスター・ヤング、セロニアス・モンク、バド・パウエル、ベン・ウエブスター、チャールズ・ミンガス、チェト・ベイカー、アート・ペパー、そしてデューク・エリントンにイタコのように成り変わって著者が勝手に空想してでっちあげた8つのショート・ショート・ストーリーである。
一読するにその出来栄えはいまいちであり、どの物語も薬と妄想と狂気と精神錯乱に満ち溢れている点でまったく同質のあがりのように思われ、読んでいてかなり退屈だが、門外漢の私がそんな悪口を言っても、ジャズ気狂いの著者は意に介しないだろう。
こういう史伝というか伝記的物語は、目を晒しながらミュジシャンの音が聞こえてくるようでなければ失敗作と決めつけられても仕方あるまい。しかし本編はともかく、ジャズの歴史と本質について見事に要約したあとがきは短いが読み応えがあった。
村上春樹による翻訳は小説と違ってこなれておらず、読んでギクシャクする箇所がある。彼は「これは世にあまたあるジャズ関係本とはひとあじ違う「想像的批評」だ」などと高く評価しているようだが、こんなイタコ本を翻訳する暇があるなら、もっと本職の小説をじゃんじゃん書いて早くノーベル賞を取っとくれ。
2009/07/03 17:38
とても一〇〇〇年前の人物とは思えません
8人中、8人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「この世をばわが世とぞ思ふ望月の欠けたることもなしと思へば」
という歌を詠んだといわれる藤原道長の自伝の現代語訳です。
こういう手放しの自画自賛を臆面もなくやってのける奴はいったいどういう人物なのかと思って手を出したのですが、なかなか面白い本でした。
まず「この世をば」と即興でなぜ詠めたのかといいますと、これは道長が朝はお天道さま、夕べはお月さまを必ず観賞する人間だったからだと断言できます。
彼の日記は必ずお天気メモから始まり、夜の名月や笠置寺参拝の折の流星の記事などまるで天体観測家を思わせるほど。功なり名を遂げ摂関政治の頂点に立った自負を月に例える必然性はその日常生活の習慣からきているといえそうです。
道長は、お天気や彼の日常や身辺で起こった怪異だけでなく、14歳違いの甥の一条天皇との政治的な協調ぶりやちょっとした反発、寺院における法華八講などの盛大な法事や除目の詳細、さまざまな儀式や賀茂祭などの祭典、頻繁に行われた作文会(漢詩を作る)のテーマなどについてもくわしく書き記していて、ちょっと永井荷風の日記に似た関心の広さを示しています。次々に病に侵されるところや、連日のように相撲取りに相撲を取らせて喜んでいるところなど、とても一〇〇〇年前の人物とは思えません。
けれども荷風と違って日記の文章にはいっさい屈折も韜晦もなく、なにをどう述べても単純明快そのものであり、彼の精神がまことに健全で、西欧のルネッサンス時代の知識人のような強靭な知性と晴朗さ持ち合わせていたことを雄弁に物語っています。
面白いのは、当時の皇族や貴族たちは「毎日が物忌デー」といえるほど数々の禁忌に取り囲まれて暮らしていたということです。
たとえば甥の一条天皇が住んでいる内裏では、しょっちゅう犬や鳥、時折は身元不明の人間の死体が発見され、その度に安倍晴明などの陰陽師が呼び出されて占い、その託宣次第でさまざまなリアクションが起こります。いまから1000年目に陰陽師たちがこれほど権力者たちに重用されていたとは驚きです。
それから忘れてはならないのが、藤原道長と紫式部、源氏物語との関係です。
寛弘2年10月1005年の浄妙寺三昧堂の供養における法王・天皇をはじめすべての皇族や貴族百官や高僧たちが居並ぶなかで粛々と繰り広げられた荘重な儀式や読経、楽器の演奏などの華麗なパフォーマンスの数々、あるいはその3年後に一条帝が左大臣道長が住む土御門邸を訪ねるシーンでは、はしなくも紫式部が源氏物語で描写した華やかな式典と権力者たちの栄枯盛衰の無常をまざまざと想起させ、光源氏のモデルに擬せられる道長の存在ともども、いずれが表でいずれが裏か、いずれが真でいずれが虚か、と日記の細部に至るまでつきせぬ興味が湧いてくるのです。
♪ほらほら千年前の巨魁が今日も土御門邸で梅の漢詩を作っているよ道長日記 茫洋
紙の本神曲 完全版
2010/12/01 08:25
「後出しじゃんけん」で偉さうに歴史を裁く詩聖ダンテ
23人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
キリスト教世界では聖書に次いで重要とされるとかいうこの本。これまで野上素一、寿岳文章両先生の訳で読みましたがどうにもこうにも陸に上った海鼠のように面白くもおかしくもない喰えない書物。いったいどこが世界の名著なのかと頭を悩まし続けておりましたが、このたびの平川裕弘先生の定評ある完全版の翻訳を地獄・煉獄・天国とつらつら彷徨してもさっぱり興味がわいてこないのでした。
その原因はきっと私がキリスト教徒ではなく、神も地獄も天国も信じていないからでしょう。それでも地獄の恐ろしげな描写はわが国の仏教の様々な地獄絵図でもお馴染みであり、蛇に我身を食らわれたり糞尿の海に生きながら永遠に漬けられたりすれば嫌だなあという思いはあるのですが、詩人ウェルギリウスのガイドから離れたダンテが、ゆくゆくは天国に入るための予備校として、これまでに犯した罪の清めを行う煉獄界というみょうちきりんな世界に入っていく辺りでは「その嘘ほんまかいな」という無知で無信仰な庶民の健全な良識がぐんぐん頭をもたげてこないわけにはまいりませぬ。
そもそもキリスト生誕以前に活躍したギリシア、ローマの神々やホメロス、ソクラテス、オデッセウス、アキレウスなどの偉大な詩人、哲学者、英雄が紀元1300年頃のフィレンツエで党派闘争に明け暮れていたイタリアの小詩人によって有罪宣告を受けて、哀れ地獄や煉獄に落され、なんで塗炭の苦しみを味あわなければならないのか。
いくらキリストとキリスト教が偉大であるからというて、その創始者と教義と教会がこの世に誕生すらしていない時代に生きた無数の秀いでた無信仰者たちを、地獄・煉獄・天国のアバウトな3つの境界に投げ入れることなぞ、それこそ神様お釈迦さまでも出来るわけがない。
ローマ帝国を制覇した新興勢力のキリスト教が、ギリシアローマの古い神々を皆殺しにしたあとで教会の祭壇から追放して地獄においやるという構図は、わが国のアマテラス神話を政治文学的に編集した「古事記」と瓜二つで、それと同じ宗教文学史の書き換えを、遅まきながら14世紀の西欧で美辞麗句を並べたててやってのけたのがダンテというわけです。
それにしてもはじめの地獄篇ではそこそこ読むに堪えた彼の詩文が、想い人ベアトリーチェに導かれて水星、金星、太陽と舞い上がる天国篇において急激に天与の霊感を失い、なんの変哲もない神様万歳の御託の羅列に堕するのはなぜでしょう。
思うにベアトリーチェに再会するやいなや、彼の浮気と変節を厳しくなじられてしまったダンテが思いっきり自信喪失した当然の報いかもしれません。
なんだって後出しじゃんけんで偉さうに歴史を裁くなダンテ 茫洋
紙の本嘔吐 新訳
2010/10/13 14:33
何が嘔吐なのかさっぱり分からない
16人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
昔この本を白井健三郎という人の翻訳で読みかけて、途中で放り出したことがありました。なんでも実存主義という哲学が大流行の頃でした。
今度手にとったのは鈴木道彦という人の翻訳ですが、こちらは当世風にこなれた訳語のせいもあってともかく最後まで読みとおすことができました。やれやれ。
しかしなんと評していいのかしらん、まったく訳の分からん変態的な小説です。
サルトル本人が色濃く投影されているロカンタンというやたら神経質な青白いインテリゲンチャンが、図書館のコルシカ人やスープの中の蟹を見ては吐き気を感じ、池に投じようとした小石に触り、公園のマロニエの根っこを見ては、そのガッツリとした存在感に圧倒され、自分自身のみならず外界、世界全体に大いなる違和と不条理(この言葉も大流行したな)を感じ、「われ思う故にわれ絶対的に存す」のデカルト的理解を脱却して、「われ存す、故にたまたまわれ存す」の実存的悟りに超絶的にエラン・ヴィタール(生命的飛躍)を遂げたと、まあ恰好よくいえばそういう哲学的小説なのでしょう。
しかし道行く人や下宿のおばさんやレストランのお姉チャンが己と異質な外部のモノに見えたり、都市や群衆やはたまた図書館の本をアイウエオ順に読んでいる孤独な独学者に吐き気を覚えたりするっていうのは、糞真面目な哲学青年の誰もが一時的に患う麻疹のような病理現象にすぎず、主人公がいったいどうして吐き気を覚えるのか誰にも分かりません。男性なのに、妊娠でもしているのでしょうか?
昔小林秀雄がこんな小説を書いたことがありました。小林を思わせる自意識過剰のインテリ青年が、川を渡るポンポン蒸気船に乗り込んだら、誰か同乗者がいて、自分も彼らも揺れている。それを見ているうちに、自分(小林)は彼らと自分が、同じリズムでポンポン揺れるのに堪えられなくなってきて、ヘドが出そうになる。
確かそういうくだりがありました。これを読んだ中野重治が「なにがヘドだか、全然分からない」と書いていましたが、当時のサルトルも小林とまったく同じ病気に罹っていたのでしょう。
だから私もこう言いましょう。サルトルよ、お前さんのもったいぶって繰り返す嘔吐とは何なのか、私には全然分からないよ、と。
嘔吐とは、高等遊民の唐人の寝言であり、世間知らずのぼんぼんの白昼夢に過ぎなかったことが、有名になってからのサルトルにはすぐに分かったはずです。
それゆえに、親の遺産で食べている30歳の青白きインテリ小僧ロカンタンは、フランスの小都市で大革命時代の貴族ロルボンの伝記を書こうとして果たせず、おまけに恋人アニーに振られて、Some of these days You`ll miss me honeyのレコードを聴きながらブーヴィルに別れを告げる。
というのが、この余りにも有名な実存主義小説のエッセンスなのです。
あにはからんやマロニエのぶっとい根っこに存在の実存を見つけたり 茫洋