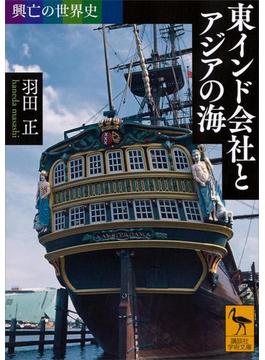視点を変えた交易史
2018/11/16 20:05
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Koukun - この投稿者のレビュー一覧を見る
学生時代に歴史教科書で学んだような、ヨーロッパ中心.国別の交易史ではなく、視点をアジア.アフリカの人々からの視点も交えた交易史なので新鮮な感じがして面白い。
さまざまなアジアの政治形態とヨーロッパ
2020/07/30 07:11
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:福原京だるま - この投稿者のレビュー一覧を見る
西アジアやインドの陸の帝国は沿岸や海上の商人や宣教師の行動に興味がなかったのに対して中華や日本の東アジアは海も管理しようとして(朱印船貿易や鎖国、海禁など)その体制に不都合なキリスト教を禁止したという話は興味深い。ポルトガルやオランダはインドや東南アジアで武力で強制的に拠点を作ったのに日本ではおとなしく平戸や長崎で貿易してたのはなぜかと思っていたが陸の帝国ムガル帝国は海の帝国ヨーロッパの沿岸拠点を征服しようとしなかったのに対して日本の権力はそれを許さなかったからだとわかった。ペルシャやインドは領域ではなく人を支配していて貿易で市場が栄えるなら外から来た人でも臣下として扱うので東インド会社に領主としての地位を与えるのに対して日本は内と外を厳格に区別する貿易体制だったので後の主権国家・国民国家のようなものが既に江戸時代にできていてそれが明治の近代化にスムーズにつながったというのが面白かった
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:雄ヤギ - この投稿者のレビュー一覧を見る
私は東インド会社について、「パイレーツ・オブ・カリビアン」やVOCマークくらいしか知らなかったが、この本では、ガマのインド洋参入から英・蘭・仏の東インド会社の性質の違い、世界情勢の変遷による会社の経営の変化なども取り上げられている。個人的には、江戸時代の出島貿易でなぜオランダが選ばれたのか、どうやってイギリスの東インド会社が現地の統治に乗り出したのかなど、気になっていたことがいくつかわかってすっきりした。
東インド会社の設立とその後の世界の変貌を描いた書です!
2019/01/27 17:39
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、東インド会社の設立とその後の200年間の世界の変貌を克明に描いた書です。私たちは東インド会社という名前は中学校や高校の歴史の授業で学んだので知っていますが、その内実や詳細についてはほとんど知りません。この会社が世界発の株式会社であったことや、グローバル化の先がけになったことなどは初耳と言う方も多いのではないでしょうか。この東インド会社は世界、特にアジアに大きな影響をもたらし、アジアを変貌させたと言っても過言ではありません。では、どのように変貌したのでしょうか。詳細は、ぜひ、本書をお読みください。知られざる新しい知の世界が待っています。
ベンチャー企業の先駆け
2020/04/27 13:43
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Todoslo - この投稿者のレビュー一覧を見る
大きなチャンスを得るために、時にはリスクを恐れずに挑戦しています。物産の輸出入だけでなく、植民地支配の足掛かりにもなっていて考えさせられました。
たくさんの東インド会社
2019/07/21 06:33
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:藤和 - この投稿者のレビュー一覧を見る
ヨーロッパ圏でいくつも立ち上がった東インド会社についての本。
何を求めて東を目指したのかとか、オランダ、ポルトガル、イギリス、フランスの各国の東インド会社の発足や衰勢が書かれています。
それに合わせて、日本の外交についても触れているので、16~18世紀前半の世界の海側からの交易についてざっくり把握するのには良いかも。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぽぽ - この投稿者のレビュー一覧を見る
東インド会社が、出来てから貿易や、領土などが、世界的になって、海を越えてグローバル化していくさまが、すごいです。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ta - この投稿者のレビュー一覧を見る
学生のころに学んだはずの部分ですが、よく理解できないまま生きていました。大人になって学ぶと面白いです。
投稿元:
レビューを見る
東インド会社は昔から気になってたんだよね!
とはいえ、英国東インド会社しか念頭になかったけど(^^;
オランダやフランスにも東インド会社があったのね。
オランダやフランスが『も』東洋にこれほど…と思いかけたところで、
ああ、『蘭領東インド』ってのがあったなあ(日本が攻め込んだ
『仏領インドシナ』ってのもあったなあ(日本が進駐した
インド洋にはまだ存在しなかった『国旗』を掲げた(主権国家という前提)の欧州列強の商人と、『国籍』という概念がまだ無い(だからこそ、外から来た人でも、王に貢献すれば褒美と役職がもらえる)ペルシャ、インドの王朝、港湾都市諸侯
こうした異文化というか、設定の異なる両者の接触の歴史である。
そして、インド洋とは又異なる『政治の海』の主である、明帝国や徳川政権と、欧州列強の接触。
「それでこうなったのか」「だからこうなってるのか」と同時に、「ちょっとちがったらどうなったんだろうなあ」と思いながら読んだ。
「茶の世界史」、「大英帝国という経験」と続けて読んだのは大正解!
投稿元:
レビューを見る
ポルトガル、オランダ、イギリス、そしてフランスにおいて設立された東インド会社は、ヨーロッパとアジアを結び、世界が一つとなる機運を作り上げた。その歴史を、ときにヨーロッパから、時にインドから、そして東インド会社の勢力の東端と言える日本から、縦横無尽に語りつくす一冊。インドにおける、現在でいうところの国籍にはとらわれない「海の帝国」と、日本をはじめとする東アジアにおける内と外を区別し陸の支配を重視する「陸の帝国」の対比も面白い。
投稿元:
レビューを見る
東インド会社を通してみる世界史。貿易のダイナミズムに弾みがつき、世界経済のグローバル化の起点になったことがわかる。
投稿元:
レビューを見る
面白かったです。
最初期の株式会社や貿易はどのようなものだったのか興味を持ち手に取りました。
加えて、400年前ごろ?の世界の横のつながりがわかったし、
各国の東インド会社の歴史的価値、世界がつながる近代化への道のりの序章なのだなと思いました。
374近代ヨーロッパは、一体化したそれ以前の世界の人々の様々な活動が総体として生み出した世界全体の子供なのである。
(中略)東インド会社の時代が終わりを迎えたとき、世界は近代ヨーロッパの論理に従って大きく変化していくのである。
投稿元:
レビューを見る
表題に違わぬ名著だと思う。東インド会社の成立前史から、その成立、隆盛そして衰退まで、各地域との関わりにめを配らせつつ丁寧にかつわかりやすく記述されている。個人的に勉強になったのは、日本史で言うと朱印船貿易の目的や、正徳新例後の貿易の衰退と国産化の進展。世界史で言うと、東インド会社の運んだ綿織物がイギリス社会を刺激し産業革命をうみ、それがアダムスミスの自由貿易論などにだいひょうされるような東インド会社の衰退につながった、という点であろうか。また、フランス東インド会社とイギリス東インド会社のインドにおける角逐や、インドの領主となったことでこうむった不利益などはなるほどと感じた。オランダ東インド会社が成立時に多くの出資者をえてロケットスタートしたことなども改めてしれた。「海の帝国」と「陸の帝国」の対比で、ムガル帝国がヨーロッパに海岸をつばまれルのを嫌がらなかったのに対し、東アジアは「政治の海」というのはなるほどとおもった。
投稿元:
レビューを見る
なんでポルトガル人日本に来た?何取引した?なんでそれ取引した?など、細かいところまで、痒いところまで手が届くような本。わかりやすい。
【読書目的】
- ポルトガル・オランダが日本にやってきた理由を理解する
- 主な貿易品と貿易の利益に関して理解する
【まとめ】
- ポルトガル・オランダが日本にやってきた理由
- 大航海時代
- 胡椒・香辛料のニーズ
- 肉の保存・味付け、医薬品としてのニーズ
- 中間業者と関税がかかっており、価格が高く、直接取引したかった
- 技術革新
- 羅針盤・造船技術
- 宗教改革
- カトリックの権威復活と拡大
- 黄金の国・ジパング伝説
- by マルコポーロ「世界の記述(東方見聞録)」
- ポルトガルが先陣を切った理由(by ウォーラーステイン)
- 大西洋岸にあり、アフリカに隣接しているという地理的条件
- すでに遠距離貿易の経験を持っていたこと
- 資本の調達が容易であったこと
(ジェノヴァ人がヴェネツィアに対抗するため、ポルトガルに投資しており、リスボンで活躍していた商人の多くはジェノヴァ人であった)、
- 他国が内乱に明け暮れていたのにポルトガルだけは平和を享受し、企業家が繁栄しうる環境があったこと
- オランダが台頭した理由:
- ポルトガルの衰退
- 香辛料の入手ルートが増え、貿易の旨みが減った。
- 港の維持費が馬鹿にならない。
- 徐々に、個人貿易など広がる。管理できなくなる。
- オランダの台頭
- ベルギーのアントワープの商人、スペイン王に対抗してアムスに移る。
- 定湿地帯で農業適さないので、漁業・海運業してた
- 中には、ポルトガルのリスボンから仕入れた香辛料をバルト海沿岸に輸送するものも
- オランダとハプスブルグが戦争→イベリア半島の港町に入れなくなった。
- イギリスの私掠船のせい(イギリスvsスペインポルトガル)で、胡椒の価格高騰。
- リスボンで買付できない(他のカトリック系が独占的に買いがち)
- そして、高度な航海技術と資本が結びついたオランダ→自分たちで東インドへ!
投稿元:
レビューを見る
「サピエンス全史」を読んだ時、こういった視座で日本目線の本があったら面白いだろうなぁと思っていたのですが、本著はまさにその1冊。
元々は、(それこそサピエンス全史にあった)ヨーロッパのルネサンスから産業革命に至る流れをもっと詳しく知りたいと思って、東インド会社をテーマとした本著に手を伸ばしたのですが、なんだか得した気分です。
「文化史的な情報としての面白さ」と「地域間の交流の相互作用を俯瞰的に見る知的刺激」が両方味わえる良著です。
シンプルに本著の内容を書いてしまうと、史上初の株式会社たる東インド会社がどのように生まれ、どんな情勢下で、何をどこからどこまで運び、どう人の暮らしを変え、最後にどう終焉していったのかを描いています。
著者の力量を感じさせるのが、豊富なデータや写真はもちろんのこと、そういった情報の出し方から考察まで、スムーズでわかりやすいこと。
会社の利益率や船の保有スタイルから、個別の人物の半生を語るくだり、ヨーロッパの上流階級における香辛料の位置づけ等々、バラエティに富んだ記述は工夫を感じて、読んでいて飽きません。
個別の感想を書いていくと、東インド会社の機関構成がまず情報として面白かったです。有限責任という現代まで続く考え方を取り入れ、オランダ会社は取締役が60人もいて、重役が17人。イギリス会社は取締役は24人で週1で取締役会を開く、等々。
国民国家の成立前に生まれた同社が、次第に時代と合わなくなっていって終焉に至るくだりは、会社という存在はいつだろうと変わり続けないといけないということを再認識しました。
それにしても、社員の副業が実質OKで莫大な財産を貯めこむくだり(例えば、イェール大学の名前の由来は、東インド会社のマドラス総督のイェール氏が莫大な寄付をしたから)は、さすがにどうなんだ、と思いました。赤字でも配当を続ける等、こういった点は現代の株式会社ではほぼ是正されている…はずです。
本著を読了して思いを馳せたのは、当時の日本の鎖国自体は正しかったのかなぁということ。
政治的自立を保ち、自給自足できる環境を作って、少なくとも17世紀は人口を増やしていた訳です。18世紀以降の停滞はどうだったんだろうとも思いつつ、ただアヘン中毒にさせられるよりは良い気もするし、これはこれで良かったのかなぁ。
何にせよ、現代世界がどのように生まれたのかを知るための鍵となる良著でした。
著者にはグローバル・ヒストリーについての著作もあるようなので、ぜひ読んでみたいと思っています。