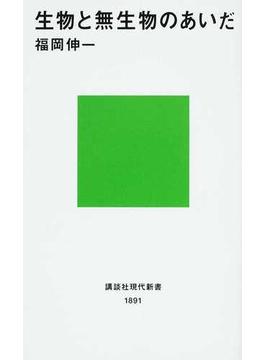「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
紙の本
生物と無生物のあいだ (講談社現代新書)
著者 福岡 伸一 (著)
【サントリー学芸賞(第29回)】【新書大賞(2008)】「生きている」とはどういうことか? 分子生物学がたどりついた地平を、歴史の闇に沈んだ科学者たちに光を当てながら平易...
生物と無生物のあいだ (講談社現代新書)
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
【サントリー学芸賞(第29回)】【新書大賞(2008)】「生きている」とはどういうことか? 分子生物学がたどりついた地平を、歴史の闇に沈んだ科学者たちに光を当てながら平易に明かす。ページをめくる手がとまらない極上の科学ミステリー。【「TRC MARC」の商品解説】
生命とは、実は流れゆく分子の淀みにすぎない!?
「生命とは何か」という生命科学最大の問いに、いま分子生物学はどう答えるのか。歴史の闇に沈んだ天才科学者たちの思考を紹介しながら、現在形の生命観を探る。ページをめくる手が止まらない極上の科学ミステリー。分子生物学がたどりついた地平を平易に明かし、目に映る景色がガラリと変える!
【怒濤の大推薦!!!】
「福岡伸一さんほど生物のことを熟知し、文章がうまい人は希有である。サイエンスと詩的な感性の幸福な結びつきが、生命の奇跡を照らし出す。」――茂木健一郎氏
「超微細な次元における生命のふるまいは、恐ろしいほどに、美しいほどに私たちの日々のふるまいに似ている。」――内田樹氏
「スリルと絶望そして夢と希望と反逆の心にあふれたどきどきする読み物です! 大推薦します。」――よしもとばなな氏
「こんなにおもしろい本を、途中でやめることなど、誰ができよう。」――幸田真音氏
「優れた科学者の書いたものは、昔から、凡百の文学者の書いたものより、遥かに、人間的叡智に満ちたものだった。つまり、文学だった。そのことを、ぼくは、あらためて確認させられたのだった。」――高橋源一郎氏
【第29回サントリー学芸賞<社会・風俗部門>受賞】
【第1回新書大賞受賞(2008年)】【商品解説】
目次
- 第1章 ヨークアベニュー、66丁目、ニューヨーク
- 第2章 アンサング・ヒーロー
- 第3章 フォー・レター・ワード
- 第4章 シャルガフのパズル
- 第5章 サーファー・ゲッツ・ノーベルプライズ
- 第6章 ダークサイド・オブ・DNA
- 第7章 チャンスは、準備された心に降り立つ
- 第8章 原子が秩序を生み出すとき
- 第9章 動的平衡(ダイナミック・イクイリブリアム)とは何か
- 第10章 タンパク質のかすかな口づけ
著者紹介
福岡 伸一
- 略歴
- 〈福岡伸一〉1959年東京生まれ。京都大学卒業。青山学院大学教授。専攻は分子生物学。「プリオン説はほんとうか?」で講談社出版文化賞科学出版賞を受賞。
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
生物学の様相を文学的に描いた、サイエンスライターによる書
2023/08/14 01:55
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:藤兵衛 - この投稿者のレビュー一覧を見る
この世界をここまで文学的な筆致で描いた本はそうそうないと思う。学問への入り口に大いに進めたい、とは思うところだが、感情的にかなり抵抗が大きかった。一番は、若い研究者の様を「奴隷」と書いてみせたことなのだろう。言わんとしていることはわかるが、ここまで強い表現を使うなら別の問題提起があってほしいし、これがレトリックに過ぎないのなら、違う表現方法を選んでほしかった。
理系のアカデミックな世界を多少なりとも知り、分子生物学の一端がわかる人が、その世界の新たな知識・知見を得るためなら読む必要はない。一研究者の書籍ではあるが、サイエンスライターが書いた作品だと思った方が、私個人はしっくり来る。
紙の本
生物と無生物のあいだ、そして研究とは何か
2022/11/08 13:50
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:令和4年・寅年 - この投稿者のレビュー一覧を見る
語り方が独得だった。偉人たちの足跡を追いつつ、自らの研究生活を振り返る。発見とは何か、研究とは何かを考えさせられる。ウイルスの話題がホットで、参考になった。
紙の本
細胞や遺伝子などに対するダイナミクスを体感する一書
2021/01/16 20:59
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:岩波文庫愛好家 - この投稿者のレビュー一覧を見る
巻頭は細菌とウイルスとに於いて生物か無生物かの区別に始まり、タンパク質やDNAへと至りながら細胞膜についての話へと帰結していく内容となっています。生物は一部が完全に欠落した場合は、それを補おうとし、実際欠落箇所に新たなピースを補っていきますが、中途半端なピースを嵌め込むと補完情報が歪になり、不完全を呈する、結果悪い影響を及ぼしていく、という内容に生命の複雑さを覚えました。
本書は生物学の本として、著者の研究過程と結果とを中心に展開されたものですが、各章の書き出しが推理小説っぽかったり、文学小説の叙景風だったりと、かなりユニークな構成となっています。これが本書の学説書として無機質感を緩和する緩衝材になっている気がします。あと、所々で出てくる難読熟語(例えば膂力『りょりょく』など)があり、理科系であろう著者の意外性を感じたりもしました。
ちょっと一風変わった様態の学説書に触れる事が出来た稀有さと、そうは言っても専門的に深奥まで掘り下げられた(何とか文系の私でも内容に付いていけた)生物学に触れる事が出来た新鮮さに乾杯です。
紙の本
生物
2021/01/11 11:17
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なま - この投稿者のレビュー一覧を見る
タイトルの「生物と無生物のあいだ」とはどういう事だろうと思いながら、この本を読み始めました。読み始めると、なぜかミステリーを読んでいるかのような感覚になりました。それだけ興味を持って読みました。
紙の本
まるで自伝的小説
2020/07/10 19:58
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:色鳥鳥 - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書タイトルは「ナゾナゾ」みたいだ。
生物と無生物のあいだにあるもの、なーんだ?
答えは現在大流行して皆様を疲弊させているウイルスです!
ウイルスは菌ではないので生物ではない。たとえば肺炎を起こす肺炎双球菌というものは単細胞微生物だから「生物」だそうで。これらは殺せるけれど、ウイルスと言う名のものはそもそも生きていない、塩のように結晶化するほど幾何学的な形をした、「なにか」なのです。
ただ、こいつらは自分を複製する能力を持っている……。
SFなどでよく問われる、生物の条件に、自己複製すること、という答えが正解とされる場合があります。それだとウイルスは生きている。でも本書の著者は、ウイルスは増える鉱物みたいなもので「生きていない」と考える。
自己複製だけが生物の条件ではない、と。
では生物の条件とは何か?
……というのが大きなテーマ。その他、著者の研究者としての経験や、DNAとは何か、といった基礎知識。また、そのDNAを、本当に発見したと言えるのは、本当にノーベル賞受賞すべきだったのは誰なのか、といった、内部のドロドロ人間模様を含めて、楽しく読めるベストセラーです。
当時、本書が話題になった理由は、ウイルスとは?といった基礎知識が、門外漢にもわかりやすく書かれているから、というだけではなくて、知性と美的感覚に溢れた文体にある、と思います。まるで自伝的小説です。
私は昔から科学が土台にしている動物実験が気持ち悪くてならず、あんたらそんなに知識があるのならもっと生き物の命を守る工夫をしてよと思うものですから、読みながら著者の話に引っかかりを感じることもあります。
本書のノックアウトマウスや、今コロナウイルスの実験に使われている、病気にされて殺される、犬猫の人生を想像すると、吐きそうになる。もし自分がそうなったらって考えたことあるんか、あんたら。
しかし、相容れない価値観、だからこそ、彼らの意見は尊重したいと思います。それは何万回生きたところで絶対に私にはたどり着けない考え方だと思うからです。
たとえば。
秩序は守られるために絶え間なくこわさなければならない。
この言葉は、とかく現在の生活を、過去のしきたりを、そのまま続けることだけが秩序だと考えがちな私たちの常識をぶち壊してくれる美しさがある、と思います。
かなり前のベストセラーということで完全にネタバレしますと。
著者はこう結論します。
生命とは動的平衡にある流れである。
分子のレベルでは、私たちは砂で作ったお城のようなもの。
いっとき、そこにとどまる、儚い秩序でしかない。
「こういう形の砂の城である」ということだけは同じだけど、中身はどんどん入れ替わっていて、全く同じ砂の城であり続けることなど、できない。
たとえば私たちはタンパク質を蓄積できない。努力しないとサラサラ流れていってしまう一方だそうで。
近頃、外部からあらわれた脅威、コロナウイルスってのは、DNAを持った鉱物のようなもので、まさに砂つぶです。
これがどういう砂つぶなのか、どうやって追い払えばいいのか、あるいはうまく共存できる日がくるのか、まださっぱりわかりませんが。
昨日までのやり方が通用しなくなったからといって「負け」ではないので、柔軟に過ごしていきたいと思っております。
紙の本
科学ミステリー
2019/06/20 19:45
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:たあまる - この投稿者のレビュー一覧を見る
福岡伸一『生物と無生物のあいだ』(講談社現代新書)は、エッセイのような科学読み物のような分子生物学の本。
研究内容と研究生活とを交互に記述する構成も、ミステリーの謎解きのような科学解説も面白かったです。
そう思って帯を見直すと、ちゃんと「科学ミステリー」と書いてありました。
紙の本
人知の及ばぬ生命体に深く安堵
2018/03/08 02:06
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:在外邦人 - この投稿者のレビュー一覧を見る
長い間読みたいと思っていた本だったが、やはり読んで良かったと思える著書だ。先ず日本語表現の美しさと、構成の的確さに感銘した。「生命体とは一体どういう概念なのか?」を探究する著者の研究生活とその詳細な説明が、門外漢にも違和感を抱かせること無く非常に興味深く描かれている。古今の科学者達の激しい競争もミステリー仕立てで描かれていて、何やら切ないものがある。人体は1年もすると分子レヴェルでは完全に入れ替わっているものなのだという説明には驚く他無かった。ヴィールスは、寄生しなければ増殖出来ないという生命体の概念とは異なる不思議な存在とは!そして生命とは、実験室で調べきれるものではなく、時間の不可逆的な要素が込められた人知の及ばぬ世界である事も、少し理解出来た様に思う。ゲノムの解析が完全に出来る時代になっても、生命体の秘密のベールは未だ解き明かされていない。科学者がAIを駆使して調べたところで、解明されるものとは考えられない。AIは無生物、人間は生物なのだから、と思った次第。
紙の本
理系と文系の間
2017/04/30 23:38
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ヤマキヨ - この投稿者のレビュー一覧を見る
生物学の専門家からの評価は辛いそうです。すでに明らかになった当たり前のこと乗られるなのだそうです。でもそのおかげで(?)文系人間の生物学入門書としてもありがたいものです。
わかりやすさ、おもしろさでは『生物学個人教授』(岡田節人・南伸坊、河出文庫)もおすすめです。
紙の本
科学(生物学)になじみのない人向けの科学書
2017/01/21 12:11
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:コスモス - この投稿者のレビュー一覧を見る
私は大学で化学を専攻しており、生物学についても触れる機会がありました。
なので、本作品に学問的なことについては真新しさを感じませんでした。
しかし、生物学についての新しい発見がどのようになされてきたのかについては、
ワクワクするように描写されているので、科学を専攻していたかに関わらず楽しむことができると思います。
そういうこともすでに知っていると言う人には面白くないかもしれないので星4つです。
紙の本
物語?
2015/12/20 22:34
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:じゅんべぇ - この投稿者のレビュー一覧を見る
新書にしては珍しい、物語風。でも最後まで読めてはいません。ヒマになったら読むかもしれませんが。そのうち、のために積ん読しときます。
紙の本
素晴らしい
2015/11/12 14:36
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ヒロ - この投稿者のレビュー一覧を見る
分子生物学研究の裏側を、軽快な文章で語っている。とにかく、著者の文章力が素晴らしく、どんどん話に引き込まれる。生物学に縁がない方にもお薦め。
紙の本
大学生向けかも
2015/09/12 20:06
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オオバロニア - この投稿者のレビュー一覧を見る
「ルリボシカミキリの青」同様に、読みやすさと生命科学ネタは保証できますが、ポスドクや研究者の喜びや悲哀が描かれているのでもしかすると理系を志す大学生向けかもしれません。
理系に興味を持つ高校生や中学生ならば「ルリボシカミキリの青」を読むことをおススメします。
紙の本
「生命とは何か」への答え。生命とは動的平衡にある流れ。
2011/07/20 00:51
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:レントゲンのパパ - この投稿者のレビュー一覧を見る
衝撃の刊行から4年が経過するも、未だおススメ棚を飾る一冊。内容も然ることながら、分子生物学者とは思えぬ美しく柔らかな文章構成は何度読んでも新鮮な感動を与えてくれます。
著者は冒頭から私たちに問いかけます。「生命とは何か?」と。
本書はその解答権を、DNA構造を発見したワトソンとクリック、PCR原理の提唱者キャリー・マリスといったノーベル賞受賞者たちに与えてくれません。遺伝子研究に多大な功績を残すも、日の目を見ることの叶わなかった影の立役者、3人のアンサング・ヒーローに求めています。
遺伝情報を運ぶ最重要分子がDNAであることを初めて発見したオズワルド・エイブリー。DNA結晶のX線解析によってDNAのらせん構造を初めて見出したロザリンド・フランクリン。そして同位体分子の質量分析から、生体を構成する全ての分子が常に代謝され置換されていく様を見て、「生命とは代謝の動的な流れであり、その流れこそが生命の真の姿」と提唱したルドルフ・シェーンハイマー。
著者は、彼らのひたむきな研究に対する情熱と決して諦めない信念、そして何より被ばくによる癌死や自殺といった非情な最後が、自身のポス・ドク生活や研究者の一面とリンクしたのでしょうね。
本書は、DNAをめぐるヒューマンドラマから、シュレーディンガーの「生命とは何か」への答えとして新たな生命観『動的平衡』など、幅広い領域をカバーしていますが、『動的平衡』に関しては新書では納まらず次回に続くようですね。
紙の本
幅広い読者層に向けたトピック
2011/05/16 22:29
4人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Genpyon - この投稿者のレビュー一覧を見る
分子生物学にまつわるいくつかのトピックを、著者の学問的来歴や個人的経験に絡めて、一冊の読み物にまとめた科学エッセイ。
生物学に縁遠い読者にも興味が持てそうなトピックが、科学史の裏話的な内容も含めて取り上げられ、また、専門的内容についても、必要に応じて分かりやすく説明されている。
本著のような科学的専門分野を扱う新書では、どのようなトピックを選択するかによって読者層が決まってくると考えられるが、本著では、より広い読者層に向けてバランスよくトピックが選択されているように思う。
好き嫌いが別れるのは、エッセイ部分だろう。基本的に科学的な読み物である本著において、エッセイ部分の語り口が多分に情緒的なのだ。科学的読み物にも情緒的な語りがあっていいのだが、本著ではそのバランスが必ずしも良いとはいえない。
もちろん万人にちょうど良いバランスはあり得ないのだが、私個人が何度か読んでみた経験に限っても、スッと読める時と、うっとおしくて読みとばしてしまう時があり、バランスとしては、かなりギリギリのところにあるのではないだろうか。
紙の本
「生物と無生物のあいだ」は、画期的な本です。
2009/09/23 16:11
8人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みどりのひかり - この投稿者のレビュー一覧を見る
シュレーディンガーの「生命とは何か」で、生命は負のエントロピーを食べているというのは解っていたのですが、この本はさらに踏み込んでいって、原子の大きさに比べ動物の体がべらぼうに大きいのは何故かという理由を説明しています。そこには驚くべき科学の発達の成果が見られます。
私はかねがね動物が体の設計図をたくさん持っているのは、どうしてなのかと思っていました。つまり、一つ一つの細胞の中に、からだ全部の設計図がそれぞれあり(人の場合20兆~60兆)、何ゆえ、設計図がそんなにたくさん要るのか不思議でした。設計図は1セットあれば良いし、予備を考えても5セットもあれば十分ではないか?それが何故、生物進化の過程で細胞の数だけ設計図が存在するようになったのか。そこの自然界における必然的過程が知りたかったのです。なぜ、生物はそのようにして複製を作ってきたのか?どういう必然性があってそうなったのか、それが疑問でした。この本のおかげでその謎も解けました。
エントロピーについてはを扱っている本は
こちら
と
こちら
がとても参考になります。
こちら
の本は小説の中に、エントロピーという言葉が出て来ますが、これを理解するための何の役にも立ちません。でも面白いのでお勧めです。
「生物と無生物のあいだ」は、画期的な本です。