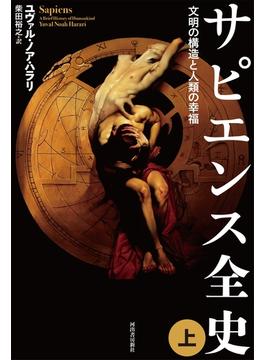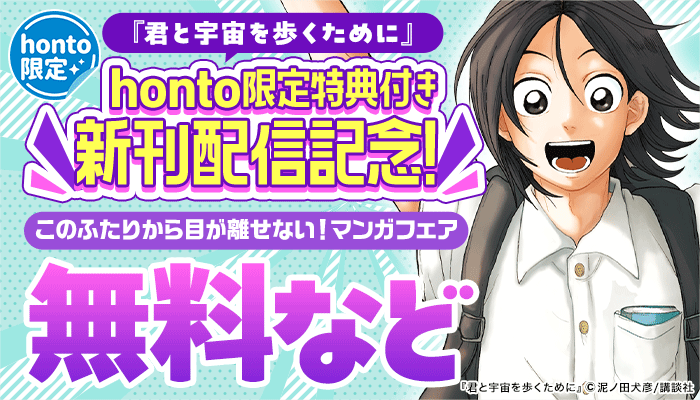- 販売開始日: 2016/09/16
- 販売終了日:2018/08/19
- 出版社: 河出書房新社
- ISBN:978-4-309-22671-2
サピエンス全史(上)
著者 ユヴァル・ノア・ハラリ , 柴田裕之
国家、貨幣、企業……虚構が他人との協力を可能にし、文明をもたらした!ではその文明は、人類を幸福にしたのだろうか?現代世界を鋭くえぐる、40カ国で刊行の世界的ベストセラー!
サピエンス全史(上)
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
書店員レビュー
丸善ジュンク堂書店のPR誌「書標」2016年10月号より
書標(ほんのしるべ)さん
新進気鋭の歴史学者による本作は、2011年に出るや世界中でベストセラーとなり、『銃・病原菌・鉄』のジャレド・ダイアモンドや、ビル・ゲイツなども推薦している。筆致は読みやすく、視点がブレないのでつかみやすく、一気に読み通すことができる。地球上に現れた最も革新的な種「ホモ・サピエンス」はいかにして文明を築き上げたのか。科学革命は我々をどこへ連れていくのだろうか。
スケールの大きな人類史
2016/11/07 15:18
11人中、10人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Takeshita - この投稿者のレビュー一覧を見る
さすが世界中でベストセラーになっている本だけあって面白い。人類は虚構を想像=創造し、それを集団で信じ行動してきたことに進歩の鍵があると言う。話題は歴史、環境問題、女性、家畜への眼差しまで多岐にわたり、西欧中心主義に偏らない公平さがある。著者が尊敬するジャレット、ダイアモンドにも似ている。それにしつも30代の若さでこれだけの本を書いたと言うのは大したものだ。
常識に切り込む刺激的な一冊。
2016/10/31 23:05
9人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:わびすけ - この投稿者のレビュー一覧を見る
以前読んだ「一万年の進化爆発」は刺激的だが言説が嘘臭かったが、同じような先史時代を扱った本書は過激だが、嘘臭さがない。データの扱い方や、論の持っていきかたなどの要因や、やはり世界的に評価されている本書の力を感じる。農耕による社会の変化が決して必然でも、人々の幸福を増すものでもなかったという言説はやはり刺激的。下巻ではどのような話になるのかとても楽しみ。
虚構の世界
2019/05/21 11:37
8人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:nobita - この投稿者のレビュー一覧を見る
確かに池上さんが褒めるだけの本だった。農業は時間に追われたり、宗教・貨幣などは実体がない。今の消費生活もまさに幸せの虚構である。ポツンと一軒家を見ているが彼らは自分の気持ちに正直に生きており実体のみがすべてであるように思う。羨ましい生活である。
一方私は有機テレビやステッククリナーが欲しいと思っている。考えてみれば、購入すればテレビ視聴や掃除に縛られるだけ。又車もデザインに凝るのはこれも虚構そのもの。走る棺桶・走る凶器まさにそれをカムフラージュするデザイン。早くかつての自分を取り戻そう。
既存概念を覆す
2017/08/16 08:47
5人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:スーさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
色々な人が推薦しているので、購入してみました。今まで私が理解してきた常識を覆す、とても新鮮な内容でした。たしかに著者の説にには説得力があります。下巻もすぐに読みたくなりました。
ホモ・サピエンスが繁栄したのは虚構を共有したため
2017/04/29 18:37
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:コスモス - この投稿者のレビュー一覧を見る
ホモ・サピエンスが繁栄出来たのは、虚構を共有し、共同体を形成できたため。逆に言うと、国民国家、人権、正義とか道徳心の基準とか・・・、いろいろなものが虚構であることを示しています。
人類は虚構を共有できたから発展できたが、それが原因で不幸な思いをしている人がいるのかもしれない。
(下巻とレビュー内容は同じ)
ご立派
2017/03/06 08:13
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:コアラ - この投稿者のレビュー一覧を見る
7万年前にホモサピエンスの脳内で生じた「認知革命」がすべての始まりである,すなわち宗教や貨幣といった共通の虚構を信じる力を得たことが人類飛躍の鍵となったと出張する大著。上巻では,1万年前の農耕革命とそれによって生じた余剰と貨幣に焦点を合わせて,人類が文明を大きく発展させて地球の支配者になった経緯を,最新科学も援用しながら描き出している。農耕によって本当に人類は幸せになったのか?他の生物にとってはどうか?等,いろいろと考えさせられる内容である。とりあえず目から鱗がぼろぼろ落ちた。
世界には、知ってるつもりで知らないことばかりだと改めて気がつく。 命つき果てるその瞬間まで、学び続けるのが「サピエンス」の在り方だ。
2022/11/30 11:06
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:mitu - この投稿者のレビュー一覧を見る
Audible Studiosにて「聞く読書」。
ウオーキングしながら、そして夜寝る前に聞き通した10時間の素晴らしい読書体験だった。
品格あふれる和村康市氏の朗読に導かれ「読破」することができた。
我々人類「サピエンス」の壮大な歴史を、ありとあらゆる視点を駆使しながら語り尽くす。
エルサレムのヘブライ大学で歴史学の教鞭を執る筆者の多彩な論説のグイグイ引き込まれていく。
「サバンナの負け犬だったわれわれサピエンスが今の繁栄を築いたのは妄想力のおかげ」
「認知革命」が神話を生み、サピエンスは集団行動が可能になる。
農業と神話による社会の発展。
そして、最強の征服者「貨幣」。
その先端を進んだ「帝国」のメカニズム。
征服者の言葉と文化で生きていく民衆。
正義と悪。
支配者と非支配者といった単純な二元論では、歴史の分析もできないし、未来への道標も見えてこない。
世界には、知ってるつもりで知らないことばかりだと改めて気がつく。
命つき果てるその瞬間まで、学び続けるのが「サピエンス」の在り方だ。
世界には、知ってるつもりで知らないことばかりだと改めて気がつく。 命つき果てるその瞬間まで、学び続けるのが「サピエンス」の在り方だ。
2021/09/17 07:31
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:mitu - この投稿者のレビュー一覧を見る
我々人類「サピエンス」の壮大な歴史を、ありとあらゆる視点を駆使しながら語り尽くす。
エルサレムのヘブライ大学で歴史学の教鞭を執る筆者の多彩な論説のグイグイ引き込まれていく。
「サバンナの負け犬だったわれわれサピエンスが今の繁栄を築いたのは妄想力のおかげ」
「認知革命」が神話を生み、サピエンスは集団行動が可能になる。
農業と神話による社会の発展。
そして、最強の征服者「貨幣」。
その先端を進んだ「帝国」のメカニズム。
征服者の言葉と文化で生きていく民衆。
正義と悪。
支配者と非支配者といった単純な二元論では、歴史の分析もできないし、未来への道標も見えてこない。
世界には、知ってるつもりで知らないことばかりだと改めて気がつく。
命つき果てるその瞬間まで、学び続けるのが「サピエンス」の在り方だ。
文化の発展は幸福をもたらすか
2020/05/05 11:22
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:サンバ - この投稿者のレビュー一覧を見る
※ネタバレあり
ホモ・サピエンスは、認知革命を経て他の人類と「言語」という点で、決定的に優れた存在となった。何千人の集団を束ね、一つの行動に向かわせる想像を作り出すことができ、ネアンデルタール人や他の動植物をあっという間に淘汰した。農業革命で、余剰作物を元手に勢力を増やし、ナワバリ意識の増大とともに、生物学的な成功を手にした。これ以降の文化の発展でその傾向はさらに強くなっていく。
しかし、前にはなかった不安に苛まれ、家畜と同じように農業あるいは科学の下で働くホモ・サピエンス。その幸福とは何なのか。
サピエンスの歴史を辿り、未来を見据える中で、止まらない発展の方向を変えうるのは、私たちなのだと教えてくれる。
ふんだんに例示を用い、専門用語には必ず理解を促す言葉を選んでおり、誰でも不安なく読み切れる本。
歴史に残る大作
2019/11/24 04:06
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ライサ - この投稿者のレビュー一覧を見る
歴史に残る大作であり、この本を読んでしまうと他の大半の名作ですら「物足りない」と感じてしまうようになる
サピエンスの特質は「虚構を信じる」「寛大さに欠ける」「残虐」であると
ところで多くの人はこの上巻で挫折したらしい
上巻のが面白いから、と某ユーチューバーは読みもせずに話していたが。
おそらくは下巻になると話が複雑化した上、歴史の流れも度外視して文章が書かれているからではなかろうか。また下巻は世界史の知識がないと読んでも理解できないことが多そうだった
新しい人類史
2019/04/24 14:15
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:sib - この投稿者のレビュー一覧を見る
20日余りで完読。読んでいる途中で日本に対する理解が欠けていると、腹が立った事もあったが、それは著者が日本発行に対するサービスで、にわかに日本記述を追加したためであろうと思うようになった。
今までにない角度から人類史を構築したもので、認知革命、農業革命、科学革命、産業革命と人間の進化についての記述が面白い。その内容が全て真実に合致しているとは思わないが、人間ってそんなに大した生き物ではないよと言われているようだ。
未来の人間に対する予測に対しては、どこまで的中するかはわからない。人間っていうのは時代を経ても、そんなに変わらないと思うのだが。
生き方を考えさせられる本
2018/10/20 22:46
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:akihiro - この投稿者のレビュー一覧を見る
農業革命は「進歩」だと思っていましたが、著者は「過ち」と捉えています(メリットも述べてはいます)。本来、人間もほかの動物のように狩猟生活に適した能力を有していたはずなのに、農耕を始めたことで新たな心配事や争いが増えてしまったという意見です。
働き方改革を考える以前に、人間として快い生き方はどのようなものかを考えさせられました。下巻は未読ですが、上巻だけでも読む価値ありです。
評判通り、大いに考えさせられた一冊
2018/08/31 23:09
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:しょひょう - この投稿者のレビュー一覧を見る
話題になっていたので、いつか読もうと思っていたままになっていたが、夏休みを期に上下巻を一気に完読。
既に多くの書評がでているので、今更付け加えることはないが、スケールの大きな人類史を客観的事実をもとに描き、著者自身の価値観を押し付けることなく、読者に問題提起してくる。
産業革命はもとより、農業革命、さらにその前の認識革命のときから、ホモ・サピエンスは他の動物とは違う次元に進んできているのだ、ということのが非常に印象に残った。
読んでよかった、と文句なく思える一冊。また読み返してみたい。
認識が新たになる面白さ
2018/05/31 09:27
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ヒトコ - この投稿者のレビュー一覧を見る
我々サピエンスが、何種もの人類の中で絶滅せず今日に至ったのは、虚構を想像し共有出来たから。
採集から狩猟、農耕へと食料確保技術の進歩が人口増加と社会の変化をもたらしたとしか理解していなかったが、
それを成し得たのも虚構を信じる力を持てたから、などなど。
宗教も政治体制も経済活動もその虚構を信じる想像力の成せる技だったのか!
農業革命で豊かになったわけでなく、食の豊かさを失いかえって飢饉のリスクを生んだ、
過去の様々な種の絶滅に人類が大きく関わっていた。
自分がこれまで人類の進化や進歩についてプラスに認識して事に思わぬリスクが生じていたとは!
難しそうな内容だと思ったが、一般に人にも分る例えなども多く、読みやすかった。
著者の説が全て正しいかどうか別にして、歴史を見る視点にがちょっと変わる一冊です。
既成概念が覆される
2021/12/31 18:10
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とりこま - この投稿者のレビュー一覧を見る
私たち「ホモ・サピエンス」の壮大な歴史を紐解きながら、なぜヒト科の中でホモ・サピエンスが生き残ったのかを解き明かしている。
「虚構」を生み出したことで大きな集団での活動を可能にしたことや、その先の農業革命、書記の発明、貨幣の発明などを経て、統一された世界に向かっているという説が斬新であった。
また、農業革命は人口増加には寄与したが、進歩ではなく、詐欺であり、人類がコントロールしたのではなく人類が穀物に家畜化された、という説は衝撃的だった。
虚構という概念でこの3000年を読み解く試みにより、まったく違う景色が見えてくる。